品質保証の取り組み
原料緑茶
日本の主な茶葉の産地
茶の栽培には、年平均気温が12.5〜13.0℃以上で湿度の高い環境、水はけがよい弱酸性の土壌が適しているといわれています。
日本にはこの条件を満たす土地が比較的多くあります。東北地方では若干の生産にとどまるものの、日本海側では新潟県以南で、太平洋側では茨城県以南で、広く栽培されています。
-
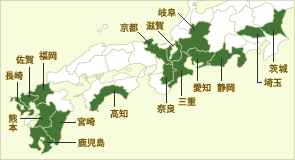
日本の主な茶産地
-

茶の種類(紅茶・ウーロン茶・プアール茶との違い)
茶は製造方法の違いから、不発酵茶、半発酵茶、発酵茶に大別されます。発酵とは、茶の葉がもつ酵素によりカテキン類などが酸化されることをいいます。
緑茶は不発酵茶に分類され、摘採後すみやかに加熱処理により酸化酵素の働きが止められます。
緑茶はまた、栽培方法や加工方法で分けられます。
たとえば、一般的な緑茶は露天で栽培されるのに対し、碾茶※や玉露はよしずや藁(わら)などで覆った茶園で栽培されます。また、玉露と碾茶は加工方法が異なっており、玉露では加工途中に揉み操作が行われるのに対し、碾茶では行われません。
一方酵素の働きを止めず完全に発酵させる茶(発酵茶)として紅茶が、ある程度発酵させる茶(半発酵茶)としてウーロン茶が挙げられます。 このほか、プアール茶に代表される後発酵茶などがあります。後発酵茶は加熱処理した後、酸化酵素ではなく微生物により発酵させます。
-
※碾茶とは
抹茶の原料となる茶。碾茶を石臼で挽いて粉状にしたものが抹茶です。
-
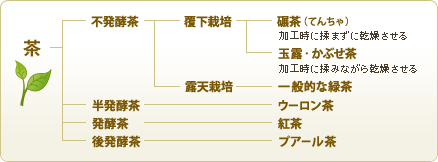
-

露天栽培
-

覆下栽培
緑茶
緑茶とは
茶はツバキ科の常緑の低木で、葉は厚く、光沢をもっています。緑茶はこの芽や茎、葉を加工してつくられます。
緑茶ができるまで
緑茶の中で最も一般的な煎茶の製造工程を紹介します。
摘み採った生葉は茶園の近くの工場に運ばれ、加熱処理と揉み操作、乾燥が行われます。ここでできあがったものを荒茶といいます。
次に、仕上げ工場に搬送され、「選別」、「乾燥・火入れ」を経て仕上げ茶となります。最後に一定の品質にするため、産地や工場が異なる茶葉のブレンド「合組」が行われます。
- 摘採(てきさい)
- 手摘みと機械摘みがあり、現在では大部分は機械摘みで行います。摘み採り後はすばやく荒茶工場に運びます。
-

手摘み
-

機械摘み
- 荒茶(あらちゃ)製造
- はじめに生葉を「蒸し」、その後「揉み」と「乾燥」を徐々に行います。それぞれの主な目的は以下の通りです。
- 蒸し:
- 葉に含まれる酸化酵素を失活させる。
- 揉み:
- 葉の成分が浸出しやすいようにする。
- 乾燥:
- 保存性を高める。
- 1. 蒸熱(じょうねつ)
- 高温の蒸気で葉を蒸す工程。
葉に含まれる酸化酵素を失活させる。その他、葉の青臭さをとったり葉を柔軟にし揉みやすくする。

- 2. 冷却
- 蒸葉に風を当て、表面についた露を除きながら冷ます。蒸れた香味が発生するのを防止する。
- 3. 粗揉(そじゅう)
- 茶葉を熱風の中で攪拌しながら乾燥させる。葉の含水率は50%程度まで下がる。

- 4. 揉捻(じゅうねん)
- 熱をかけずに加圧しながら揉み、水分ムラをなくす。また粗揉での揉み不足を補い、葉の成分が抽出されやすくする。
- 5. 中揉(ちゅうじゅう)
- 再び熱風にかけ軽い力で揉み、均一に水分を除去する。含水率は30%程度まで下がる。

- 6. 精揉(せいじゅう)
- 加熱した盤上で茶葉を揉みながら撚(よ)っていく。針のような細長い伸び型に整える。含水率は10%程度まで下がる。

- 7. 乾燥
- 最後に高温の熱風にあて、十分に乾燥させる。茶葉の保存性を高め、貯蔵中の香味の変化を抑制する。
- 仕上げ茶製造
- 「選別」により茶葉の形状をそろえ、「乾燥・火入れ」により茶特有の香味を生み出します。
- 1. 選別
- 大小さまざまな状態で混じりあっている茶葉を、篩(ふるい)にかけたり切断するなどして、形状を統一する。風力や色彩による選別にかけ、形状の異なる茶葉などを除く。
- 2. 乾燥・火入れ
- 茶葉を再加熱し乾燥をすすめる。貯蔵性を高めると同時に、茶特有の香り立ちを引き出す。含水率は5%以下まで下がる。
- 合組(ごうぐみ)
- 安定した品質の茶の提供と、消費者の嗜好にあった茶を生み出すことを目的に、産地や工場が異なる茶をブレンドします。合組は荒茶の状態でも行われます。
緑茶の品質保証(福寿園での取り組み)
福寿園と共同で取り組んでいる国産茶葉の品質保証について紹介します。
国産茶葉100%使用
毎年、取引のある製造工場と栽培農家を訪問・視察し、栽培から仕上げまでの各所で国産以外の茶葉が混入しないしくみが整備されていることを確認しています。


茶葉の安全性を確認
農薬が適正に使用され栽培された茶であることを生産履歴で確認するとともに、残留農薬の分析を実施しています。
近隣の畑から飛散してくる可能性のある農薬や土壌残留性の高い農薬まで分析項目を広げ、安全性を確認しています。

残留農薬等の検査書
品質確認を徹底
福寿園の茶匠により厳選された茶葉は、さらにサントリーグループの研究所でも品質確認を行います。福寿園・サントリーグループの両者で品質確認を徹底して行い、香り・味はもとより安全性についても確かなものにしています。








