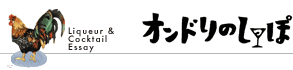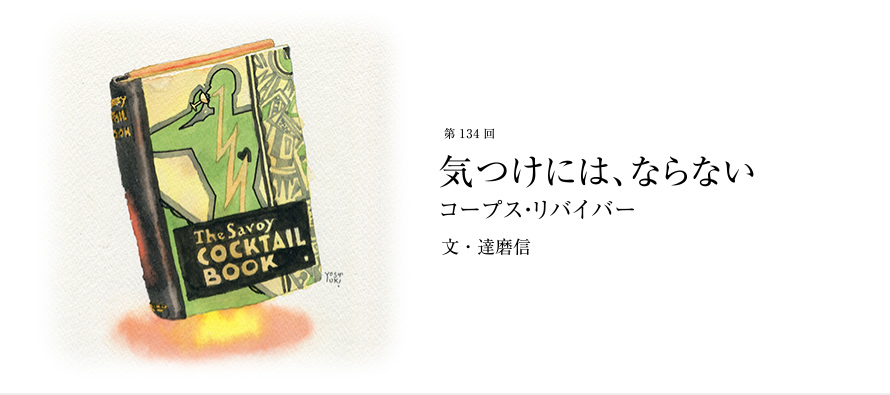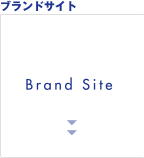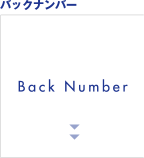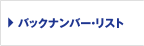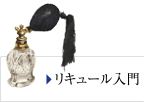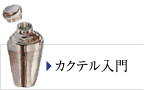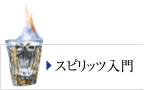適正飲酒を皆が心がける時代になったような気がしている。21世紀に入ってから徐々に変わっていったのではなかろうか。とはいえ、コロナ禍での家飲みが習慣化してニュースにいろいろと取り上げられた時期もあった。しかしながら最近では深酒とか二日酔いなんていう言葉が聞かれなくなり、飲み方がキレイになりつつある。
そんな時代にあって申し訳ない。長くpic me up(気つけ、元気回復)と呼ばれ、迎え酒として語られつづけているカクテル「コープス・リバイバー」についてお話しよう。
カクテル名はかなり強烈である。corpseは死体のことであり、多くのカクテルブックに“死者をよみがえらせるもの”と説明されている。このカクテル名が文献に登場したのは19世紀半ば過ぎのことで、かなり古くから存在していたようだ。
現時点での「コープス・リバイバー」の初出は1861年、ロンドンで出版されていた週刊の風刺漫画雑誌『Punch/The London Charivari』にカクテル名が登場している。レシピの記述はないようだが、やはり迎え酒的なニュアンスの紹介である。
きちんとしたレシピが掲載された初出文献は、同じくロンドンで1871年に出版された『The Gentleman’s Table Guide』(E. Ricket/C. Thomas共著)になるのではなかろうか(もっと古いものがあるかもしれない)。ブランデーとマラスキーノ(サクランボのリキュール)の1 : 1にビターズを2ダッシュと掲載されている。現在知られている材料とは大きく異なる。
この「コープス・リバイバー」のレシピが落ち着くまでにはかなり紆余曲折があったようだ。いろんなレシピが存在したらしい。バーテンダーたちが肉体の回復を願って考案、アレンジしていったのかもしれない。
現在もNo.1、No.2、No.3などさまざまなレシピが存在している。おそらくだが、1930年にロンドンのサヴォイ・ホテルのバーテンダー、ハリー・クラドックが編纂した『The SAVOY Cocktail Book』でNo.1、No.2のレシピが紹介され、そこからレシピが定着したのではなかろうか。
クラドックのカクテルブックには今回紹介するNo.1に注釈があり、“午前11時より前に飲むこと”と記されている。この一文が迎え酒としてのポジションを確固たるものにしたといえよう。
また、「コープス・リバイバー」は1920年代から30年代にかけてパリのホテル リッツのバー・マネージャーだったフランク・マイヤーの功績とした文章をよく目にするが、彼の『The Artistic of Mixing Drinks』(1936年)のなかではまったく言及がないようだ。誰が生んだレシピであるかはよくわかってはいないらしい。
ちなみにNo.2はジン、ホワイトキュラソー(オレンジリキュール)、キニーネを配合したフレーバードワイン、レモンジュースをすべて同量、そしてアブサンを1ダッシュしてシェークする。ただしレシピにあるフレーバードワインは現在つくられていないため、バーテンダーは別のフレーバードワインで代用するしかない状況にある。かつての味わいの再現は難しい。