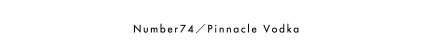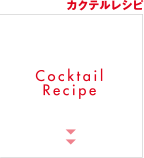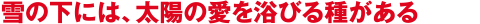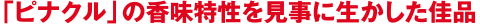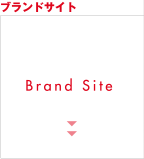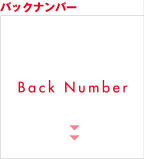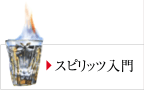ウオツカはすっきりとした透明感、クセのあまりない清冽な味わいのスピリッツだ。カクテルにおいてはベースとして厚みのあるアルコール感をズンと効かせながら、他の材料の香りや味わいを引き立てる名脇役となる。
ところがフランスはコニャック地方でつくられる「ピナクル ウオツカ」をストレートで味わうと、クリアさのなかに独特のジューシーさがあり、とてもユニークな新鮮味を感じる。そのジューシーさというのが洋梨のようなフルーティーさ、なんともいえない瑞々しい(みずみずしい)シズル感にあふれている。
清冽ながらしなやかな弾力性ともいえるだろう。そこには嫌味がない。粘性とはまたひと味違うものだ。
「ピナクル」とは“山の頂き”のことらしい。ストレートでしっかりと味わいながら爽やかなライトブルーのボトルを見つめる。中央上部には小さく白い山の頂きがデザインされている。
味わいとともにわたしのアタマに浮かび上がった映像は、春を知らせる雪解け水の流れだった。まだ少し寒いけれど、冬に縮こまった心身を清々しく洗い、解きほぐし、大地の温もりを待つ感覚である。
すると「ピナクル ウオツカ」の味わいと映像イメージに重なるようにひとつの曲、しかも最後の部分だけが耳の奥から聴こえてきたのだった。それは、こんな歌詞である。
---------思い出して。厳しい冬の雪の下には、陽の光の愛を浴びる種があり、春になればバラの花が咲くことを-------
誰にでも衝撃を受けた映画がいくつかあるはずだ。とくに感性が鋭敏な年若い頃に観た映画で胸を熱くした作品は、かなりの年齢を重ねてもこころに強く刻まれている。
1980年に日本で公開された映画『ザ・ローズ』(アメリカ1979年)。メアリー・ローズ・フォスターというロック・シンガー役のベット・ミドラーのぶっ飛んだ演技、魂の叫びそのもののライブシーンにわたしは衝撃を受けた。
ジャニス・ジョップリンをモデルにした映画ではあるが、ロックミュージックがビジネスとして成り立ち、ベトナム戦争の悲惨さを引きずり、そしてドラッグに犯された時代を描いている。この時代背景からすれば、ジャニスがすべてという訳ではないとわたしは思っている。
多分、いま再びこの映画を観たとしても、ベット・ミドラーのライブシーンだけを追いかけて、ストーリー展開には目を向けないであろう。遠い昔の現実、自分自身のこころがすでに歴史解釈に染まってしまっている。あの時代にアメリカ文化をシャワーのように浴びていた若者であったからこそ共感でき、胸を熱くしたのだろう。
しかしながら、主題歌といえる映画のラスト曲『ザ・ローズ』のインパクトは強烈だった。魂の叫びで全編染まっていたはずなのに、最後に突然、静かに抑えたバラード調の曲が流れたのだ。“愛は花。その種があなた”という内容の歌詞だが、わたしには美しい讃美歌のようにこころに沁みた。ローズが神に抱かれたのだった。
いまでもあのラストの衝撃は忘れられない。
これまで国内外の多くの歌手が『ザ・ローズ』をカバーしている。日本でもドラマの主題歌や番組内のBGMに使われ、また日本語歌詞にして歌われてもいる。それはそれでよしとしよう。でも、誰が、どんなにこころを込めて歌い上げようとも、讃美歌としてわたしの胸を打つことはない。1980年晩秋、劇場席でしみじみと聴いたベット・ミドラーの歌声に勝るものはない。