-
〈現代オペラ〉クロニクル
大野セレクションの室内楽
オペラ『リトゥン・オン・スキン』
- JAPANESE
- ENGLISH
- サントリーホール
- サントリーホール主催公演 2019-20シーズン
- サマーフェスティバル2019
- 第29回 芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会
- JAPANESE
- ENGLISH
8/31(土)
15:00開演(14:20開場)大ホール
第27回 芥川作曲賞受賞記念サントリー芸術財団委嘱作品
- 茂木宏文(1988~ ):『雲の記憶』チェロとオーケストラのための(2019)※1世界初演
第29回 芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会
※曲順が下記の通り決定しました。
- 鈴木治行(1962~ ):『回転羅針儀』室内管弦楽のための(2018)
- 初演=2018年4月15日
京都コンサートホール 小ホール
京都フィルハーモニー室内合奏団第213回定期公演
指揮:齋藤一郎/京都フィルハーモニー室内合奏団

- 稲森安太己(1978~ ):『擦れ違いから断絶』大アンサンブルのための(2018)
- 初演=2018年11月3日
ツォルフェライン 塩倉庫、エッセン市(ドイツ)
NOW! 現代音楽祭「旅」コンサート
指揮:ピーター・ヴィール/ストゥディオ・ムジークファブリーク - 北爪裕道(1987~ ):自動演奏ピアノ、2人の打楽器奏者、アンサンブルと電子音響のための協奏曲 (2018)※2
- 初演=2018年10月5日
パリ国立高等音楽院サル・レミー・フリムラン
パリ国立高等音楽院作曲科修了演奏会
指揮:ピエール=アンドレ・ヴァラド/打楽器:ミンユ・ウェン、ティボー・ルプリ/パリ音楽院桂冠管弦楽団
候補作品演奏の後、公開選考会
(司会:伊東信宏)
- 選考委員(50音順):斉木由美/坂東祐大/南 聡
- 指揮:杉山洋一
- チェロ:山澤 慧※1
- 打楽器:菅原 淳/石田湧次※2 エレクトロニクス:有馬純寿※2
- 管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団
- 協力:(一社)日本作曲家協議会/(一社)日本音楽著作権協会/日本現代音楽協会
「第29回芥川也寸志サントリー作曲賞
選考演奏会」 応援企画
SFA総選挙
~あなたの、清き、耳の一票を!
8月31日(土)公演当日、賞にノミネートされた3作品を聴いて、あなたが最も「いいなぁ」と思った作品に1票を入れてください。
作曲家への感想、応援コメントも受け付けます。
- 投票資格:
- 候補作品の演奏を3曲とも聴くことができる方
- 投票時間:
- 演奏会終了後、公開選考会が始まるまで
- 投票場所:
- ホワイエ(ロビー)の投票箱
※得票結果は、作曲賞決定後に発表します。
※SFA総選挙は演奏会の応援企画として非公式に実施するものであり、その結果は公開選考会での選考には一切関係しません。
■料金
- 指定 2,000円/学生 1,000円
| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月14日(火)10:00〜5月16日(木) |
|---|---|
| 一般発売: | 5月17日(金)10:00〜 |
※学生席はサントリーホールチケットセンター(電話・Web・窓口)のみ取り扱い。25歳以下、来場時に学生証要提示、お一人様1枚限り。
茂木宏文(作曲) インタビュー
山澤 慧(チェロ) インタビュー
作曲家プロフィール
写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。
出演者プロフィール
写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。
作曲ノート
茂木宏文:『雲の記憶』 チェロとオーケストラのための(2019)
ある一瞬の雲を切り取った時、それはもう過去のもので、その雲はその時一切の可能性を否定されます。ある形として存在しようとした時、その瞬間にそれ以外の可能性がなくなる。その繰り返しが、もし何かを想像すること、何かが存在することの宿命なら、その極限を想像してみたいと思うことがあります。しかし、それは常に先へ先へとこぼれ落ちていくもので、その目的地を未だ見ることはありません。
きれいな空気から雲は発生しづらい。ある時そんな話を聞きました。空気中にあるほこりや塵、小さい粒に水と親しみやすい性質をもったものがあり、空気中の水蒸気の分子が吸着して水分子の膜を作る。そして、これに対して水蒸気の凝結が起こり、雲の粒になっていくという過程があるそうです。空気中にある水蒸気は、核となる粒と共にいつの間にか空を覆い、水面の無い空で自らを液体や固体へと姿を変え地上に降ってくる。この絶え間ない循環の中で、雲は少しの間その途方も無い循環のプロセスを、人間が知覚出来るようその時間をゆるめ、その一端を私たちに見せてくれているのです。
この作品の独奏とオーケストラとの関係は、雲とそれを囲む大気の関係に似ています。雲と呼ばれているものは独立して存在しえないし、大気の循環があれば雲は自然と発生する。この作品の主題は、正にこの混ざり合いながら引き離され、また溶け合うその関係性から生まれたものです。
単なる「現象」をこのように捉えることが良いのかわかりませんが、流動的しかし、その形を保ちある時には不幸をもたらすが恵みを運んで来てくれる雲と、その現象に自らを重ね、そして抱くある種のポエティックな衝動を否定的に捉えることもないなと思いながら、この曲を仕上げました。全体は途切れることのない単一楽章で、オーケストラと独奏の対比と、室内楽的アンサンブルの質感を随所にちりばめながら構成されています。
最後に、今回の独奏を快く引き受けて下さった、この作品の献呈者でもあるチェリストの山澤慧さんには様々な助言を頂き、彼なしではこの作品は完成し得なかったことを感謝と共にここにお礼申し上げます。また、指揮者の杉山洋一さん、新日本フィルハーモニー交響楽団の皆様、そしてサントリー芸術財団の方々、すべての関係者の方々に心より感謝致します。
鈴木治行:『回転羅針儀』 室内管弦楽のための(2018)
ある時期から私の作曲は、音響を作るというよりも時間体験を作るという意識に変わった。普通は、音楽を作るというのは音を作ることを意味し、その作られた音の持続を体験することが時間体験ということになる。本来は、時間体験は結果であり、作曲家が意識して作るのは音それ自体であるだろう。しかし、いったん音を飛び越え、時間体験を作ることに焦点を当ててみると、ある時間体験を引き起こす、そのために音を作る、という発想になる。音による分節なくして時間体験もない。そこでは、音は体験を齎すためのきっかけ、もしくは媒介のようなものとなる。いま、時間軸上に2つの点が穿たれるとする。人間には記憶というものがあるので、この2つの点は関係づけて認識される。同じ点が再び回帰してくると、それは「反復」と呼ばれる。戦後の前衛音楽は反復を忌避したが、この方向の選択はある意味「記憶」を活用して音楽を関係づけ、時間を分節する道を自ら閉ざした。何も音楽に限らず、複数の事物が並んでいれば人はそこに関係性を見出さずにはいられない。時間軸上に関係性の網の目を張り巡らせ、ある時間体験を創出することが、私にとっての作曲だといえる。
この『回転羅針儀』を聴くと、前にも出てきたような音響が何度も回帰することに気づかれるだろう。しかし、その反復は非常に不規則で、ある時は非常に短い断片だったりする。断片があまりに短いと、それは一種のサブリミナルな体験となる。一瞬にして通り過ぎた今のは一体何だったんだ?という引っかかり(記憶に刺さった棘)は、音楽が進行してゆく中、やがて記憶の海底に沈潜し表面的には忘れられてゆくが、やがてそれがもっと長いスパンで立ち現れた時、記憶の底から再び意識の水面上に浮上してくる。その時、2つの点と点は時間軸上で関係性の糸によって結ばれる。この作品は、このように糸を錯綜して張り巡らせた記憶の織物といえるだろう。
稲森安太己:『擦れ違いから断絶』(2018)
近年の私の創作の主な興味は、音楽時間の構成の仕方を様々な方法で試みることである。時間を構成する重要な要素の一つにリズムがあり、リズムの扱い方を工夫することで独特な時間の流れを感じさせる作品を作曲したいと思っている。こうした興味に基づいた作曲の原点とも言える作品が 2011年の『すれちがう二人』(Vn, Pf)である。この作品で二人の奏者は常に異なるテンポで奏し続け、最小公倍数で出会うリズム点で一瞬アンサンブルを揃える際にイベントが起こる仕掛けの作品である。2013年には続編とも言える『なおもすれちがう二人』(Fg, Bn, Vn, Elec)を発表し、電子音による厳密な時間操作に裏打ちされ、よりリズムのズレが際立つ作品となった。どちらの作品にもMiscommunicationという英語が原題に含まれ、今回演奏される『擦れ違いから断絶』が3作目となる。
『擦れ違いから断絶』では、アンサンブルは常に2つ以上のグループに分割され、どのグループも異なる時間軸のテンポを持つ。アンサンブルを成立させる便宜上、同一テンポで書かれているが、例えば冒頭では5連符の16分音符3つ分が一つ目のグループのテンポであるのに対し、6連符の16分音符3つ分と4つ分がそれぞれ変拍子の拍を成す複雑な拍節感を持ったグループが同時に演奏する。難儀なリズム構造がアンサンブルをフラストレーションにさらすが、何としても共通の音楽時間を見出したい意欲を持って演奏を続け、曲の最後には全員が一つのテンポに辿り着く。しかし、安寧の地に到達した喜びはアンサンブルのビオラ奏者にとっては大きすぎたようで、過度な感情表現を始め、アンサンブルから顰蹙を買うところで曲は終わる。
本作品はエッセン・フィルハーモニーの委嘱によってNOW!現代音楽祭のために作曲され、ツォルフェライン炭坑業遺産群塩倉庫でストゥディオ・ムジークファブリークによって初演された。
北爪裕道:自動演奏ピアノ、2人の打楽器奏者、アンサンブルと電子音響のための協奏曲(2018)
ステージ上、中央に置かれた自動演奏ピアノと左右両端に1人ずつ配置された打楽器ソロ奏者の三者をソリストとする協奏曲。自動演奏ピアノはコンピュータを使用したリアルタイムの遠隔操作により鍵盤とハンマーが自動的に動いて演奏されます。
私はここ数年にわたり、「機械」の挙動にみられる特徴を「人間」が演奏する音楽に取り入れる手法を実践してきましたが、今回は本物の「機械」である自動演奏ピアノを中心に据えることにより、その関係性にさらに多角的に迫れるのでは、と考えました。左右の打楽器ソロ奏者は、いわば機械に対する「人間」を象徴し、さらにそれに対応して左右対称に配置された器楽アンサンブル、そして会場を取り囲むスピーカーから発せられる電子音響は、空間的効果を伴ってそれらを拡張します。
曲の開始後しばらくは、主に打楽器ソロ奏者たちの演奏によって音楽が主導され形作られていきます。しかしやがて動き出した自動演奏ピアノが繰り出す人間離れしたジェスチャーは、時に彼らを圧倒し、いつの間にか彼らが自動演奏ピアノの動きに追随していたり、という状況もしばしば生まれます。「機械」と「人間」の様々な形での対峙が表現される中、曲の各所に見られるこうした主導権交代のドラマ、あるいはそれぞれの演奏表現の中に必然的に表出する両者の特性やキャパシティの差異が、この作品を形作る重要な要素となります。演奏時間は約20分。
今回の機会に際し、各所のご協力によりヤマハの自動演奏ピアノ「ディスクラビア」、それも、サントリーホールという大規模な会場に対応すべく、日本国内にも1台しか存在しないというフルコンサートグランドピアノサイズのディスクラビアを特別にご用意頂けることとなりました。さらに最高の演奏家たちとスタッフにも恵まれてこの作品の日本初演を迎えられることをとても幸せに思います。関係者各位に心から感謝いたします。
茂木宏文(作曲)/山澤 慧(チェロ) インタビュー

—茂木さんと山澤さんの出会いのきっかけを教えてください。
茂木まさに2年前の2017年サマーフェスティバルで初めて会いました。僕自身ジャンルにこだわらず、ボーダーレスにいきたいなというのは元々ありました。演劇も映画など他の芸術分野も好きですし。山澤くんの活動を見ていると、そのようなボーダーレスな感覚が合うように感じています。
山澤彼に「このフレーズって多少荒くても良い?」って尋ねにいったのが初めてのやりとりだったような気がします。
—2017年は茂木さんが芥川作曲賞を受賞された時ですね。その時の作品(『不思議な言葉でお話しましょ!』)の印象はいかがでしたか?
山澤弾いてみて、弾きやすいというのが最初の印象でした。僕は楽譜というのは、パート譜だけを見てメッセージみたいなものを読み取れる楽譜と、読み取れない楽譜というのがあるように思っています。で、読み取れる楽譜だったような気がします。何したいかがわかる。
茂木作曲のレッスンに通っていた時期に、演奏者が練習したくなる楽譜を書いた方が良いとその時先生から言われました。やっぱり生身の人が弾くわけだから、簡単すぎてもだめだし、難しすぎて訳が分からなくてもだめだし、練習して臨みたくなるような楽譜を書いたほうが良いと。
山澤すごくその通りだと思います。
茂木最終的に自分が書いたものが、実際演奏者が見て「これはなんだ?」と思っていらっしゃる方もいるかもしれないですけれど、でも作品を書く段階では「演奏したくなるような作品」ということも考えながら書くように努力はしています。
山澤その意識があるかないかで全然違うかもしれない。難しすぎてももちろんだめだし、簡単すぎてもだめというのは結構重要なところかもしれない。簡単すぎると練習しないし、何をしたら良いかという意識が薄れてしまうような気がします。
—今回世界初演となる『雲の記憶』の作曲経緯についてお聞かせください。
茂木この芥川作曲賞では、自由に、好きに書いて良いと言われるので、現代の作曲家にはすごく貴重な機会だと思っています。オーケストラの作品でも良いし、コンチェルトでも良いなと考えていました。そしていろいろなことを考える中で、自分の作品の中にヴァイオリン・コンチェルトはあるけど、チェロ・コンチェルトはないな。いわゆる古典派から脈々とある作品を自分の作品リストの中に欲しいなという思いを元々持っていましたが、この機会にそれを思い出していました。ちょうど2020年に山澤くんがB to Cに出演しますが、それに際してまずは先に彼が僕にチェロの独奏を書いてくれますか?とコンタクトをくれて。その時、これは何かのご縁。同い年というのもあってチェロ協奏曲ということになりました。

—実際に制作課程でのおふたりのやりとりはどのような感じですか?
山澤レクチャーじゃないけど色々見せたりしました。チェロの弾き方とかめずらしい奏法とか、逆にこれはやりにくいよとか。
茂木それで過去の作品などを例にして、どうやって弾くのかを実際に演奏してもらったり、ポジションのこととかも含めて見せてもらってから、じゃあどういう風にしようかな、というようにして進めていきました。
山澤その後ある程度書いてから再度会いに行って、その場でパッセージを弾いたりしました。その時はまだ完成、というところまでではなかったのですが、おおよそできている状態で楽譜を見せてもらって。その後、最後の部分がさらに足された形で楽譜が送られてきました。
茂木そんなやりとりを続けて、今年の5月に完成しました。
—『雲の記憶』の聴きどころを教えてください。
茂木『不思議な言葉でお話しましょ!』(2017年芥川作曲賞受賞作品)の時もそうだったんですが、やっぱりオーケストラ内での対話というのが一つのテーマとしてずっとあるので、今回の作品もそれを踏襲しています。それがもしかしたら聴きどころというか、もちろん、メインとなるのはソロのパートなんですけれども、それ以外の色んな楽器が、どうやってオーケストラ全体と絡んでいくのか、チェロとどういう風に対話をしていくのかというところで聴くと、おもしろいのかなと思います。オーケストラの中では使用頻度の低い楽器を使っているので、探しながら聴いてもらえると、おもしろいかもしれません。

—ソリストの視点から山澤さんはどのようなところが聴きどころだと思いますか?
山澤ドヴォルジャークのチェロ・コンチェルトのように、今回の作品にはチェロがメロディーを奏でる前半部分、カデンツァを一人で引いて、その後オーケストラの音響の核となるような後半部分があります。特に後半部分はチェロが時にオーケストラに対して影響を結構及ぼすような関係になっていきます。たとえば、チェロがクレッシェンドしたらオーケストラもそれに反応するというように。そのあたりをうまく表現できるといいな、と思っています。
—ちなみに、茂木さんはチェロを弾いたりはするんですか?
茂木作品のメインにしたい楽器はできるだけ触るようにはしています。チェロはほとんど弾けないんですけれど、学生の時に少しですが経験していたので、今回書く時もこっそり弾いたりしました。でも素人なので、逆効果でもあるなと思いました。難しいと思っていても、プロは簡単にできてしまうところもあるので。だからどこまでが可能なのか不可能なのか、逆に考えすぎてしまいます。
山澤今回は、結構ぎりぎりのラインを攻めているかな。でも曲が完成する前に会った時には、どうしても弾きにくいところがあって、そこは変えてもらうように話をしました。作った人の意図を直接聞けば分かるのは凄いことですよね。
—これからの新しい音楽を、演奏家として作り手としてどのように関わっていきたいと思いますか?
茂木本当のところは、どこまでが「現代音楽」か、あるいはどこまでが「古典」なのかというものは案外あいまいだなと感じています。調性感があれば現代音楽じゃないのか、無調だったら現代音楽なのか、そういうのもなかなか判断しづらいと思います。書き手としては現代音楽を書いているという感じではなく、この手法みたいなものがこの作品には必要だから、こういう風にしている、というだけなんです。クリエイティブなものというか、今までなかったものを次の世代に、と活動されている方もいますけれども、自分は新しいものというよりは、自分が今の段階で書きたいもの、このテーマだったらこういう風に書く、表現したいものをこういう風な形で出していきたい、というのが一番にあります。それが、結果として新しい表現であったり、次の世代に影響を与えるものであれば嬉しいです。
山澤ちょっと違うかもしれないけども、僕は新しい音楽ではプログラミングが重要かなと思っています。プログラムに現代曲を上手に組み込んでみたり。新しい音楽ばかりを集めるコンサートももちろんありますが、クラシックと20世紀の音楽を組み合わせて、お客さんが興味を持つようなプログラムを組むというのがすごく重要なことだと演奏家としては思っています。
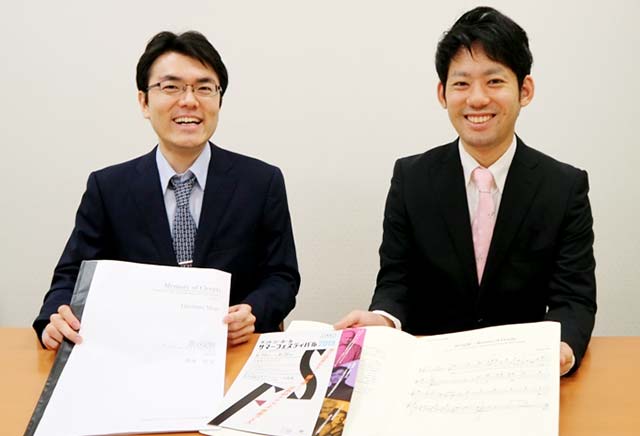
茂木ある時期クラシック音楽がもっと解放に向かっていたのが、現代音楽というジャンルによって、どこかで逆に内にこもるようになってきてしまったところがあるように感じています。もちろんヨーロッパなどでは、またそれが解放に向かっているのかもしれないですけど、日本、あるいは日本だけではないかもしれませんが、文化的な背景も含めて、現代音楽というものが、どうしても内へ向かってしまってしまい、今ちょっと停滞しているのかなと感じることもあります。でも音楽ってもう少しラフなものだと思いますし、もちろん知識のある人たちはその知識で楽しめるし、知識がない人でもある程度のところは楽しめるんじゃないかな、と思っています。ベートーヴェン、モーツァルト、ブラームスとかの延長に、今の音楽があるというところが、どこか切れてしまったように感じます。それをもう一度今の新しい音楽も、昔からの流れの中で出てきたっていうのをわかってもらえると、もしかしたら、現代音楽アレルギーの人も楽しめるし、現代音楽とはこういうもの、と枠に入っている人たちも、もう少し自由に現代音楽というか、音楽そのものに戻ってこられるのかな、という気がします。だから、新しい音楽の演奏会に足を運んでもらいたい、生の演奏を観て、聴いて、感じてもらいたいと思います。
山澤もしかしたら僕ら世代よりもう少し上の世代かもしれないけれど、現代音楽だからと言って身構える人が少なくなっているというか、新しい音楽を弾くことを普通にとらえている演奏家が増えてきていると思っていて、その空気感がもっと一般的なものになるといいなと思います。
茂木そうですよね。元々興味がある人はもう言わなくても来るわけで。興味がないというか、まだこういう新しい音楽に触れたことのない人たちの耳にどうやって届けるか…… 以前、山形交響楽団の方々に自分の作品を演奏していただいた時、小学生くらいの男の子がすごく自分の作品を良かったと言ってくれたことがありました。その時に思ったのは、あまり年も経験も関係なく、大人が「なんか難しいなあ」って言うと、子どもも「こういうのって難しいっていうんだ」という風になっちゃうのかな、と考えてしまいました。だから、アウトリーチなどを通してもう少し現代作品に対しての裾野を広げるための企画や活動を続けていくことも必要かもしれませんね。
—ありがとうございます。8月31日の演奏会、楽しみにしております!
候補作品作曲家のメッセージ
- 1)
- 候補作品作曲の経緯と聴きどころ
- 2)
- あなたにとって「音楽」とはどのような存在ですか?
鈴木治行

- 1)
- 作曲の経緯は、2017年秋に、京都フィルの音楽監督である齋藤一郎氏に新作の委嘱をいただいたということです。聴きどころは、同じことをいつも言ってる気がするけど、記憶の中に刺さった棘と棘の間に結ばれる関係性の糸を、聞き手一人一人に編んでいただくということでしょうか。
- 2)
- 身近にあるのが空気のように当たり前になっている一方で、ふと気づいて何気なく凝視してみる。するとその度に意外な一面を発見するので、一生飽きることがない。そんな存在。
稲森安太己

- 1)
- 候補作品『擦れ違いから断絶』は、エッセン・フィルハーモニーホールの委嘱でNOW!現代音楽祭で初演するため、ストゥディオ・ムジークファブリークのために作曲されました。層状に折り重なったリズム構造と、楽器の演奏行為の強調を通したパフォーマンス要素が聴きどころです。
- 2)
- 音楽は私の人生に節目を作りました。人生で経験する様々な価値を音楽から学びました。作曲を通していろいろな経験をしました。人の曲を聴くことで好奇心を刺激されました。未知のものへの好奇心が強いので、あっと驚かせてくれる音楽に出会うとき、知らない世界を探って行く作曲という道の尊さを感じます。
北爪裕道

- 1)
- 候補作品は、留学していたパリ音楽院の卒業作品として制作。音楽院にはディスクラビア(ヤマハの自動演奏ピアノ)が1台ありましたが故障していました。各所に交渉の末、この曲の初演に間に合うように急遽新しいものを購入してもらえることになりました。また器楽と共演させる協奏曲は前例がないようだったので、制御方法を考え諸問題の解決に試行錯誤しながら演奏プログラムを作成、技術面でも大変でしたが充実した制作過程でした。その後、私の演奏プログラムは他の作曲家の作品上演にも使用されています。
- 2)
- 当初、いちばん正体のわからないものに思えたので音楽を、特に作曲を学ぶことにしました。いまでも、最終的にロジックだけではつかみ切れないようなところに魅力を感じます。また音楽をある種の言語と考えると、それが古今様々な人の感性を渡り歩いてきたことが成り立ちの中に感じられて、その奥行きにひきつけられます。














