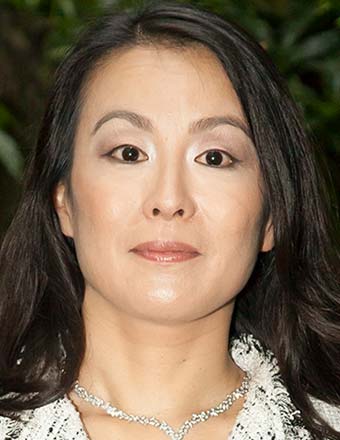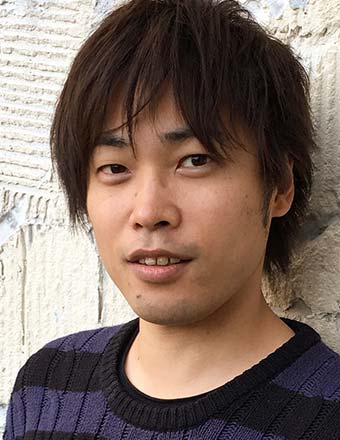8/26(日) 15:00開演(14:20開場)大ホール
第26回芥川作曲賞受賞記念サントリー芸術財団委嘱作品
- 渡辺裕紀子(1983- ):『朝もやジャンクション』(2018)※1世界初演
第28回芥川作曲賞候補作品(50音順/曲順未定)
- 岸野末利加(1971- ):『シェーズ・オブ・オーカー』(2017)※2
- 初演=2017年6月9日 東京オペラシティ コンサートホール Music Tomorrow 2017
指揮:ローレンス・ レネス 管弦楽:NHK交響楽団 - 久保哲朗(1992- ):『ピポ - ッ - チュ』〜パッセージ、フィギュア、ファンファーレ〜 (2017)※3
- 初演=2017年6月2日 東京藝術大学奏楽堂 藝大21 創造の杜2017「藝大現代音楽の夕べ」
指揮:ジョルト・ナジ ヴァイオリン:山本佳輝 バス・クラリネット:佐藤芳恵
テューバ:池田侑太 ピアノ:奥村志緒美 管弦楽:藝大フィルハーモニア管弦楽団 - 坂田直樹(1981- ):『組み合わされた風景』(2016-17)※4
- 初演=2017年5月28日 東京オペラシティ コンサートホール
2017年度 武満徹作曲賞本選演奏会
指揮:カチュン・ウォン 管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
- 候補作品演奏の後、公開選考会(司会:伊東信宏)
- 選考委員:鈴木純明、野平一郎、菱沼尚子(50音順)
- 指揮:杉山洋一※1 ※2 ※3 ※4
- ヴァイオリン:山本佳輝※3 バス・クラリネット:佐藤芳恵※3 テューバ:田村優弥※3 ピアノ:奥村志緒美※3
- 管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団※1 ※2 ※3 ※4
- 協力:(一社)日本作曲家協議会、(一社)日本音楽著作権協会、日本現代音楽協会
■料金
- 指定 2,000円/学生 1,000円
| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月10日(木)10:00〜5月16日(水) |
|---|---|
| 一般発売: | 5月17日(木)10:00〜 |
杉山洋一(指揮) インタビュー
作曲者プロフィール
写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。
出演者プロフィール
写真をクリックすると、プロフィールがご覧いただけます。
作曲ノート
渡辺裕紀子:『朝もやジャンクション』(2018)
人が持つ記憶について興味を持ち、近年作品を書いています。音が鳴っているその瞬間だけでなく、頭で作り上げる段階から実際響いた後の残像、演奏家がその音を紡ぎだすために聞いて来たであろう過去の音の軌跡、また響き一つ一つに宿る長い歴史的関係性など、一つの作品に対し、時間軸が放射線状に広がっていくイメージを持っています。その中でも、今回は自身の過去にのびる時間軸に魅力を感じ、そこに焦点を当ててアプローチしました。
『朝もやジャンクション』では、生活の中のごく個人的なもの、ふとした瞬間を題材として扱っています。そこにある時間は自身の日々であり、私の感覚そのもので、生きるしるしのようなものです。
これら集められた瞬間は、所謂「美しいもの」とは何故かかけ離れていることも多く、時に人工的であったり、人が意識しないようなごく普通の風景であったりします。自分でも説明できないものも多くあります。ただ不思議なことに、創作過程でその風景を掘り下げていく中で、幼少期の思い出や、母のお腹の中にいたときの感触であったり、忘れていた昔の自分自身に出会うことがあり、過去と未来を行き来するように、思いがけず記憶の旅をすることになりました。
幾つかの音風景の中でも、タイトルの一部にもなっているジャンクションは、2016年に訪れたエジプトの街の音風景に関係しており、作品の核を担っています。鳴りやまないクラクションと信号のない道で突っ走る車、その間をすり抜けていく人たち。混沌とした街と、公共電波で定期的に流れるコーランの朗唱。物凄い力強さと繊細さが絶妙なバランスを保っており、そこでの体験は、その後も忘れられない記憶となって私の心に刻まれています。
2018年5月28日
岸野末利加:『シェーズ・オブ・オーカー』(2017)
オークルの陰影
赤、オレンジ、金色、時には紫 - 燃え上がるような色彩を放つオーカーの層。
学生だった頃訪れた南仏ルシヨンで目にしたオーカーの鉱脈の光景は今でも忘れることができません。オーカーは赤土や黄土とよばれ、酸化鉄を多く含む色彩豊かな土です。
先史時代から人類はオーカーの持つ色に魅了され、世界各地で顔料や絵の具として、時には体に塗り、時には洞窟壁画のために利用してきました。
顔料が特定の波長を反射したり吸収した結果、そのスペクトルが人の目に特定の色と感じられるように、音の周波数成分が音色として私たちの耳に伝わります。
『シェーズ・オブ・オーカー』(オークルの陰影)では、律動や縦の響き、横への流れに加え、音の色合いとコントラストを作品の構成要素としています。私にとってオーケストラは、豊かな色彩と大きなエネルギーを生み出す母胎のようです。光の当たり具合、時間、角度の違いにより異なる印象を与えるオーカー層のように、絶えず様相を変化させながら展開していく音の有機体を生み出したいと思いました。
また作品を構築していくにあたり、土の粒子を思わせるビズビグリアンド(Bisbigliando, ほぼ同じ音高で音色の異なる音)の音群とグリッサンドを主な素材とし、20分強の時間のカンバス(画布)に、顔料を飛び散らせ、塗り付け、垂らすことにより、一種の絵画を描き上げたいと思いました。このジェスチャーは、様々な楽器の組み合わせやテンポの変化によって、拡大されたり縮小されたりしながら展開していきます。例えば鑑賞者が、離れたところからは全体の構成を、作品のすぐそばからはモチーフの細部の色合いや息づかいを楽しめるジャクソン・ポロックの作品のように、焦点を変えることにより素材が異なる趣や様相を持って浮かび上がってくる……。そんなイメージを念頭にこの作品を作曲しました。
(ケルンにて、2017年4月)
久保哲朗:『ピポ-ッ-チュ』〜パッセージ、フィギュア、ファンファーレ〜 (2017)
本作品はヴァイオリン、バス・クラリネット、テューバ、ピアノの4人のソリストグループとオーケストラ、打楽器の後面に配置される4人のオブリガートヴァイオリンによって構成される。ソリストグループはオーケストラ内でソリストとしての役割はもちろん、アンサンブルやオーケストラの一部としても機能し、オブリガートヴァイオリンはソリストグループの影としての役割を成している。
作品では時間をパラレル的に扱うことで、新たな時間感覚を得られないかを模索した。異なった時間軸を持つそれぞれのセクションは、一方向の進行ではなく並行するように配置され、多層的に織り込まれる。さらに上記の編成によって音楽内の視点は絶えず分散化され、多様なコンテクストが生み出される。各セクションは独立した時間・色彩・響きの中を生きながらも、互いに緩やかに干渉し合うことで統一的なフォルムを浮かび上がらせる。
坂田直樹:『組み合わされた風景』(2016-17)
多くの場合、楽器から発せられる音は混成的な成り立ちをしている。例えば、管楽器は必然的に楽音と同時に息音によるノイズを発生させる。また、弦楽器を演奏したときにも、うっすらとした擦弦のノイズが伴う。これら、ピュアな楽音を指向した際にも生じる(生じてしまう)噪音は何を意味しているのだろうか? これらは聴かれるべき“音楽”に対する、埃のような無視されるべき存在なのだろうか? 水と油のように対立する二つの音響が、実は一つの楽器の音のなかに同居していること。この事実に耳を傾けるとき、私は言い知れない美しさを感じる。そこには、ある宇宙観が示されている、そのようにさえ思われるのだ。
上記の直感は果たしてどのようなものだったのだろうか。『組み合わされた風景』ではこの問いかけを出発点として、性質の異なる音が混在する様子を見つめようと思った。考えを推し進めるなかで、先に述べた楽音、噪音に加えて、グリッサンドやインハーモニックな音響などを導入し、より多様な音の関係性へと視野を広げた。また、それらのあいだに対比を作るだけではなく、そこから調和的関係を引き出そうとした。20分の音楽のなかで様々な素材が生み出され、それらが相互作用を起こし、混成化が行われ、そして消え去っていく。そういった音の風景をオーケストラで描いてみた。