江戸モード大図鑑-小袖屏風にみる美の系譜-
1999年12月21日(火)~2月6日(日)
小袖の文様に視点を据え、野村コレクションの小袖の優品と、同時代の絵画資料によって、江戸時代のモードの展開とその多彩な表情を通覧していきます。全6章を江戸のモード図鑑をひもとくように構成します。

1999年12月21日(火)~2月6日(日)
小袖の文様に視点を据え、野村コレクションの小袖の優品と、同時代の絵画資料によって、江戸時代のモードの展開とその多彩な表情を通覧していきます。全6章を江戸のモード図鑑をひもとくように構成します。

1999年11月2日(火)~12月12日(日)
彦根藩三十五万石の藩主を勤め、徳川将軍家の篤い信頼をうけた名家、井伊家。その伝来の名宝を通じて、近世大名が収集し守り伝えた日本の美と、近世大名の文と武の幅広い営みの様子をご紹介します。

1999年9月14日(火)~10月24日(日)
信貴山朝護孫子寺が所蔵する国宝「信貴山縁起絵巻」を一巻ごとに、巻頭から巻末まで通して、特別に公開します。日本絵画史が生んだ最も洗練された絵巻の醍醐味を、心ゆくまでご鑑賞ください。

1999年7月20日(火)~9月5日(日)
弥生時代から現代に至るまでの日本のガラスの発展過程を検証すると同時に、今日生起している急激な変化を認識し、21世紀に向けてのガラス芸術の可能性をも探ろうとするものです。

1999年6月1日(火)~7月11日(日)
本阿弥光悦が生み出した芸術性あふれる作品と、共に同時代を生きて豊かな創作活動を行った俵屋宗達とその一派の作品を一堂に陳列し、その後の琳派の流れの礎を築いた彼らの芸術に迫ります。

1999年4月13日(火)~5月23日(日)
サントリー創業100周年記念展の第一弾として、所蔵品の中から名品を厳選し、皆様にご覧いただくものです。生活の中で培われ、守られてきた、日本古来の伝統美の素晴らしさをご堪能ください。

1999年1月26日(火)~3月22日(月)
国立モスクワ東洋美術館が所蔵する18~20世紀前半に制作された染織品、装身具、絨毯、金工品、陶磁器などの工芸品を一堂に展示します。シルクロードを彩る鮮やかな色彩、大胆な意匠をお楽しみください。

1998年12月4日(金)~1月17日(日)
1988年の第一回展以来、推薦や公募、推薦と公募の併用と展覧会の形式を変えながら、現代造形芸術の様々な展開を紹介してきたサントリー美術館大賞。10年目となる第八回展です。

1998年10月21日(水)~11月24日(火)
漢字の成り立ちを伝える甲骨文、碑拓法帖のほか、中国の文人たちによる優品と、空海、最澄のほか、小野道風、藤原佐理、藤原行成らをはじめとする日本の能書の代表作品を一堂に展観します。

1998年9月1日(火)~10月11日(日)
この展覧会は、日月すなわち日輪と月輪が描かれた絵画や、太陽や月をかたどった工芸を一堂に展示し、日月が芸術の世界でどのように表現されてきたかをさぐろうとするものです。

1998年6月30日(火)~8月9日(日)
本展覧会は、初代長次郎に始まり十五代吉左衞門に至る樂家歴代の作品に、樂家と縁の深い本阿弥光悦、田中宗慶らの代表作品を加えて一堂に展示し、樂陶芸の全容を展観するものです。

1998年4月28日(火)~6月21日(日)
クリーヴランド美術館の東洋美術の所蔵品から、平安・鎌倉時代の仏画をはじめ、江戸時代の風俗画にいたる日本絵画の名品を中心とし、中国、韓国、インドの作品併せて100点を選りすぐり展示します。

1998年3月10日(火)~4月19日(日)
「嚢物」とは、たばこ入・筥迫・鏡入などの総称です。近世風俗資料の優品を集めた「百楽庵コレクション」を通して、自由かつ機智に富んだ発想と豊かな江戸の遊び心に迫ります。

1998年1月27日(火)~3月1日(日)
この展覧会は、動物が描かれた絵画を中心に展示し、動物が芸術の世界でどのように表現されてきたかをさぐろうとするものです。動物表現のこれからの可能性や、人間と動物との幸福な関係を見つめます。

1997年12月2日(火)~1月18日(日)
子どものいる情景を描いた絵画や書物、子どもたちが眺め、読んだ絵巻や絵本、節句人形や疱瘡絵を始めとする祝いや祈りの品々、玩具、菓子などを集め、「子どもの領分」をみつめなおした展覧会です。

1997年10月7日(火)~11月24日(月)
三種の神器の一つ、草薙の剣を御神体として祀る熱田神宮。無類の質と量を誇る刀剣をはじめ、所蔵される宝物は約4000点余にのぼります。本展では、これらの名宝より厳選した100余点を一堂に展示いたします。

1997年8月12日(火)~9月28日(日)
現代グラスアートの第一人者であり、アメリカ初の「ナショナル・リヴィング・トレジャー(人間国宝)」としても著名なデイル・チフーリ氏(1941-)。チフーリ芸術の全貌を紹介する、日本初の本格的な展覧会です。

1997年6月10日(火)~7月21日(月)
小林一三のコレクションを収蔵した逸翁美術館の所蔵品は、茶道具や蕪村・呉春を中心とした文人画に特色が見出せます。その5000点余におよぶコレクションの中から100点を厳選してご紹介いたします。

1997年4月22日(火)~6月1日(日)
メキシコ太平洋岸に展開するナヤリ・ハリスコ・コリマの三州における紀元前2世紀から紀元後6世紀にかけての副葬品を中心に、メキシコ西部地域に生きた人々の日常生活にまつわる、土の造形文化をご清覧ください。

1997年2月25日(火)~3月30日(日)
幕末を代表する奇想の画家、浮世絵師・歌川国芳。その生誕200年を記念し、鈴木重三氏を監修に迎え、国内外のコレクションから可能な限り良質の版画作品と挿絵本、260点余の優品を一堂に集めて紹介します。

1997年1月4日(土)~2月16日(日)
桃山の文化は、絢爛豪華で多彩なものでありました。当時の典型的な大画面の屏風を中心に、その原型となった作例や、江戸時代以降の展開を表す作品も視野に収めて一堂に展示し、近世の闊達な美意識の再現を試みます。

1996年11月12日(火)~12月23日(月)
異なる領域を自由に横断・結合する本展は、「工芸」と「現代美術」の枠組みをこえ、素材に潜む「美」の可能性を探る真摯な試みを重ねてきました。歴代の受賞者をはじめ、新たに制作を依頼した18作家の作品を展示します。

1996年9月24日(火)~11月4日(月)
明治23年(1890)、帝室技芸員制度は画家・工芸家の窮状を救い、美術工芸を奨励することを目的に設置されました。帝室技芸員たちの代表的作品を通して、当制度の歴史と、近代美術史上に果たした役割を振り返ります。

1996年7月31日(水)~9月16日(月)
今日、寺院が宝物公開によって維持されることは一般的ですが、元禄七年の法隆寺出開帳は、まさにその先駆でありました。本展では、国宝「観音菩薩立像(夢違観音)」を中心に、当時の出開帳を可能な限り再現いたします。

1996年6月4日(火)~7月14日(日)
本展は、NHK大河ドラマ「秀吉」の関連企画として開催され、秀吉の生涯を肖像画や自筆書状、戦国合戦図を交えて辿るものです。あわせて「黄金と侘び」という言葉に象徴される、桃山文化の精華をご紹介します。

1996年4月16日(火)~5月26日(日)
当館が35年間をかけて収集した作品の中から、当館の顔とでもいうべき名品の数々を展示いたします。初披露の重文「佐竹本・三十六歌仙絵 源順」を中心に、屏風絵をはじめとした73点の優品をご清覧ください。
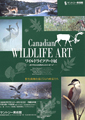
1996年2月27日(火)~3月31日(日)
雄大な自然とそこに棲息する野生動物を描くワイルド・ライフ・アートは、自然環境保護運動を巻き込んだ、ある種の社会芸術運動ともいえます。カナダにおけるその活動を、5人の画家の作品約100点によって紹介します。

1996年1月4日(木)~2月18日(日)
東洋陶磁の伝統的技法をもとに、自由な精神に溢れた陶芸を創作した人間国宝、石黒宗磨(1893-1968)。陶芸作品約160点に加えて、宗磨が心を注いだ書画約10点を展示し、宗磨芸術の神髄に迫ります。

1995年10月31日(火)~12月17日(日)
ベル・エポック─よき時代─ともよばれる、1900年前後のヨーロッパ。当時を彩ったエミール・ガレのガラス作品75点と、トゥールーズ・ロートレックのポスター37点による、光と色の芸術をお楽しみください。

1995年9月15日(金)~10月22日(水)
「影絵」の世界には、近代的感覚と古代以来の感情が併存しています。幕末から明治中期に残された「影」の作品や、江戸時代の「幻燈機」「写真鏡」など170点余によって、十九世紀の「影絵」と「映像」の諸相を再現します。

1995年8月5日(土)~9月10日(日)
本展は、NHK大河ドラマ「八代将軍吉宗」と連動して、吉宗個人の愛用品や絵画等をはじめ、当時の文化・風俗・生活をしのばせる美術工芸品、歴史資料など約200点を展示し、吉宗の人間像とその時代を外観するものです。

1995年6月13日(火)~7月30日(日)
近代ヨーロッパのガラス工芸はヴェネチアで13世紀頃から発達し、17世紀には王侯貴族の要請のもと、ボヘミアをはじめとするヨーロッパ各地に伝わりました。主に17世紀から19世紀の作品、約200点をご紹介します。

1995年4月18日(火)~5月28日(日)
高台寺は、豊臣秀吉の夫人北政所(ねね、秀吉没後出家し高台院)が秀吉の冥福を祈り、自らの菩提寺とした禅寺です。高台寺霊屋の修復落慶を記念して、高台寺蒔絵の名品をはじめとする寺宝約140点を、一堂に公開します。

1995年2月21日(火)~4月9日(日)
平成6年に開館したサントリーミュージアム〔天保山〕の開館記念展、「美女100年─ポスターに咲いた時代の華たち」のテーマを引継ぎ、同館の収蔵品から、女性を描いた欧米のポスター約90点を厳選して展示します。

1995年1月4日(水)~2月12日(日)
近年、当館は中世美術の分野でも収蔵品が充実してきております。本展では当館のコレクションのうち、鎌倉から室町を中心とした中世美術に光をあて、絵画・漆工・陶磁・金工にまたがる作品約80点をご紹介します。

1994年11月1日(火)~12月25日(日)
第6回目を迎えたサントリー美術館大賞展ですが、公募部門には前回を大きく上回る、500点をこえる力作が寄せられました。大賞に決定した佐藤邦生氏の「含蓄丸」をはじめ、豊かな現代造形の数々をご覧ください。

1994年9月6日(火)~10月16日(日)
縄文時代から近世にいたる女神を表した彫刻や絵画の名品約120点を展示し、美術作品から日本の女神信仰の歴史をたどる初めての展覧会です。生み出した時代の理想の女性像たる、女神たちの美をお楽しみください。

1994年7月12日(火)~8月21日(日)
沖縄の風土と自然が育んだ誇るべき生活芸術のうち、中でも琉球漆器は、紅型とともにその代表といえるでしょう。浦添市美術館の多彩な琉球漆器のコレクションに加え、当館所蔵の紅型をあわせて展示いたします。

1994年5月17日(火)~7月3日(日)
極めて絵画的な技法である、「色絵」。伊万里、九谷、鍋島など全国各地の窯が生んだ個性的な美、そして京都における野々村仁清、尾形乾山による洗練された雅陶の意匠を、当館所蔵の作品70点余を通じてご清鑑ください。

1994年3月29日(火)~5月8日(日)
国立民俗博物館所蔵の「野村コレクション」を中心に、国内外に所蔵されている「小袖屏風」の全貌を初めて展観し、染織資料を加えて同コレクションの精髄を紹介するとともに、近世染織芸術の華麗な流れを通観します。

1994年2月15日(火)~3月21日(月)
菱川師宣は、肉筆画、一枚摺の作品、版本という浮世絵特有の表現スタイルを確立し、多くの弟子を教育して菱川派を形成しました。その没後300年を記念して、師宣の画業の展開と、菱川派の近世絵画における特質を探ります。
1994年1月5日(水)~2月6日(日)
豊かな主題と色彩をもって、人々の生活空間を華やかに飾ってきた屏風絵は、当館の絵画コレクションの柱でもあります。収蔵品のうち、重文「四季花鳥図屏風」を中心に、関連の深い絵巻作品もあわせてご覧ください。

1993年11月23日(火)~12月26日(日)
平安末期に、奥州藤原氏が築いた平泉の優美な黄金文化。中尊寺金色堂の堂内諸仏をはじめ、国宝・重要文化財を中心に公開し、平泉文化の全貌を展観するとともに、東北の仏教文化をあますところなく紹介いたします。
1993年10月12日(火)~11月14日(日)
能楽が式楽に定められた江戸時代、謡本の出版が盛んとなり、謡曲は尾形光琳をはじめとする多くの芸術家に影響を与えました。中世から近世にかけての能楽や謡曲の展開および、絵画・工芸作品の意匠との関わりを探ります。
1993年8月31日(火)~10月3日(日)
西鶴没後300年を記念して、その業績を自筆色紙・短冊・版本などの資料で回顧し、さらに背景となった元禄文化の名品を紹介します。また特別出品として、幻の西鶴作品「色里三所世帯」の現存唯一の完本が里帰りいたします。
1993年7月13日(火)~8月22日(日)
古来、日本人は四季折々の風物を愛でては酒を酌み、また婚礼や元服などの儀礼でも、酒盃を傾けて人生の節目としてきました。当館の所蔵品の中から、日本人の美意識が反映された酒器の名品を展示いたします。
1993年5月29日(土)~7月4日(日)
「描かれた日本の姿」に焦点をあて、300年にわたるヨーロッパ古地図の歴史を、世界初公開の作品を含む120点余によって展観します。桃山から江戸時代にかけて制作された「地図屏風」、全8点とあわせてご清覧ください。

1993年4月13日(火)~5月23日(日)
本展は、アンコール遺跡救済事業の一環として企画され、平山郁夫氏ご夫妻のコレクションから厳選した作品をご紹介するものです。カンボジアを中心に、その周辺諸国の絣が一堂に展示されるのは、我が国で初の試みとなります。
1993年2月16日(火)~4月4日(日)
第5回を迎える当展には、海外からの応募が半数を数える、460点をこえる作品が寄せられました。大賞展への入選作品とあわせて、シャトーベイシュヴェル国際現代芸術センターへの招待作家5氏の作品を展示します。

1992年12月22日(火)~2月7日(日)
聖徳太子が建立した日本最古の官寺、四天王寺。その開創1400年を記念して、四天王寺所蔵の国宝6件、重要文化財20件を含む寺宝の数々に加え、聖徳太子にゆかりの深い寺院の収蔵品など、約390件が一堂に会します。

1992年10月31日(土)~12月13日(日)
ワーグナーの肉筆による楽譜や手紙、肖像画、カリカチュア、身の回りの品々など、バイロイト・リヒャルト・ワーグナー博物館よりオリジナル資料の数々を招喚いたしました。ドイツ国外では初の規模と内容の展覧会となります。
1992年9月8日(火)~10月18日(日)
いつも人々とともにあった、「生活の色」である「藍」。本展では、当館の染織コレクションから、「民衆の藍」を代表する「筒描」と「こぎん」、80余点をご紹介します。「筒描」コレクションは、今回が初公開となります。
1992年7月21日(火)~8月23日(日)
当館の開館以来、収集されてきたガラス器の中から、優品約110点を厳選して展示します。日本・ヨーロッパ・中国のガラスに、近年コレクションに加わったエミール・ガレの作品など、多彩なガラスの美をご清鑑ください。
1992年6月9日(火)~7月12日(日)
長谷川等伯と能登、久隅守景と加賀、俵屋宗雪およびその画系に連なる画家たちと加賀の地とは、切っても切れない関係にあると言えるでしょう。加賀・能登の風土と社会が、彼らの画業にいかなる影響を与えたかを探ります。

1992年4月25日(土)~5月31日(日)
本展は「NHKスペシャル・正倉院を撮る」の関連企画として、正倉院の故郷を中国に求め、中国出土の金・銀・ガラスの名品120点余と、NHK撮影のハイビジョン映像とによって、日中文化交流の様相を展観するものです。

1992年3月15日(日)~4月19日(日)
芸能の伝統の中で形を磨かれ、洗練されてきた舞う姿・踊る形は、絵画の世界においても、常に魅力的な題材であり続けました。中世から近世にかけての舞踊図を一堂に集め、舞踊や芸能の変遷と美術との関わりを探ります。
1992年2月8日(土)~3月5日(木)
本展では「絵と器」を二つの柱に据え、最近5年ほどの間に加わった新コレクションを中心として、約60点を展示します。「生活の中の美」というテーマを大切に、そしてより自由に展開してゆく当館の姿をご覧ください。

1991年12月25日(水)~2月2日(日)
当大賞展は従来、ノミネート方式によって作家に制作を依頼していましたが、4回目となる今回、開館30周年を記念して公募形式に変更いたしました。寄せられた作品424点の中から、入選作品40点をご紹介します。
1991年11月16日(土)~12月15日(日)
モーツァルトの没後200年を記念して、ヴィーン楽友協会、ザルツブルク国際モーツァルテウム財団が所蔵する貴重な資料の数々が初来日いたします。目前によみがえる、天才の生涯の軌跡をお楽しみください。

1991年10月3日(木)~11月8日(金)
陶磁器20点、木工品10点、浮世絵等の影響を受けた絵画作品20点、現代画家の作品15点をはじめとする約100点を通して、17世紀から現代にいたるオランダ美術の歴史に見出せる、日本の影響の足跡をたどります。

1991年7月30日(火)~9月16日(月)
パリ装飾美術館の所蔵する膨大なコレクションの中から104点を選出し、19世紀から現代にいたるフランスのガラス工芸の流れを概観します。中でもアール・ヌーボーと象徴主義の作品群は、本展の中心と言えるでしょう。

1991年6月12日(水)~7月8日(月)
かざりの機能、動機や目的に着目し、〔荘厳・祭祀・装身・調度〕という4つの柱を設けました。平安から江戸後期にかけての工芸・絵画等の代表作を一堂に集め、「かざる」という行為のさまざまな様相を探ります。

1991年4月24日(水)~6月2日(日)
当館の開館30周年記念を祝して、「梅・柳に遊禽図」「竹に虎図」「籬に草花図」などの金碧障壁画を中心に、妙心寺天球院伝来の名品を展示いたします。桃山の障壁画様式が最終的に到達した美の様相をご清覧ください。
1991年3月5日(火)~4月14日(日)
3縄文時代から現代にいたる長い歴史を持ち、その素材も技法も極めて多様である日本の浮彫は、実に多彩な内容を形成しています。国宝6点をはじめとする日本の代表的な浮彫の名宝、約80点を一堂に集めて展観します。
1990年12月18日(火)~1月27日(日)
大著「日本誌」で高名なエルンスト・ケンペル(1651-1716)は元禄3年(1690)に来日し、日本の文化と歴史を初めてヨーロッパに紹介しました。ケンペルが持ち帰った資料を中心に、彼の業績を振り返ります。
1990年10月30日(火)~12月9日(日)
工芸と美術の境界に対して問題を提起し続けた当展も、3回目を迎えました。大賞を受賞したマリア・ルゴッシー氏の「Ocean」をはじめ、現在最も活躍のめざましい16名の造形作家による新作の数々をご清覧ください。

1990年9月4日(火)~10月14日(日)
ロシアが生んだ大作曲家、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー。自筆譜や作曲手帳、実際に使われた指揮棒など、ソ連の国境を初めて越える貴重な資料で、チャイコフスキーの生涯を生き生きと再現します。
1990年7月10日(火)~8月26日(日)
キャンベル美術館はキャンベル・スープ・カンパニーによって創設された、食器の一大コレクションを有する美術館です。コレクションの柱であるスープ入れやスープ皿など82点による、日本で初めての展示となります。
1990年5月29日(火)~7月1日(日)
ビザンチン芸術の輝きを汲みながらも、素朴さと力強さを持ち合わせたブルガリア・イコン。アレクサンドル・ネフスキー寺院の所蔵品をはじめとする、12世紀から19世紀の代表的なイコン61点を、日本で初公開します。
1990年4月24日(火)~5月24日(木)
経験主義的なものの見方が広がった江戸時代、写生が重視されました。本展は1987年に当館で開催された「日本博物学事始─描かれた自然Ⅰ」を受け継いで、日本各地の名所風景を写し出した「真景図」の魅力を探ります。

1990年3月7日(水)~4月15日(日)
フィリップ・グランヴィル氏が世界中のポスターを蒐集し、その生涯をかけて築いたグランヴィル・コレクションは、1989年に当館に継承されました。4000点近い作品群の中から特に名品を選び、ご紹介いたします。
1990年2月3日(土)~3月11日(日)
伊達政宗が派遣した「慶長遣欧使節」支倉常長と、わが国の南蛮美術の紹介をテーマに、ヨーロッパ各地から遺品を集めて展示します。あわせて、仙台市博物館が所蔵する伊達政宗・慶長遣欧使節関連資料の数々をご覧ください。
1990年1月6日(土)~1月28日(日)
江戸時代は武家文化が花開いた一方、江戸を中心とする都市の庶民が豊かな生活文化を築きました。髪飾りや鏡台、手箱など、女性の身近に置かれた化粧具の数々を展示します。作品に注がれた、江戸の巧芸をご覧ください。