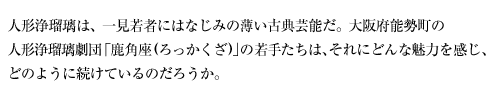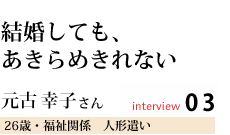
元古さんは、母娘二代鹿角座の一員だ。遠方に嫁ぐため、鹿角座を離れることが決まっている。でも離れることに「未練たらたら」で「あきらめきれない」。人形が好きで、もっと上手くなりたいと続けてきた。かつては、練習がもの足りないと思うこともあったという。
「(年上のメンバーには)かわいがってもらえるんですけど、私はもっと練習を詰め込んでいいんじゃないかと思っちゃう時があった。」

しかし、「人形が好き」という気持ちが、元古さんを鹿角座にとどめた。ここには、足遣いはこの人、主(おも=頭)遣いはこの人と、目標にする人形遣いがたくさんいる。「皆さんのいいところを見て、いつも技を盗んでる」という。それに、歳を経て、鹿角座の存在自体が面白いと思えるようになった。今は鹿角座で人形浄瑠璃に携わってきたことが「私の自慢」だと語る。
「私みたいな普通の人が人形浄瑠璃をやっていて、普通のおっちゃんとかおばちゃんとか普通の子が、こんな壮大なセット組んで、こんな地元パワーでやってるっていうところが魅力やと思う。」
また、地域に対しても昔と見方が変わった。学生の頃は交通の便が悪く、都会的でないのが不満だったが、今は「ないのがいいと思えるようになった」という。やめたい時期を乗り越えて、長く関わることで、活動にも地域にも見えなかった魅力が見えてきた。自分なりに、活動に対する愛着を持てたことで、離れても何とか鹿角座に関わり続けたいとい思えるのではないだろうか。

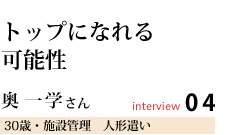
高校2年生の時、興味本位で鹿角座に入ったが、一生懸命なメンバーとの温度差を感じ、一年ほどでやめてしまった。4年前、偶然メンバーの家族と会い、何度も誘われるうち断りきれずに再開した。初めは裏方でと思っていたが、研修で訪れた国立文楽劇場で、人間国宝の吉田簑助師の演技に魅せられた。少しでも師匠に近付きたい、それが人形遣いを続ける原動力になったという。
「簑助師匠は一回倒れて後遺症も残っている中で、人形を艶やかに遣うんです。とんでもない人にぼくら教えてもらっているんだと気付きました。もちろん師匠に追いつくことはできませんけど、練習していれば少しくらい、あの表現に近付けるんじゃないかと思って。」

続けるうちに、人形浄瑠璃そのものにも興味が湧いてきた。3人で一つの動きを表現し、決まると一つになった感動がある。その三人一体の人形が何体もある、そこに太夫、三味線、お囃子、大人数揃ってひとつの作品を作り上げ、お客さんが分かってくれる、そしてわかってくれたことにまた感動できる、それは人形浄瑠璃ならではの魅力ではないかと奥さんはいう。
「鹿角座はアマチュアの中でもトップになれる可能性を秘めている」こう思うことで、志高く練習にむかいたいと奥さんはいう。
将来の鹿角座について尋ねると「(能勢の見所を聞かれた時)いつか6月の定期公演と言えるようになりたい」と夢を語ってくれた。自分にとっても地域にとっても、誇れる鹿角座にすることが大きな目標だ。

- 左:松田正弘さん(淨るりシアター館長)、右:中辻一平さん(舞台監督)

- 淨るりシアターでの練習
淨るりシアター館長の松田正弘さんは、鹿角座のプロデューサー的存在である。松田さんは、前館長の大内祥子さんとともに、新しく開館するホールを「淨るりシアター」として方向付け、能勢の人形浄瑠璃を育ててきた一人だ。
人形浄瑠璃は始めて十年ほどだが、メンバーには、次の時代に伝える地域の財産と考えてほしいという。恵まれた環境を当たり前と思わず、意識を高くもってほしいと叱咤激励する。「地域住民がプライドを持てる浄瑠璃にしたい」という松田さんには、地域文化を担う気概が感じられる。
若手たちが、やりがいや芸を磨く楽しさを感じられるのは、一流の芸に触れられることも大きな要因だ。鹿角座は文楽座の重鎮から監修を受け、プロの人形遣いや太夫に直接稽古してもらえるので、芸の厳しさや技を磨く充実感を、肌で感じることができる。
実は、人形浄瑠璃を始めるために、能勢町の人たちは、文楽座の師匠たちに熱心な依頼をした。はじめはまったく相手にされなかったが、ようやく許可を得て、今にいたる。
一流の師匠たちの協力によって、立ち上げてすぐに、公演を行えるレベルにまで上達した。文楽座との結びつきは、鹿角座の強みだといえる。
たまたま人形浄瑠璃を始めたのかもしれない。しかし続けられたのは、能勢町の人形浄瑠璃だったからこそだ。
若手たちは、鹿角座にしかない人形浄瑠璃の魅力に少しずつ気付き、それをより良いものにすることに、情熱を傾けている。