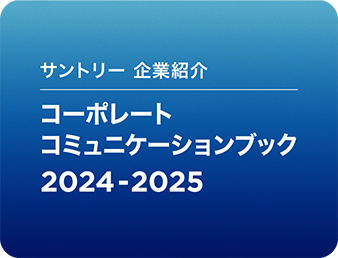ALCOHOL
元地方営業マンの情熱!? ビール界の新星・ビアボールはなぜ生まれた?
23.08.03
様々なフィールドで活躍するサントリーの社員=サントリアンにスポットを当て、「挑戦」をテーマにインタビューしていく特集企画。第4回目は、ビール市場に新風を吹かせた「ビアボール」の商品開発を手がけたサントリー株式会社ビールカンパニーマーケティング本部イノベーション部の佐藤勇介さんにインタビュー。
飽和状態のビール市場に向けて、サントリーが放った新たな一手。それが炭酸水でつくる自由なビール「ビアボール」です。「これまでにないビール」が完成したのは、ビールづくりにおいて柔軟な姿勢を持っているサントリーだからこそ。その誕生のきっかけは、飲食店への営業を担う現場の営業マンとしての経験でした。その担当者が佐藤勇介さんです。

相撲道、一直線。内定前夜にともに悩んでくれた採用担当
佐藤さん:会社員になるまでは、わんぱく相撲から始まり、大学まで相撲漬けでした。僕が活躍した日の夜はビールを片手に家族で勝利を喜ぶのですが、祖父も相撲をやっていたこともあって、いつもは口数が少ない祖父が陽気に、饒舌になるんです。
「よう頑張ったな」という言葉とともに、家族が瓶ビールを注ぎあって、笑いながら家族でワイワイと過ごす楽しい時間が幸せな景色として僕のなかにある。だから僕のお酒とは、分かち合う、称え合うもの、なんですね。

勢(いきおい)関や豪栄道関、妙義龍関と同世代の、角界「花の61年組」の佐藤さん。プライベートでは勢関の引退興行(2023年6月4日)を主宰
そこまで打ち込んだ相撲。卒業後の進路を角界ではなく、就職としたのはなぜでしょう。
佐藤さん:相撲に取り組んだ日々こそ、自分自身をつくった礎と思いました。ただその「佐藤勇介という人間」がどれほど社会で通用するのか、自分は「佐藤」を試したかった。もともと相撲は大学で辞めると決めていたし、そもそも挑戦や逆境が好き。ですから就職こそが、社会への挑戦の入り口でした。
サントリーを選んだのは、先輩の方々とお話をさせていただくなかで、「こうなりたい」「こうありたい」を応援してくれる社風を感じたからです。それと僕の採用担当者Oさんとの出会いが入社へ背中を押しました。
サントリーの最終面接の前に、他社の内定をもらっていました。その状況はOさんにも伝えてありましたし、面接でも正直に話しました。そして「採用、おめでとう」という電話をいただいた。でも、それに続く言葉が「ぜひ、うちに」という勧誘ではなく、「(内定の会社とどちらを選ぶか)悩むよね」という僕の気持ちに寄り添う言葉でした。
その電話を受けたとき、祖父と一緒でした。「明日、連絡します」と電話を切りましたが、そのときはすでにサントリーに行くことを決めていた。Oさんの言葉が嬉しかったのと、祖父の向こうにビールがもたらす幸せな景色が見えていたのかもしれません。
がっぷり四つの営業スタイルから見えてきたもの
入社後、希望の営業に配属され、担当エリアは四国・中国地方だったそうですね。
佐藤さん:広島と岡山が担当エリアでした。入社した2009年からは広島で、家庭用飲料をスーパーマーケット中心に、2012年から5年間は、岡山で業務用(飲食店向け)を担当しました。
当時の上司から「営業とは担当エリアの『色』を変えるのがミッション。そのためには街を好きになれ」と、また「名前を残せ、道行く人から挨拶をされるようになれ」とも言われました。いかに自分を売るか、どうやって販売いただく酒販店様、飲食店様と付き合っていくか、がっぷり四つで取り組む必要がありました。

営業時代の佐藤さん。飲食店とがっぷり四つの付き合い
岡山での日々は佐藤さんをどう鍛えましたか?
佐藤さん:関わる方すべてが社会人としての先生でした。日々、叱咤激励の嵐……。皆様に育てていただきました。なかでも岡山市・倉敷市を中心に展開されている酒販店様の専務にはお世話になりましたね。
出会ったばかりのころ、商談後に「営業だったから爪ぐらい手入れしなさい」と注意されました(その後、すぐコンビニに爪切りを買いに行きましたが…)。「汚い手で、口に入れる商品を提案されて飲みたいか? 美味しそうに思うか? 少なくとも俺は思わない」「相手の気持ち、立場になって提案するのが営業。そんなことを考えられない営業とは仕事はできない」と。
この方からは、人の気持ちを考えること。そしてその気持ちを受けて自分はどう動くべきなのか――このことを徹底的に教えていただいた。僕ががっぷり四つに組みに行ったというより、専務が組んでくれたということになりますね。
2017年にイノベーション部(当時は前身部署の新商品開発グループ)に異動になり、岡山を離れる際は「オレが育てて、都会へ送り出した」「えらくなって帰ってこい」と、はなむけの言葉をいただきました(笑) 。
飲食店と寄り添い続けてきたからこそ生まれたビールの新しい形

異動されて、当初は営業との違いにとまどったのでは?
佐藤さん:サントリーを知ってもらい、街に浸透させる。そしてサントリーを好きになってもらう。新たな部署ではそれが岡山というエリアから全国規模になるだけ、そう考えて取り組みました。
ただ営業時代は自分一人で仕事が完結していましたが、今度は自分自身がハブとなって、営業や宣伝、広報といった各部署に仕事を委ねていかねばならない。とくに営業面では「自分ならこうする!」と自分が出てしまいそうになりましたが、こらえています(笑)。
岡山時代に得た「人を考え、どう動くのか」が生きていますね。その経験が、「ビアボール」のアイデアのきっかけと伺いました。
佐藤さん:営業方針でもある飲食店様のニーズを汲んで提案する、という営業スタイルを心掛け、いろいろなカテゴリの酒類をミックスして、全体の利益を拡大するような提案を行っていました。なかでもウイスキーやサワーは炭酸などで割ることでさまざまな提供方法があるので、在庫過多にならずお客様もいろんな楽しみをできる商品です。しかし、ビールは機材もいりますし、なかなかバリエーションのある提案ができませんでした。
当時から、ビールもウイスキーやサワーのように割るだけでできればいいのに……と、炭酸を使った新しい飲料を提案する方が現実的だと漠然と思っていました。

時代が追いついた!? 2年越しの思いが「ビアボール」

コロナ禍で人々のお酒に対する楽しみ方も変わりましたが、なにか影響はありましたか?
佐藤さん:「ビアボール」のアイデアは、2018年とその翌年にも会社に提案していました。ですが、いつも不採用。コストパフォーマンスも高いと判断していたのですが、このアイデアはあくまでも飲食店目線で、ご家庭で楽しむというお客様目線には立てていませんでした。
ただコロナによって風向きが変わったんです。自宅で飲む時間とつくる過程にこだわる「家呑み」の普及です。コロナは結果的にお酒に向き合う時間を育み、その変化は大きいものでした。
またビール市場は飽和状態にあり、新たな価値観の創出が不可欠でした。ビールは常に「もっとおいしい」を追求してきましたが、その結果「おいしいのは当たり前」になった。そんな市場に対して、味以外の訴求ポイントを提示しなければならない。新しい価値の創出は業界としても必要だったんです。
そうした流れのなかで、コロナ禍によってコスパ目線からお客様目線で「ビールを炭酸で割る」というアイデアを再評価するきっかけになった。これがブレークスルーになり、製品化へ進むことになったんです。

このアイデアを復活できたのは、上司が「ボツのアイデアを捨てなかった」ことにもあります。アイデアそのものはよくても、ひねりが足りない、時流に合わないということがある。そういったアイデアをもう一度チェックしてもらったときに、「ビールを炭酸で割る」というアイデアを練り直すチャンスをくれた。
つまり、ぼく自身が明確にできなかったニーズを顕在化することで、商品としての立ち位置も明らかになりました。失敗を単なる失敗にしない・させない。この会社の姿勢も「ビアボール」誕生の鍵になったと思っています。
2022年11月のデビューから半年、お客様からはどんな反応がありましたか?
佐藤さん:ビール好きが受け入れてくれたことが嬉しかったですね。とくに邪道とされる「ビールに氷」も意外にも受け入れてもらえましたし、割り方次第でお酒に強い方、弱い方を問わず飲んでいただける。飲み方の多様性が提案できたのはよかったと感じています。
また、ちょっと一口だけ飲みたいというときも、栓ができるので缶ビール、瓶ビールとは違い飲みきる必要がない。この「少し」という気持ちに寄り添える点も評価をいただいています。アルコール度数も量も自由に調整できる、使い勝手のいいビールになりました。
われわれメーカーとしては、お酒がおいしいだけでなく、飲む時間もおいしいことを提案しなくてはなりません。アルコール度数が低くても高くても、一定の美味しさを提供できる製品が実現したことで、メーカーとしての「お酒は美味しい、楽しい」という思いを伝えられる製品になったのではないかと思っています。

そして一番の魅力は1本のビアボールを分かち合って飲めること。お酒が強い人も弱い人も、瓶ビールのように同じ1本を分け合って楽しんでいただいていることは、僕にとって嬉しい光景です。
岡山時代、厳しく指導してくれた酒屋の専務から、「会ってないけど、いつも見てる」と言われます。それは今回のように取材を受けてメディアに出ている僕を見てくれていることに加えて、ビアボールという製品を通して僕を見てくれているからだと感じています。
将来ですか? ビアボールが息の長い製品になってくれて、それを孫と飲むのが夢ですね。
製品づくりのパートナー┃「SHIBAURA HORUMON HANARE」様との付き合い
「ビアボール」は、2022年1月から10か月間のテストマーケティングが行われました。その場所は田町にある居酒屋「芝浦ホルモンハナレ」。店主の金子幸生さんは佐藤さんをはじめとするスタッフを「とにかく熱い。やる気がある。真摯。当初からいまでもその姿勢は変わらないですね」と評します。
同店では、「ビアボール」発売前に月に1回、お店を貸し切って、提供方法の確認が行われました。その際にオペレーション面で「最初に炭酸を入れた方が、泡が落ち着く時間を短くできるとアドバイスしたのですが、素直にそれを受け入れるんです。サントリーほどの大企業が、いち飲食店のスタッフの言うことを真剣に聞いてくれている。こうした飲食店との向き合い方にも感動しました」

いつしかそんな熱さや、やる気が伝染し「僕らが頑張らないと、お客様に伝わらない」という気持ちに。同店のお客様の中心は40~50代の男性で保守的な飲み方をする人が多いため、お勧めしまくったそうです。
「ビールと違い、抜栓してからも保存ができること、また飲み放題メニューに組み込めるなど利点も多い」と金子さん。「ビールが苦手な人も濃さを加減できますし、薄くしてチェイサー代わりに、また最後の仕上げにと、いろんな飲み方をされていますよ」と常連さんに愛されている様子を語ります。
すでにアレンジレシピも考案されつつあるそうですが「うちのお客さんは変化球を嫌うので『普通が一番』とアレンジ飲みを受け入れないんです。でも『ビアボール』ほどの変化球はない(笑)。それでも味がいいからでしょうね、わずか1年あまりですでに『いつものお酒』になっています」

サントリー株式会社 ビールカンパニー
マーケティング本部イノベーション部
佐藤勇介┃さとう・ゆうすけ
1986年生まれ、大阪府出身。立命館大学を卒業後、2009年にサントリー株式会社に入社。営業部として広島や岡山などの中四国エリアの営業を経て、2017年にイノベーション部の前身部署である新商品開発グループに配属。「頂」や「金麦〈ゴールド・ラガー〉」に携わり、2021年4月よりイノベーション部で「ビアボール」を担当。