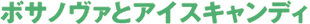
由紀さおりとピンク・マルティーニのコラボレーションに欧米が酔いしれている。なめらかな絹のようであり、また繊細で可憐なレース模様のような彼女の歌声は、国境を、言語を超え、人々の乾いたこころの壷を潤す。
テレビ報道で人気を知り、そのとき流れていた『マシュ・ケ・ナダ』が、ボサノヴァをアレンジしたボサ・ロックに出会った40年以上も前の小学5年生の夏休みを思いださせた。
高校生だった兄のレコード・ストックからドーナツ盤を無作為に選んで聴きまくっていた中に、ブラジル人の若いグループ、ボサ・リオの『サンホセへの道』があった。暑い日だったが、曲が流れはじめると涼やかな風が吹きわたるような心地になる。
「よし、もう一度、聴くぞ」と気合いを入れて、なぜかソーダ味のアイスキャンディを手にした。ペロペロとそれを嘗めながら聴き惚れる。いつの間にか腰を振りステップを踏んでいた。誰かが覗き見したならば、さぞや滑稽に思えたことだろう。
“サンホセへの道を知っていますか。わたしのふる里なのですが、長く帰っていないので道に迷うかもしれません。広々としてのびのびと生きられるサンホセでこころの平穏を取り戻したいのです。大都会での夢は塵となって消え去ってしまいました。気づいたら友だちもいなくなって、でもふる里には友だちがたくさんいます。サンホセへはどう行けばいいんでしょう”
ロサンゼルスで夢やぶれてサンフランシスコ湾南岸の故郷サンホセ(サンノゼ)へ帰る、といった内容の詩だ。中学生になり英語を学ぶと、歌詞の持つ意味が理解できるようになった。軽快なリズムなのに、随分と深い話だなと、えらく感銘したのを覚えている。
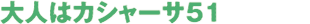
いまはカクテルの「カイピリーニャ」なんぞを飲みながら涼風を感じている。ブラジルの「カシャーサ51」というサトウキビの搾り汁からつくられる酒をベースにした“田舎者”という名のこのカクテルは、こころのサンホセへ誘ってくれる。
酒に詳しい人ならば、カシャーサはラムとどう違うんだ、と思うことだろう。これには昔のポルトガルとスペインの交易問題が尾を引いていて、ブラジル人にとってはスペイン統治にあったカリブの国々の酒と同じ括りで語るなということになる。「ラムではない。カシャーサだ」というのが彼らの言い分だ。日本での認知は遅かったが、世界的には極めてメジャーな蒸溜酒である。
カリブ生まれのラム、とくにホワイト・ラムはカクテル好きのアメリカ人に合わせて洗練されていった香味なのではなかろうか。酒好きの日本人でクセのある焼酎をロックで嗜む人は「カシャーサ51」の味わいを気に入るはずだ。カシャーサ・ロックを試してみることをすすめる。
辛口で荒々しい感じがするカシャーサの味わいは、クラッシュドアイスにライムと砂糖を加えた「カイピリーニャ」に生きる。これからの季節、ライムをグイグイつぶしながら冷えた液体を身体に流し込むといい。清々しい酸味に潜んだ甘さに生き返った気分になり、脳天を涼やかな風が駆け抜けると、こころに平穏が訪れる。
グラスにストローを添えたりするが、わたしはそんな上品なものはいらない。ぶつ切りのライムやクラッシュドアイスがボコボコ、ザクザクとラフな感じで入ったグラスを傾けると、氷が鼻にあたり、同時にライムの爽快な香りがフワーっと鼻腔をくすぐってくる。その感覚が大好きだ。
カクテルでは他に、「カシャーサ・リッキー」もさっぱりとした清涼感にあふれている。都会的なエレガントさを求めるならば「カシャーサ・サワー」。シェークしたレモンの風味が粋で、バーで「カイピリーニャ」ののどかさを堪能したあとにこのサワーをオーダーしたならばお洒落で格好いい。カシャーサの幅広い愉しみ方をよく知っている人だ。
『サンホセへの道』を聴いた夏、セルジオ・メンデス’66にも出会う。兄がアルバムを持っていて、ボサ・リオをプロデュースしたのがセルジオ・メンデスだと知った。アルバムの中にあったのが『マシュ・ケ・ナダ』で、この曲もアイスキャンディを嘗めながらステップを踏んだ。
彼はビートルズの『フール・オン・ザ・ヒル』や『デイ・トリッパー』などもボサノヴァ風にアレンジしていて、それが小学生には新鮮だった。
1964年のクーデターによる軍事政権樹立で、セルジオ・メンデスをはじめ多くのミュージシャンが圧制から逃れるためにブラジルを去った。結果的にこれがブラジル音楽、ボサノヴァを世界に広め、アメリカやフランスの音楽シーンに影響を与えることになる。
小学5年生の少年はそんなことは知らず、ブラジル人がアメリカの町を歌ったり、英語の歌詞だったりすることに疑問を抱くこともなく、酔いしれた。
いま、由紀さおりのおかげでボサノヴァに目覚める子供たちがいるかもしれない。子供の頃はアイスキャンディを嘗めながら、大人になったら「カイピリーニャ」を飲みながら聴きなさい、と教えよう。





















