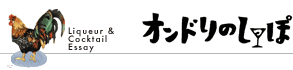先日、例によって気になっていたカクテルをまた試してみた。『ウイスキー・カクテル』という名前がついていてウイスキー、アロマチックビターズ(薬草を使った苦味酒)、シュガーシロップをステアする。ビターズとシロップを1ダッシュずつというのがどうも気にかかる。
ビターズボトルのひと振り、1ダッシュなんてわずか1ml、多くても2ml程度の液量である。これがウイスキーの隠し味として生きるものなのだろうか。
主役のウイスキーはスコッチやライまたはバーボンとある。ベースをいろんなブレンデッドスコッチ、ライウイスキー、バーボンで試してみた。
やはり、想像した通り、ほとんどがインパクトのないダレた味わいで、唯一「ジムビームライ」ベースの香味感覚がそれなりにゆるせるものだった。
ライ麦由来のドライでスパイシーな香味にビターズの苦味とシロップの甘さが溶け合い、みかん的というか柑橘類の甘酸っぱさに似た味わいがある。ただし純粋に美味しいとはいえない。
戸惑っているところに、仲良しのバーテンダーがさり気なく新たな一杯をつくってくれた。同じ「ジムビームライ」ベースだった。
味わいに厚みが感じられ、甘酸っぱさにふくらみがある。ビターズとシロップを2ダッシュずつにしたという。劇的な変化だった。これには納得した。
連載66回で「シカゴ」というカクテルを紹介した。そのなかで酒がいまのような洗練がなく、玉石混淆の時代にブランデーを美味しく味わうために生み出されたカクテルではないか、と述べた。「ウイスキー・カクテル」もまた同様かもしれない。少量のビターズのパンチとシロップの甘みを補うことで荒々しい酒を華やぎのある味わいに変えたのだろう。
それとビターズとシロップの液量がわずかに増えたことで美味しくいただけたのは、現代のビターズボトルの注ぎ口(穴)よりも大昔のそれは大きかったかもしれない、という推論もあり得る。昔といまでは1ダッシュの液量が異なっているとも考えられる。
これはあくまでも推察でしかない。酒が洗練されたいま、古いカクテルのなかにはレシピの数値をそのまま液量比として捉えてはいけないものもあるのではなかろうか。「ウイスキー・カクテル」が2ダッシュによって麗しくなったように、あくまで調合の配分感覚として捉えたほうがいいような気がする。
現代において昔の人たちが楽しんだ味わいを再現するのは難しいのかもしれない。とはいえ、「ようわからんなー」というのが本音である。

ベースを「ジムビームライ」で味わっていたら、ライ麦つながりで「ようわからん」ひとつの小説を思い出した。
アメリカの“青春小説の名作”と紋切り型で片付けていいのかどうかわからないが、いまでも人気の高い『The Catcher in the Rye(ライ麦畑でつかまえて)』である。
ジェローム・デイヴィッド・サリンジャー(1919−2010)が上梓したのは1951年。わたしが野崎孝訳でこの本をはじめて読んだのは1990年頃だった。すでに30歳を超えた読者であり、サリンジャー執筆時の年齢とほぼ同じくらいだった。
ウイスキーをはじめとした酒の文章を書く仕事から逃れられないことを自覚しはじめた頃で、ライ麦畑というタイトルならばライウイスキーに関することに多少なりとも触れているのではなかろうか、という単純な理由から手にしたのだった。わたしの場合、物語世界に浸るという読み方が当てはまらない場合がままある。そしてこのときは、名高い作品であるにも関わらず、まったく予備知識なんぞ持たないまま読みはじめたのである。
酒は作中にいくつも登場した。スコッチ&ソーダ、ラム&コーラ(キューバ・リバー)、トムコリンズ、バーボンの水割り、フローズン・ダイキリ。ところがライウイスキーの文字は見当たらなかった。
読みすすんでいくとフランシス・スコット・フィッツジェラルド(1896-1940)の代表作『グレート・ギャツビー』(1925発表)をフックとして話を導いている。
さらには、タイトルはスコットランドのロバート・バーンズ(1759−1796)の詞『ライ麦畑で出会えたら』のmeetをcatchに入れ替えたものだとわかった。バーンズのこの詞は日本では『故郷の空』と題して歌われ、他には『麦畑』、そしてオヤジ世代にはザ・ドリフターズが歌った『誰かさんと誰かさん』で馴染み深い。
ギャツビーにバーンズの詞。サリンジャーのこの小説は伏線がいっぱいあり過ぎて、なんだか「ようわからん」のであった。しかも、そもそもわたしが手にした意図がライウイスキー探しであったから、えらく醒めたこころで読んでしまったのだ。読後に、少年の社会体制や権威、訳知り顔の大人への嫌悪や反抗、と論評されているのを知っても、素直に頷けなかった。
たしかに論評の通りではあるが、いくらでも深読みできる罠がたくさん仕掛けられている。また詮索するのは読者の勝手であり、作者にしてみれば1940年代後半の自分の胸の内にあるものをひとりの若者の姿に変えて、興味をそそる物語として描き出しただけのことかもしれない。
そして「ウイスキー・カクテル」のグラスを傾けながら思うのだった。考案者にしてみれば、そのときにふさわしい味わいに仕上げただけのことである。
一杯のカクテルが、いろんな想いを巡らせてくれる。本を読むのと同じように、酒を味わうことは、とても楽しいものだ。