2010年3月27日(土)~5月23日(日)
※作品保護のため会期中、展示替をおこなう場合があります。
※各作品の展示期間については、美術館にお問い合わせください。
南蛮船がもたらしたヨーロッパの舶載品に憧れ、和ガラスの製造は「写す」ことからスタートしたと考えられます。まずプロローグでは、西洋のガラス製品にならったことを示す和ガラスや、製造に関わる資料などを紹介します。

藍色ねじり脚付杯
1口
江戸後期 18世紀後半~19世紀前半
神戸市立博物館蔵
(c)加藤成文

婦人職人分類 びいどろ師
喜多川歌麿
1枚
寛政年間(1789~1801)頃
神戸市立博物館蔵
(c)加藤成文
文献などをひも解くと、まず暮らしに取り込まれた和ガラスは、レンズ類や食にまつわる器が主流だったことが分かります。透明で熱に弱いガラスは、特に涼を呼ぶ宴の舞台に登場したことでしょう。
第1章では、食と宴の席に取り入れられていった、美しく涼やかなガラス器の数々をご紹介します。

色替唐草文六角三段重
1組
江戸中期 18世紀
日本民藝館蔵
さらに作品を表示

黄緑縞文徳利
1口
江戸中期 18世紀
サントリー美術館蔵
皿や盃ばかりでなく、次第に身を飾る装身具にも、ガラス製のものが登場します。「びいどろのかんざしむらのはで娘」(誹風柳多留・安永5年[1776])と詠まれたように、櫛・簪・笄といった和ガラスは、小粋な娘たちに人気があったようです。また、男性の装いに、ガラスの印籠や根付などがあらわれました。第2章では、洒落者にもてはやされた和ガラスを紹介します。

ビーズ飾り印籠袋・切子瓢形根付
1点
江戸後期~明治前期 19世紀
江戸ガラス館蔵
(c)加藤成文

ビーズ飾り魚文櫛
1点
江戸後期~明治前期 19世紀
びいどろ史料庫蔵
(c)便利堂
他にはない透明な素材のガラスは、文具や喫煙具といった、たしなみの場面でも活用されました。こうした嗜好性の強い和ガラスは、特に茶席に登場する機会が多かったに違いありません。ガラス製の茶壺や振出のほか、煙草盆や煙管なども見られます。第3章では、数寄者に愛された和ガラスをご紹介します。

切子 文具揃
1揃(8点)
江戸後期~明治前期 19世紀
サントリー美術館蔵
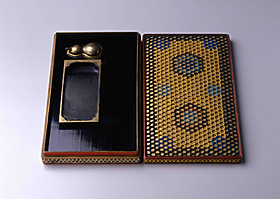
ビーズ飾り硯箱
1点
江戸後期 18世紀後半~19世紀前半
瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室蔵
涼をよぶガラスの素材感は、夏の花器や風鈴、金魚玉などに取り入れられます。また、芸を凝らした雛道具や、ガラス棒入り虫籠やビーズの吊灯籠など、さまざまな細工物が作られました。こうした日本の手わざを再認識させる和ガラスの中には、今では見ることのできないものも少なくありません。第4章では、目に愛らしい、遊び心一杯の和ガラスを紹介します。

金彩波頭文金魚玉
1点
文政3(1820)年
瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室蔵

ガラス棒入り虫籠
1点
江戸後期~明治時代 19世紀
瓶泥舎びいどろ・ぎやまん美術館準備室
※本サイト内の記述、画像の無断転載・転用を禁止します。