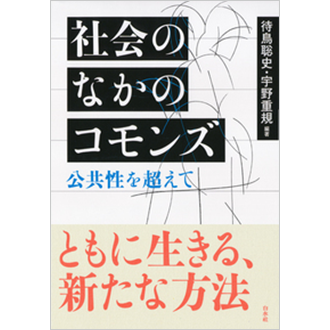2020年代のメタ公共性論へ向けて
谷口 功一 Koichi Taniguchi
2015年9月から足かけ4年、合宿も合わせると13回にわたって行われた通称「コモンズ研究会」が終了し、先日その成果を『社会のなかのコモンズ――公共性を超えて』(白水社)として刊行した。
政治学者の待鳥聡史さんの主宰する研究会だったため、わたしは「待鳥研」と呼んでいたが、田所昌幸・宇野重規・江頭進・苅部直・砂原庸介の各氏をメンバーとする豪華な顔ぶれの研究会では毎回活発な議論が行われ、また、安田峰俊・間宮陽介・松沢裕作・野口祐子・渡辺智暁・松本恭治・宮城大蔵・篠田英朗・遠藤乾、そして上記の本にも執筆者として加わった鈴木一人の各氏をゲストとして招いた研究会は、まさに豊饒な「知のコモンズ」とも言うべきものであったと言えるだろう(時おりふらりと姿を現す山崎正和・阿川尚之などの先生がたからの含蓄あるお話もこの研究会の楽しみのひとつだった)。
通常の研究会とは別に、メンバーの江頭氏が勤務する小樽商科大のある小樽での合宿も行われたが、旅の地での昼間の正式な研究会と夜半、ご当地のスナックでも延長されて行われた非公式の研究会は、実に思い出に残るものであった。ちなみに江頭氏を中心とする小樽市人口減少問題共同研究会による著作も、同じく白水社から刊行される予定であり、コモンズ研の成果は、その内部だけに留まらない外部とも有機的な連関と広がりを伴うものとなったのであった。
研究会はその名称が示す通り「コモンズ」という言葉(概念)にまつわる事象を各々の専門から緩やかで自由な形で論じ合うものであり、研究会はそれぞれの分野で第一線を走る研究者たちそれぞれの知見が融合する場でもあった。
本の副題に「公共性を超えて」とあるが、このフレーズは研究会の性質をよく表しており、そこでの議論の多くは「コモンズ」という概念を入り口にした、ある種の〈メタ公共性論〉であったようにも思われる。会の具体的な様子は、上記の書籍の中に収録された待鳥・宇野対談のパートに詳しいが(そして、本書を繙く時、まずはこの対談から読み始めることをお薦めしたいが)、所有権をはじめとする近代の制度への「窮屈さ」「しんどさ」を感じつつも、さりとて「公私があいまいな前近代」へと回帰する「誘惑」に乗るわけにもゆかず、そのような中で「過剰な負担を社会にかけないメカニズムをどうつくればいいのか」を様々に考え論じたのが、この研究会だったのである。
本書の中では「公共性論ないしコミュニタリアン的な自己犠牲の場でもないし、また前近代的な人格依存の世界でもない」場として「コモンズ」というものを措定し、各自の専門に基づき、入会・地方都市の商店街・住宅・先住民の保留地・政党・宇宙、そしてミートボール(?)などという具体的な事象を通じてコモンズのありようが議論されているのであった。
わが国において所謂「公共性論」を正面から謳ったものの嚆矢は、2000年に刊行された齋藤純一による『公共性』(岩波書店 思考のフロンティアシリーズの1冊)であったと記憶している。しかし、いつの間にか、それから20年近くの歳月が流れているのであった。この20世紀最末尾の頃と現代とを比較するなら、我々の政治と社会を長らく規定してきたリベラリズムやデモクラシーの状況も著しく変化しており、その点でも改めてメタな観点から「公共性を超えた」議論が必要とされるのではないかと思われるのである。
それ自体ひとつの「知のコモンズ」を作り出そうとする営みであった待鳥研の実験的著作である本書『社会のなかのコモンズ』を、来たる2020年代へ向けての〈メタ公共性論〉の先駆けとして手に取って頂ければ幸いである。