片岡 義博(かたおか よしひろ)
ジャーナリスト
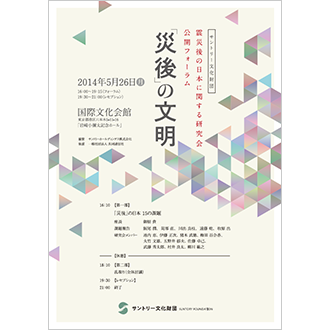
片岡 義博(かたおか よしひろ)
ジャーナリスト
2014年5月26日(月)、国際文化会館において「震災後の日本に関する研究会・公開フォーラム『「災後」の文明』」(座長:御厨貴東京大学客員教授)を開催しました。
当日パンフレット(PDF 2.8Mb)
震災後、日本が直面する課題について5人の報告者がそれぞれ異なる視点から3つの課題を提示し、10人のメンバーを交えて論じ合う――。これをそのままリポートしても、総花的を絵に描いたような内容になる。フォーラムのまとめで御厨座長は「災後の文明を構想するには、従来の構造をリシャッフル必要がある」と語った。この報告に当たっても、第1部の課題報告と第2部の全体討議を少々乱暴にリシャッフルさせてもらった。
「絆」の時空間
議論を通じて何度も俎上に載ったキーワードの一つが「絆」だった。震災をきっかけに流行語になった言葉である。
苅部氏は「感情的な強い一体感ではなくとも家族や狭い地域を超えた他人とのつながりを人々が意識するようになった。絆を単なるスローガンに終わらせず、望ましい社会の構想に生かせないか」と提言した。
大竹氏の調査・分析によると、震災によって助け合いの精神が日本全体に広がったという認識はいわば幻想であり、共同体意識は家族・地域という狭い範囲に限定された。「調査で意外な発見は、計画停電の地域の人たちの共同体意識が高まったという結果だった」と大竹氏は指摘した。苅部氏の提言に引きつければ、自分の地域への一体感が強まることを地域づくりの知恵につなげられないか、となる。
ここで問題になるのは共同体意識が及ぶ圏域だが、五野井氏は「震災後、半径5キロ圏内の非常に狭い生活圏か、ショーヴィニズム(自国優越主義)の土台となる国という2軸しかなく、中間の広い共同体がなくなってきている」という危惧を示した。
川出氏の問題意識もこれに通じる。大災害直後に被災者間に強い連帯感が生まれる現象を指す「災害ユートピア」という言葉を引きながら、川出氏は「震災直後の状況と復興事業の段階は違ってしかるべきだ。さらに連帯感が親密空間・被災地域・国家のどの単位で形成されるのかが問題」と時間的、空間的な整理の必要性を示した。
そのうえで「復興事業の段階では個々の自助、国家による公助、その中間にある市民同士の助け合いの3軸がある。日本では市民同士の連携はまだ浅く、今後、シティズンシップ教育などを通じて深める必要がある」とした。
武藤氏は自らの体験から、個人情報保護が壁となって地域で情報共有ができず、「絆が昔ながらの絆ではない」実態を紹介した。
池内氏と柳川氏が問題としたのは時間軸に関わることだ。
「災害ユートピアは災害を何かの契機にしたいという意志の中に形づくられる。我々は当時、これを突破口に何をしたいと思ったのか立ち返ってみる必要がある」(池内氏)
「震災の前後で大きく変わったのは、問題そのものよりも問題に対する人々の感じ方ではないか。震災以降の大きな変化は、絆そのものではなく、絆があるということに我々が気づいたことだ。それをどうプラスに転化していくか」(柳川氏)
川出氏は「震災直後、私たちが当たり前だと思っていたものは実は当たり前ではないという認識を日本人全体が共有した。この認識を積極的に生かすことだ」とコメントした。
浮上する国家の役割
絆が示す連帯意識の広がりを、遠藤氏はさらに「国内連帯」と「グローバル化」との関係に拡大し、その事例に震災後に激しい論争を呼んだTPP問題を挙げた。
「この問題は都市と田舎、中心と周辺、工業と農業という二項図式で国論を激しく二分した。グローバル化の流れも国内連帯への希求も止まらない。二項ともに大事で、グローバル化を前提に国内連帯を守るスキルを身につけるほかはない」
このとき重要なのは国家の存在であるという。
「戦前、日本は世界に暴力的な形で過剰に関与した。その反省からか戦後は世界に対する関与を対米貢献に限定してきた。災後の文明を語るならば、普遍的なルールに積極的に関与しながら自国の連帯を守る構図を描く必要がある。それには国家の果たす役割が大きい」
牧原氏も国家の役割の再評価から話を切り出した。
「冷戦後に生まれた国際・国家・地方という三段階モデルで、国家は規制緩和や分権化という形で小単位に分解する改革を進めた。しかし金融危機後や震災後に求められているのは、一度分解した単位をどう再結合するかだ。伝統的な統制主体から調整主体へ役割転換した国家像が印象付けられた」
調整主体としての国の役割については、伊藤氏と村井氏の取材成果が示唆を与える。
福島県の相馬市長に取材した伊藤氏が強調したのは2点。
(1)発災時と復興のプロセスにおいて、震災前からの自治体間の連携の仕組みづくりが重要になる。
(2)現場の情報を吸収しながらうまく制度を連結させていくために国の役割は非常に重要になる。
自衛隊に取材した村井氏は「国に属する自衛隊の活動に際して、自治体の役割は地域情報を的確に提供すること。さらに、たとえば捜索打ち切りの決断でも最終的には自治体が現場に説明して責任を持つことだ」と説明した。
災害ユートピアをめぐる議論でも「被災者と被災しなかった人々との間の連帯感が問題になるなら国家の存在を意識しない限り難しい」(猪木氏)、「復興事業では今回、日本では国家の役割が大きいことが透けて見えた」(川出氏)という発言に見られるように、フォーラムの全体を通して国家の機能・役割が浮上することになった。
「無知の知」とリスボン地震
しかし一方で、復興政策に直接関わる飯尾氏が強調したのは、国家や自治体の能力の限界を知ることの重要性だった。地元からはあれもこれもと要求するが、現場では予算もマンパワーも限られているという実態は容易に想像できる。飯尾氏は言う。
「どこまでできて、どこからできないのかという相場感を共有するためにも、政策形成の過程に多数の人が参加する必要がある。震災復興はそろそろ現場で自立することを考えざるを得ない。そのためには難しくても自立を促す支援策が必要になる。そして将来の大災害に備え、防災・減災に向けた複数のシナリオを事前に用意しておくことだ」
これに対する問い。「震災後の日本で個人の自立は非常に重要だ。しかし今は玉石混交の情報洪水の中、暫定的に正しい情報を個々が判断、選択している。その中で自立に向けた政策リテラシーをどう身に着けさせ、どう政策に落としていくのか」(梅田氏)
「復興が持つ語感は戦後の成長パラダイムに乗っている。戦後の人口増時代はパイを分け合うシナリオが想定できたが、災後の人口減の中では負担を分け合うシナリオとなる。災後のシナリオに、どう複数の可能性が想定できるのか」(佐藤氏)
飯尾氏の答え。「社会や政策のことは簡単にはわからないということを、まずみんながわかることだ。わからないことを前提に知恵を出し合い、地元でなすべきことを考える。複数のシナリオを強調するのも、思った通りにはならないという含意で、これがだめならこっちというふうに現実の制約の中で考えていくしかない」。いわば「無知の知」のすすめである。
川出氏がリスボン地震を素材に提起した問題も「人間の限界を知る」ことに関わる。1755年、リスボンを壊滅させた大震災によって何が変わったのか。
川出氏によれば、リスボン地震の「災後」は、自然の脅威に対する人間の備えが不十分だったとの反省から、地震のメカニズム解析や防災都市計画によって災害を克服する意識を持つようになった。これに対して東日本大震災の「災後」は、津波に原発事故という自然と人為が複合した大災害への対処が問われた。その意味で文明対自然という二項対立では立ち行かなくなっている。
遠藤氏はリスボン地震をめぐるヴォルテールとルソーの論争を引き、「悲嘆は悲嘆の領域に任せるというヴォルテールの諦観には、ルソーのように近代的人為で全ては回収できないというメッセージを感じた」という。
これを受けて川出氏は「リスク管理で対処可能な部分と、諦めざるを得ない部分がある。生命操作にしても諦める領域を失った世界はちょっと怖い。人類が持つ力をあえて封じ込める選択もありだろう。災後の文明は、ほどほどを知る文明ではないか」と語った。
人間が持つ能力の限界を見極めるという意識もまた、震災後に広がったといえないか。
専門知をどう生かすか
近代の始まりとしてのリスボン地震を日本に引き寄せたとき、苅部氏は、戦後の始まりである1945年が大きな問題提起だったと見る。
「太平洋戦争時のナショナリズムは情緒的な一体感という意味での非常に強固な絆だった。戦後、日本国憲法の原理は合理的秩序としての国家を目指した。ところが情緒のレベルで国家の一体感を捉える感覚が何となく残り続けたのではないか。それがそろそろだめになってきたことが今回の震災で表れてきた」
これは科学技術という専門知への対応にも絡む。米国の圧倒的な科学技術力に負けた日本にとって、科学的精神を尊ぶことは戦後のスローガンだった。しかし科学技術の評価には本来、どんな技術をどう使うかを判断すべきなのに、モラルのレベルで評価していないか。
「今回の原発事故でも科学技術の中身に関する評価ではなく、関係者の道徳的な立場を攻撃し合うかたちで論じられてしまう。本来は戦後で片付くべき問題が災後になって噴出し、もう一度新しいかたちで論じなければいけなくなっている」と苅部氏は見る。
原発事故をめぐって科学者や技術者、官僚の権威は大きく失墜した。もはや専門家に全てを任せられない。かといって素人だけでは判断できない。リスク対処に当たっても新たな専門知との向き合い方が求められている。会場から神里達博氏(科学論)が発言した。
「倫理的に正しい科学者とそうではない科学者がいて、我々はそれを民主的に選別できるという幻想がある。しかし先端では原理的に科学では答えが出ない問題が出てきている。それに関してはヨーロッパのように、民主的な参加の仕組みと、政治的な決定に向けた合意形成のフィールドをつくる必要がある」
専門知は自然科学だけではない。国の復興推進委員会メンバー、松原隆一郎氏(経済学)の会場からの発言は、社会科学の専門知に関わることだ。
「阪神・淡路大震災の時は、災害も含めたリスクを経済の成長でカバーできたが、今回は恐らくそれがカバーできない近代以降初の震災になる。成長なしに何かのかたちで復興を実現しなければならない。その何かとは物的な公共事業だけではなく、絆と呼ばれる共同体意識、デモクラシー、NPO、アーカイブ…。専門家でも扱えないこうした知識を何とか新しい公共性につなげていくことが災後に求められている」
議論を受けて御厨氏は「震災後、何かが動き始めていることは間違いない。災後の文明があるならば、今ある構造をいったんリシャッフルする必要がある。たとえばデモクラシーや民意という言葉も具体的な復興や将来の災害に備えるためにリ利用、リシャッフルすべき道具としてある。議論すべき多彩なテーマが出た。ここからが新たな出発点だ」と総括した。
さて、山崎氏による閉会の挨拶もまた、専門知の活用に深くかかわる内容だった。それは「今年35周年を迎えるサントリー文化財団が、単に言論界を動かすだけではなくて、ついに直接政治を動かし始めた」という指摘から始まった。どういうことか。
国が委嘱した復興構想会議を切り盛りしたのは財団の中核メンバーであり、それと相和して、この災後日本の研究会も立ち上がった。米国に始まる知識人の政治への直接参加は日本の場合、1960年代からの佐藤内閣を学者らが支えたことに始まる。その一人だった山崎氏が文化財団の設立に関わり、そこからさらに知識人の政治参加が進んだ。
「民主主義政治に知識人の参加は不可欠だ。政治家は選挙母体となるローカルな利益に動かされがちで、官僚は有職故実にとらわれ杓子定規になりがちだ。国民は空気に流され、ポピュリズムの危険がある。ここに知識人が入ってブレーキをかけなければならない」
財団で行われた知的交歓が個々に還元されて、やがて政治の場に反映されていく。その知的交歓の現場を、私たちはこのフォーラムで見ることができた。
(了)
片岡 義博(かたおか よしひろ)
ジャーナリスト