成果報告
2013年度
1955年以降のニュー・ジャズにおける即興演奏の美学的研究
- ラトガース大学大学院アート・メディア・カルチャー学部ジャズ・ヒストリー・アンド・リサーチ学科 前期博士課程1年
- 佐々木 優
■研究の背景と目的
1955年はジャズ史において画期の年であった。この年、ビバップ・ムーブメントの中心にいたチャーリー・パーカーが死去し、ジャズ界は大きな中心を失った。しかし、この年を境にいくつもの新しい動きが現れる。オーネット・コールマンのフリー・ジャズ、マイルス・デイビスのモード・ジャズ、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプト派などである。これらの諸動向は総称して「ニュー・ジャズ」と呼ばれている。
ラッセルは、コールマンやデイビスの音楽を論じた文章の中で、ビバップの演奏家が事前に決めたコード進行に基づいて即興演奏を行ったのに対し、ニュー・ジャズの演奏家は総じて「予め決められたコード進行に対する闘い」という問題意識を持ち、この問題意識の中で「汎調性」という調性概念に目を向けた、と指摘する。当時の状況を振り返れば、シェーンベルクが音楽史に登場してほぼ半世紀、ケージはすでに1951年≪4分33秒≫を上演、調性の問題は、もはや時代遅れの感が否めなかったはずである。だが、それでもそこにニュー・ジャズの関心があったと、ラッセルは言う。この指摘は、当時のジャズを考える上で非常に示唆に富むものであるにもかかわらず、これまで真剣に検討されてこなかった。
検討されなかった一因は、ラッセルの説明の難解さにある。例えば、ラッセルは汎調性について、「もし、管楽器奏者とベース奏者が汎調性という方法で同時に即興演奏したならば、全く新しい垂直調性が自然に生じる。そしてその時、すべての水平調性は消え去る」と言う。ラッセルのこうした考えは、常識的な西洋音楽の調性理論から見た場合、理解不能な世迷い言と映るであろう。
既成の調性理論を援用していては彼らの発言は理解できない。そこで、本研究は、汎調性を「即興演奏の場において初めて浮上する調性概念」とみなすことで、彼らの発言を解釈することを着想した。だが、汎調性が即興演奏に固有の調性であるならば、それを論じるには演奏を演奏のまま捉えるための知的枠組みが必要となろう。本年度本研究が取り組んだのは、この「演奏論的枠組み」の構築である。
■研究の成果
本研究が構築した演奏論的枠組みの概要を次頁に図示する。この図は、二人の奏者が同時に演奏する共演の場を図示している。本研究は、即興演奏を一種の「変換行為」と考え、即興演奏を「その場で思いついた『想像上の音』を、鳴り響く『物質的な音』へ変換すること」と規定する。想像上の音が物質的な音へと変換されるには「楽器」と「記号」という媒介者が必要である。楽器は、奏者の身体的動作(これを「器楽操作」と呼ぶ)を物質的な音へと変換する媒介者である。一方、想像上の音を器楽操作へ変換するには、想像上の音を器楽操作と対応させる能力を有していなければならない。こうした対応付けの能力は記号化の能力であり、奏者はこの能力を、実際に楽器で音を出すことを繰り返すことで身に付ける。
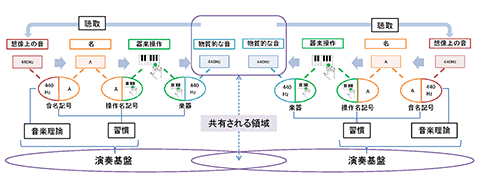
記号の項と項との対応を定めるのが「習慣」である(例えば、440Hzの高さの音をAと呼ぶ等)。一方、記号の運用の規則を定めたものが「音楽理論」である(例えば、A,B,C,D,E,F,Gという音の列をAマイナー・スケールと定める等)。 習慣と音楽理論は、一奏者の中で総合され、奏者にとっての「演奏基盤」となる。演奏基盤には、奏者間で共有されていない「私的な部分」と、奏者間で共有される「間主観的な部分」とがある。(前者の例:「♩ ♬」というリズムを、「タン・タ・タ」と呼ぶ奏者と「duu・di・di」と呼ぶ奏者がいる等/後者の例:ビバップのようにコード進行を決めておく等)。
演奏基盤以外に奏者同士が共有するものが、物質的な音の領域である。共演において、奏者は自分が出した音も共演者が出した音も同時に聴取する。聴取において、物質的な音は、想像的な音へ変換されるが、その際に演奏基盤は、聴取したものに対する解釈系として機能する。一方、各奏者の内部での記号の操作は、私的な領域で行われ、互いに感知できない。
■今後の見通し
以上が本研究で構築した演奏論的枠組みである。この枠組みを用いれば、例えば先ほどのラッセルの発言の中にあった「垂直調性」と「水平調性」という謎めいた調性概念を、「物質的な音の領域において生じる調性」と「演奏者の内部に生じる調性」と解釈する可能性が開けてくる。この枠組みに基づいて、汎調性に関する演奏家の発言と演奏実践を分析し、汎調性を解明すること。これが本研究の今後の課題である。
2015年5月





