成果報告
2013年度
儀礼・居住空間の復原による日本中世における王朝文化の変容に関する研究
- 同志社女子大学生活科学部 助教
- 赤澤 真理
1.研究の動機
寝殿造の空間は、平安王朝文化の舞台であり、日本におけるひとつの理想的な住宅像として理解が共有されてきた。しかし、貴族住宅において当時の人々がどのような生活を繰り広げたのかについては、未だ実像がつかみにくい状況にある。特に本研究では、中世の宮廷が、『源氏物語』に示された居住文化を継承しながらも、儀礼・居住空間が変化してゆく過程を明らかにし、王朝文化の変容過程を究明することを視座として、研究を推進した。
2.経過報告
研究期間中は、特に中世の住空間において、男性と女性の空間領域がどのように区分されていたのかに関心を持ち、中世住宅において、后や女院、内親王といった高位の女性達が儀礼の際に自らの座所周辺を女房装束によって装飾した「打出」という空間演出の方法を検討した。具体的には、東京国立博物館等に所蔵される打出が描かれている絵巻(「駒競行幸絵巻」)の調査、宮内庁書陵部蔵の有職故実書を複写・翻刻し、物語の記述を古記録と照合し、資料を収集した。その結果、打出は11世紀には御簾から女房の装束を自然に出す用例が確認でき、儀式や行事時に高貴な女性に仕える女房達の座所を暗示する役割があった。それは次第にしつらいとしての「打出」として発展し、儀礼空間の公卿座(男性貴族)にも使用されるようになる。11世紀後半から12世紀には、打出によるしつらいが確立する。用例には、儀礼時の女院・后の座所周辺を装飾する、拝礼・通過儀礼の空間を装飾する、御使を迎える際の妻戸口等を明示する、などがあり、女房が実際に着用し装束を出すもの、几帳に架けて設置する(女房は不在)の双方の事例が確認できる。男性官人の記した古記録には、「打出」は「過差美麗」と記され、厳格な儀礼の際には華美な打出は、忌避された。打出には、華美すぎず、儀礼空間に華やぎを添える微妙な均衡が求められた。
本研究により、韓国及びトルコの宮殿や貴族住宅を実見する機会を得た。江戸城の大奥等の日本近世住宅と同様に、明確に男女の領域が区分される各国の宮廷生活と比較し、日本中世は、宮廷や貴族住宅の男性と女性の領域が未分化であり、行事や生活ごとに場をしつらうことに特質があることを再認識した。人目にふれてはいけない女性の座所を儀礼空間に示し、男女が場を共有する道具立てとして、打出が発展したと考えられる。
3.今後の課題
今後は、下記の4点を課題とすることが明確になってきた。(1) 女房装束の打出の意匠・色彩・装飾等の演出方法を検討するとともに、鎌倉時代後期から室町時代までを検討し、寝殿造の変容過程を背景に、打出の衰退過程を明らかにする。(2) 打出の記述を通して、女院・后等が行事の空間にどのように参加したのかを抽出し、中世における女性の社会的な存在様態を検討する。(3) 打出という女性の服飾を設置あるいは出すことによって、視覚的には見えない領域を外部から暗示させようとする仕掛けを日本文化の一つとして位置づける。打出は、神や天皇などの存在を調度や建築等により可視化し、権威を演出する手法に通じるものと考えている。(4)本研究の課題とした、居住空間の分析を継続する。同時代の中世女房日記を、同時代の古記録と指図と照合し、日常生活における女房の生活領域や境界、内部空間を描き出す。実像がみえにくかった中世の生活空間を、建築や内部空間から浮き上がらせ、王朝文化の変革期における居住空間の実態を究明していきたい。
本研究の内容は、下記において口頭報告した。現在、学術論文を執筆している。
「女房装束の打出による寝殿造の空間演出とその性格」国際服飾学会、2014年度第2回研究会、同志社女子大学、2014年10月
「平安時代の貴族邸宅における遊興空間」平安京京都研究集会「平安時代貴族邸宅論」
京都産業大学、2014年11月
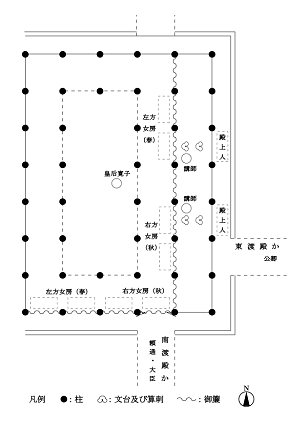
天喜4年(1056) 皇后宮寛子春秋歌合(復原図:赤澤真理)
左方に座る女房が春、右方に座る女房が秋にまつわる装束を身に付け、女性達の儀礼の空間が打出により装飾された。
2015年5月












