成果報告
2010年度
アフリカ諸国における日本のNGO活動の役割とは
―
学校建設活動の実態について
- 東京大学大学院工学系研究科博士後期課程
- 井本 佐保里
1.研究の背景と目的
本研究は近年活発化しつつあるアフリカ諸国に対する支援について、そのより効果的な手法について提言することを目的としている。
2.調査概要
調査概要は表1に示す通りである。
【調査対象】調査対象としたのはケニア共和国において1998年より継続して活動を行う特定非営利活動法人アフリカ地域開発市民の会(以下Cando)によって(1)現在教室建設事業が実施されている6校、及び(2)2006年に事業実施を行った1校の計7校である。【調査方法】(1)についてはCandoにインターン員として所属しながら実際の教室建設の業務に携わり、教室建設のプロセスを記録した。(2)については小学校の歴史に詳しい教員及び保護者を対象にインタビュー調査及び実測調査を行った。
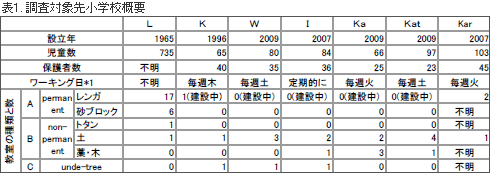
3.考察
3-1.NGO側の視点から見る教室建設事業の実態
(1) スケジュール
各小学校における建設事業は以下のようなスケジュールで行われる。但し、学校ごとにスケジュールの内容及び進行スピードに違いが見られるが、それらは、立地(水場からの水の運搬のしやすさ、レンガを作成するための土の質など)や、保護者・学校の運営状況(リーダー的存在の有無、合意形成・情報共有のできる体制の有無)の違いによることが明らかになった。
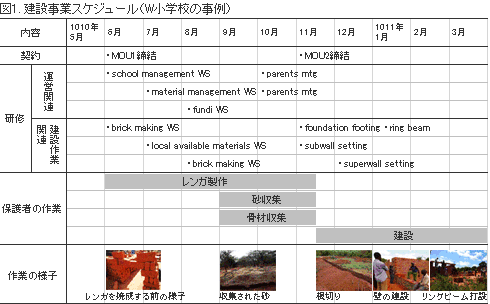
【step1.事業実施校の選定】事業実施校についてNGOが選定することは行わない。地域の行政官から地域の全小学校に伝えてもらい、応募校を募る。その後は説明会を開催し、応募小学校間で話し合いを行い当事者間で実施校を決定する仕組みを取っている。【step2.覚書の締結】実施校が決定されると、NGOと小学校間で覚書を交わし、事業が実施される。【step3.資材収集】事業が始まると、NGOスタッフ、専門家により運営、及び資材収集、資材管理に関する研修を実施する。同時に、保護者はその研修内容を踏まえて資材の収集を行う。資材には、レンガ、砂、骨材(砂利)がある。一方、セメント、木材、鉄筋はNGOより供与される。【step4.覚書2の締結】資材収集が完了すると、NGOと小学校間で覚書2を交わす。【step5.建設】建設は「根切り」→「基礎」→「壁」→「リングビーム」→「屋根」→「スラブ」の順序で進んでいく。作業は保護者が雇用した職人の指導を受けながら保護者一緒になって行う。
(2) 保護者の参画・NGOの参画
同事業において、保護者は全行程の中心的役割を果たしていることが明らかになった。一般的に同地域における小学校の設立や教室建設、運営は保護者中心で行われており(harambee =work togetherというシステム)、同事業では現地の手法を踏まえて活動を行っている。特に資材収集については、一部の購入しなければ手に入らない資材や道具はNGO側により供与されるが、その他は全て保護者によって行われる。また、建設も保護者が中心となって行う。一方、NGO側は、建設の作業進捗に合わせて専門家による作業研修の実施、コーディネーターによる運営に関わる研修の実施を行っている。
3-2.現地の小学校の中でのNGO支援の位置づけ
一方、小学校の長い歴史の中でNGOによる支援はどのように位置づけ、評価することができるのだろうか。学校設立と教室建設のプロセスから明らかにした。【設立/立地計画】小学校設立のための企画は立地と強い結びつきを持っていることが明らかになった。インタビュー調査の結果、各小学校は既存の小学校までの距離が遠く(L小学校の場10km)、特に年少の子どもの通学に困難を来たすことが新たな学校設立の動機となりその立地計画の基盤となっていることが明らかになった。また、多くの小学校の敷地は地域住民によって提供され、特にL,K,Iは無償で提供されており、土地提供者の存在も立地計画に大きな影響を与えていると考えられる。【施設規模/配置計画】施設規模としては、まず1つまたは2-3の教室から始まっている。その後、1年ごとに児童が昇級し1学年ずつ増えるため、1年に1教室の増築を目指すことが一般的となっている。このような教室増築が想定される中で、将来像(全体の配置計画)も必要となる。最終的な8学年分(ケニアで初等教育は8年)の教室がどのように配置されるのか、初期の段階で動線、方位などから計画を立てている事例もあれば、要所で保護者会議を設け、当面の予定を決定していることが明らかになった。【教室建設】(1)誰が建てるのか:教室の建設のほとんどは保護者によって行われている。しかしある程度の技術と知識が必要となるpermanent structureの教室を建設する際は職人を雇用し、保護者と協働で建設を行うことが一般的であるようである。(2)建設費:保護者からの寄付(実態としては強制的な)を徴収することが一般的である。また、2003年以前はdevelopment fundとして保護者より一定額の資金が徴収されていた。一方、調査対象とした学校では、ある程度施設環境が整った段階で、行政からの資金支援や、NGO団体による資金・技術支援が行われている。(3)教室の種類:各学校の教室は表1に示すように大きくA. permanent structure(石、レンガ、コンクリートブロック等による建物)B. non-permanent structure(木や藁、土、トタンなどによる建物) C. under-tree(木陰を教室として使用しているもの)の3つに分類される。学校側はこの3種の教室を使い分けながら建設を行っている。一般的に、行政から公立小学校として認可され、教員の派遣を得るためにはAの教室を持つことが条件であり、これがAの教室建設を促す要因のひとつとなっていると言える。しかし特に保護者の数が少なく経験も少ない新設校においては、Bの教室、またはCの教室が多く見られる。また、時間をかけてAの教室の建設を行いながらも、特に児童の急増等で緊急に教室が必要となった際にBの教室を建設するなど、建設は容易だが恒久的な使用が難しいBと、建設に大きな時間、費用、労力を要するが恒久的に使用が可能で政府から認可されるAの両方を場面に応じて選択しながら建設が行われていることが明らかになった。それでも教室が足りない場合にCの利用、2部制の採用が行われていることが明らかになった。
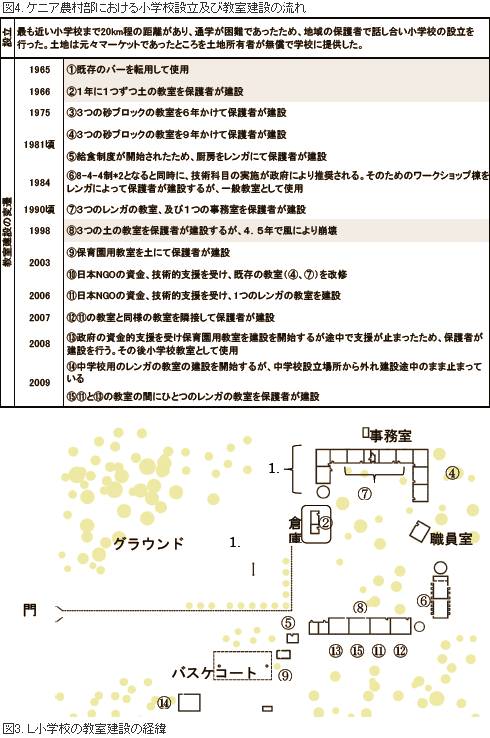
4.まとめ
本研究により、調査対象としたケニア農村部の小学校における設立及び教室建設プロセスにおいて、特に、地域の保護者が主導的役割を果たしていることが明らかになった。保護者による活動が行われた上で外部団体であるNGOや行政からの支援及び行政による認可が行われていることは注目に値する。特に調査対象としたNGO団体は、同地域の教室建設や学校運営の特徴をよく捉え、活動の枠組みを作っていると評価できる。一方、保護者は教室建設経験を重ねることや外部からの支援によって技術の習得やマネージメント能力を向上させていることが推察できる。このような過程を経てケニア農村部の小学校は力をつけ、同地域の中でより大きな役割を果たすものへと移行していく。今後、さらに保護者、行政そして外部団体の3者それぞれの役割を明確化し、それぞれの関係性、果たす役割について明らかにしていくことを目指す。
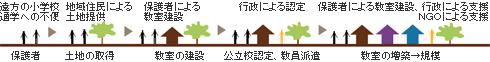
(2011年9月)





