選評
思想・歴史 2000年受賞
『夢分析』を中心として
(岩波書店)
1950年、大阪市生まれ。
京都大学医学部卒業。
大津赤十字病院医師、京都南逓信病院医師を務めたのち、京都大学教養部助教授などを経て、現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。
著書:『ラカンの精神分析』(講談社)、『無意識の組曲』(岩波書店)
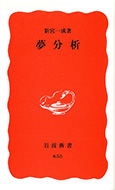
新宮氏の文章を読んでいると、ふと「幽玄」という言葉が思いうかぶ。『広辞苑』の定義によると、奥深く微妙で、容易にははかり知ることのできないこと。新宮氏の文章は、というより論理は、つねに夢現の幽いあわいを往還する。その様はこよなく精緻で、かつ恐ろしい。
〈夢〉という主題は、80年代に世に問われた『夢と構造』『無意識の病理学』から近年の『ラカンの精神分析』『無意識の組曲』、そしてこの年頭に出版された『夢分析』まで、フロイトとラカンの理論研究とならんで、新宮氏の臨床研究の太い撚り糸のひとつである。ここでなされてきたのは、夢の意味の解読というよりも、夢のしくみそのものの分析だ。その物語ではなく構造をあきらかにすることだ。
非一人称的な体験としての夢、それを分析するまなざしを貫くのは、ひとの存在を支えてきしむ柱木の脆さである。新宮氏は、夢を、というより精神分析のいう欲動そのものを、話すというひとの営みと深く絡まりあった現象として見る。では、夢を語るのはだれか。あるいは、なぜ語るのか。それをめぐって、思索は連綿と続く。
夢は自分を外から掴む装置としてあると、新宮氏はいう。〈外〉は意識の〈外〉(無意識)であるとともに、言葉たちの〈外〉であり他者たちの〈外〉でもあり、さらに流れる時間の〈外〉でもある。そしてそこに死と不在というテーマが浮上する。
「そがありけむあたりにわれきたるべし」。これがフロイトが晩年に定式化した精神分析の極北だと、新宮氏はいう。「精神分析は、何か根源的に消え去ってしまったものを、その探究の基盤に置いている。……私がそれによってさしあたって毎日を生きている基本認識である〈私は在る〉は、無意識においては〈私はかつて生きていた〉として書かれている。無意識からの話は、まるで死者からの言づてのように響く」とも。
生まれることと死ぬことのあいだで、意味に過剰にこだわりながら、そして意味から退却しながら、自分をかろうじて支えるという、あるいはついに破綻してしまうという、わたしたちの存在の《不幸》。その不幸の構造を穿つ書物が、これほど深くわたしたちを読むことの愉悦へと引きずり込んでもいいのかと、ちょっと訝しく思われるくらいに、記述の襞は厚い。それは論理的かつ詩的であり、数理的かつ音楽的である。自己言及の不完全性や無理数の論理が語りだされ、シューマン、デルボー、宮沢賢治が読む者の情動を底から巻き込むかたちで語りだされる。そして存在することそのことが夢と深く交叉し、読み進めるうちに、書き連ねられた文字じたいが死体のように見えてくる。そういえば、イ音の幻聴を論じた卓抜なシューマン論では、「音楽を作る作業は、死体の艶と粘りとを、空気の中にまき散らすことであるとさえ言える」と結論づけられる。
新宮氏の思考は、哲学と文学と音楽と科学と論理学のあいだを自在にたゆたうかたちで、ひとの在/不在が果てしなく裏がえる光景に、しかとつなぎとめられている。
鷲田 清一(大阪大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)





