「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」は、コンサート・ホールが、鑑賞の場に止まらず創造空間となることを目指して、1986年故武満徹の提唱により始まりました。世界の第一線で活躍する作曲家へ管弦楽作品を委嘱し、世界初演を行います。
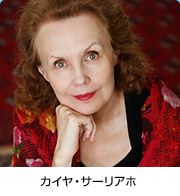
8/24(水)室内楽
19:00[開場18:20] ブルーローズ(小ホール)
*18:30〜 プレコンサート・トーク[カイヤ・サーリアホ&細川俊夫]
■カイヤ・サーリアホ(1952-):7匹の蝶*(2000)
:テレストル(地上の)*(2002)
:トカール**(2010)
:ノクチュルヌ***(1994)
:光についてのノート*,**(2010)![]()
- チェロ:アンッシ・カルットゥネン*
- 指揮・ピアノ:石川星太郎**
- ヴァイオリン:アリーサ・ネージュ・バリエール***
- アンサンブルシュテルン
-

アンッシ・カルットゥネン -

石川星太郎
入場料:[自由席]一般 3,000円/学生 1,000円
-
5月10日(火)10時~
セット券
「テーマ作曲家〈カイヤ・サーリアホ〉」2公演セット券[8月24日&30日(S席)] 5,000円〈限定100セット〉
※東京コンサーツ(03-3200-9755)のみ取り扱い。(5月10日発売)
- ※先行発売および一般発売のインターネットでのチケット購入にはサントリーホール・メンバーズ・クラブへの事前加入が必要です。(会費無料・WEB会員は即日入会可)
サントリーホール・メンバーズ・クラブについてはこちら(PDF:4.17MB) - ※学生席はサントリーホールチケットセンター(電話・WEB・窓口)のみ取り扱い。
25歳以下、来場時に学生証要提示、お1人様1枚限りです。 - ※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。
- ※出演者・曲目は予告なしに変更になる場合があります。
■ジャン・シベリウス(1865-1957):交響曲第7番(1924)
■カイヤ・サーリアホ(1952-):トランス(変わりゆく)*(2015)![]()
サントリーホール、フィンランド放送交響楽団、スウェーデン放送交響楽団、
チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団、hr交響楽団共同委嘱
■ゾーシャ・ディ・カストリ(1985-):系譜(2013)![]()
■カイヤ・サーリアホ(1952-):オリオン(2002)
- 指揮:エルネスト・マルティネス=イスキエルド
- ハープ:グザヴィエ・ドゥ・メストレ*
- 管弦楽:東京交響楽団
-

エルネスト・マルティネス=イスキエルド -

グザヴィエ・ドゥ・メストレ -

東京交響楽団
入場料:[指定席]S席 4,000円/A席 3,000円/B席 2,000円/学生席 1,000円
-
5月10日(火)10時~
- ※先行発売および一般発売のインターネットでのチケット購入にはサントリーホール・メンバーズ・クラブへの事前加入が必要です。(会費無料・WEB会員は即日入会可)
サントリーホール・メンバーズ・クラブについてはこちら(PDF:4.17MB) - ※学生席はサントリーホールチケットセンター(電話・WEB・窓口)のみ取り扱い。
25歳以下、来場時に学生証要提示、お1人様1枚限りです。 - ※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。
- ※出演者・曲目は予告なしに変更になる場合があります。
「テーマ作曲家〈カイヤ・サーリアホ〉」2公演セット券[8月24日&30日(S席)] 5,000円〈限定100セット〉
※東京コンサーツ(03-3200-9755)のみ取り扱い。(5月10日発売)
サーリアホについて
サーリアホの音楽 細川俊夫
私がはじめてカイヤ・サーリアホを見たのは、1992年のダルムシュタット国際夏期講習であったように思う。ちょうどその頃出産を終えたばかりのサーリアホは、赤ちゃんを抱いたまま講習会に参加していて、その姿はまるで北欧からやって来た魔法使いが、子供を抱きしめているようにも見えた。サーリアホの音楽の官能性に満ちた美しい響きと独自の音の構築は、いまだにセリエール音楽の洗礼から抜けだせないでいる多くのダルムシュタットの作曲家たちのなかで、際立った存在であった。戦後の前衛音楽家たちは、音の独善的な知的な構築のなかから、新しい音楽を見つけようと努力し続けていたが、音そのものの持つ生命力、官能的な力は忘れられようとしていた。そうした世界のなかで、日本の武満徹やフィンランドのサーリアホのような作曲家は、ヨーロッパから見れば周縁の場所から登場し、共に自然との深い交感のうちに音を紡ぎだしていた。音そのものの植物的ないのちの躍動を音楽の織物(テクスチャー)のなかに生かすことの出来たのは、中央ヨーロッパとは異なった自然観を彼らは持っていたためだろうか。あるいはサーリアホは、男性中心の世界では忘れられていた独自のコスミックな音創造を、女性であることからで生み出すことが出来たのだろうか。今年の夏のサントリーでの彼女との出会いのなかで、こうした問いをあらためて考え直してみたい。
作曲家からのメッセージ
サントリーホール30周年記念の年に国際作曲委嘱シリーズのテーマ作曲家としてお呼びいただき、大変光栄です。この素晴らしいホールにはたくさんの愛すべき思い出がありますが、初めて訪れたのは、1990年に武満徹さんにご招待いただいたときでした。
ですから、彼の没後20年である本年に2つのコンサートを行えることはとても感慨深いです。細川俊夫さん、サントリー芸術財団、サントリーホールのご招待に感謝いたします。
私のもっとも身近で尊敬する仲間である、チェロのアンッシ・カルットゥネン、ヴァイオリンのアリーサ・ネージュ・バリエール、そして指揮者のエルネスト・マルティネス=イスキエルド。この3人とともに私の作品を共演する日本の音楽家の皆さんとの出会いを大変楽しみにしております。
管弦楽公演では私の曲に加えて、2人の作曲家の傑作を取り上げました。ひとりは私と同国のフィンランドの作曲家として名高いジャン・シベリウス、そしてもうひとりは若いカナダ人のゾーシャ・ディ・カストリです。そして何より嬉しいのは、グザビエ・ドゥ・メストレのハープソロによって、私が作曲したハープコンチェルト《トランス》をサントリーホールで世界初演できることです。
[カイヤ・サーリアホ]
出演者からのメッセージ
《光についてのノート》は、チェロとアンサンブルが様々な奏法を用いつつ多様な関係を構築することで、神秘的で幻想的な光の世界を映しています。私にとってその透明度の高い美しい響きがとても魅力的です。
また、鳥が村人たちにダンスを教えるというアボリジニの物語から着想を得た《テレストル(地上の)》は、第一部は速いテンポのコミカルな音楽。そして第二部は(第一部と対をなして)その様子を別の視点から俯瞰するような曲で実にユニークです。
カイヤ・サーリアホさんの音楽は、私たちの様々な感覚に積極的に接触して来ます。長年サーリアホさんと活動されているカルットゥネンさんやアリーサさん、アンサンブルの素晴らしい音楽家たちと共に彼女の作品を実際に音にし、皆さんと一緒に「サーリアホ体験」できる機会を与えていただいたことに感謝しています。
[石川星太郎(24日出演 指揮・ピアノ)]
プロフィール

カイヤ・サーリアホ
パリに拠点をおき国際的な活動をするフィンランド出身の作曲家。ヘルシンキ、フライブルグ、パリで学び、1980年代に本格的なキャリアをスタートさせた。スペクトル楽派に近い協和と不協和を連続的に扱う書法によって個性を確立したあと、1990年代に人間の声への理解を新たにしたことにより、以後、オペラばかりでなく、あらゆる音楽ジャンルで、独特の叙情性をもった作品を次々と生み出す。アプショウ(ソプラノ)、ホイテンガ(フルート)、カルットゥネン(チェロ)、アックス(ピアノ)を始めとする演奏家との密接なコラボレーションでも知られる。
8/30(火)作曲家
ジャン・シベリウス
Jean Sibelius(1865-1957)
ロシアの圧政下にあり、ナショナリズム運動が高揚しつつあったフィンランドに生まれる。ヘルシンキ大学にて法律を学ぶ傍ら、ヘルシンキ音楽院に通う。その後のウィーン留学中に自国の文化の豊かさに気づく。フィンランドの英雄叙事詩『カレワラ』(1835年出版、1849年増補版出版)の題材にちなんだ作品は多い。また、実際に民謡を採譜したり、採譜した民謡旋律を自作に取り込んだりもした。だが、例えばバルトークのように民謡素材を直接引用するのではなく、シベリウスはあくまでも民謡に潜む精神から創作へのインスピレーションを受けるという形で活用した。「フィンランド的なもの」の模索を通じた創作活動は、とりわけ国内で共感を呼び、早くから国民的作曲家として評価された。
[池原 舞]
ゾーシャ・ディ・カストリ
Zosha Di Castri (1985-)
ニューヨーク在住のカナダ人作曲家、ピアニスト。作品はカナダや欧米各国で広く演奏されており、ハンブルクの現代音楽祭クラングヴェルクターゲの第3回国際作曲家コンクールに入賞、2011,12年にはSOCAN財団賞(カナダ)、2012年にはジュール・レジェ賞(同)を受賞している。アコースティックな作品に留まらず、電子音楽やサウンド・インスタレーション、ビデオ、パフォーマンス・アート、コンテンポラリー・ダンス等、異ジャンルとのコラボレーションも積極的に行っている。フルート、ピアノ、エレクトロニクス、大型彫刻のための《Akkord I》等、ミクストメディア作品も制作。コロンビア大学では作曲、電子音楽、音楽史の指導を行っている。
[小林幸子]
8/24(水)出演者

アンッシ・カルットゥネン(チェロ)
フィンランドのチェロ奏者。ジャクリーヌ・デュ・プレらに師事し、ロンドン・シンフォニエッタの首席チェロ奏者や各音楽祭の芸術監督を務める。2012年にはサーリアホとカーネギーホールでマスタークラスを担当、パリ・エコール・ノルマル・ド・ムジークやUCバークレーでも指導を行う。リンドベルイ、サーリアホ、フランチェスコーニ、譚盾らの160を越える作品の初演を行っており、彼のために29もの協奏曲が作曲されている。2013年には2つの録音がグラモフォン賞にノミネートされ、サロネン指揮フランス放送フィルと共演したデュティユー作品が受賞した。
[小林幸子]

石川星太郎(指揮・ピアノ)
1985年東京生まれ。東京藝術大学音楽学部指揮科を首席で卒業。同時にアカンサス音楽賞受賞。2006年以降は武生国際音楽祭に毎年出演し、2013年以降は神戸市室内合奏団の3月定期演奏会の指揮者を務めている。レパートリーはバッハの宗教曲から現代音楽まで広範。これまでに指揮を田中良和、ハンス=マルティン・シュナイト、ゲルハルト・ボッセ、リューディガー・ボーンに、ピアノを林達也、ユーラ・マルグリス、トーマス・レアンダーに師事。現在ロベルト・シューマン大学デュッセルドルフ在学中。指揮科助手も務めている。
アンサンブルシュテルン
2006年、石川星太郎を中心とした芸大在学生によって結成される。以来、固定メンバーを決めず不定期に演奏会を開いており、細川俊夫《恋歌III》の日本初演はCD化され高く評価された。石川星太郎のドイツ留学に伴い活動は一時中断していたが、今後は定期的な活動が計画されている。
8/30(火)出演者

エルネスト・マルティネス=イスキエルド(指揮)
スペイン・ナバラ交響楽団名誉指揮者およびバルセロナ216首席客演指揮者。バルセロナに生まれ、同地とパリで学ぶ。1985年に現代音楽アンサンブルのバルセロナ216を設立し、指揮活動を開始。以来、スペイン国立管の助監督、アンサンブル・アンテルコンタンポランでブーレーズの助手、ナバラ響とバルセロナ響の音楽監督を歴任。各国のオケと共演しており、サーリアホ作品などオペラも指揮する。またグラモフォン等で録音を行っており、ディアパソン・ドールほか受賞も多数。2006年よりサン・ジョルディ王立芸術アカデミー(スペイン)会員。
[小林幸子]

グザヴィエ・ドゥ・メストレ(ハープ)
ハープ界の第一人者であり、ハープのための新しい委嘱作品に加え、オーケストラ作品などを見事なアレンジと超絶技巧で演奏して楽器の可能性までも広げていく卓越した奏者である。フランス生まれ、9歳からハープを学ぶ。1998年USA国際ハープ・コンクール優勝後、2010年までウィーン・フィルのソロ・ハーピストを務める。その後、ソリストとして活躍し、ガッティ、ムーティ、ラトルなどの指揮者や世界的なオーケストラと、また室内楽ではダムラウやミュラー=ショットらと共演。ソロ・リサイタルでも世界中で演奏している。

東京交響楽団
1946年創立。現代音楽の初演などにより、文部大臣賞、京都音楽賞大賞、毎日芸術賞、文化庁芸術作品賞、サントリー音楽賞、川崎市文化賞等を受賞。川崎市とフランチャイズ、新潟市と準フランチャイズ契約を結び、八王子パートナーシップオーケストラとしても、コンサートやアウトリーチ活動を展開しているほか、新国立劇場ではレギュラーオーケストラとして毎年オペラ・バレエ公演を担当。教育面ではサントリーホールと共催の「こども定期演奏会」が注目されている。音楽監督にジョナサン・ノット、正指揮者に飯森範親を擁する。今年創立70周年を迎え、10月にウィーン楽友協会を含むヨーロッパ5カ国での公演を予定している。








