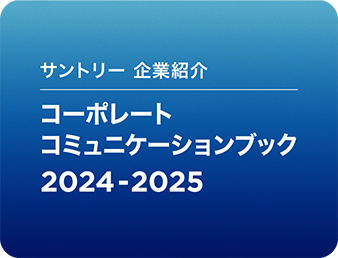CORPORATE
あくなき調査と研究の先に。サントリー文化財団が育む「文化」と「社交」
24.06.07
優れた研究・評論活動を表彰する「サントリー学芸賞」や論壇誌『アステイオン』の企画を行う「サントリー文化財団」。同財団は、サントリーグループの企業理念である「利益三分主義」を体現する組織として活動を続けています。その具体的な活動を通して、社会にどのように貢献しているのか、財団の若手職員である安田泉穂さんに伺いました。
学芸文化振興事業と
地域文化振興事業の2つの柱
サントリー文化財団は1979年、サントリー創業80周年を記念して設立されました。サントリーの「利益三分主義」の精神のもと、さまざまな文化貢献活動に取り組んでいます。
 1979年に行われた「サントリー文化財団」設立記者会見。左から開高健氏(作家)、佐治敬三(サントリー社長)、山崎正和氏(大阪大学教授)、高坂正堯氏(京都大学教授)と錚々たるメンバーが集まった。肩書きは当時のもの
1979年に行われた「サントリー文化財団」設立記者会見。左から開高健氏(作家)、佐治敬三(サントリー社長)、山崎正和氏(大阪大学教授)、高坂正堯氏(京都大学教授)と錚々たるメンバーが集まった。肩書きは当時のもの
サントリーグループが大切にする価値観「利益三分主義」とは、お客さまや取引先、社会のおかけ?て?事業が成り立っているという考えのもと、事業で得た利益は「事業への再投資」「お得意先・お取引先へのサービス」「社会への貢献」の3分野に還元するというものです。
そんなサントリー文化財団のミッションについて、同財団の若手職員の安田泉穂さんは、「知をつなぎ、研究者、ジャーナリストなど文化活動に携わるいろいろな領域の人たちが交流する『社交の場』を提供すること」だと語ります。

それを実践するための事業は「学芸文化振興事業」と「地域文化振興事業」の2つから成り立ちます。
学芸文化振興事業では、「研究助成」「調査研究」「サントリー学芸賞」「海外出版助成」の4つの事業を実施。「研究助成」では、若手研究者の研究や、さまざまなジャンルの専門家の集うグループ研究への助成を行っています。

「例えば、グループ研究助成の助成テーマの一例として、『スナック研究』というものがあります。スナックを夜の公共圏として研究するもので、生活文化に密接にリンクした内容となっています。助成対象となる研究に共通しているのは、サントリーの『やってみはなれ』精神です。成果を出すことが最終的な目的ではなく、その研究がこれまでの枠にとらわれず専門外の人にもつながっていくことを重視しています」
「調査研究」では、『アステイオン』の編集のほか、専門家、実務家などが4?10人で1チームとなって数年かけて研究会を開催し、報告書や書籍にまとめています。
『アステイオン』最新号。1986年に創刊したサントリー文化財団が企画・編集を行う論壇誌
「調査研究には複数の研究会があり、現在は例えば、『信用の人類史』という研究会を行っています。これは、人類がどうやってお金を信用するようになったのかを歴史的背景から紐解く内容になっています」
また、広く社会と文化を考える、独創的で優れた研究・評論を表彰する「サントリー学芸賞」では、選考においては“知的なワクワク感”がポイント。過去の受賞作品には、福岡伸一さんの『生物と無生物のあいだ』(講談社/2007年)などがあります。
「海外出版助成」では、日本語で書かれた本や日本について書かれた本を日本語以外で出版することを助成。例えば、古典の英訳本、司馬遼太郎をモンゴル語で翻訳した本などの出版を通じて広く日本への理解を深めてもらうことを目的としています。
 「サントリー学芸賞」のほか中央公論「新書大賞」も受賞した88万部を超えるベストセラー
「サントリー学芸賞」のほか中央公論「新書大賞」も受賞した88万部を超えるベストセラー
一方、地域文化振興事業では、「サントリー地域文化賞」「地域文化活動支援」の2つの事業を展開。「サントリー地域文化賞」は、全国各地で行われている地域文化活動やそれを担う人たちに贈られるものです。
「受賞対象は、伝統文化はもちろん、地域のことを長年調査する活動、地元の歴史や特性を生かしたユニークなイベントなど、かなり多岐に渡ります。これまでの受賞例には、全国各地で伝承される歌舞伎や、北海道での“バル街”イベント、長野県で開催される国内最大級の人形劇フェスティバルなどもあります」
受賞者の活動をさらに支援するのが「地域文化活動支援」です。活動の様子を動画に収録し、サントリーの公式YouTubeチャンネルで紹介するなどして、積極的に情報を発信しています。

論壇誌『アステイオン』は
こうしてつくられる

大学院での研究生活を経て、2022年からサントリー文化財団で働くようになった安田さん。広い意味で研究者を支援し、社会に発信していく財団の活動に惹かれて就職を決めたと言います。現在、安田さんは先輩の大栗さんとともに『アステイオン』の編集をメインに、研究助成やサントリー地域文化賞などに関わっています。
「『アステイオン』は、社交の場としての財団の研究活動を記録することなどを目的に1986年に創刊。『サントリー学芸賞』を受賞した方々に書いてもらう場にしたいという狙いもありました。『アステイオン』は、財団が社会と直接つながる手段としても大きな存在価値があります。財団の初代理事長でもある佐治敬三の『やってみなはれ』のひとことが、雑誌の創刊の後押しとなったと聞いています」
 創刊から38年。記念すべき100号のアニバーサリー号が2024年5月に発売
創刊から38年。記念すべき100号のアニバーサリー号が2024年5月に発売
財団が培ってきた人脈を最大限生かして、社会に発信する場──。それが『アステイオン』のミッションです。
「『アステイオン』という名前は、洗練された都市的なものを意味するギリシャ語の『アスティ』に由来します。専門的な言葉で書いてもらうというよりは、広く社会の方々にも読んでもらえる内容を目指しています」
現在は年2回の発行に加えて、2021年から「WEBアステイオン」をスタート。本誌からの転載だけでなく、ウェブオリジナル記事も掲載しています。
「私にとって思い入れがあるのは、98号、“中華”の特集号(2023年5月発行)ですね。私が初めて特集を担当した号で、中国周辺の地域の視点から中国や中華を捉えるという企画です。9つの記事それぞれに新しい発見が多くあり、“幕の内弁当”のような非常に充実した内容になったと思っています」


また、『アステイオン』では4年前から出版記念イベントとして「アステイオントーク」も実施していますが、98号ではこのトークイベントに特集執筆者全員を招待。イベント終了後に懇親の場を設けたことも、安田さんにとって有意義な体験となりました。
「本誌に寄稿して終わりではなく、実際に執筆者のみなさんが顔を合わせて交流することができました。まさに社交の場を実践できた点で、本当にやってよかったと思っています」
2024年5月には、記念号となる『アステイオン』100号も発売。「『言論のアリーナ』としての試み」と題して、アステイオン38年の歴史から社会の変遷を振り返る内容で、これからの言論、論壇、メディアや雑誌はどうなっていくのか、という問いに答えるものです。
サントリー精神に支えられて
「文化」を育み発信
サントリー文化財団の設立以来、副理事長として精神的支柱となり、その活動をリードしてきたのが、劇作家・評論家の山崎正和氏(2020年没)です。山崎氏のこれまでの功績をたたえ、サントリーの社員にも広く知ってもらうことを目的に、2024年、サントリーワールドヘッドクォーターズ(台場)に「山崎正和サロン~アステイオン~」が誕生しました。
 サントリー文化財団副理事長だった劇作家・評論家の山崎正和氏。1999年に紫綬褒章、2018年には文化勲章を受章 (c)相澤實
サントリー文化財団副理事長だった劇作家・評論家の山崎正和氏。1999年に紫綬褒章、2018年には文化勲章を受章 (c)相澤實
「サントリー文化財団の6つの事業を考案されたのも山崎先生で、財団の設立・運営の中心的な存在です。山崎先生が大切にされた『社交』を再現する場として、お酒を酌み交わしながら会話を楽しめるメモリアルサロンとなっています。この場の空気感から、知に触れる歓びを多くの人に感じてもらえるといいですね。そして、このサロンが社員の交流する場となってくれたら、と思っています」
 本インタビューは「山崎正和サロン」で収録。サロンには山崎氏が使っていたデスクやチェア、文具を配置して書斎を再現
本インタビューは「山崎正和サロン」で収録。サロンには山崎氏が使っていたデスクやチェア、文具を配置して書斎を再現
このように、さまざまな調査や研究を通して、社会に知をつなぎ、社交の場を提供してきたサントリー文化財団。そのキーワードとなる「社交」について、安田さんは次のように自らの言葉で語ります。
「社交とは、お互いに知っている人も知らない人も、かしこまった場だとなかなか言えないようなことを立場にかかわらず率直に言える、そんな研ぎ澄まされた自由さがある場だと思っています。私たち財団の役割は、さまざまな事業を通じて、しがらみのない交流の場を提供し、豊かな思考を育むことにあります」

サントリーはウイスキーをつくっている会社ですが、ウイスキーは10年も、15年も先にできあがるものを仕込んでつくられるお酒です。そういう長い時間をかけて大切なものを育む価値観が、サントリーグループの中には当たり前のこととして根づいています。そして、その価値観が、サントリー文化財団のように「文化を育み社会に還元する事業」にもつながっているのです。
「私たちが目先の成果を求めるのではなくて、『やってみなはれ』という気持ちで、さまざまな研究や調査を後押しできるのも、そんなサントリー精神がこの文化財団に色濃く反映されているからです。それはとても心強い点でもありますね」
利益三分主義、社交、やってみなはれ──。そんなサントリー精神に支えられて活動するサントリー文化財団は、これからも豊かな文化を育成し、社会に向けて発信し続けていきます。
アステイオン
発売月:5月、11月(年2回発行)
価格:1320円
WEB:WEBアステイオン