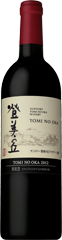登美の丘ワイナリーでは、垣根栽培のB-10と呼ぶ区画でのメルロの剪定も始まりました。

先日お伝えしたように、垣根栽培のやり方では、大きくは「ギュイヨー・ダブル」と「ギュイヨー・シングル」の2つの仕立て方を採用しています。(「垣根仕立てのメルロの剪定作業。今年を考えて、来年の先も考えて。」)
今回レポートするB-10区画のメルロは「ギュイヨー・シングル」という仕立て方です。1本のぶどう樹の主幹から1本の枝を残して剪定する方法で、この1本の枝を「結果母枝(けっかぼし)」と言って、この結果母枝から今年ぶどうが生る「結果枝(けっかし)」が芽吹きます。「ギュイヨー・ダブル」が2本の結果母枝を左右に配するのでダブル、この「ギュイヨー・シングル」は1本なので、シングルと言うわけです。
そして、この結果母枝にいくつ節目を残すのか(=結果枝をいくつに設定するか)は、今年のぶどうの品質を決め、収穫量をコントロールするうえで非常に重要で、それはシングルでもダブルでも同じこと。必ずしも全ての芽が芽吹くわけではないリスクを考慮して、このB園のメルロでは1本の結果母枝に10本の結果枝を出すことを目的として12個の芽を残すように剪定をしています。

では、剪定作業の一連の動きを解説します。
|
|
まず最初に栽培スタッフは、剪定するぶどう樹としっかり向きあいます。どの1本の枝を結果母枝にするかその枝ぶりを見ながら判断していきます。前年の枝の成長が1本1本のぶどう樹によって異なりますので、瞬間的に1本を選択できる樹もあれば、じっくり悩んでしまう樹もあります。 | ||
|
|
残す結果母枝を決めたら、作業はすこぶる早いです。前年の結果母枝を主幹の元から切り落とします。スタッフによって、樹の状態によって作業の後先はもちろん変わりますが、結果母枝を1本残すことに変わりはありません。 | ||
|
|
そして、選んだ結果母枝に12芽残すことを数えて、13芽手前で先端を切り落としてあげます。切り口からの乾燥や寒さで芽が影響を受けないように配慮してあげてのことです。 | ||
|
|
残した結果母枝を「磨いて」あげます。余分に出ている巻きひげなどをきれいに切り落としてあげるのです。 | ||
|
|
前年の結果母枝から伸びた結果枝をどんどん切っていきます。1本切ってから、また1本と、左手に切った枝をまとめて持ちながら次々と切っていきます。 | ||
|
|
切り取った結果枝をまとめてワイヤーから引き抜きます。この時、しっかりとワイヤーに絡まっていたりすると、かなりの力仕事になります。シャンシャンとワイヤーが音を立てて揺れ動きます。 | ||
|
|
結果枝を切り落とした結果母枝をワイヤーに水平に配蔓していた留め金を外して、取り除きます。 | ||
|
|
枝を取り去った後のワイヤーに絡んでいたぶどう樹の巻きひげを丁寧に取り除いてあげます。この巻きひげを残しておくと、後に病害の原因になったりするので注意が必要です。 | ||
|
|
1本のぶどう樹の剪定が完了した形は1本の主幹から1本の結果母枝が上に伸びたようになっています。春になって水を吸い上げて枝の柔軟性を確認してから水平にしてあげます。 1本の樹が終われば、また次の樹をじっくり観察するところから。この作業を栽培スタッフはずっと繰り返すのです。 |
90年代以前の登美の丘の垣根栽培は「ギュイヨー・シングル」がメインでした。その後、「ギュイヨー・ダブル」が主流となり、全ての垣根栽培のぶどう畑の中で「ギュイヨー・シングル」なのは現在この区画だけです。「ギュイヨー・シングル」のままに剪定しているのは、この区画のぶどう樹の間隔が植え付けられた際の設計のままで、「ギュイヨー・ダブル」にするには樹間が狭いということが理由のひとつです。
先日の「ギュイヨー・ダブル」の中でもレポートしましたが、永年作物であるぶどう樹の剪定作業は今だけのことを考えているわけではありません。来年のその先を考えながら剪定作業を行なって行きます。
1本1本のぶどう樹と向き合って、しっかりとした、良いぶどうの実りを得るために栽培スタッフは、ずっと剪定作業に取り組んでくれています。
先日積もった雪の中、空気が澄んで晴れ渡っていたこの日、「今日は甲斐駒(ヶ岳)も八ヶ岳も最高にきれいに見えとるよ」と、笑って声をかけてくれましたが、約20cmの雪の上を歩くのも大変でした。それ以上に、雪を踏みしめている長靴の下からは凍てつくような冷たさが1時間もいるといたたまれなくなりました。足の指先が凍りつくような痛みすら感じて悲鳴を上げてしまいましたが、さすがに栽培スタッフの長靴の中には中敷2枚が入ってて、靴下には貼るカイロを装着してるそうです。「過酷な仕事だよ」とこぼしますが、目の奥には誇りと自信が感じられ、やさしく笑いかけてくれました。


おそらく、このような雪の中での剪定作業を他の国のワインメーカーが見たら呆れるかも知れません。ですが、これが我々が取り組む日本のワインづくりであり、この雪も含めて登美の丘の自然をあるがままに受け入れて、自分たちができる最善の働きかけをしてぶどうをつくり、ワインをつくり、品質を上げていく取り組みを毎年毎年我々は積み重ねています。