 |


 |
「もはや戦後ではない」が流行語となった1956(昭和31)年を過ぎたあたりから、日本人の生活は洋風化の一途をたどります。この当時、円熟したモルトウイスキーと高品質のグレーンウイスキーだけでつくられる、“原酒100%のウイスキー”であるサントリーオールドは、中元歳暮の時期を除いて店頭に並ぶことがないとさえいわれる高嶺の花でした。働く男たちの憧れの酒──1950年代から60年代にかけて、オールドは「出世してから飲む酒」の象徴だったのです。
1960(昭和35)年、池田内閣は所得倍増計画を発表。1964(昭和39)年の東京オリンピックを境に、日本は高度経済成長の波に乗ります。オールドの需要が伸び始めるのは、経済力のひとつの証として、ウイスキー市場が次第に高級化していくのと機を一にします。1968(昭和43)年にはGNPが米国に次いで自由主義世界第2位を記録するほど日本の国際収支は大幅な黒字を計上、円が変動相場制に移行する1971(昭和46)年の貿易自由化を目前に控えて、消費者の目と舌は、いつしか洗練の度合いを高めていました。庶民が口にする酒の種類も、ビールやウイスキーにとどまらず、バーボン、ブランデー、ワインなど多岐にわたり、ライフスタイルの洋風化と消費者の高級志向に弾みがつきます。
一方、バーでのボトルキープの慣習が広まり、“ダルマ”“タヌキ”の愛称で呼ばれ、ここにきて大きく需要を伸ばしつつあるサントリーオールドを、これまで日本酒しか置いていなかった、寿司屋、天ぷら屋、割烹、さらには家庭にも浸透させようと、「二本箸作戦」と呼ばれる一大キャンペーンが展開されたのもこの頃です。そのきっかけとなったのが、「十年まえは熱燗で一杯やったものですが……一日のピリオド。黒丸。」というコピーも鮮烈な1970(昭和45)年の新聞広告でした。寿司屋の主人が店を閉めた後、割烹着のままカウンターで一息ついて一杯やる酒が日本酒ではなくサントリーオールドという図が、和魂洋才のダイナミックな提案として注目を浴びます。この提案は見事受け入れられ、この年に100万ケースのレベルだったオールドの販売数は、驚天動地の急伸を見せ、1974(昭和49)年に500万ケースを突破すると、1978(昭和53)年ついに1000万ケースの大台に乗り、1980(昭和55)年には世界の酒類市場空前の1240万ケースに達しました。 |
 |

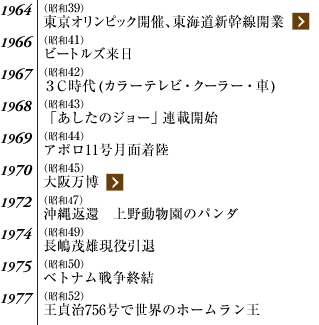
 |
 |

 |
|
|
 |