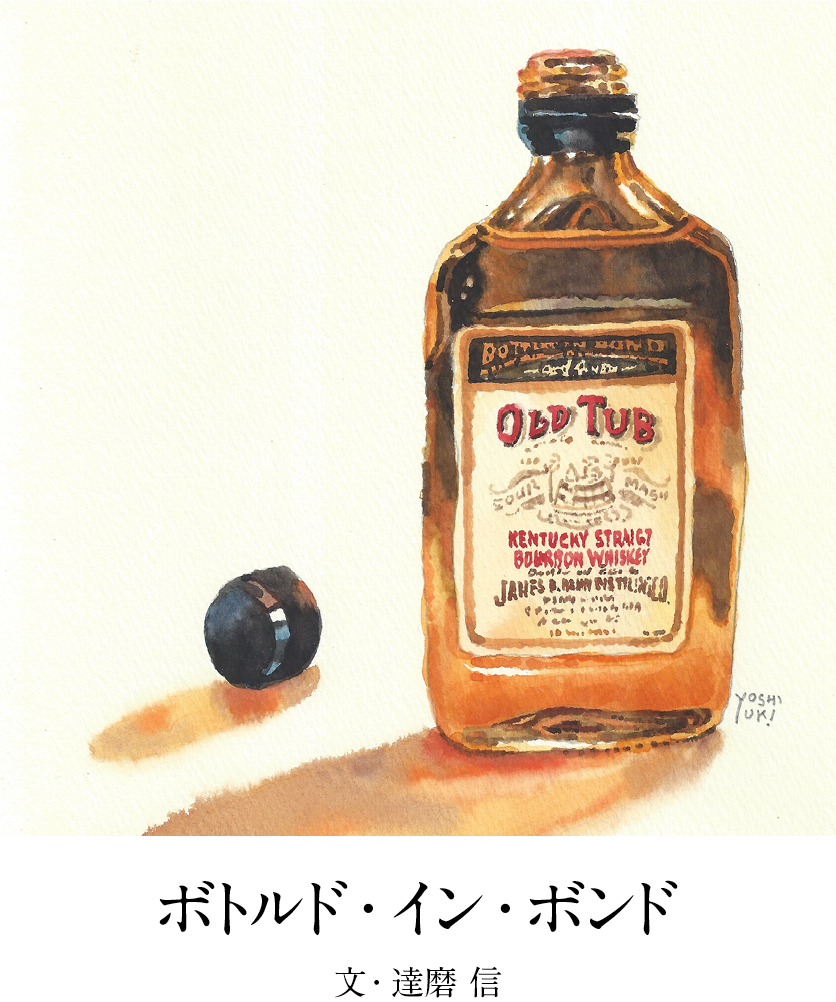第22回「ジャーマン・アメリカン」からのつづきです。
19世紀のアメリカンウイスキーは、東部を中心につくられていたライウイスキーを主役にしながら、ケンタッキーのバーボンウイスキーが伸張する。それ以前は、一部上流階級はシャンパン、シェリー、マデイラワインなどを好み、一般市民はまずはビール、つづいてライウイスキーというわかりやすい図式にあった。ところが19世紀に入ってから変化していったのである。
面白いことに1817年から45年間もウイスキーの課税が廃止されていた。復活したのは南北戦争中の1862年のことで、ライとバーボンの生産増大は財政当局にとって見逃せない魅力的な税源となっていたのだ。ウイスキーはナショナルドリンクへと成長していた。
一方で禁酒運動が高まり、課税するにはもってこいの機運でもあった。禁酒派の圧力に加え、南北戦争によって当然のように財政難に陥ると1865年にはついに10倍もの課税となる。
そこで何が起きるか。そう、続々とムーンシャイナーと呼ばれる密造業者たちが暗躍しはじめる。Moonshinerと綴るが、人里離れた山奥や渓谷に隠れ、月明かりの下でひっそりと蒸溜した様子を物語る。彼らがつくる密造ウイスキーはムーンシャインと呼ばれた。ウエストバージニア、ケンタッキー、テネシー南部のアパラチア山脈がムーンシャインの拠点となった。
1870年代末にはウイスキー産業の発展はよりめざましく、トラストを結成するほど大企業化されていく。1876年には蒸溜酒税収は国内税収の50%を超え、なかでもウイスキー税収は大きな割合を占めるようになっていた。これは驚くべき数字といえるだろう。ただし所得税徴収がなかった時代のことである。
そんななか、山奥では粗末な蒸溜器を使いながら密造する者たちがたくさんいたのだ。1878年の政府報告では5,000の密造蒸溜器が存在すると記録されている。ただし正確な数字を求めるのは困難であっただろう。
悪酒がはびこれば市場は混乱し、税収にも影響をおよぼす。そこで1879年にウイスキーの3年熟成(現在は2年)が定められた。スコッチウイスキーが熟成2年を法律で義務づけたのが1915年(翌16年3年熟成に改訂)だから、熟成に関しての法制化はアメリカのほうが進んでいたということになる。
それでも密造酒は世に出まわる。さらにはウイスキー需要拡大に乗じて、水で薄めたり香料を混ぜたりしたイミテーションのひどい代物で取引する業者まで現れた。