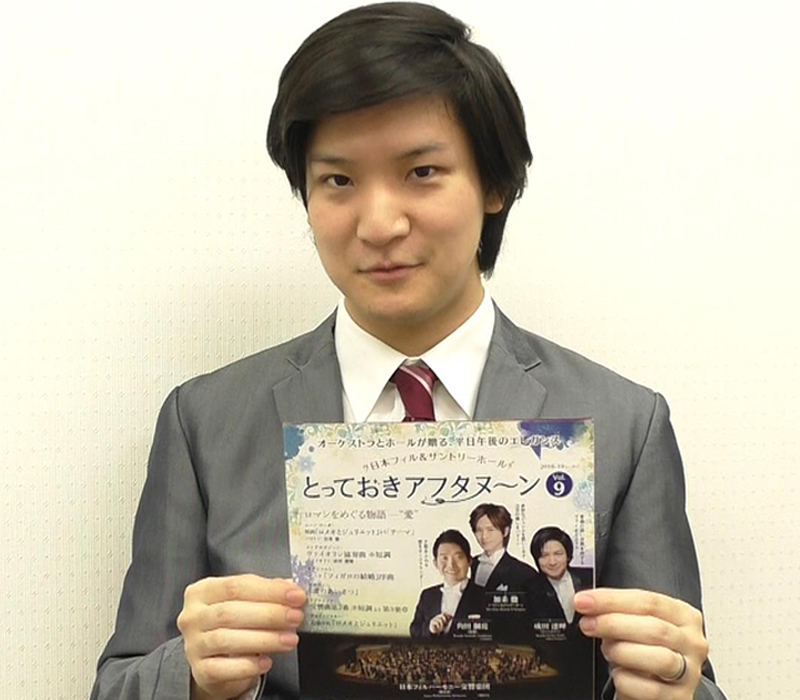<ロマンをめぐる物語 ―“愛” >
ヴァイオリン・成田達輝インタビュー
サントリーホールと日本フィルハーモニー交響楽団が平日のマチネでお届けするシリーズ「日本フィル&サントリーホール とっておき アフタヌーン」。2018-19シーズン最終回のソリスト、ヴァイオリンの成田達輝さんにお話を伺いました。

成田達輝
ⒸMarco Borggreve

成田達輝
ⒸMarco Borggreve
角田鋼亮さん指揮する日本フィルハーモニー交響楽団と、メンデルスゾーン『ヴァイオリン協奏曲 ホ短調』を演奏されますね。
いわゆるヴァイオリンの名曲、すばらしい曲です。今までに何度も演奏してきました。最近では2016年にプラハ交響楽団と。日本フィルさんとも、2013年に山田和樹さんの指揮で演奏しています。が、何回演奏しても、まだよくわからないんです。謎ですね。こういう有名な協奏曲を演奏する時には、その作曲家がイメージしている音はもちろん大切にしながらも、自分がどう感じるかを大切にしなければいけないなと思っています。曲が書かれた当時と現代の演奏法は違いますし、歴史的演奏法をなぞるよりも、自分がその時に感動している音というのが常にあればいいなと思って弾いています。演奏家がその場で「あ、素晴らしい音だ」と感動することが、音に伝わり、聴く人に伝わると思うんです。今どき、インターネットで検索すれば曲はすぐダウンロードできますし、有名な作品が収録されたCDは何百枚もありますし。聴いていただくお客様には、自分はどういう演奏が好きなのかということを探りながら聴いていただき、音楽家はどういう音が訴えかけられるのかということを真剣に考えて演奏する。それが“とっておき”な時間になるのではないかと思います。
まだ謎だとおっしゃっていましたが、それを読み解きながら、感じながら演奏されるのですね。
そうですね。謎……わかることは、ないんじゃないですかね。楽器との関係でも同じです。この楽器のことはもうよく知っているからどんな風に弾いても自分の音だ、となって、一つにまとまる。それで曲と対面し、何度も何度も演奏することで自分のものになり、また一つにまとまる。それを繰り返していても、人生で経験するいろいろなことを通して、自分が成長して変わっていく。楽器は変わらないけれど、それに応えてくれる。もしも楽器が応えてくれなくなれば、ちゃんと次の楽器に巡り会う。そういう風に回っていると思います。
成田さんが今使われているのは、かのストラディヴァリウス、1711年製の「タルティーニ」ですね。
2016年に出会ったのですが、もう自分の音、自分の声です。それまで使っていたグァルネリは、自分の声帯になるような感覚で、そこから発声する感じ。ストラディヴァリウスは、楽器本体から音は出るんだけれども、それは自分の許したものでもあるし、自分がもともと持っている音や声などのトータルが楽器から出ている。
音楽は、絶対に音楽家の中にあるんです。そういうのをうまく伝えられる演奏会になったらいいな。
-

ⒸMarco Borggreve
成田さんが最近、ご自身のストラディヴァリウスについてお話しされていたインタビューのなかで、「協奏曲を演奏する時、どんなピアニッシモで弾いても、オーケストラと違う次元に音があり、お客様に伝わる」とおっしゃっていましたね。
そうですね。違うレベルというのは、技術や音量のレベルではなく、音色の独自性というのでしょうか。楽器が自分とコネクトすると、自分らしさが伝わるので、他にはない自分の音楽になる。音楽というのはその人の個性を伝えるものだと思うんです。その個性をいかに伝え得るかということが、楽器にも大きくかかわってくる。ぼくが共感できるのは本当に個性的な演奏家、ギドン・クレメールさんやイヴリー・ギトリスさん。そういった人たちの個性はどのようにして作られるのか、それは自分が感じたままの経験を演奏してきたからだと思う。今26歳という年齢ですが、ぼくは、まだそうやって自分らしさを伸ばしていきたいのです。
というのも、一昨年になってやっと、自分の音楽というのを客観的に見られるようになったからです。それまでは、自分の中にある音楽がどういう形をしているのだろうと繰り返し模索していたのですけれど、一昨年の夏以降ですね、なぜかわからないけれど、初めて認識した……どう言ったらいいんでしょう、子どもが生まれたような感じで、本当に客観的な関係になったのです。自分の中にあるもの、現時点での自分の音楽性を理解した。あとはそれをどういう風に伸ばしていくか、育てていくか。あとはいろいろな曲を経験して、音楽ってこういう考え方もあった、こういう見方もあったのかということを学んでいく。そういう段階にやっと入りました。
-

「日本フィルハーモニー交響楽団 第44回夏休みコンサート」
指揮:角田鋼亮、2018年7月
では今回は、成田さんがそういう段階に入ってから初めて弾くメンデルスゾーンの協奏曲ということになりますね。とても楽しみです。協奏曲ですから、オーケストラとの一体感というのも大切だと思いますが、日本フィルとは、どのような印象がありますか?
ぼくがいちばん最初に、オーケストラとヴァイオリン協奏曲を初めて共演させていただいたのが、日本フィルさんなんです。15歳の時に出た「東京音楽コンクール」でのプロコフィエフの作品で。すごく緊張していましたし、よく覚えています。そのあと、このメンデルスゾーンは先ほど話した2013年に、山田和樹さんの指揮で。だから日本フィルとの協奏曲の共演は、まだ3回ぐらいかな。
オーケストラの音色って、オーケストラだけで鳴った時の音色と、指揮者が入った時に大きく変わるので、一概には言えないかもしれません。今回の指揮者の角田さんとの共演は3回目ですが、角田さんと日本フィルさんは、昨年の夏休みコンサートで17公演もご一緒されてとても良い関係と聞いていますので、角田さんと日本フィルさんの親密な関係性に、ぼくもどんどん巻き込んでほしいです。
指揮者、オーケストラと共演する協奏曲では、ソリストとその他みたいに分断せず、いかにひとつになるか。有機的なものをつくりながらも、それぞれの個性が出てくるということが、音楽が響く一番正しいやり方だと思いますね。そしてソリストとしてどういう風に振る舞うか、責任も感じています。
リハーサルというのは、やりとりを一方的にさせないというか、できるだけすべての音に配慮して、音で少しずつ波長を合わせていくという作業です。そして、その取り組みを本番の最後までやめないということですね。
音だから形として残らない。音による学びの素晴らしいところは、そこです。常にその瞬間というか、常に流動的で学ぶことができる。そして、みんなで共有して、あとはその場限りでさっぱりと。
-

「日本フィルハーモニー交響楽団 第44回夏休みコンサート」
指揮:角田鋼亮、2018年7月
昼14時からの公演になりますが、演奏者側にとって、夜公演と気分が違うことなどありますか?
確かに、精神的な準備の仕方は違うかもしれませんね。友人のピアニストの言葉を借りれば、演奏会前は常に、自分の刺激と内面の静けさをいかに保つかということを考えています。冷静と情熱の間みたいな。どちらかに偏ってもいけないし。あとは、昼の公演の後は、夕方からビールを飲みに行けますね(笑)。
聴きに行く方も、夜のコンサートだと、それを楽しみに1日ずっと待ち時間みたいになりますが、昼のコンサートだと、楽しみに行って、聴いて、それからまだ半日あるという。
そうですよね、火曜日の昼にコンサートに来る気持ちって、のびのびした感じですよね。
コンサートって、お客さんとつくるものです。オーケストラが100人いても、オーケストラだけではなくて、それを聴いているお客さんがどのように反応しているかという微細な波みたいなものを実は演奏家も感じとっていて、それによってまた演奏も変わっていきます。それは本当に大切にしたいですし、それこそ素晴らしいサントリーホールの響きでそれを共有できるというのは、すごいことだと思います。
先日、サントリーホールの音響設計をされた豊田泰久さんと一緒に、ゲルギエフ指揮ミュンヘン・フィルのリハーサルを聴く機会があって、どの席がいいかという話になって。ぐるぐるぐるぐる客席を巡って、色々なところで聴いてみたんです。ピンポイントですが、バルコニー席のステージに向かって左側のLCブロック6列6番、ぼくはここが音響的に完璧だと思いました。サントリーホールは2階席の一番後ろで聴いても、全部聴こえてくる。色々な場所で聴いてみると、バランスが変わってきて、面白いですよね。素晴らしいホールですよ。サントリーホールはその多くが木でできていますから楽器と同じで、どんどん変わっていきますし、木が演奏家と聴衆に与えるエネルギーも変わってくる、そういうことは絶対にあると思います。
最後に、“とっておき”アフタヌーンにちなんで、成田さんにとっての“とっておき”を教えていただけますか? 日々の暮らしの中で、自分にとって今これがいちばんお気に入り、みたいな。
なんだかんだ言ってぼくは、ヴァイオリンを弾くことが本当に好きで、ヴァイオリンを弾いている時がいちばん落ち着きます。いちばん安心するし、いちばん楽しいんですよね。ヴァイオリンをひとたび弾き始めると、ふっと、今まで考えすぎていたものも全部収まるし、瞑想と同じで、より自分らしくなるというか、ニュートラルになるんです。もし何かとても悲しいことがあると、それをヴァイオリンの音が慰めてくれます。不思議ですね。ぼくの“とっておき”は、やはりヴァイオリンを弾くことです。練習しない日が1日あると、ずっと不安です。弾くと感覚が戻ってくるというか。不思議ですね。
それは小さい頃からずっとですか?
もしかしたら、この楽器になってからかもしれません。サントリーホールの木が語りかけてくるのと同じように、ストラディヴァリウスは300年前に作られたものですから、この楽器しか持っていない波長があるというか。一緒にいると落ち着きますね。結局、音楽が自分を落ち着かせるのだと思います。音楽をやっている時が、自分がいちばん自由なんです。
ヴァイオリンを弾くことがいちばんの“とっておき”という成田さんの演奏、楽しみにしています。