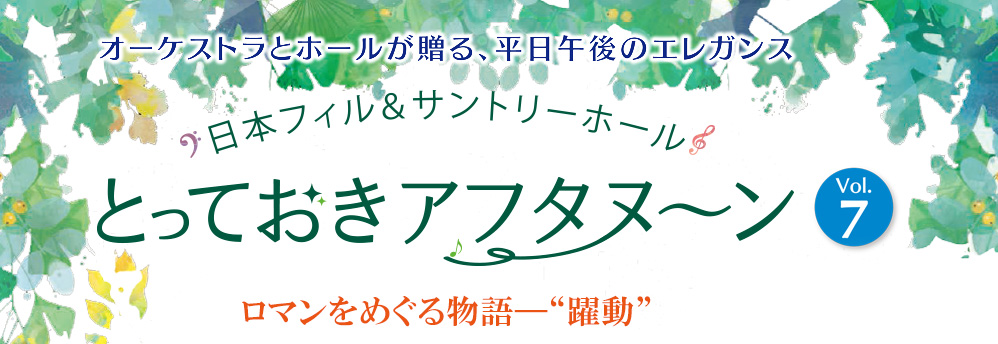
チェロ・宮田大インタビュー
サントリーホールと日本フィルハーモニー交響楽団が平日のマチネでお届けするシリーズ「日本フィル&サントリーホール とっておき アフタヌーン」。2018シーズン初回の5月2日公演に登場する宮田大さんにお話を伺いました。
*ホテルオークラ東京から
「特別なおもてなし」プランはこちら
チェリストの宮田大さんが、最初にサントリーホールのステージに立たれたのは2002年。桐朋学園音楽部門創立50周年記念コンサートで、同窓の名だたる演奏家の皆さんによるオーケストラをバックに、まだ在学中の宮田さん(16歳)がソロを弾かれました。
こんなに大きなホールで演奏するのは初めてで。指揮の小澤征爾さんから、上の方まで音が届くように演奏しなさいと言われたのを覚えています。サントリーホールは、本当に、思い出がたくさんあるホールです。
2010年には国際コンクール優勝者として、2011年以降はソリストとして、毎年さまざまなオーケストラとサントリーホールで共演されています。
2年前には無伴奏のリサイタルを初めてやったのですが、これだけ大きな空間でポツンとひとりぼっちで弾くと思うと萎縮してしまいそうですが、それまでサントリーホールでたくさんやらせていただいていた経験から、大きなホールと思わずにいられたことが自分の中ではよかったんです。大きなホールなのに響きがすごく近くに感じるというイメージを、演奏者としても聴き手としても持っていましたから。オーケストラとのリハーサルのときに、客席のいろいろな場所に座ってみて、後ろのほうまでどのぐらいの音が聴こえているのか確認したりするんです。ですから、音が響き渡ることを知っている馴染みの空間で、気持ちよく演奏することができました。
「とっておきアフタヌーン」Vol.7では、鈴木優人さん指揮、日本フィルハーモニー交響楽団との共演です。
鈴木さんは、同じような時期にデビューした同年代の音楽家という思いがあります。指揮者としての鈴木さんとは初めての共演なので楽しみにしています。彼も楽器を弾くプレーヤーだから、より一層、指揮は面白いと思います。本当に音楽がわかってくれている方だと思います。
日本フィルの皆さんとは、2年ほど前に九州ツアーで密度濃く共演させていただいて、いちばん長い時間一緒にいたオーケストラなんじゃないかな。2年前にツアーでドヴォルザークのコンチェルトを、リハーサルを含めてたくさん弾かせていただいたのですが、何度も弾く中で、自分がいつもと違ったテイストで弾くと皆さんどういう風に反応してくれるのかなということを心掛けながらやっていたんです。自分がいろんなテイストで弾くと、オーケストラがすごく反応してくださる。一度で、ああ、この人たちは自分と一緒に音楽をやってくれようとしているということが頭にインプットされました。今回のチャイコフスキー、より一層楽しみです。
今回演奏される曲は、チャイコフスキー『ロココの主題による変奏曲イ長調』。宮田さんの超絶技巧を存分に楽しめる曲だと、鈴木さんがおっしゃっていました。
そうですね、もちろん技巧的な部分もあるのですが、『ロココ~』のいちばんの魅力は、小編成のオーケストラで小回りがきくと言うか、自分がオペラの一幕を歌っているように、オーケストラの人たちと一緒に空間を、物語をつくっていくような感じだと思うんです。早いパッセージもありながら、チェロの魅力的な音色でアリアを歌うような場面もあったり、いろいろな楽器と絡み合ったり。さまざまな楽器の音色が出てきますので、チェロとしては、とても太った役者の声なのか、きれいな女性なのか、声の響き方とか通り方とか音色のバラエティを想像しながら演奏できたらと思います。派手にテクニカルな感じで弾くのではなく、かすかに聴こえるチェロの繊細な音や、いろいろなニュアンスをオーケストラと共有しながら弾きたいです。お客さんには、耳を澄まして、物語を想像して、オペラを一幕見ているような気持ちで聴いていただけたら嬉しいですね。15分ぐらいの短い曲ですが、内容の詰まった作品です。
チャイコフスキーはメロディーメーカーですし、とても物語性があると思います。チャイコフスキーのチェロとオーケストラのための作品はこれだけなんです。チェロ協奏曲は無くて。ピアノコンチェルトとかヴァイオリンコンチェルトとか、華やかで、めちゃくちゃいい曲だったりするんで、すごく羨ましいです(笑)。この曲を、チャイコフスキーがチェロのためにこういう風につくったということは、チェロの人間の声に似ているような音で、ひとつのオペラを見ているように聴いてほしいという気持ちでつくったんだろうなと感じます。
やはりチェロのいちばんの魅力は、人間の声に近いというところなんですね。

宮田大 無伴奏チェロ・リサイタル(2016年9月10日)
そうですね。太い音がしたり、高い、むせび泣くような音がしたり、人間のサイズから性別からいろいろと真似できる楽器なのではないかと思います。『ロココ〜』の中でも、いろいろな人間が出てくる感じです。
オーケストラの中でも、低音を支える役目をしながらも、めちゃくちゃいいシーンでチェロがメロディーを持っていく、みたいな(笑)いいところで使ってくれる作曲家が多いですね。伴奏もできるしメロディーもできるし幅広い魅力があるのではないかと思います。
それに、チェロの音色は、夜寝るときも朝起きるときも、ちょっと悩んでいるときもリラックスしているときも怒っているときも、どんな時でも聴ける音なのかなと思います。ま、曲によってもあると思いますが。
宮田さんにとってチェロはどんな存在ですか?
こうやって喋っているよりも、チェロで奏でているときのほうが、言いたい言葉がもっと言えているというか、どういう風に悲しいのか、どういう風に楽しいのか、自分の中にある感情が楽器を通していちばん出るかなと思います。
チェリストはみんな心臓のちょっと上あたりにアザがあるんです。アザができるぐらいずっと楽器が身体にあたっていて、常に振動を受けているので、一体感があります。そうそう、サントリーホールの舞台の床のいい位置にエンドピン(床に立てて楽器を支える棒状の部品)を刺すと、演奏中に足がしびれるんです。音の振動が床から伝わってきて、チェロと自分が円状になって響かせているという感じです。口開けて弾くと、もっと響くのかな?スピーカーみたいに。脂肪たっぷりの人のほうが響いたりもするのかな?検証してみたいですね(笑)。
サントリーホールの堤館長とは桐朋学園の同窓で、最近では室内楽の祭典「チェンバーミュージック・ガーデン」などで共演されていますね。
とってもお忙しいのに私の演奏会にはよく来て下さって。でも何もおっしゃらないんです……本当はいろいろ講評とか言ってほしいんですけれど、何もおっしゃってくれないんですが、最後に握手をして「よかったですよ」と言って下さるあの笑顔を見るだけで、あ、よかったんだと思おうと考えています(笑)チェリストはみんな個性が違ってきますし。みんな仲が良いので、お互いにリスペクトしていければいいのかなと。
昼間の公演(マチネ)は、夜の公演とは気分が違いますか?
自分は、昼の公演のほうが好きですね。夜の公演は楽屋入りしてから本番まで待つ時間が長いので。昼公演は、朝起きてからコンサートまで気分がもっていきやすくて、集中できます。お客様も、お年を召された方とか、最近はお昼の公演のほうが来て下さる方が多いみたいですね。
“とっておき”アフタヌーンにちなんで、宮田さんにとっての“とっておき”を教えてください。
そうですねー……好きなお酒を飲んでいる時間は、とっておきかな。常に演奏のことを考えていますし、夜11時ぐらいまで練習できちゃう部屋に住んでいるので、弾かないようにお酒を飲むというか。スイッチを切り替えて、飲んじゃったから、今日はもう練習終わり、みたいな。休みがあるようでないような、ないようであるような暮らしなので。
あとは、スキューバダイビングですかね。色合いとか、日常生活とはぜんぜん違いますし。無音の時間。自分の吸っている息の音しか聴こえないので。先日も、沖縄公演のあとでちょっと潜ってきたんです。今回は、鯨の鳴き声が聴こえて。鯨とかイルカとか、ちょっとした鳴き声を出すような子たちしか喋らない、そういう音しか聴こえないので、まったく違う世界ですね。とっておきの時間かもしれません。
リサイタル、協奏曲のソリスト、室内楽など、様々な場面で活躍の場を広げる宮田大さん。お昼間の特別なひととき「とっておきアフタヌーン」では、また新たな魅力を感じていただけることと思います。ありがとうございました。

「チェンバーミュージック・ガーデン2016」
チェロ:ロベルト・ノーチ、大友肇、堤剛と共演
「チェンバーミュージック・ガーデン2017」
ヴァイオリン:成田達輝、ピアノ:ハオチェン・チャンと共演









