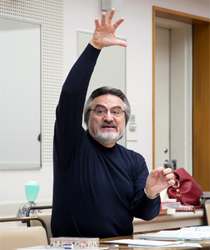サントリーホール オペラ・アカデミー 2017の活動
-

ジュゼッペ・サッバティーニ
6年目の長いシーズン
エグゼグティブ・ファカルティとしてジュゼッペ・サッバティーニが指導するサントリーホール オペラ・アカデミーの6年目は、例年より少し長いシーズンとなった。というのも2017年2月から約半年、ホールのリニューアル休館期間があったからだ。そのため、修了コンサートは17年9月末と1年以上に及ぶシーズンとなった。
また、シーズン途中で「声楽アンサンブル・コンサート」が5月25日に催され(練馬文化センター小ホール)、オペラ・アカデミーのメンバーによるロッシーニの『小荘厳ミサ曲』の演奏もあった(ピアノ2台とハルモニウムによるオリジナル編成版)。プリマヴェーラ・コース第3期の修了者は16名。これまでで最も多く、その点でも充実したシーズンだったといえるだろう。
サントリーホール オペラ・アカデミーに参加する理由
6シーズン目とあってサッバティーニは例年以上に生徒一人一人の声の質、歌唱力、成長段階に即した指導を行ったように見えた。親身な指導だが、それは同時に手を抜かず、弱点の核心を突くことでもある。
名古屋拠点でレッスンの度にバスで上京してアカデミーに参加した受講生は、「調子が悪い時でも行けば必ず身になると思い頑張って行きました」とその意気込みを話す。彼女はサッバティーニ以外の月2回のファカルティ・レッスンにも参加していたのだから、その姿勢は本物だ。「自分でも気付いていた悪い癖、誤魔化していた部分を、ここではっきり指摘され真正面から向き合うことができた。こういう機会がなければ決して直すことができなかった」とのこと。
別の受講生はこう話す。
「ここへ来ると根っこから直してくれる。2年間通い続けるのは大変だけど、将来を考えれば、いずれはやらねばならないこと。そう考えれば集中して直してしまったほうが、むしろ速いと思いました」
-

ジュゼッペ・サッバティーニ
-

変わらぬ厳しいレッスン
その“大変な”レッスンは今シーズンも変わらぬ様子だった。
「単純に声を出してはダメだ!美しく響く声を出しなさい」
「単なる大声と正しい発声による大きな声は違う!」
「自分が聞いていいと思う感じと他人が聞いて良いというのは違う」
「声を響かせる位置がおかしい」、「体幹の使い方を忘れたのか」
「今日は少し良くなった。あと98パーセントやる事がある」
かくも厳しい愛の鞭を1時間にわたって受けるのは精神的にも、体力的にも受講生には簡単ではないだろう。一方、歌い通せば5分にも満たない曲を1時間も掛けて解体し、注意点を指導するサッバティーニの指導力、丁寧さにはやはり脱帽する。
例えば、ヴィブラートをつけた発声一つとっても、「単なる発声とヴィブラートを掛けた声はこう違う」と歌ったり、時にはジェスチャー、ハミング、口笛を交えて細かく指導していくプロセスには驚いた。(サッバティーニの口笛は音程もしっかりしていて実にうまい!)
発声の基本は一年目に習得済みが前提。今シーズンの指導は曲作りにあるのだが、それでも発声がおかしいと有無を言わさずその場で修正が入る。
興味深いことに、アドバンスト・コース受講生でも同じような感想を話す。
「調子を崩し、自分の歌い方を失っていた時に、ここへ来ると、調子を取り戻すことができた」
アドバンスト・コース受講生はすでに一般の舞台でも歌い始めている若手たちだが、オペラの舞台に立っている者にも手抜きなく指導することが、逆に参加動機になっているようだ。
アドバンスト・コースのレッスンはこんな感じの指導になる。
「声をブラッシュアップすることを忘れずに」
「音階を流さず、一つ一つきちんと出すように」
「テンポは恣意的にならないように」
音が上下に飛ぶ難しい曲ほど「音程は正確に」と指摘。おかしければ、その場で確認させる。また、レチタティーヴォでも「音階を勝手に変えないように」と間違いは見逃さない。
プリマヴェーラ・コースとは違い、受講生には知識もあり修正能力があるとわかっているので、指導態度はソフトだが、修正ポイントはやはり基本に戻れということで一致する。
能力を伸ばす
こうレポートすると、厳しい印象が先行してしまうが、そうではない。
指導内容への理解が深まり、且つ実践できている受講生には、「もっと歌って」、「なかなか良いよ」と止めずに、そのまま歌わせる。そして、上手く歌えると本番さながらにサッバティーニは立ち上がって、大きく指揮しながら、抑揚の付け方や、テンポの動かし方などをそのまま指導していく。或いは、「こんな風に歌ってみたらどうだろう」とその場で、自ら歌ってみせる(相変わらずの美声で)。
そして、良ければはっきり褒め、「しかし、ここを直すともっと良い」というように、さらに磨ける点を指摘する。
プリマヴェーラ・コース受講生の場合、往々にして歌い通すことで精一杯で、最後まで辿り着くと安心してしまうことがあるが、「終わり方も大事!」と、すかさず最後の数小節を繰り返し歌わせ、フィニッシュのまとめ方も指導する。
長いシーズンだったせいもあり、プリマヴェーラ・コース受講生全体との意思疎通が例年になく良かったように感じられた。そのため、サッバティーニも10数名の受講生の全レッスン結果を記録しているので、段階的に良くなった部分も積極的に褒める。2年目にもなると、出来の善し悪し、オペラ・アカデミーの指導内容の実践度の進み具合に個人差がはっきり出るので、それを織り込んだ指導だった。
そして、今の段階だと、どのような曲を歌えばその成果がわかるか、というような具体的な方向も示したりもする。
レッスンから一歩離れると、「厳しい日々を一緒に過ごしていた受講生は皆可愛い」と愛情を示すサッバティーニだが、今後の方向性については、決してごまかさない。
「ここで受けたレッスンから、自分がどの水準にあるのか理解できたでしょう。その上で、コースの終わりまでにどの水準を目指すのか自分で決めて下さい。全員がソリストになれるとは思わないように。しかし、それぞれが伸ばす目標は決められる筈です」
ソリストの場合、どのような劇場で歌うことを目指すのか、そこまでの具体像を考えるようにと諭すこともあった。また、ソリストになれない場合は合唱ということになるが、その場合どんな合唱に参加するのか、或いはアンサンブルなのかということになる。
練馬文化センターで演奏されたロッシーニの『小荘厳ミサ曲』は水準の高い演奏だった。声質は普段ソリストのレッスンを受けていると感じさせる手応えがはっきりあるもの。そして、曲中、ソロを受け持てる者とそうでない者が出てくるのも、日常のレッスンの結果だとわかる内容だった。一般聴衆の前で披露する以上、手抜きが出来ないと考えるサッバティーニやファカルティによる選抜は当を得ていたと感じられた。
-

-

ロッシーニ『小荘厳ミサ曲』 指揮:ジュゼッペ・サッバティーニ 演奏:サントリーホール オペラ・アカデミー(2017年5月、練馬文化センター)
今シーズンのレッスンの力点
サッバティーニによる「曲作り」レッスンはこんな感じだった。まず、歌詞の説明をする(させる)。言葉を確認する(させる)。そして、歌っているのは誰か、どんな人物か。どのような場所で歌っているのか。その情景はどのようなものか、と対話していく。
例えば、「夕方」という言葉が歌詞に出てくると、陽がまだあるのか、それとも沈んでいるのか。空の色は何色か。というようにまるで映画の1シーンのごとく細かに問答をする。次いで、なぜそのような場面が設定されているのか。「夕方」というには単に歌い手の背景なのか、或いは心情に反映しているのか。いや、心情を反映した情景ではないのか…
「夕方や日暮れの情景は、打ちひしがれた時の心情」
そう説明するように、歌詞の読み込みはどこまでも深くなっていく。そしてさらに、夕方から語り手は次にどう進むのか、という展開を考えさせ、その時の気持ちにまで踏み込むように持って行く。
愛に関する歌の場合は、その愛はどのような状態なのか、今始まったばかりの愛か、過去はどうだったのか、ここでは過去別れたことがあるのではないか、などとやはり歌詞を深く読み込んでいく。そしてさらに、歌詞には現れていない部分にも言及する。
「2人の関係は壊れたことがあっても、愛と言う存在は壊れない、というのが歌の趣旨ではないのか」
歌詞は単なる言葉の連なりではなく、〝詩〟で有る以上、詩によって何を表現しようとしているのか、という点まで考えるのは当然のことだろう。
サッバティーニは、ある時は歌詞の内容をまるで劇を演じているかのように、ジェスチャーを交えて詳しく説明する。もちろんイタリア語で。このアカデミーで、まずイタリア語を学ぶようにと指導されている大きな理由だ。
「歌詞の中の世界を良く理解し、そこにいるかのように想像しなさい」
「情景、そして心情、それが歌」
こうしたやりとりが受講生と交わされた後、ほとんどの場合、歌は見違えるようによくなる。
「日本の音大ではイタリア古典歌曲は1年目でやる程度。それもちょろっと。ところがここへ来て、こんなにも深い世界があるのかと驚かされます。特にサッバティーニ先生の解説には驚きの連続で、こんな音楽があるのか、と気付かされ、身につけることで大きな力になりました」と受講生は話す。
リハーサルから本番へ
筆者がシーズン修了時のコンサートを聴くのは6回目だったが、これまで直前の練習と較べてもコンサート本番で大きく変わる受講生がいることに驚くことがあった。そこで、今回その秘密を知りたいと思い、リハーサル見学の機会を得た。
形式的には本番同様、出演順に受講生が登壇して歌い、それに対してサッバティーニやファカルティたちがアドバイスをしていくもの。全員が登壇するためにレッスン時とは違い、一人一人の時間は歌プラスアルファぐらいの時間のみで決して長くはない。形だけみれば、拍子抜けするぐらいシンプルなものだった。
しかし、僅かな時間でのやりとりが本番に向けて、受講生たちの声を大きく変えていくことがわかった。
その最大の理由はホールの響きだ。小ホールといえども、ブルーローズは400名前後のキャパシティがある。普段レッスンで使うリハーサル室は、リハーサル室としては天井がとても高く、音も響くが、やはりブルーローズとは違う。今期は声量ある生徒が多いと思っていたが、それでも本番の舞台は異なる。
「ここへ来ると音のごまかしがきかないぞ」
「荒が目立つホール。上手い人には味方するが、誤魔化している人には厳しい」
そうした注意点がサッバティーニやファカルティから次々と飛ぶ。正しく発声されている声はより響くが、そうでない音は逆になる。リハーサル室では少しの差に聞こえていたものが、ブルーローズでは大きな差になって表れるのだ。
そのため、曲づくりや表現に関する最終的なアドバイスもさることながら、リハーサルでの最も大きな課題は、ホール内でどれだけ音を伸ばせるか、響かせることができるのかに指導の重点があることがよくわかった。
修了コンサート
2年間を締め括る「アカデミー修了コンサート」は、ホールの改修が済んだ後の9月28日にブルーローズで行われた。第3期プリマヴェーラ・コースの歌手はソプラノ7名、メゾ・ソプラノ3名、バス、バリトン4名の計14名と例年より多くなった。大ホール同様新しい床に張り替えられたブルーローズは、多くの来場者があっても一段と音が響くように感じられた。
休憩を挟んだ第1部は、プリマヴェーラ・コース受講生によるイタリア歌曲。トスティだけでなくオペラで著名なドニゼッティ、ヴェルディ、ロッシーニの歌曲を取り上げる受講生もいた。オペラ作曲家の歌曲は、アリアなみにドラマティックで、各作曲家の特徴をすぐ想起させるような曲想なので、聴く側も楽しめるものだった。
第2部は例年どおりアドバンスト・コース受講生によるオペラ・アリア。ベッリーニ『カプレーティ家とモンテッキ家』、ロッシーニ『セビリャの理髪師』、同『ブルスキーノ氏』のアリアが披露された。
第1部受講生も後半になると技術も歌声も聴き応えあるものだったが、第2部ではピアノの反響板をより高く上げていたこと一つ取っても、第1部受講生にはまだまだ伸ばすべき点があると気付かされた。
「イタリアへ行かずとも本場の指導を受けられる貴重な機会」
コンサート後、受講生たちからはこうした声が寄せられた。
一方、今回修了コンサートに2名のピアニストが参加したように、鍵盤奏者も「歌の理解をより深められる貴重なレッスンだった」と話す。単なる伴奏ではなく「曲をつくる」のは鍵盤奏者も同じだと理解したという声が聞かれた。