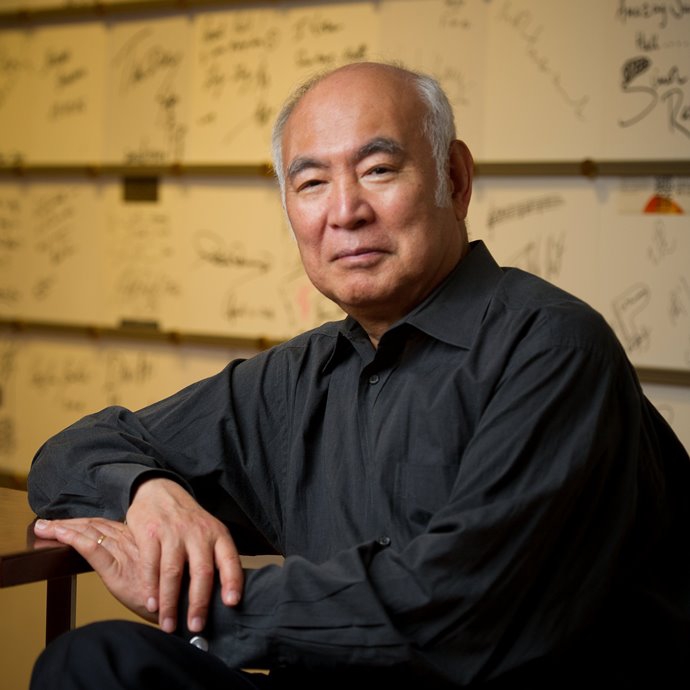
古今東西の室内楽の名作を集めてお贈りする「チェンバーミュージック・ガーデン(CMG) 」は2011年からのスタートで、本当に色鮮やかな音楽の花が咲き競う「庭(ガーデン)」を楽しんでいただける音楽祭として、東京の初夏の風物詩となって来たように思います。
今年も様々なプログラムをご用意しましたが、ひとつ大きな特徴としては、管楽器を含む作品が例年より多く、ホルンのラデク・バボラークさんをはじめ、工藤重典さん(フルート)、吉井瑞穂さん(オーボエ)、吉田誠さん(クラリネット)など、名手に集まっていただき、比較的演奏されるのが珍しい管楽器を加えた室内楽を取り上げることになりました。
室内楽と言えば、弦楽四重奏曲やピアノを加えた室内楽作品が中心となっていますが、管楽器もとても重要な役割を持っていますので、あらためてそこに光をあててみたいと思っています。さらには、そこに三味線や尺八というCMGで初めて取り上げる邦楽器も加わります。こちらも乞うご期待です。
また、こちらも恒例となりましたベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲を演奏する「ベートーヴェン・サイクル」には、ロシア出身の実力派であるアトリウム弦楽四重奏団が登場します。ヨーロッパを中心に活躍し、高い評価を得ている彼らの演奏も楽しみです。
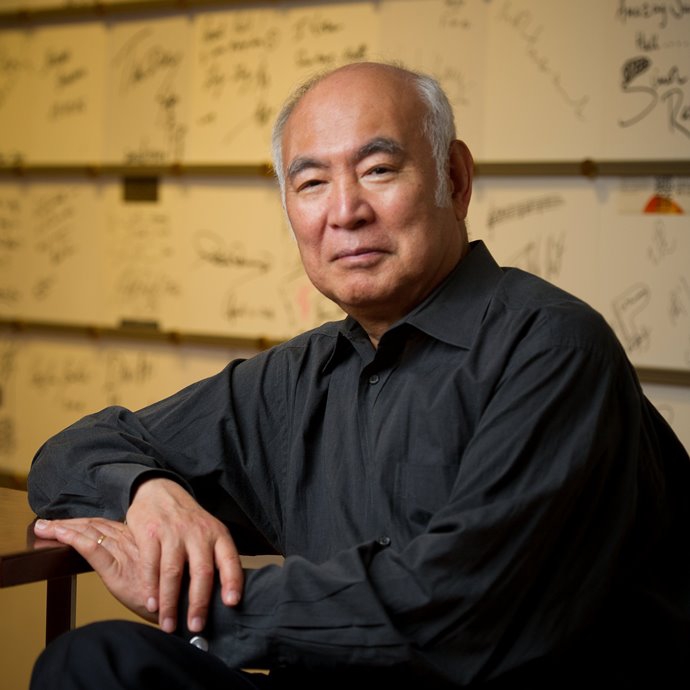
CMGオープニングは「堤 剛プロデュース 2022 」
毎年、チェンバーミュージック・ガーデンは私のプロデュースした公演でスタートしますが、昨年もCMG に登場して頂いたピアノの小菅優さんとクラリネットの吉田誠さんをお迎えして、クラリネット、チェロ、ピアノという珍しい編成の室内楽を取り上げることにしました。と言うのも、昨年のおふたりの演奏が素晴らしかったこと、またおふたりによるブラームスのクラリネット・ソナタなどの録音が素晴らしかったことが強く印象に残ったからです。
シューマン作曲でキルヒナー編曲による「カノン形式による6つの小品 作品56」からスタートします。ブラームスが晩年に書いた「クラリネット三重奏曲 作品114」、そして私も知らなかった作品ですが、フォーレの「ピアノ三重奏曲 作品120」(クラリネット、チェロ、ピアノでも演奏可)、さらには藤倉大さんの『Hop 』(2020年のCMGで委嘱)も取り上げます。
藤倉さんの『Hop 』は 、実はチェロにとっては難しい作品で、前回のリハーサルでは苦労したのですが、とても演奏しがいのある傑作だと思うので、もう一度取り上げたいと思いました。
もともと「堤 剛プロデュース」の公演は、これまでに知られていなかった作品や、珍しい楽器の組み合わせ、そして意外な演奏家の組み合わせを意図して始めたものですので、今年もそうした「新しさ」を楽しんでいだたければ、と思います。

「ベートーヴェン・サイクル」 にはアトリウム弦楽四重奏団が登場
2022年の「ベートーヴェン・サイクル」はロシア出身の弦楽四重奏団として、いま世界中から引っ張りだこのアトリウム弦楽四重奏団がやっと登場してくれることになりました。作品の並べ方を見ても、これまでの弦楽四重奏団とは違った展開になりそうですし、新しいベートーヴェンの一面を見せてくれるだろうと思っています。
また、このサイクルの中に、彼らと親しい現代の作曲家であるボドロフさんの「弦楽四重奏曲第2番」が入っているのも注目ですね。これは 2020年のベートーヴェン生誕250周年とアトリウム弦楽四重奏団結成20周年を記念して書かれた作品だそうですが、こうした現代曲とベートーヴェンの対比というものは、常に時代を超えた音楽の力というものを教えてくれます。
「ベートーヴェン・サイクル」 も2011年の CMGスタート時からずっと継続している企画ですので、本当に固定ファンが多くなってきました。今回は全6回の構成ですが、全公演通して来られる方も多いのではないでしょうか。休憩中や終演後のお客様の反応を見ていると、「あそこの指使いはこうだったね」とか、かなり専門的な話をなさっている方も見受けます。実際に自分たちでもベートーヴェンの弦楽四重奏曲を演奏されている方々もきっと増えて来ているのではないでしょうか。そういう熱心なお客様に支えられている CMGの柱とも言えるシリーズです。

午後のひと時をゆったり過ごす「プレシャス 1 pm」はより多彩に
2022年は4つの「プレシャス」なコンサートを午後にご用意しました。まず「Vol. 1 」は私と小山実稚恵さんによる「北国からのソナタ」です。グリーグの「チェロ・ソナタ」は彼の「ピアノ協奏曲」を彷彿とさせる作品で、そのせいか、逆にあまり演奏されないようですが、とても良い曲だと思います。そしてラフマニノフの「チェロ・ソナタ」は小山さんと何度も共演した名作で、また違った作品の魅力が出せたら良いなと思っています。
「Vol. 2 」はフルートの工藤重典さん、オーボエの吉井瑞穂さんという 日本を代表する管楽器奏者ふたりに加え、ピアノの広瀬悦子さんという素晴らしいメンバーで、管楽器アンサンブルの魅力をじっくりと楽しんでいただけるプログラムです。モーツァルトのオペラ「魔笛」からの「恋人か女房か」など、オペラの世界を管楽器で楽しむという点にも注目したい選曲です。


「Vol. 3 」には「三味線の室内楽〜フォークロアからの逆襲」と題しまして、三味線の本條秀慈郎さん、尺八の善養寺惠介さんに加え、ヴィオラの鈴木康浩さん、 チェロの辻本玲さんが集まった異色のアンサンブルが登場します。最近では邦楽器の演奏家の方々がいわゆる西洋の音楽に挑戦するということが多くなってきましたが、その流れを私たちも受け止めて、このCMGの中でも新しいアンサンブルの地平線が広がって行くことを期待しているプログラムです。邦楽曲だけでなく、バッハ、ヒナステラ、バルトーク、シベリウスという西欧のフォークロア(民謡)もあり、また鮎沢京吾(本條秀慈郎)さんの世界初演作品『vic 』(三重奏版)も演奏されるという興味深い内容です。
実はクラシック音楽の中にも、邦楽で使われる5音階を使った作品があり、代表的なものとしてはハンガリーの音楽があげられます。個人的なことになりますが、1963年にハンガリーで行われたカザルス・コンクールに参加した時に、ハンガリーの方から「あなたの演奏は私たちのスタイルに似ている」と言われたことがあるのですが、考えてみれば、ハンガリー人のルーツはモンゴロイドで、私たち日本人とも共通するところがあります。その人々が西へ移動してハンガリー人となり、東へ来て日本人となったのかもしれず、私はどこかに共通点があるような感じがしています。
「Vol. 4 」はホルンの世界的な名手ラデク・バボラークさんとハープの吉野直子さんが共演する「第一人者たちの交歓」で、これは本当に贅沢な1時間となることでしょう。このおふたりによる録音もあるぐらいで、気心の知れた大人の演奏家同士の会話を楽しみたいと思います。


世界的ホルン奏者ラデク・バボラークによる「個展」
今年はせっかくバボラークさんにいらして頂けるので、バボラークさんの幅広い世界を堪能して頂きたいと思い、このコンサートを企画しました。ご存知のように、バボラークさんはホルン奏者に留まらず、指揮もなさるし、ご自分で会社を設立して、録音にも積極的に取り組むなど、新しい時代のアーティストの代表でもあります。
今回の「個展」では、ピアノに菊池洋子さん、そしてアトリウム弦楽四重奏団、日本人のホルン奏者の方にも協力して頂き、バボラークさんだからこそ出来るプログラムを組みました。ホルン四重奏によるブルックナーの「アンダンテ」、ホルンとピアノによるモーツァルトの「ヴァイオリン・ソナタ ホ短調」、そして2本のホルンに弦楽四重奏が加わるベートーヴェン「六重奏曲」など、デュオとアンサンブルの妙味を楽しめるはずです。

フォルテピアノの古くて新しい魅力に迫る「フォルテピアノ・カレイドスコープ」
最近のCMGの企画の中で好評なのが、フォルテピアノによるコンサートです。今年は3つの公演を用意しました。ひとつは、フォルテピアノの小川加恵さんを中心としたデンハーグピアノ五重奏団によるコンサートで、ここでは1835年製のシュヴァルトリンクというフォルテピアノを使い、ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第3番」(室内楽用編曲版)、日本初演となるアンリ・ジャン・リジェル作曲の「華麗なる大五重奏曲」、そしてフォルテピアノ独奏による藤倉大さんの委嘱新曲などが演奏されます。
もうひとつのコンサートは渡邊順生さんと酒井淳さんによるベートーヴェンのチェロ作品集ですが、渡邊さんは 1795年製のホフマンと1818年製のシュトライヒャーを使い分けます。日本の古楽界を牽引されて来られた渡邊さんの演奏はもちろん、チェロの酒井さんの繊細な演奏にも、ぜひご注目ください。
そして2022年は初の企画として「室内楽のしおり」というコンサートを開催します。ここにもデンハーグピアノ五重奏団の皆さんに出演して頂きますが、サントリーホール室内楽アカデミーで学ぶ京トリオの皆さんにも協力して頂いて、現代のピアノと弦楽器によるアンサンブルの響き、そしてフォルテピアノと同時代の弦楽器の響き、その違いを通して、室内楽の名曲の様々な姿を浮き上がらせてみようと言う面白い企画です。室内楽の世界に少しでも親しんで頂きたい、そのための入り口となるようなコンサートですので、たくさんの方に経験して頂きたいと思っています。


ヴァン・クライバーン国際コンクールの覇者ソヌ・イェゴン(ピアノ)を迎えて
CMGでは、世界で活躍するアジアの演奏家にも注目しています。それが「アジアンサンブル@TOKYO」ですが、今年は仙台国際コンクールで優勝後、アメリカのヴァン・クライバーン国際コンクールでも優勝した韓国出身のピアニスト、ソヌ・イェゴンさんを迎えます。日本からはヴァイオリンの郷古廉さんを中心に、室内楽アカデミーで学ぶヴァイオリンの東亮汰さん、ヴィオラの田原綾子さん、チェロの横坂源さんに参加して頂き、ブラームスの「ピアノ五重奏曲」などを演奏して頂きます。イェゴンさんにはモーツァルトの「幻想曲」、ブラームスの「6つのピアノ小品 作品118」でソロの演奏も披露して頂きます。
アジアから世界へ向けて羽ばたく若い演奏家の姿を、多くの音楽ファンの方に知って頂く良いチャンスとなります。

ミュンヘン国際で優勝した葵トリオによる三重奏の新しい世界、そして躍動するクァルテット・インテグラのコンサート
CMGと並行して、サントリーホールでは室内楽アカデミーを開講し、若い演奏家を育ててきました。そして、その中から葵トリオがミュンヘン国際コンクールで優勝し、現在も室内楽アカデミー第6期に在籍するクァルテット・インテグラは、初めて参加した国際コンクールである、ハンガリーで行われたバルトーク国際コンクール弦楽四重奏部門で優勝しました。それぞれの団体によるコンサートは、まさに若い勢いを感じさせてくれる演奏会になるのではないかと期待しています。
第6期の室内楽アカデミーに参加するフェローによる「ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会」も土曜日の午前中に2回開催されますが、素晴らしいファカルティ(教授陣)に鍛えられている若い演奏家たちの音楽への真摯な取組みには、私もいつも感心させられます。2年間にわたる第6期の締めくくりのコンサートとして、その成果を皆さんと共有したいと思っています。


フィナーレは華やかに
そして、毎回、多彩な編成と選曲で楽しませてくれる「フィナーレ」にはバボラークさん、吉野直子さん、アトリウム弦楽四重奏団、 渡辺玲子さん、そして室内楽アカデミーのファカルティである原田幸一郎さん、池田菊衛さん、磯村和英さん、毛利伯郎さん、練木繁夫さんが登場して、この長い「ガーデン」を締めくくります。まさに「ガラ・コンサート」の名にふさわしい盛り上がりとなるでしょう。
様々な困難が明らかになっている今ですが、音楽の力はそれを癒し、また未来への励ましを与えてくれるはずです。今年もコンサートの配信も用意しておりますので、ライブでも、またご自宅などのお好きな場所でもCMG を楽しんで頂けたらと思います。
(インタビュー・構成:片桐卓也/音楽ライター)
