【連載コラム ⑤】 サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2021
小菅 優プロデュース
武満 徹「愛・希望・祈り」~戦争の歴史を振り返って~
没後25年を迎える武満徹の室内楽と、戦時中に書かれた作品を組み合わせて6月15日・17日にお届けする小菅優プロデュース公演。
ピアニスト・小菅優自身が、公演の企画意図や聴きどころを綴る連載の第5回です。(全6回を予定)
⑤ ストラヴィンスキーと「兵士の物語」
私があなたのうちに感知したものは、
生への好みと生の意味、生あるすべてのものへの愛であったし、
生あるすべてのものがあなたにとって、前似て音楽であり、
音楽となる可能性を有しているということであった。
(ストラヴィンスキーについて)
ラミュ著(後藤信幸訳)「ストラヴィンスキーとの思い出」より
時間を前回の話から戻し、第1次世界大戦の真っ只中の作品について今回はお伝えしたいと思います。「兵士の物語」は、今年没後50周年のイーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)が1918年に書いた作品です。
ストラヴィンスキーはペテルブルクのマリインスキー劇場の首席バス歌手の父とピアニストの母の間に生まれ、子供のころからオペラのスコアをピアノで弾いたり、即興演奏にふけったり、音楽的才能を見せていました。両親の勧めで法学部に入りますが、大学でリムスキー=コルサコフ(19世紀後半ロシアを代表する作曲家)の息子と友達になり、その関係で彼の父親に作品を聴いてもらい才能を認められ、和声や対位法の指導を個人的に受けました。その後バレエ・リュスの創立者で重要なプロデューサーのディアギレフがストラヴィンスキーの幻想曲「花火」を聴いたことをきっかけに彼をパリへ呼び、そのコラボレーションは「火の鳥」、「ペトルーシュカ」などの傑作を生みだし、そして暴力や生贄を含むロシアの異教の祭りを題材にした「春の祭典」がパリの聴衆の中で大スキャンダルになったのは有名な話です。
それまでフランスとロシアを往復していたストラヴィンスキーは1914年にスイスのヴォー州に移転します。彼の作品をいくつも初演して、彼が心から敬愛していた伝説の指揮者エルネスト・アンセルメ(1883-1969)は1915年にスイス・ロマンド(フランス語圏)を代表する詩人で小説家のシャルル=フェルディナン・ラミュ(1878-1947)を紹介します。ラミュはヴォー州のローザンヌで農民の出身の家庭に生まれ、常に自然を愛し、幼いころから地方の素朴な生活、人々の伝統や会話、物腰などを観察していました。そのため小説の登場人物は描写の枠を越え、実在感に溢れています。
独自の哲学と多大な教養の持ち主のラミュとストラヴィンスキーは初対面で互いに惹かれ、会ってはポール・セザンヌ(印象派からポスト印象派、キュビスムへの架け橋となったフランスの画家)への愛、食べものやワイン、ヴォー州の美しい自然を共有します。そして、ストラヴィンスキーは度々トルストイ、ゴーゴリやプーシキンなどのロシア文学の巨匠たちの話をきかせ、ラミュは地元の美しい風景を案内し、スイスについて語ります。ラミュが後に出版された「ストラヴィンスキーとの思い出」の中で何度も強調するように、彼らの友情は全く異なるルーツを超越し、根本的な人間としての交流を生んだのです。

2005年カーネギーホールで、翌06年にはザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・デビュー。デュトワ、小澤らの指揮でベルリン響などと共演。10年ザルツブルク音楽祭にポゴレリッチの代役として出演。現在はベートーヴェンの様々なピアノ付き作品を取り上げる新企画「ベートーヴェン詣」に取り組む。17年第48回サントリー音楽賞受賞。16年ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集完結記念ボックスセットをリリース。17年から4年にわたり、4つの元素「水・火・風・大地」をテーマにしたリサイタル・シリーズ「Four Elements」を開催し好評を博した。 ©Marco Borggreve
その後、彼らは作品においてもコラボレーションをするようになります。ロシア語の歌詞をラミュとストラヴィンスキーは緻密にフランス語へと翻訳し、この共同作業は「猫の子守歌」、「狐」などロシアの民謡や民話を題材にした歌や語り付きの作品を次々生みだします。ロシア語のもつ特質と陰影やアクセントをストラヴィンスキーが説明し、ラミュが翻訳すると、ロシア語とフランス語の音節と音節一つ一つを照らし合わせていきました。ときにはおやつやワインをシェアしながら2人は幾度も会い、その言葉のリズムや音節の変化が自然になるよう試行錯誤します。「私は彼の洞察力、直感的能力、それからロシアの民謡詩の魂や詩心を、フランス語のように縁遠い別種の言葉に移しかえる天分に驚嘆した。」とストラヴィンスキーが書いているように、ラミュのお蔭でロシアの詩の魂が宿ったフランス語での上演がかなったのでしょう。
そして1917年。ストラヴィンスキーはロシアの共産革命のため、ロシアから来る収入を奪われ無一文となり、帰国することができなくなってしまいます。その上、長年世話になっていた家政婦の死、弟の死の知らせ、と不幸が相次ぎました。アンセルメやラミュ、多くの人達が同様に生活に苦労していた時期です。
しかし、友人たちとの交流は大きな支えとなり、新たな作品へと彼は情熱を燃やします。第1次世界大戦による不況のため、大規模なオーケストラの公演はできなくなり、ロシアバレエ団も活動休止。ストラヴィンスキーはラミュと共にその時代に即応したプロジェクトを考えだし、小編成で巡回する「一座」の構成で、小劇場のような作品ができないかというアイディアが出てきます。
2人はすぐ作品の制作に取り掛かりました。ロシアの民俗学者アレクサンドル・アファナシエフ(1826-1871)の民話集より、脱走した兵士と、その魂を奪おうとする悪魔の冒険のお話が、この劇に適している題材を提供します。この物語はロシア的でも、国境を越えて訴えることのできる共通する情況と感情があり、「本質的にヒューマンな面」がラミュとストラヴィンスキーの心をとらえました。そして、劇作家ではないラミュはその作品の物語風な構成を提案し、7人の小アンサンブルと語り手、兵士、悪魔役と、目的通りに小規模で上演できる作品が完成します。
指揮はアンセルメ、同じ友人のサークルの優れた画家ルネ・ヴィクトール・オーベルジョノワ(1872-1957)が背景と衣装を受け持つなど、素晴らしいメンバーの協力を得られることはできましたが、お金が全くなくては実現には程遠い状況でした。拒否が相次いだあと、幸いにもヴェルナー・ラインハルトという芸術に多大な理解のある素晴らしいスポンサーが現れ、その寛大な援助によって、初演の準備が進みます。
そうして実現したローザンヌでの初演は、ストラヴィンスキーがこの初演ほど満足する演奏はその後なかったと述べているほど大成功でした。しかし、もともとの目的の「巡業」を達成するため、ツアー日程が決まっていたにもかかわらず、このタイミングでスペイン風邪が流行ってしまい、それはすべてキャンセルとなってしまいます。
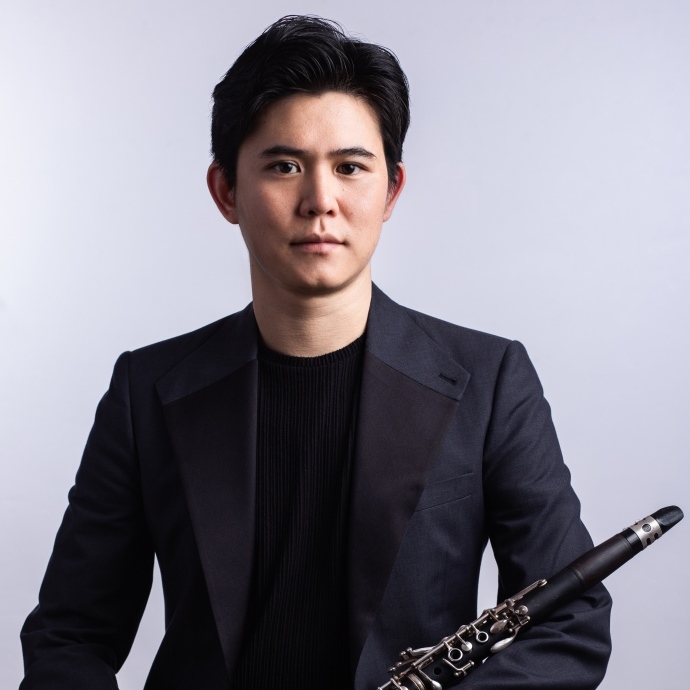
©Aurélien Tranchet

今回演奏するのはその後アマチュアのクラリネット奏者でもあったラインハルトのオーガナイズによって行われた室内楽公演のために編曲されたクラリネット、ヴァイオリン、ピアノのためのトリオ版の組曲です。ここでは主要場面が5つの曲で展開されます。
第1曲は劇で常に繰り返される「兵士の行進」、第2曲は小川のほとりで兵士がヴァイオリンを弾き、最後に悪魔に脅かされるまでのシーンを描く「兵士のヴァイオリン」。悪魔の誘いで兵士はヴァイオリンと「金を齎す本」を交換してしまいますが、金持ちになってもヴァイオリンを弾けず心が満たされないことに気づきます・・・そしてのちにカードゲームで悪魔に財産を奪われますがヴァイオリンを取返し、喜んで演奏する第3曲の「小コンサート」、ヴァイオリンの演奏のお蔭で病が治り「タンゴ―ワルツ―ラグタイム」に合わせて王女が踊りだす第4曲、そしてヴァイオリンを弾くことで悪魔を退治できると悟った兵士が続けて演奏し、その音楽が耐えられなく体をよじり、苦しむ悪魔のダンスが繰り広げられる第5曲「悪魔の踊り」で組曲は終わります。
劇の最後で語られる、欲張ると何もつかめなくなり、今持っているもので満足し幸せを感じないといけない、というラミュのテキストのメッセージが、この第1世界大戦のときだからこそ意味深く伝わってきます。
通常の演奏会が不可能なため小編成のプロジェクトの試み、伝染病による公演のキャンセル・・・100年以上前の話が、つい最近聞いたような、とても身近な話に感じます。活動が制限されてしまったり、不況が続くなかでも今可能なことを探し、創造性を常に保つ芸術家たちの情熱、そしてそれをサポートする芸術への愛を忘れない人々。彼らのお蔭で現代の私達は今こうしてこの素晴らしい芸術作品を演奏できるのです。
(連載第6回につづく)

【公演詳細・チケット購入・関連リンク】
- 6月15日(火)19:00開演 小菅 優プロデュース 武満 徹「愛・希望・祈り」~戦争の歴史を振り返って~ I
- 6月17日(木)19:00開演 小菅 優プロデュース 武満 徹「愛・希望・祈り」~戦争の歴史を振り返って~ II
- 小菅 優 (ピアノ)による連載コラム ① 武満 徹との出会い、このプロジェクトについて
- 小菅 優 (ピアノ)による連載コラム ② メシアン:『世の終わりのための四重奏曲』の初演までのお話
- 小菅 優 (ピアノ)による連載コラム ③ メシアンの 『世の終わりのための四重奏曲』 に気づかせられるもの 吉田 誠(クラリネット) × 小菅 優(ピアノ)
- 小菅 優 (ピアノ)による連載コラム ④ 武満 徹のピアノ付き室内楽作品
- 小菅 優 (ピアノ)による連載コラム ➅ ショスタコーヴィチの謎