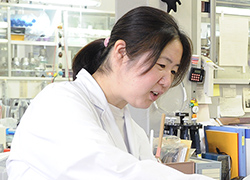青い花を咲かせる植物は自然界にたくさんありますが、まず研究チームが青色遺伝子を取る対象として選んだのは、濃い紫色のペチュニアでした。そのわけは、以前からペチュニアはアントシアニンなどの花色研究のモデル植物だったため、すでに次のような知見が集積していたからです。

〇青色遺伝子はチトクロームP450型水酸化酵素(肝臓で解毒を担っている酵素の仲間)遺伝子であること
〇この遺伝子は花びらでは働いているが、葉では働いていないこと
〇青色色素を作らない赤いペチュニアには青色遺伝子がないこと
〇花弁が開く時に青色遺伝子が強く働くこと
〇染色体上の遺伝子座がわかっていたこと
これらをヒントに、ペチュニアが持つ2つの青色遺伝子の候補を3万種の遺伝子の中から300種ほどまでに絞り込みました。最初はペチュニアに候補の遺伝子を戻して花の色が変わるかテストし、青色遺伝子か否かを判断する計画でした。ところが、それでは花が咲いて色がわかるまでに数か月かかってしまいます。そこで、結果が出るまでの時間を短縮するため、植物ではなく酵母に候補の遺伝子を入れて活性をテストすることに。おかげで、一週間で答えが出るようになり、たくさんの遺伝子の活性を調べることが可能になりました。

そして、1991年6月13日、ついに青色遺伝子の取得に成功します。
サントリーは、すぐにこの遺伝子の特許を出願。どのライバルチームよりも早く申請して特許を独占できたことが、この研究に単独で取り組む決め手となりました。このような活性を持つ遺伝子の特許申請はこれが初めてだったため、非常に広い範囲の特許が成立したのも幸運でした。実際に、この遺伝子をペチュニアやタバコに入れる実験をしたところ、青色色素の「デルフィニジン」の量が増えることが立証されました。これらの成果を記した論文は世界最高峰の科学雑誌「Nature」にも掲載されています。