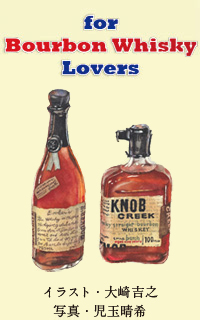アメリカはこのようにして西へ西へと拡大、発展していくことになるのだが、人口の多くはまだまだ東部に集中していた。ホテルが建設されていくなかで、旅はもちろんのこと、そうした施設とは無縁の人々がたくさんいた。ホテル内の酒場なんぞ別世界、という人々がほとんどだった。
19世紀前半から半ば過ぎの南北戦争前までは、労働者は昼休みにはビールを職場で当たり前のように飲んでいた。工場の近くには酒場が乱立し、昼になるとそこへブリキ缶を持った人たちが集まり、缶にビールを満たしてもらうのだった。
それが1杯5セントのフリー・ランチ(無料の昼食)へとつながっていく。ビールがグラス1杯5セント。これを注文すると料理がついてくる。豆入りスープに茹でキャベツ、塩漬けキャベツとソーセージ、それにライ麦パンといったメニューだったらしい。
これが確立したのが産業都市として発展し、水運、そして鉄道の物流拠点でもあった1870年代のシカゴである。10年も経つと全国に広がる。酒場がさらに増え、フリー・ランチの過当競争時代となる。
さらにシカゴではフリー・ランチだけでなく10セントと値段の高いビジネスマンズ・ランチなるものが登場し、それなりのレストランの20~30セントのランチと遜色のない料理を出す酒場も登場したらしい。
この間、移民は増えつづけており、フリー・ランチに出身民族色が顕著になりはじめる。アイルランド系やドイツ系の移民が集まる店ではポテト、ソーセージは欠かせなかった。イタリアからの移民が増えると、スパゲティを出す酒場も生まれた。結局は濃い味付けの料理を出して、さらにもう1杯、ビールを別注文させようとの魂胆であった。
西部開拓が一段落した中西部の19世紀末は採算を度外視したメニューで生き残りをかける店もあり、すぐさま苦しい経営状態に陥っていたらしい。
さて、こういう状況を苦々しく思っていたのが禁酒運動家たちである。19世紀になり産業が発達していくなかで、多くの労働者たちは昼にビール、夜はサルーンでライウイスキーを飲む。やがて、飲酒を悪としてしか捉えられない者たちには許されないフリー・ランチの習慣が根付いてしまったのである。
こんな酒場の動向が禁酒運動に拍車をかけた。20世紀に突入すると、酒を愛する者たちの肩身が狭くなっていく。
一方でフリー・ランチは民族間の相互理解を深め、異文化交流の場にもなったと評価する声もあった。1890年代半ばの経済不況により大量の失業者があふれたときには、5セントのフリー・ランチとは関係なく、彼らに無料で食事を提供し、福祉活動に貢献した酒場もたくさんあったという。
(第58回了)