

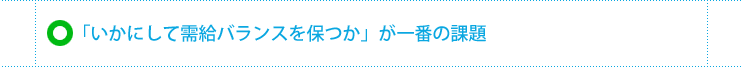
-

大学の交響楽団の定期演奏会でサントリーホールの舞台に立った瞬間、「こんな素晴らしいホールを持っている会社ってすごい」と思った。それが、音楽芸術の振興に力を入れている企業に入りたかった彼女とサントリーの出会いだった。
熱意が通じて入社を果たした彼女は、現在ロジスティクス部で輸入洋酒の発注や通関、在庫管理や需給予測などの業務を行っている。需給予測に基づいて海外の提携先製造会社に製品を発注する。船会社と船積み・輸送スケジュールの調整、管理を行う。貨物が到着した後は通関会社に通関、検品を依頼する。これが通常業務の一連の流れである。国内の在庫を管理しながら需給予測を立て、製品の安定供給を維持するのが役目だ。
「品切れさせず、なおかつ過剰在庫にもならないようバランスをとるのが一番難しい」と言う。貿易に付き物のトラブルにも悩まされる。製造の遅れ、ストライキ、輸送時の破損、製品不良などが発生すると在庫が不足し、納品も大幅に狂ってしまう。だから、いつ問題に直面しても万全の態勢で対処できるよう、日頃から準備は怠らない。「でも、できればトラブルは起こってほしくありませんね」と言う彼女には苦い思い出があった。

-


ロジスティクス部に異動になって初めて迎えた師走のある日、輸送代理店から一通のメールが届いた。「サウサンプトンの港でクレーン事故発生」。彼女はこのときその事故が自分の仕事にどれほどの影響を及ぼすことになるかわかっていなかった。「何を呑気に構えているの」と上司に叱られて初めて事の重大さを知ったのだ。蓋を開けてみたら、港は完全閉鎖で機能停止という危機的状況、いつ復旧するかの目処もついていなかった。さあ、大変だ。製品の代替輸送を手配し、在庫調整をしなければならない。数字とにらめっこしながら打開策を模索する日々が続いた。すべてが手探りの状態だった。部内の誰もがそれまで経験したことのないほどの“大事件”だったからだ。
「おかげで、もう怖いものなしです」と今でこそ笑って話すが、当時は周囲の冗談に笑う余裕さえなかった。事故の影響で遅れていた最後の製品が東京に到着したのは3月半ば。需給シミュレーション相手に挌闘する生活からやっと解放されたときにはひと冬を越していた。「その後しばらくは脱け殻同然だった」のも頷ける。当時の姿を思い浮かべながら「自分でもよくぞ持ちこたえたと思います」と語る彼女はちょっぴり誇らしげだ。