SUNTORY CHALLENGED SPORTS PROJECT


トライアスロン 女子運動機能障がいPTS5東京2020パラリンピック日本代表 谷真海 × 義肢装具士 臼井二美男 「走ってごらんよ」というひと言に、すごくワクワクした。
今回は、競技者として走り幅跳びで3度、トライアスロンで1度のパラリンピックに出場し、現在は選手としての競技活動のみならず、パラスポーツの普及活動にも尽力する谷真海選手と、義肢装具士として、生活義足はもちろん、多くのパラアスリートのためにスポーツ義肢の開発・制作を行っている臼井二美男さんにインタビュー。世界で活躍してきた谷選手のこれまでの歩みや、それを長きにわたりサポートしてきた臼井さんとの関係性について、おふたりに伺った。

――谷選手がパラアスリートになろうと思ったきっかけは?
谷 もう20年も前の話ですが、骨肉腫という病気で右脚の膝下から下を失い、義足での生活となりました。当時はまだ大学生で、普通の大学生活を過ごすだけでは前向きになれない自分がいて。もともと水泳や陸上といったスポーツをしていたこともあり、またスポーツに打ち込めば情熱を取り戻すことができるんじゃないかと思ったんですね。でも、当時はパラリンピックなどの情報がほとんどなくて。何かやってみたいけれど、何をしていいのかわからないというところからスタートして、自分で検索をしたり人に話を聞いたりするなかで、あるとき臼井さんと出会ったんです。足を失っていちばん出来ないだろうと思っていたのが「走ること」だったんですけど、臼井さんに走れる可能性を示してもらえたことで、すごく人生が開けた感じがしました。それからは前向きに、どうせやるなら大会にも出たいし、いろいろとチャレンジしたいっていう気持ちになっていきました。

――走り幅跳び、トライアスロンと、多岐にわたる競技人生を歩んできた谷選手。それぞれの競技について、選んだ理由は何ですか?
パラスポーツをはじめて最初に走り幅跳びという種目を選んだのは、まず走ることに喜びを感じたのが第一です。そして、誰かと競い合うというよりも、自己ベストを1cm、2cmと更新していくという種目の特性が自分に合っていたから。少しでも自己記録を更新していきたいから頑張るというところが、当時義足になって、また一歩ずつ歩み出すという自分の思いにリンクして、凄くやりがいを感じたんです。
トライアスロンは、実は走り幅跳びをしていた頃から少し挑戦してみたり、ずっとやってみたいと思っていた競技なんです。走り幅跳びでパラリンピックに3度出場して、自分のなかに「より長く競技として他のスポーツにも挑戦していきたい」という気持ちが生まれたちょうどその当時、リオデジャネイロ大会から正式種目になったこととか、東京での開催が決まったことなどとか、そうした色んな要素があって、トライアスロンに変更して準備をしようということになりました。
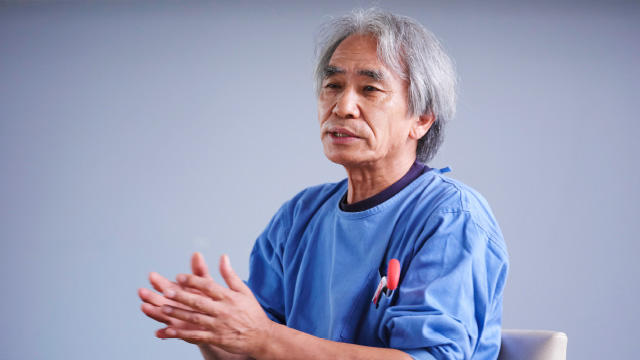
――臼井さんのお仕事である「義肢装具士」とは、どのような職業なのでしょうか?
臼井 まず、「義肢(ぎし)」というのは、手や足の切断によって失った部分を補うもので、「装具(そうぐ)」とは、手足はあるけれど機能障害や麻痺などがある場合にそれを補うものです。その両方を作るのが「義肢装具士(ぎしそうぐし)」という仕事で、厚生労働省の国家資格のひとつでもあります。基本的には、骨折したりだとか膝を痛めたとか、肩を痛めたとか、そうした広く一般の人たちが使う装具というものが多く、仕事の9割は装具に関するもの。残りの1割ぐらいが義足や義手といった切断義肢という感じなのですが、僕の場合は入社した当時から義足や義手を担当することが多くて、義足でできるスポーツに関しても興味を持っていました。それで今に至るというわけです。
僕が真海ちゃん(谷真海選手)と出会ったのは、今から約20年前。その頃の彼女はまだ義足で、パラリンピックにも日本人の女子選手は彼女だけでした。当時に比べると今は義足を履いて競技をする女性選手も増えてきていますが、義足や義手を通じてサポートをしてくれるところは、全国的にもまだまだ少ないというのが実情です。スポーツ義肢というのは作ってもそこまで利益がないものですからね。でも、仕事のやりがいや社会貢献というところに価値を感じて取り組む製作者が増えてくれたらいいなと思って、私も日々製作に取り組んでいます。

――初めて出会ったときのことや、印象に残っている出来事について教えてください。
臼井 真海ちゃんが最初に相談に来たとき、杖をついて来たんですね。それは義足がうまく適合していなかったのと、痛いから体重をかけられずに、杖に頼っていたから。僕のような仕事をしていると、ひと目見るだけで「たぶんこの子は義足が合っていれば普通に歩けるな」というのがわかるので、それを解消してあげたらやっぱり歩けるようになりました。だからすぐに「走ってごらんよ」って話をしたんです。そしたらもう、あっという間に走る技術を覚えちゃって(笑)。
谷 臼井さんは、パッと見ちょっと怖いかなって思ったんですけど(笑)。でも最初からすごく話しやすくて。なんでも相談できるというか、義足の悩みって表現しづらいことが多いんですけど、そのニュアンスを汲んでくださって「これはこうしたら良くなるね」というのが的確だったんですね。だから初めて会ったときから安心感がすごくありました。最初に相談に行ったときは、ヘルス・エンジェルス(現・スタートラインTokyo)の練習会にお邪魔するという感じで行ったので、義足を見てもらうだけで走るつもりなんてまったくなくて。でもそこで「走ってごらんよ」って言われて、これからどうなっていくんだろうって、すごくワクワクしたのを覚えています。
臼井 僕はみんなをアスリートにしたい訳じゃないんです。スタートラインTokyoにしても、義足の人の集まりみたいなもののなかで、みんなで運動をしたり走ったりすることで、可能性が広がればいいと思っている程度で。そのなかで上を目指そうという人がいたら、サポートをしようという感覚です。それに、足だけを見てスポーツ義足さえ作ってあげればいいという訳ではないんです。その人の家族だったり、家庭環境だったりをある程度把握していないと、アスリートの道をすすめるのは難しい。特に子どもさんの場合まずは親御さんともコミュニケーションを取らないと、経済的な問題や、これから続く治療の話もありますからね。そういうところを全部みながら、スポーツ義足をつくったり、競技へ進むためのサポートをしています。人生相談じゃないですけど、そういうところも大事なんですよ。
谷 そう、だから臼井さんも、すぐにはスポーツ用義足を作らないってスタンスなんですよね。まずはそのスポーツができる筋力を戻してからまた来なさいという感じで。
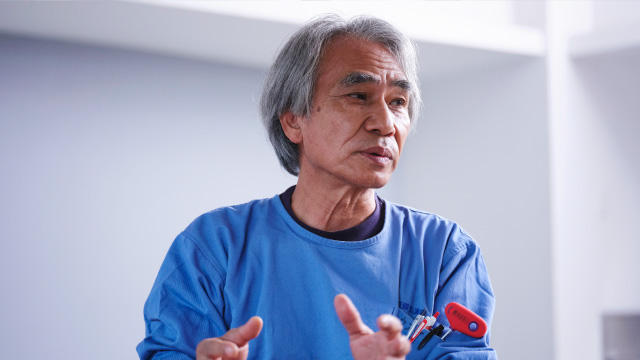
臼井 真海ちゃんの場合は水泳をやっていたとか、陸上をやっていたというのを最初に聞いていたし、あとは自分から相談に来たというのもあって、自分を変えたいんだなって思いが伝わってきて。やればなんでもできそうだというのは早めにわかったんですね。でも、そうは言っても急に足に筋肉はつかないので、焦らずやろうという感じで。ただ、真海ちゃんが最初に出場した関東大会では大雨が降ってしまって、本番で転んじゃったんです。それがショックで辞めちゃうんじゃないかって思ったんですけど、負けずに続けてくれましたね。
谷 そのときに辞めなかったのは、練習会に行けば仲間がいるというのは大きかったと思います。いろんなひとがいて、私と同じように義足の人ももちろんいるので、同じ悩みを共有したりして。義足の悩みって、他人にしても分からないだろうなって思っています。でも、そこにいるひとはみんな共感できるひとだし、臼井さんもいる。そういう場所があるって、素晴らしいことだなって感じました。
だから私は「もう臼井さんなしでは!」というくらい、これまで二人三脚でやってきたと思っているんですが、臼井さんはその二人三脚をたくさんの人としているので、そこは本当に凄いなって。トップアスリートだけをサポートしている訳じゃなくて、色々な人が臼井さんを頼っているので。義足ってスポーツをするときもそうですけど、私たちにとっては普段生活するうえでも欠かせないものなので、何かあったときに臼井さんに相談できるというのは、本当に心強いです。

――谷選手は選手として、臼井さんはサポート役として、合計4度のパラリンピックを経験されています。特別な思い出や、印象深い大会は?
臼井 彼女の場合、下腿部(膝から下)の長さが30%ほどしか残っていないので、短距離だとパワーを出しにくい分、不利になる。だから、短距離もやるけれど、最終的には跳躍競技がいいんじゃないかと相談して、走り幅跳びを本格的に取り組むことにしたんですね。でも、2003年に初めて訪ねてきてから、まさかたった1年で日本代表になって、2004年のアテネ大会に行けるとは思っていませんでした。やっぱり本人が持っている能力で、2003年秋の大会だとか、陸上大会でいい成績を出して2004年の最終選考で記録を出せたというのは、それだけ思いが強かったんじゃないかと思います。
谷 もともとパラリンピックという存在を教えてくれたのも臼井さんで、当時ビデオ映像を観せていただいたときに、自分が思っていたイメージとは全然違ったというか。リハビリの延長ではなく、純粋にかっこいいなと思いました。臼井さんが作った義足で実際にパラリンピックに出場した鈴木徹さんや古城暁博さんにもお話を聞く機会があって、パラリンピックにはいつか出場してみたいなっていう思いはありました。でも、私もそんなに早く出場できるとは思ってませんでしたね(笑)。
臼井 パラリンピックで印象深いのは、やっぱり僕もアテネ大会ですかね。メカニックとして日本選手団に帯同することになったのもアテネ大会からですが、オリンピック発祥の地ということもあって盛り上がっていて、観客も子どもが凄く多かったのを覚えています。街を観光していてもよく声をかけられましたし、とにかく未来を担う子どもたちにこの大会を知ってもらおうという思いが凄く伝わってきて、僕自身にもいい経験になりました。
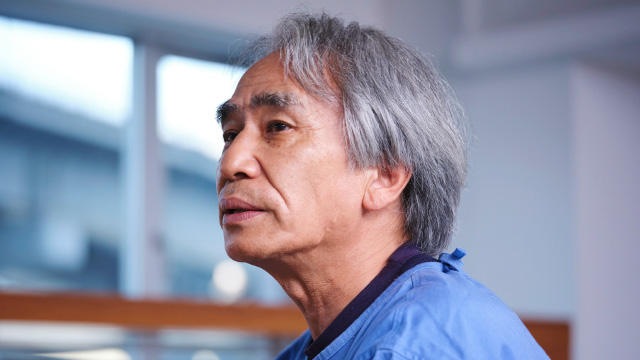
谷 世界中から頂点を目指して、限界にチャレンジした選手たちが集う場所というのがすごくいいなと思っていて。そこを目指そうと思うきっかけとしてアテネ大会があったので、これぞパラリンピックだなっていうのを肌で感じることができたのはアテネ大会かな。でも、大会として印象に残っているのはロンドン大会です。どの会場も超満員で、陸上は午前の部と午後の部の観客を入れ替えるんですが、それでも全部満員。他の競技を見に行ったときもそうですが、会場も街もメディアも、全部がすごく盛り上がっていて、本当に素晴らしかった。その経験があったからこそ、自分が東京大会の招致活動に関わったり、東京大会を目指すのもありかなと思えたので。まさに理想とするパラリンピックを経験できたのが、ロンドン大会です。
臼井 ロンドンはパラリンピック発祥の地というのもあって、障がい者スポーツの歴史も古いので、競技を"観る"というよりも、"楽しむ"という感覚が地元の人たちに昔から染み付いているような気がしましたね。僕たちも学ぶところが多かった大会だと思います。

――今後もパラ競技やスポーツ義肢を広めていくために、どんな取り組みをしていきたいですか?
谷 20年前に病気になって義足になったとき、しばらくは絶望感しかなかった。私が立ち直るのに時間がかかったのは、情報がなかったからだと思うんですね。そうなってしまっても、こうやって生きていけるんだ、スポーツができるんだっていう情報がすぐに入るようになったことだけでも、パラリンピックの存在はすごく大きいと思います。だから、パラリンピックをはじめとするパラスポーツを、ひとつの競技でもいいから知ってもらう。そして、スポーツのひとつとして楽しんでもらうということが大切だと思うんです。
そういう意味でも、私もチャレンジを続けて、子どもたちに伝えていく。パラスポーツというのは本当に伝えられるメッセージが多いので、障がいがある人だけにではなくて、子どもたちに大きな夢を持ってもらうとか、諦めないで取り組むことだとか、人と比べないで自分自身を好きになることとか。そういったことを伝えていきたいです。そして、一般の方たちにもパラスポーツがもっと広がれば、社会全体も変わってくるんじゃないかと、私は思っています。
臼井 義肢については僕からも発信をしていて、おかげさまで全国に8カ所ほどスタートラインTokyoと同じような義肢系のクラブができて、地方でもパラスポーツをやりたいという人が楽しめる環境ができました。でも、やっぱりそれではまだまだ少ないと思っているので、そうした環境づくりにはこれからも力をいれていかなければならないと思っています。これまで通りのことを継続して、できる限りつづけていこうと思いますが、意志を継ぐ後輩たちを育てていくことも大切ですね。
それと、この仕事を35年くらいやってきていちばん感じるのは、障がいを持った人がスポーツをすると、本人がちゃんと自立するということ。最初は両親に連れられてイヤイヤ来るような子もいるんですが、慣れてくると目標を持って取り組むようになったり、なかには本当に選手になる子もいる。そうやって本人が自立していけるというのは、一生にも繋がることですし、周りの両親や兄弟にとってのよろこびのひとつになる。スポーツがもたらす効果というのは本当に大きいというのを、やっていてすごく感じています。そうやって成長した子たちが、真海ちゃんのように選手になって、今後は子どもたちを一緒に導いてくれる。それが僕にとっていちばんうれしいことです。
PROFILE
たに まみ●パラトライアスロン選手、陸上競技選手/トライアスロン 女子運動機能障がいPTS5東京2020パラリンピック日本代表、東京2020パラリンピック日本代表旗手
1982年3月12日生まれ、宮城県出身。サントリーホールディングス株式会社CSR推進部所属。早稲田大学在学中に骨肉腫によって右脚膝下を切断。卒業後サントリーに入社し、走り幅跳び(義足・機能障がいT64)で2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンと3大会連続でパラリンピックに出場。2013年には東京大会の招致活動において、最終プレゼンテーションでスピーチを行う。2016年からはトライアスロン(運動機能障がいPTS4)に転向し、翌年9月の世界選手権で優勝。日本人初の世界一となる。その後、結婚・出産などを経ながらアスリートとして活動を続け、東京大会の代表として4回目のパラリンピック出場を果たし、日本選手団の旗手も務めた。現在は、選手としての競技活動に加え、パラスポーツの普及にも精力的に活動している。
うすい ふみお●義肢装具士/切断者スポーツクラブ「スタートラインTokyo」主催
1955年8月28日生まれ、群馬県出身。大学中退後、8年間のフリーター生活を経て、財団法人鉄道弘済会・東京身体障害福祉センター(現・公益財団法人鉄道弘済会・義肢装具サポートセンター)に就職し、義肢装具士としてキャリアをスタート。1989年から生活義足に加え、スポーツ義足の制作にも取り組み、1991年には切断障がい者の陸上クラブ「ヘルス・エンジェルス」(現・スタートラインTokyo)を創設、代表者として切断障害に義足を装着してのスポーツ指導を行いながら、これまで数々の日本記録保持者やトップパラアスリートを輩出する。また、2004年アテネ大会から2016年リオデジャネイロ大会まで、日本代表選手のメカニックとしてパラリンピック本大会にも帯同。生活義足でも、これまで誰も作らなかった義足を開発、発表するなど、義足を必要としている人のために日々研究・開発・制作に尽力している。








