今回のレシピは、ステークアッシェです。フランス語でsteak hachéで、「haché」は「斧」の事です。つまり、斧で肉をみじん切りにするような料理という意味です。わたくしがワインの仕事についたばかりの頃の師匠である柴田さんのお供でブルゴーニュに行ったのは1988年の事でした。その頃に生産者を案内してくれたのは、当時は、まだボーヌにもあったカルベ社の輸出部長のブシャールさんでした。カルベ社の創業者はジャン・マリー・カルベで、1818年にローヌ渓谷のタン・レルミタージュでメゾン カルべを設立しました。カルベ社の事業は広がりを見せ、フランス全土のワイン、特にボルドーワインの取引金額が増えていきました。ジャン・マリーの息子のオクターブは1876年にボルドーのシャルトロン地区の中心部に壮麗な建物を建設し本社としました。シャルトロン地区はボルドーが2007年に「月の港ボルドー」として世界遺産に認定された時の中心的な場所で、ガロンヌ川沿いの一等地です。その後カルベ社は更に発展し1890年代にはブルゴーニュに子会社を設立しました。ボーヌ市街を1周するマレシャル・ジョフル通りの内側の、これまた一等地です。ブシャールさんはそのオフィスに勤務していました。当時のフランスワインはネゴシアンの手印でフランス全土のワインをカバーするのが普通でした。当時サントリーが扱っていたカルベ社のワインはボルドーやブルゴーニュは勿論の事、ミュスカデやロゼ・ダンジュ、コート デュ ローヌといった各地のワインもカルベのラベルでしたし、ムルソー プルミエクリュやシャブリのグランクリュもカルベのラベルでした。1980年代はブルゴーニュで、徐々に、ドメーヌがネゴシアンにぶどうやワインを売り渡すのではなく、ワインを瓶詰めし自分のラベルを貼って、自力で商売を始めた時期でした。わたくしがステークアッシェに初めて出会ったのは、まさに柴田師匠とブシャールさんにつれられてドメーヌ訪問をしている時でした。ブシャールさんは、苗字からお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、1731年創業の名門ドメーヌ&ネゴシアンのブシャール ペール エ フィスの一族でした。ブシャールさんは、なかなかに失礼な人でした。柴田師匠には礼を尽くし、尊敬の念をもって接していましたが、当時は小僧だったわたくしには、かなりぞんざいな接し方でした。初めて出会った時に名刺を出して「久保です」と名乗ったら、しばらく名刺を眺めて「キュ ボ・・・」とつぶやきけらけらと笑い出しました。通訳に付いてきてくれていたパリオフィスの人に何を笑っているのか聞いたら「cul beau=美しい尻」と言っていると教えてくれました。でも、お陰様でブシャールさんに直ぐに名前は、覚えてもらう事が出来ました。
午前の2軒のドメーヌの訪問が終わり、ランチにボーヌ市内のビストロに行きました。フランス旅行をされた事のある方ならお分かりかと思いますが、ビストロのメニューは黒板に手書きの事が多いのですが、その文字が独特です。わたくしには全く読めずに、パリオフィスに人に掻い摘んで内容を教えて貰いました。メインの所の下の方に書いてあったステークアッシェの所で「ステークアッシェはハンバーグみたいなもんです」と教えてもらい、注文しました。するとブシャールさんが笑いながら「それはお子様メニューだぞ」と言われました。「えっ?ハンバーグなんでしょう?」と言うと「ハンバーグとは全然違う、ステークアッシェはステークアッシェだ。ステークアッシェには混ぜ物はしないんだ」と厳しく教えられました。今回、この記事を書くにあたり改めてLe Règlement Sanitaire International (RSI)(フランス国際保健規則)を調べました。国際保健規則は日本の農林規格のような存在で、食に拘りのあるフランスらしく、近隣他国よりも厳しいので有名です。ステークアッシェの所には「牛肉のミンチで、加えて良いのは1%を上限とする塩と15%を上限として牛肉から抽出したプロテインを接着剤としてのみ」と規定されています。わざわざ注釈に他国では骨から取ったプロテインを添加しているものを認可しているが、フランスではステークアッシェとしては認められない」と書き添えています。一方、ハンバーグのパティの規定は41%以上の牛肉、20%未満の脂肪でそのうち10%は動物性の脂肪である必要がある。その残りに使って良いのはエンドウ豆、大豆タンパク質などと定められています。確かにこの規定を見ると別物ですね。今回のステークアッシェでは、肉は和牛の小間切れを使いました。小間切れ肉は粗みじん切りにして、塩と胡椒を振って良く捏ねます。付け合わせはフライドオニオンです。玉ねぎスライスをオリーブオイルでかりっと揚げます。それとイタリアンパセリ、ケイパーを添えます。そうそう、ディジョンマスタードを忘れずに添えましょう。相性抜群ですよ。
さて、このステークアッシェにテイスティングメンバーが選んだイチオシワインはロス ヴァスコス クロマス カルメネール グラン レセルバでした。ロス ヴァスコスのワイナリーとしての起源は非常に古く、1750年、今から約270年以上前、チリに移住してきたバスク系のスペイン人が創業したのが始まりです。「ロス ヴァスコス」の名前は「バスクの人たち」という意味に由来しています。1988年にエリック ド ロートシルト男爵が栽培適地を探し求めて世界中を旅していた頃にロス ヴァスコスに出会いました。世界展開を考えていた男爵は、この比類のない特別な土地に惚れ込み、ロス ヴァスコスの経営をスタートさせました。Viña Los Vascosは、サンティアゴの南200km、アンデス山脈と沿岸山脈の間のコルチャグア地方、チリの中央渓谷にあります。そこはチリに共通の半乾燥土壌で、しかもぶどう栽培の敵である霜が降りないという理想的な微気候に恵まれていることは、地元の人々が何世代にもわたって知っていた秘密だったのです。カニェテン山の麓の山々に囲まれた敷地は3,600ヘクタールで、そのうち640ヘクタールにぶどうが植えられています。10年以上も前の事ですが、ロス ヴァスコスを訪ねた事があります。当時醸造長だったクリスチャン ル ソメール氏が小高い丘に連れて行ってくれると、大きな盆地が広がっていました。眼下には昨日宿泊させてもらった迎賓館や池、その先の醸造施設、そしてそれらを取り囲む広大な畑が見えました。クリスチャンに「ロス ヴァスコスの所有地はどのあたりまでですか?」と尋ねると、にやりと笑って「見える範囲全部さ」「今は580haが植わっているが徐々に増やす予定だ」と答えてくれました。現在では640haにカベルネ・ソーヴィニヨン(68%)、カルメネール(9%)、シラー(8%)、シャルドネ(5%)、カベルネ・フラン(2%)、ソーヴィニヨン・ブラン(2%)が栽培されています。1990年代初頭に大規模な植え付けが行われたため、ブドウ園は平均樹齢15年の区画群と樹齢40〜50年の区画群に分かれています。最も古いブドウの木は樹齢60年です。クロマス カルメネール グラン レセルバの「クロマス」はギリシャ語で色を意味する言葉に由来します。ロス ヴァスコスでは、色を自然からのメッセージであると思っています。すべてのトーン、すべての色合い、すべてのニュアンスが自然からのメッセージなのです。クロマス カルメネールはロス ヴァスコスの区画のなかでも赤い色合いの強い土壌に植えられています。この赤い土壌はアンデス山脈のあちらこちらにある土壌で鉄分が豊かです。カルメネールはチリを代表するブドウ品種ですが数奇な運命を辿った品種である、と言えます。カルメネールは、かつてはボルドーの主力品種でしたが、現在では本家ボルドーではほとんど絶滅状態です。カルメネールは開花期に低温になると極端に結実しなくなり収量が安定しません。チリではフィロキセラ前にカルメネールも持ち込まれました。栽培はされていましたが、カルメネールとは認識されておらず「青臭い香りのするメルロ」だと勘違いされ続けてきた品種なのです。DNA鑑定によって、チリのメルロの一部が、実はカルメネールだと判明したのは、なんと持ち込まれて140年以上も後である1994年の事なのです。カルメネールというぶどう品種の由来となった「Carmin」は「深紅の」という意味で、カルメネールから生まれるワインの色の濃さを示しています。収穫期に、ワイナリーに運び込まれたカルメネールの選果する人の指を真っ赤に染める事からもこのぶどうの赤色の強さが判ります。グラスに注ぐと色は濃く、斜めにしたグラスの中心部は黒みを帯びているかのような濃い赤です。赤系のベリーやブルーベリーやブラックチェリーを思わせる香りや、スパイス、ハーブを連想させる香りもあります。口に入れると、充実感のある果実味で、豊かな味わいと長い余韻を持った逸品です。
ステークアッシェと合わせると、牛肉の素材としての味わい深さが感じられます。
「牛肉の素性の良さが端的に見えてきますね」
「お肉を甘く感じさせる素敵なマリアージュです」
「ステークアッシェが混ざりっ気のない牛肉そのものですからね。牛肉の旨味がストレートに感じられます」
「カルメネールはカベルネ・ソーヴィニヨンみたいな構造の大きな品種では無いですよね」
「お肉とワインの相性を考える時の、大事な要素に、口に入れてから飲み込むまでの咀嚼の回数があります。塊のままで焼いた肉は咀嚼の回数が必要になり、その分だけワインサイドもボディの大きさや品種としての強さが必要になるのです」
「ステークアッシェは刻んだ肉料理だから、フルボディな逸品や構造のある品種でなくても、頃合いのバランス感になるのですね」
「ディジョンマスタードを付けると更に美味しくなります」
皆様も是非一度ステークアッシェに挑戦してみてください。腿肉のような脂の少な目の部位がお薦めです。ステークアッシェはストレートに牛肉の美味しさが感じられる素晴らしい調理方法です。輸入牛でも、もちろん美味しくできますが、もし、最高のステークアッシェを食べてみたいなら、お薦めの牛は、岩手短角牛や肥後赤牛の腿です。本当に度肝を抜かれる様なステークアッシェが味わえますよ。
レシピに戻る


ロス ヴァスコス クロマス カルメネール グラン レセルバ
| 国 | チリ |
|---|---|
| ぶどう品種 | カルメネール |
![]()
2位に選ばれたのは、サントリーフロムファーム 岩垂原メルロでした。サントリー塩尻ワイナリーのフラッグシップワインである岩垂原メルロはJR塩尻駅から西方向に進み、桔梗ヶ原エリアを通って、奈良井川を渡った対岸である岩垂原の協力者さんたちが育ててくれたメルロを醸しました。サントリー塩尻ワイナリーでは、2011年ヴィンテージから桔梗ヶ原と岩垂原のメルロを発売しました。桔梗ヶ原と岩垂原は、標高はどちらも700mで同じくらいですが、岩垂原はその名前の通り、堆積した礫がごろごろとしていて、水捌けの良い土壌に恵まれています。
マリアージュ実験に使ったのは2019年ヴィンテージでした。2019年は春先低温傾向が続き、芽吹きから開花にかけて10日程度の遅れが見られました。9月は降水量が平年の28%と、極めて少なく、晴天が長く続いたのでグレートヴィンテージの期待が高まりました。しかし10月に入り、大型台風の直撃と集中豪雨により平年の2.4倍もの降水量となりました。厳しい天候条件ではありましたが、山本さんを始めとする岩垂原の協力者さん達の卓越した栽培管理のお陰で、成熟を待って収穫したぶどうは糖度が高く、種までよく熟した健全な果実を得ることができました。グラスに注ぐとやや濃いめのラズベリーレッドです。ブルーベリーやサワーチェリーなどの果実を連想させる黒紫~黒の果実の香りに、針葉樹や塩尻らしいシダの葉のトーンがあります。そこに樽由来の甘香ばしいスパイシーさが溶け込んでいます。口に含むとしっかりとした骨格を感じさせる緻密な果実味と、豊かな酸味、滑らかなタンニンの程よいバランス感です。岩垂原らしい大地の力が感じられるワインです。
ステークアッシェと合わせると、和牛のコクをより強く感じました。甘さに寄る感じではなく、和牛の複雑な旨味が、より複層的になり、重厚さが増す感じのマリアージュでした。このサントリーフロムファーム 岩垂原メルロ2019は昨年開催された日本ワインコンクール2024で金賞を頂戴しました。


サントリーフロムファーム 岩垂原メルロ
| 国 | 日本 |
|---|---|
| ぶどう品種 | メルロ |
![]()
3位に選ばれたのはレゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨンでした。レゾルム ド カンブラス の「レゾルム」とは、楡の木を示す言葉で、昔からフランスのあちらこちらに生えている樹です。中世では楡の木で大聖堂や船が造られ、その後は楽器や鉄道にも使用されるなど、フランスの人々にとって非常に馴染み深く、身近な存在です。また、「カンブラス」は、南仏の典型的な語感を持つ言葉で、伝統的な建築様式の農家をイメージして造られた造語です。「レゾルム ド カンブラス」という名前には、明るい南仏の空の下で、人々がその木陰に集い、和気藹々と大きな木のテーブルを囲むようなイメージで、”上質かつ親しみやすい味わいのワインを日常的に愉しんでいただきたい”という、つくり手の思いが込められているのです。レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨンは少し淡さのあるブラックチェリーレッドです。カシスやブラックチェリーを思わせる香りに、ほのかなスパイスのニュアンスがあります。口に入れると、程よい凝縮感のあるクリーンな果実味と、熟した滑らかなタンニンが特長の、親しみやすい味わいの赤ワインです。ステークアッシェと合わせると、肉の塊から滲み出る脂とカベルネ・ソーヴィニヨンとが出会って甘く感じさせます。ステークアッシェの刻まれた肉ならではの食べ心地の良さと、このワインの強すぎない程よいボディ感とが良く合っていました。
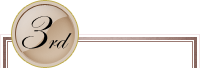

レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン
| 国 | フランス |
|---|---|
| ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
![]()
レシピに戻る
