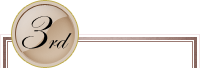今回のレシピは、みそたまりとはちみつ漬けの焼き豚です。皆様は「みそたまり」という調味料をご存知ですか?知っている方は、かなりの発酵食品通です。大手のネットショップで検索しても、みそたまりは2社くらいしかヒットしません。みそたまりは、味噌を発酵させて作る際に、表面に少しだけ、滲み出てくる液体を取り出したものです。たまり醤油はお醤油の仲間なので、別のものです。日本に味噌や醤油が伝わったのは、遣唐使が仏教を伝えた時であるという説があります。日本では、奈良時代くらいまでは、醤油と味噌と塩辛の境界線は、明確にはありませんでした。もっとも古くからある「醤油と味噌と塩辛の仲間」は魚や海老などからつくった塩辛系のもので醤(ひしお)と呼ばれていたようです。時期的には縄文時代後期です。縄文時代後期と言うと、大体今から3000年から4000年前くらい前なのですが、その頃から土器製塩法で製塩が行われるようになりました。その塩を保存料として、魚や海老、獣の肉を漬け込んで醤に類似したものをつくっていました。701年の大宝律令には、官職名として「主醤」(ひしおのつかさ)という醤を管理する役職の記述があります。このころから醤は重要な産物だったのです。その後、穀物で作る醤も作られるようになりました。奈良時代の739年に書かれた正倉院大日本古文書には、未醤や滓醤(かすびしお)や豉の価格の記述が登場します。どうやら、この時期に味噌と醤油と塩辛系の醤が、きちんと分かれたものと考えられます。味噌の名前の語源は「未だ醤にならないもの」という意味を表す「未醤」(みさう・みしょう)です。未だ豆の粒の形があるので醤の手前の物と言う意味のようです。いずれにしても遣唐使よりも100年以上前の話です。味噌も醤油も塩辛系の醤も日本の風土に根差した重要な食品だったのです。
昨年末にひょんなことから、みそたまりの存在を知り、ちょっと使ってみると「ワインが美味しく感じるなぁ・・・」と思って興味が湧きました。ワインスクエアの取材で、料理とワインのマリアージュ実験をして相性を確認する時には「一つの料理に16種類のワインを試す」パターンで実験をしてイチオシ、2位、3位を決めています。その実験の逆のパターンで、実験してみようと思いつきました。つまり、ひとつのお料理、例えばしゃぶしゃぶを、ポン酢だけで一つのワインとの相性を評価し、次にポン酢に少しみそたまりを入れて同じワインとの相性を評価する。様々な料理で、通常の料理で、みそたまりが有るか無いかで「ワインの味がどう変わるか?」の実験をしました。実験を繰り返して吃驚しました。白ワインも赤ワインもシャンパンも、どれもみんな、みそたまりを使った方が美味しかったのです。「これは、どういう風に作られているのか、自分の目で確かめないといけない」と思い立ち、3月に秋田県湯沢市の蔵を訪ねました。秋田県で二番目に古い味噌・醤油蔵で、ほとんどの作業を手作業でやっていました。麹室を温めるのも、炭を熾し麹室の床の穴にいれます。そのままでは翌朝までもたずに燃え尽きてしまうので、稲藁を燃やした灰をお布団代わりに掛けてあげるのです。その稲藁も、現在主流のコンバインでは、刈り取ると同時に稲藁が粉砕されてしまいますので、昔ながらの鎌で刈り取ってくれる農家さんに、特別にお願いして稲藁を供給してもらっています。麦を焙煎するのは、何と石炭です。まるで千と千尋の神隠しの釜爺とススワタリの世界ですよ。醤油を絞るのも袋にいれた醪を木製の槽にいれ、上から押して絞ります。古い木製の槽なので、強く圧搾すると、木製の槽が壊れてしまいますので優しく押します。蔵見学に伺った日は、なんと、醤油も味噌も手で瓶やパッケージに詰めていました。
今回は、そのみそたまりを使って焼き豚を作って頂きました。焼き豚には、大きく分けて3種類あります。中華料理の叉焼と焼豚(チャーシュー)、そして日本のラーメン屋さんでよく見かけるチャーシューです。中華料理の叉焼と焼豚は、五香粉などのスパイスを付けたり、マリネ液で味付けをした肉を焼いて作ります。叉焼の「叉」は金串の事ですから、串に刺して焼かれます。焼豚は基本オーブンです。日本のラーメン屋さんのチャーシューのほとんどは煮豚です。今回、鈴木薫先生に考えて頂いたレシピは、みそたまり、はちみつ、白ワインと粗挽き黒こしょうで作ったマリネ液に豚肩ロース肉を一晩漬け込んでからオーブンで焼いて作る中華調理の焼豚に近い料理です。
このみそたまりとはちみつ漬けの焼き豚にテイスティングメンバーが選んだイチオシワインはヴィッラ サンディ ロザートでした。ヴィッラ サンディはイタリア プロセッコ最高峰の造り手とも称される名門です。イタリアでのワイン評価本として定評のあるガンベロロッソでの最高評価ワイナリーのひとつです。代々ワイン生産に携わってきたモレッティ・ポレガート家がワイナリーを所有し、ヴィッラ サンディの伝統を守りながらも、地域のぶどう栽培をより近代的なものへと導いています。ジャンカルロ・モレッティ・ポレガートが現在の当主です。ワインに対する造詣が深く、力強いリーダーシップと誇りを持ち、家業の伝統を引き継ぎ、前進させているのです。ヴィッラ サンディの名前は、サンディ家により建立された1622年より現存するVilla(邸宅・屋敷)に因みます。トレヴィーゾの文化遺産になっている邸宅は、ナポレオン・ボナパルトも立ち寄ったとされる由緒正しき建造物です。建物はヴァルドッビアデーネ プロッセッコD.O.C.G エリアと、ピアーヴェD.O.C/モンテッロD.O.C. エリアの中間にあり、ワイン造りに最適な場所なのです。ヴィッラ サンディ ロザートのぶどう品種はグレーラとピノ・ノワールで、ステンレスタンクで、低温で発酵されます。色調はほんのりとオレンジ色がかった淡いピンクの、美しいロゼスパークリングワインです。香りはボリュームがあります。甘い香り立ちで、イチゴや赤いさくらんぼやプラムを思わせます。味わいはまろやかです。ブリュットタイプで辛口なのですが、ほんのりと果実が完熟した甘さを感じます。みそたまりとはちみつ漬けの焼き豚と合わせると、相性の良さに驚きました。
「この焼き豚は、いつも食べている焼き豚よりも複雑な味わいですね。広東料理の叉焼って、甘さが前に強めに出てくるのですが、味わいは、割とシンプルな印象がありました。また、老酒とかの甘い酒とは合うのですが、辛口のワインとはイマイチの印象だったのでした。でも、この焼き豚は違いますね。ヴィッラ サンディ ロザートと本当に良く合いますし、自然な美味しさが口に広がります」
「はちみつのコクのある甘さだけじゃない甘さがありますよね。それが辛口のヴィッラ サンディ ロザートと自然に馴染みますね」
「みそたまりマジックですね。味噌がじっくりと発酵と熟成をしていくうちに滲み出てくる自然な甘味と旨味のかたまりですからね」
「ヴィッラ サンディ ロザートは辛口ではあるのですが、優しい口当たりも求めて、ある程度ドザージュしていますから、甘さとの親和性は高いのですよ」
「豚の脂が甘く溶けますよね」
「ヴィッラ サンディ ロザートはロゼなので、白ワインよりは、タンニンが含まれはしますが、動物性脂肪と出会って甘さに転換するほどの量ではありません。はちみつ、みそたまり、ヴィッラ サンディと豚の脂の甘さ感が共鳴しているんだと思います」
「黒こしょうをしっかりめに振っているので、味わいを引き締めていて、とても美味しいです」
皆様も、豚肩ロースが特売の時には、是非このみそたまりとはちみつ漬けの焼き豚の事を思い出してください。そしてヴィッラ サンディ ロザートとの素晴らしいマリアージュをお楽しみください。