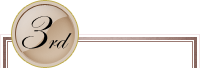今回のレシピは、鰹のたたきカルパッチョです。カツオはサバ亜科マグロ族カツオ属カツオ種です。カツオ属は1属1種で、広がりがありません。カツオと呼ばれる魚で、近い親戚は同じマグロ族で属違いであるソウダガツオ属のヒラソウダとマルソウダです。ちょっと遠い親戚は、ハガツオです。ハガツオはマグロ族ではありません。ハガツオ族で、族まで違うので大分遠くなる感じですね。漢字では歯鰹と書き、サバ亜科では珍しく、大きく鋭い歯があります。カツオに比べると顔が細身で、別名狐鰹とも呼ばれますが、大変美味しくてしかも安い魚種です。刺身でも美味しいのですが、鰹と鰆の中間的な感じの味わいです。もっと遠い親戚もいます。マナガツオです。マナガツオはスズキ目ではありますがイボダイ亜目ですので亜目まで違う、遠い遠い親戚です。カツオは赤身の魚ですが、マナガツオは白身ですから、果たして親戚と呼べるかも怪しいですね。昔から「西にサケ無し東にマナガツオ無し」と言い慣わされて来ましたので、初めて築地市場を訪れた1984年に、仲卸の店先にマナガツオがあって、ちょっと驚きました。その仲卸の方に伺うと「関西じゃ、刺身でも食べる美味しい魚だよ」と教えられました。マナガツオの隣にシマガツオもありました。魚の名前を尋ねると、仲卸の方は「これはエチオピアだ。売っている俺が言うのもなんだけど、あんまり美味しくないから、マナガツオにしな」と親切に教えてくれました。シマガツオは、スズキ亜目シマガツオ科シマガツオ属なので、カツオとは亜目も違う、もう、親戚とは呼べないくらい遠い魚です。シマガツオは鱗が物凄く硬いので、普通の鱗取りでは取れません。鰤の様に、鱗は皮ごと包丁ですいて取ります。さて、鰹です。山口素堂の「目には青葉、山ほととぎす、初鰹」で有名な鰹ですが、江戸っ子は、大変に珍重しました。江戸の後期、文化9年に歌舞伎役者である中村歌右衛門が鰹一本を3両で買ったという記録が残っています。1両の名目上の金平価は金4.4匁(16.4g)(実際の含有量は時代に拠る)です。原稿を書いている3月27日時点の金の価格を掛け合わせると、なんと鰹一本が58万円になります。驚きの価格ですよね。もっと古い時代の記録では、大和朝廷の献上品の一覧に、鰹節の原型である干した鰹が既に記録されています。鰹節の堅さ故、堅魚の名前が与えられ、それが転じて、カツオに鰹の文字が充てられるようになりました。ギネスブックには世界で最も堅い食品として鰹節が掲載されていました。さて、近年の初鰹と呼ばれる春から初夏の漁獲ですが、2022年は、シーズン初めから、サイズが大きくて、戻り鰹級の脂の乗りの鰹が沢山とれました。一方本来の戻り鰹の秋漁の季節には、大きな鰹が少なく、2022年通年の合計では2021年よりも17%の減少となりました。2023年は、サイズは小さかったのですが、とても美味しかったですよね。2024年の漁は、まだ始まったばかりですが、脂の乗りの良い絶品が、獲れているようです。このコラムを担当するようになって19年目で400本余りの料理とワインのマリアージュの原稿を書いてまいりましたが、実は「鰹のたたき」は初めての料理なのです。今回は鈴木薫先生にワインに良く合う鰹のたたきのレシピを作っていただきました。「たたき」は、漢字では「叩き」もしくは「敲き」と表記します。本来は、食べる材料を包丁で細かく叩いた料理で、「たたき塩辛」の事なのです。包丁ではなく、擂り粉木で叩いた料理では叩き鮑、叩き烏賊、叩き牛蒡や叩き納豆などがあります。現在の、「鰹のたたき」は日本料理の「焼霜造り」的な料理で、叩く動作を、あまりしませんよね。農林水産省の「うちの郷土料理」では鰹のたたきを高知の郷土料理として掲載しています。そのページでは「『鰹のたたき』は漁師が船上で食べていたまかないだったものが一般に伝わったとされている。保存技術のない時代、船上で鮮度が落ちた鰹を食べるために、"たたき"という料理法が発展したともいわれている。『鰹のたたき』にすることで、鰹特有の生臭さも軽減される。「鰹のたたき」の"たたき"とは、その名の通り"叩く"を意味する。調理の際に、塩やタレをかけて叩いて味を馴染ませたことに由来するといわれている。」と解説しています。鰹のたたきは、叩くものだったのですね。総務省が2023年に発表した「都道府県庁所在市別1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量(二人以上の世帯)」によると、一番鰹を食べる県庁所在市は高知市で年間7,030円です、2位の水戸市の3155円の何と2.2倍も食べているんですよ。流石、高知ですよね。
フライパンにオリーブオイルを熱し、鰹の表面を焼きます。薬味は新玉ねぎとクレソンと煎った松の実です。この鰹のたたきカルパッチョにテイスティングメンバーが選んだイチオシワインは、フロムファーム 塩尻メルロ ロゼでした。フロムファーム 塩尻メルロ ロゼは、実は、ロゼを作るためのロゼではないのです。塩尻ワイナリーの赤ワインのフラッグシップは岩垂原メルロですが、この岩垂原メルロや塩尻メルロを濃くするために、セニエという醸造テクニックを使います。ワインの色や香り成分はぶどうの果皮に含まれています。ぶどうを破砕した醪から果汁を一部抜いて発酵すると、果汁に占める果皮の割合が高まります。それをそのまま発酵させると、通常に仕込むワインよりも濃いワインが出来るというテクニックです。一方引き抜いた方の果汁ですが、本来岩垂原メルロや塩尻メルロになる高品質の果汁です。引き抜いた時には、ぶどうを破砕した時に、ほんの少しだけ色素が出て、淡いピンク色が付いています。それを、白ワインを仕込むように発酵させると塩尻メルロ ロゼが出来上がるのです。
グラスに注ぐと、濃さは淡めでピンクのタッチが強い、美しいロゼカラーです。若々しい赤い林檎の様な爽やかさと、日本のさくらんぼ、佐藤錦を連想させる甘い香りに、チャーミングなピンクの花のニュアンスがあります。キリっと引き締まった酸味で、イキイキとした瑞々しさを持った果実味が特長の、フレッシュな辛口ロゼワインです。
鰹のたたきカルパッチョと合わせると鰹の身そのものもが持っている鉄っぽい味わいが心地よく広がります。
「鰹は赤ワインと思い込んでいましたが、ロゼも美味しいですね」
「鰹のたたきって、おろし生姜と小葱を添えてスライスニンニクで醤油をかけるパターンばかりで食べていましたが、玉ねぎとクレソンと松の実も美味しいですね」
「うん、レモン果汁と醤油とオリーブオイルというのも新鮮です」
「松の実が個性的ですよね、樽熟の白ワインと合わせるとナッティな風味が強く出過ぎて、少し邪魔になるのですが、塩尻メルロ ロゼだと、丁度居心地の良い強さのナッティさになります」
「優しいロゼの方が、鰹の素材そのものの美味しさが判る気がします」
「鰹って少し癖がありますが、塩尻メルロ ロゼとだと、嫌みのない綺麗な調和が楽しめますね」
皆様も、良い鰹を見かけられましたら、是非この鰹のたたきカルパッチョの事を思い出してください。そしてフロムファーム 塩尻メルロ ロゼとの素晴らしいマリアージュをお楽しみください。