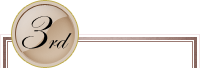今回のレシピは、桜海老と筍、ウドのペペロンチーノパスタです。サクラエビはサクラエビ科、サクラエビ属に属する小さなエビで、主に駿河湾の深海に生息しています。生きている時には桜の花びらを思わせる、透き通った、淡いピンク色、干すと緋寒桜を思わせる濃い目のピンク色をしているので桜海老の名前が与えられました。この素敵な名前が命名されたのは、実は海無し県である山梨県の甲府での事なんですよ。2023年8月3日と4日、「日本財団 海と日本プロジェクトinやまなし実行委員会」主催で「山梨海の文化調査隊!山梨発祥!?サクラエビの歴史と今を探る!」が開催されました。その会場で、桜海老が甲府で命名されたとする研究結果が発表されたのでした。かつて静岡市の桜海老加工業者である望仙の方が甲府へ行商に訪れた際に、甲府の方から「こりゃ、桜の様に美しい、そうだ、これは桜海老だ」と言われたのが最初だそうです。当時、駿河湾で獲れた桜海老は日持ちするように素干しに加工され、駿河湾沿いの各地を発着点とし山梨までいろいろな海産物などを運んでいた富士川舟運によって主に運搬されていました。桜海老の主な生息地は駿河湾なのですが、駿河湾の東では相模湾や東京湾にもいます。西だと遠州灘にも居るようですが、遠州灘より西には生息しないと考えられていました。また、駿河湾以外の相模湾、東京湾や遠州灘では漁が行われておりませんので日本で流通している日本産の桜海老は100%駿河湾産です。桜海老の漁はいつ始まったかが明確に記録されている珍しい漁です。静岡県道396号の富士由比線にある「ゆい桜えび館」によると、初めての桜海老漁は偶然から始まったそうです。1894年の12月に由比今宿の望月平七と渡辺忠兵衛という二人の漁師が夜に鯵の曳舟漁をしようと海に出ました。沖に出て網を浮かせる浮樽(カンタ)を忘れてきた事に気が付きます。でもそのまま帰る訳にもいかず、網をいれたところ、普段よりもずっと深い所に網が沈んでしまったのですが、沢山の桜海老が獲れたそうです。現在では2隻の漁船で、深い所を網で曳く方法で漁が行われています。駿河湾では、資源を守るため、春漁と秋漁しか行わない自主規制をしております。春漁が大体70日、秋漁が60日くらいで、残りの期間は漁をしません。しかも漁をする事が許されている船は、由比漁港と大井川漁港に属している60組120隻の漁船だけなのです。しかも、漁が許されている期間でも、我先に沢山獲りつくしてしまわないように、全船の水揚げを一旦取りまとめて利益を分け合う"プール制"を導入しました。これによって120隻の許可された船たちは運命共同体になったのです。この画期的な仕組みは1977年に導入され、今日でもそのルールが運用されています。この厳重な資源管理を実施していたのですが、2018年には漁獲量が激減しました。この年の春漁は19回出漁したのですが、約312tしか取れませんでした。これは記録が残っている範囲では最低だったそうです。組合では春漁を中断し資源保護を目指したのですが、資源は回復せず、2018年の秋漁でも試漁検査で小さいサイズしかいない事が判り、1度も出漁する事無く秋漁が終わりました。翌2019年の春漁は、3月24日解禁で約70日の予定でしたが、5月になっても思うように漁獲出来ず、5月31日で終漁となり、85トンで史上最低だった2018年の1/4しか取れませんでした。漁協では有識者に調査を依頼し2018年当時は「2017年8月から始まった黒潮の大蛇行により、水温の高い黒潮が駿河湾に流れ込まなかったためではないか?」という仮説が立てられました。由比港漁協は、黒潮の蛇行の他にも富士川の汚濁も原因では無いか?と静岡県に訴え、静岡県が富士川の河口付近の放水路の汚濁調査をしたところ、汚濁の2つある指標の一つであるSuspended Solid(水中に浮遊する粒子径2 mm以下の不溶解性物質の量)が水道取水の基準値25 mgを大幅に超える427 mgだった事が判明しました。汚濁の原因のひとつは、富士川支流の早川の防砂ダムが殆ど埋まってしまい、汚濁物質が直接流れ込んでいる事ではないか?との仮説も提唱されましたが、現在まで抜本的な対策は打たれておりません。2018年の不漁のあと、五島列島沖にも桜海老が存在する事が確認出来たと言う発表がされ、また、台湾沖でも桜海老が漁獲されるようになり、日本に輸出されております。駿河湾での不漁の原因は不明のまま、2022年春漁が、3月30日解禁を迎え、3月31日912㎏の初競りが行われました。 2019年の大不漁とは違う「良い手ごたえ」の解禁でした。結局春漁の水揚げ量202tで、少ないながらも最悪期からの回復の兆しを見せました。2023年の解禁は4月4日の夕刻でした。5日には約40tもの水揚げがあり、関係者も「初日としては記憶にない豊漁」と口を揃えていました。黒潮研究家の美山 透氏によると、2017年8月に始まった黒潮大蛇行は、現在も続いており、既に期間が6年8か月目で、観測史上最長になっているそうです。2018年の大不漁の時に有識者達が集まって立てた仮説の時に、原因とされていた2つの要素である「黒潮の大蛇行」や「富士川の汚濁」だけが、「2018年来の桜海老の大不漁」の原因では、なさそうですね。今年の桜海老のスタートは3月25日からのようです、今年はどうなんでしょうね?楽しみです。さて、ウドです。ウドはウコギ科タラノキ属の大型の多年草です。数少ない日本原産の植物だと言われていて、英語でもフランス語でもUdoです。ウコギ科の植物で山菜として食べられるのはウドの他には、こしあぶらやタラの芽が有ります。ウドは漢字表記では独活と書きます。これは、風が無いのに葉が動くから「独り」「活く:うごく」でウドと書き習わすようになったとされています。「ウドの大木」は、すぐに大きくなる性質と、大きくなった時には、堅くなって食用に出来なくなる事と、早く成長する為に、中心部がスカスカで材木としては使用できなかった事から、「図体ばかり大きくて、約に立たない物」の比喩として使われています。市場に出まわるウドは3種類です。山に分け入って採取してくる「天然もののウド」と東京都の立川あたりで良く行われている地中に室を掘って、完全に遮光して作る「軟白ウド」と畑でウドを育てる「露地栽培ウド」の3つがあります。ややこしいのは「天然もののウド」も「露地栽培ウド」も両方「山ウド」と呼ばれる時がある事です。「天然もののウド」は白い部分がありません。「露地栽培ウド」は根もとに土を寄せて栽培しますので葉の部分は緑で茎の部分は白い事が多いです。「天然もののウド」は市場に出回る期間は短く3月から5月くらい、栽培ウドは6月から10月を除けば市場にあります。今日は桜海老とウドと筍でペペロンチーノパスタを作っていただきました。
この桜海老と筍、ウドのペペロンチーノパスタにテイスティングメンバーが選んだイチオシワインは、ラ コスト ロゼ ド ニュイでした。ラ コスト ロゼ ド ニュイはシャトー ラ コストがプロヴァンスで手掛けるロゼワインです。シャトー ラ コストは南仏エクス アン プロヴァンスとリュベロン国立公園のちょうど中間に位置します。広大な200haの敷地に130haのぶどう畑が広がっています。マスタープランは著名な建築家の安藤忠雄氏によるものです。2011年からは一般に公開され、現在は、レストランやヴィッラも併設されています。ゆっくりと滞在してワインとグルメ、そしてアートが楽しめる、ラグジュアリーなワイナリーなのです。広大な敷地には、安藤氏設計のギャラリーを中心に、F・ゲーリー、J・ヌヴェル、R・ピアノ、N・フォスター他、世界の名だたる建築家やアーティストによる作品30以上が点在しています。正に美術館に滞在している気分になれるスペシャルな場所なのです。シャトー ラ コストのワインは、自然環境に配慮したサスティナブルな農法に基づくオーガニックワインです。畑だけでなく、ワインづくりのすべての工程において環境に配慮しています。環境に負担をかけない醸造施設は、かのジャン・ヌーヴェル氏が設計したものです。ラ コスト ロゼ ド ニュイの原産地はAOP コトー デクサン プロヴァンスです。品種はグルナッシュ、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨンです。
グラスからは白桃やストロベリーのようなチャーミングな香りが静かに立ち昇ってきます。口に含むと、 果物をほおばったような、瑞々しくたっぷりした果実感とフレッシュさにあふれるロゼです。桜海老と筍、ウドのペペロンチーノパスタと合わせると、ロゼの、いろんな素材全部を受け止めくれる包容力の大きさを実感できました。ウドの、緑の印象溢れるフレッシュさとほろ苦さ、筍の大地の素朴な味わい深さ、桜海老のコクのある旨み、それらを総て包み込んで纏めてくれます。
「美味しいですね」
「色合いも、桜海老とロゼが丁度良く合っていて、気分があがりますよね」
「ロゼワインの懐の深さと言うか、どんな素材にでも合わせてくれる柔軟さが光りますね」
「お口の中が、幸せです」
「最初に揚げた事で、桜海老の殻が香ばしくなっていて、噛むと、パリパリした食感と、その奥から味噌の濃厚なコクが出てきます。そこにウドや筍の複雑な味わいが、それぞれに自己主張するのですが、ワインを飲むと、ロゼの指揮の元、一体感のある旨みに変化していきました・・・」
「その旨みが、美味しさの余韻となって、細く長く、ずぅーーーっと続いていきます」
「本当に良いマリアージュですね」
皆様も桜海老を見かけられましたら、是非この桜海老と筍、ウドのペペロンチーノパスタの事を思い出してください。そしてラ コスト ロゼ ド ニュイとの素晴らしいマリアージュをお楽しみください。