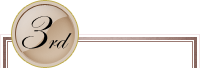今回のレシピは、ローストビーフの押し寿司です。清水桂一編の[たべもの語源辞典]によると、「すし(鮨、鮓、寿司)」に関して、スシのスは醋であり、シは助辞である。すなわし「すし」とは「酸し」の意である。古く『延喜式』927年に記された、諸国の貢ぎ物のなかに多くの「すし」が出てくる。これらは「馴れずし」で魚介類を塩蔵して自然発酵させたものである。発酵を早めるために飯を加えて漬けるようになったのは慶長(1596年から1615年)ころからと伝えられる。飯に酢を加えて漬けるようになったのは江戸時代になってからである。江戸末期になって酢飯のほうが主材になって飯鮨(イイズシ)とよばれるようになり、散らし鮨や握り鮨が生まれる」とあります。寿司の原点は魚介の塩辛だったんですね。江戸前の握り鮨は小泉與兵衛が考案したとされています。小泉與兵衛は、酢飯に山葵を挿んでネタを乗せ、さらに握った料理を考え出しました。最初は、それを岡持にいれて繁華街を売り歩き、次には屋台で提供しました。この斬新なファーストフードは直ぐに江戸っ子たちの大人気となりました。與兵衛は文政7年1824年に、かつての元町、今の両国1丁目8番地に華屋を出したので、華屋與兵衛と呼ばれるようになりました。両国幼稚園の前には、墨田区が出した木製の「与兵衛すし跡」の看板がありますし、その向かいには墨田区の教育委員会が作成した「与兵衛鮨発祥の地」の記念の金属板が設置してあります。華屋は昭和5年に廃業しました。さて江戸前の握り鮨よりも前から存在していたのが関西風の押し鮨です。岩波書店の広辞苑 第七版を見ると「方形の型の中にすし飯を詰め、その上に魚介類・卵焼などの種(タネ)をのせて押しかためて作る鮨。箱鮨。大阪鮨。」とあります。奈良の柿の葉寿司や京都の鯖の棒鮨も木枠に入れて押しますので、押し鮨の仲間です。1728年発行の嘯夕軒宗堅 が著した「料理網目調味抄」に箱寿司に酢を注ぐと記されていて、その箱寿司が大阪寿司の事のようです。料理網目調味抄は国立国会図書館デジタルコレクションで画像閲覧できます。今度はローストビーフです。ローストビーフはイギリスの伝統的な郷土料理と言われています。1731年に発表されたバラード曲の「オールドイングランドのローストビーフ」の題名にもなっています。ご存知の通り、牛肉をローストした料理で、イギリスやアメリカでは、日曜日に教会に行ったあとのランチやディナーに、よく出される料理の1つです。ふわふわで、もっちりとしたシュークリームの皮のような、ヨークシャープディングが付け合わせの定番で、ホースラディッシュが添えられます。ソースは、グレイビーソースを掛けます。グレイビーソースは、牛肉の塊に焼き色を付ける時のフライパンに残った肉汁や焦げを、ワインや水、ビール、スープストックなどを加えて溶かしながら煮詰めて作ります。炒めた小麦粉(ルー)や片栗粉でとろみをつける事もあります。より、滑らかにする為に牛乳や生クリームを足す場合もあります。グレイビーソースは食べる直前に作るソースのため、あまり長時間は煮込まないソースです。
今回の鮨飯には紫玉ねぎに塩をしたものと、松の実を炒ったものとケイパーを入れました。
さて、このローストビーフの押し寿司にテイスティングメンバーが選んだイチオシは、ドメーヌ バロン ド ロートシルト サガ R ボルドー ルージュでした。ドメーヌ バロン ド ロートシルト ラフィット(Domaines Barons de Rothschild LAFITE)は、ロートシルト家のワイン部門で、シャトー ラフィット・ロートシルトを所有しています。シャトー ラフィット・ロートシルトは、1855年のパリ万博の時に実施されたメドックの格付けで、1級シャトー、しかも4つ選ばれた1級シャトーの中でも、筆頭格付けに選ばれました。「ロスチャイルド」は英語読み、フランス語読みは「ロチルド」ドイツ語読みは「ロートシルト」です。初代のマイヤー アムシェル ロートシルトはフランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)出身なのです。1770年ころまでは小さな商店で、「ロートシルト(赤い表札)」の付いた小さな小さな店だったそうです。最初は古銭商と現物の商品を少し扱い、後に両替や手形の割引なども、するようになりました。後のヴィルヘルム9世 に取引を許され、急速に規模が拡大し銀行業へと成長していきました。1789年のフランス革命の後、フランスはユダヤ人解放政策を実施しました。1803年にヘッセン=カッセル方伯に選帝侯の資格が与えられる事になり、ヴィルヘルム9世はヘッセン選帝侯ヴィルヘルム1世となり、更に大きな権力を持つようになったのです。1804年には、マイヤー アムシェルの三男、ネイサンはロンドンの金融街シティに移り、N・M・ロスチャイルド&サンズを創設して本格的な金融業となりました。マイヤー アムシェルには5人の息子がいたのですが、その息子たちをヨーロッパ各国に派遣し、一大金融網を築き上げました。1806年 にナポレオン・ボナパルトがヘッセンにも侵攻しました。選帝侯ヴィルヘルム1世は、一旦は破れ、国外に亡命しました。ロスチャイルド家は選帝侯の巨額の財産の管理権・事業権を委託されたのです。以降ロスチャイルド家はフランス当局の監視を巧みにかわしつつ、大陸中を駆け回って選帝侯の代わりに選帝侯の債権の回収にあたり、回収した金は選帝侯の許しを得て投資事業に転用して、莫大な利益を上げるようになったのです。また、ナポレオンは大陸封鎖令を出して、 敵国イギリスとの貿易を禁じました。大陸封鎖令によりヨーロッパの大陸諸国ではコーヒー、砂糖、煙草、綿製品など商品の価格が高騰した一方で、イギリスではこれらの商品の価格が、輸出先を失った事によりダブつき、暴落しました。ロンドンのネイサンはイギリスでこれらの商品を安く買って大陸へ密輸し、それを父や兄弟たちが大陸内で確立していた通商ルートを使って大陸各国で売りさばくようになりました。これによってロスチャイルド家は更に莫大な利益を上げたのです。ラフィットグループの全てのワインにはキャップシールに黄色の帯があしらわれています。これはロスチャイルド家のシンボルカラーであるイエローから来ています。 19世紀前半、まだ馬車しか情報伝達手段がなかった時代のこと、ヨーロッパ各地に分散し各国の中枢に入り込んだ5人の息子たちが各国の政治や経済の異変をいち早く察知し、世界一早いといわれた馬車で使者を送り合い、国債の暴落や株の動きなどに誰よりも早く対応、巨額の富を得ました。 その使者の馬車にはこの帯と同じ色の旗が掲げられていたのでした。5人の息子のうち3男ネイサン(英・ロンドン)と5男ジェームズ(仏・パリ)がワイン事業に参画しました。3男ネイサンはシャトームートン ロートシルトを購入、5男ジェームズはシャトー ラフィット ロートシルトを購入しました。サガ Rのサガは「伝説」、Rは「ロ―トシルト」の意味です。ラフィットグループを率いたエリック男爵は、5男ジェームズの子孫です。エリック男爵は、親しい友人たちや家族のために、シャトーワインに近いスタイルで日常的に気軽に楽しめるワインをつくっていました。それがこのサガRのルーツで「男爵の秘蔵ワイン」と呼ばれていました。現在は男爵の娘、サスキア・ド・ロスチャイルドが、当主として伝統を守りながらも、多様性の時代を乗り切るための新しい風を吹き込もうとしています。
サガ Rの赤2020はメルロ70%とカベルネ・ソーヴィニヨン30%で醸されています。グラスに注ぐと、ボルドーの赤にしては、少し明るい色です。さくらんぼやブルーベリーのような心地よい香りが昇ってきます。ボルドーらしい気品ある香りです。口に含むと穏やかで、柔らかくエレガントです。4つの1級シャトーの中で最もエレガントなのはシャトー ラフィット ロートシルトだと言われる「ラフィット エレガンス」の系譜を感じさせる味わいです。ローストビーフの押し寿司と合わせると、まとまりの良い美味しさを感じます。
「牛肉との相性の良さが前面に出るのかと思いきや、調和やバランスの良さのマリアージュですね」
「うん、押し寿司を軽やかに包み込む感じです」
「松の実やケイパーとも、良く合っているのですが、何かが突出している、と言う訳でもないんですよね」
「力強さではラトゥール、優美さではマルゴー、派手な主張ではムートン・・・・なのですが、『やっぱりラフィット エレガンスが一番!!』と言う王侯貴族が多かったから、ラフィットが筆頭格付けになったのでしょうね。サガRは「男爵の秘蔵ワイン」なので、そのエレガントな世界観を持っている気がします」
「押し寿司と良く合っています」
皆様もローストビーフの押し寿司にトライしてみてください。自分でローストビーフを焼く時は、肉の塊は大きい方が美味しく出来ますよね。だから、大体余ります。そんな余ったローストビーフの絶好の活躍の場所が、この押し寿司です。もちろん、市販のローストビーフでも、とっても美味しく出来ます。そしてドメーヌ バロン ド ロートシルト サガ R ボルドー ルージュとの素晴らしいマリアージュをお楽しみくださいませ。