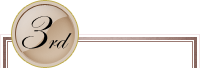今回のレシピは、バーミークローブ ラッナー ホイ(帆立貝と春野菜のタイ式あんかけ揚げ麺)です。ミークローブは、きちんと言うと、バーミークローブです。バーミー(中華麺)とクローブ(パリパリした、とか、カリカリした)でパリパリした麺の意味です。発音は、端折って、ミークローブになります。ラッナーは「あんかけ」です。日本のタイ料理屋さんではラート ナーと表記しているところもあります。ラート(掛ける)で、ナー(上 )なので直訳すると上に掛けるという意味で、あんかけです。発音は、これも、「ト」を端折ってラッナーになります。ホイは貝です。タイでは、ラッナーは庶民的な料理で、屋台や町の食堂、フードコートなどによくある料理です。バンコク郊外には有名なラッナー専門店があり、わざわざ買いに行く人もいます。具材は、豚肉、牛肉や鶏肉、海老などの海鮮を選んでオーダー出来る所が多いです。また麺も茹でた米麺、この揚げ中華麺からチョイスも出来ますし、ご飯に掛けて食べる事も選べます。タイでは、ホタテ貝は、一般的にはあまり使われません。ホタテ貝は寒冷海洋性なので、タイの近海には居ないので輸入になってしまいます。高い食材なので庶民的なラッナーにはあまり使われません。なので、今回のこのレシピは、鈴木都先生が考案した「日本食材を使ったタイ料理」という訳です。日本のフランス料理店が、鮎などの、フランスにはない素材を上手に取り入れて献立をつくっているのと同じ工夫ですよね。春野菜は、今回、新玉ねぎ、芽キャベツ、スナップエンドウ、アスパラガスを使いましたが、お好きな野菜なら何でも良いと思います。料理の名前は「あんかけ」ですが、食べる時に、パリパリの食感も楽しむおつまみ感が欲しかったので、あえて下に麺を敷かず、具の周囲に置きました。
このバーミークローブ ラッナー ホイ(帆立貝と春野菜のタイ式あんかけ揚げ麺)にテイスティングメンバーが選んだイチオシワインは、サントリー フロムファーム 津軽ソーヴィニヨン・ブランでした。サントリーでは、昨年の9月に日本ワインのブランドを一新いたしました。「畑からぶどうづくりと向き合うサントリーの、産地が見え、つくり手が見えるワイン」をメインテーマに「サントリーフロムファーム」シリーズです。ラインナップは4つです。日本の頂点を目指し、世界のトップ水準に伍していく意気込みの「シンボルシリーズ」、サントリーのワイナリーの伝統と品質のこだわりの「ワイナリーシリーズ」、産地の個性や魅力を愉しんで頂きたい「テロワールシリーズ」と「品種シリーズ」の4つです。今回イチオシに選ばれたフロムファーム 津軽ソーヴィニヨン・ブランは、「テロワールシリーズ」になります。青森県弘前市の津軽富士と呼ばれる岩木山の南斜面にある、太田さんと木村さんという2軒の契約農家さんが、このソーヴィニヨン・ブランを栽培してくださっています。標高は100~150m、南に向いた緩やかな斜面に火山灰土壌が堆積していて水はけは良好です。ヴィンテージは2021年、でグラスに注ぐと、爽やかな香りが広がります。いかにも津軽らしい香り立ち・・・・そうです!りんごのニュアンスが明確にあるのです。青りんごと甘く熟したグレープフルーツなどを連想させる果実の香りに、白桃のタッチもほんの少しあります。セルフィーユの様な甘いハーブとテイスティング用語で「ブルジョン ド カシス」(カシスの新芽)と表現される植物感が爽やかさを与えています。軽やかながら凝縮感のある果実味と、冷涼エリアらしいハリと伸びのある酸味が特長の、引き締まった味わいの充実した辛口ソーヴィニヨン・ブランです。
ラッナー ホイと合わせると、春野菜と津軽ソーヴィニヨン・ブランとが、香りだけでもマリアージュしているのが判ります。
「香りが、共鳴というのか、共振というのか、お互いに強め合って清々しい感じになっています」
「ソーヴィニヨン・ブランの個性的な香りの要素には、グレープフルーツやパッションフルーツのチオール系の香りと野菜を連想させるメトキシピラジン系の香りがあります。津軽ソーヴィニヨン・ブランは、ワイン単体で飲むと、そんなにメトキシピラジン系の香りは強く感じないのですが野菜と合わせると、顔をのぞかせますね」
「野菜もですが、ホタテが凄く美味しいです」
「ソーヴィニヨン・ブランのピュアな酸味で、ホタテの甘みが、真っすぐに感じ取れますね」
「青森にとって、ホタテは大事な海産物です。天然ホタテだと圧倒的に北海道のシェアが高いですが、それでも青森は2位です。養殖ホタテになると青森県がシェア6割以上を占めて堂々の1位です」
「青森の風土が育んだ物同士の、本質的な相性なんでしょうかね・・・」
皆様も、是非、バーミークローブ ラッナー ホイ(帆立貝と春野菜のタイ式あんかけ揚げ麺)を作ってみてください。そしてサントリー フロムファーム 津軽ソーヴィニヨン・ブランとの素晴らしいマリアージュをお楽しみくださいませ。