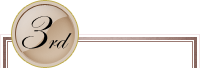今回のレシピは、花かつおの揚げ豆腐です。小学生の頃に、とうふの漢字が豆腐である事を初めて知った時に、「豆が腐るって、納豆の事じゃないの?」と不思議に思ったのを鮮明に覚えています。豆腐も納豆も共に中国から日本に伝わりました。豆腐は紀元前2世紀の頃に、淮南王劉安が発明したと伝えられています。中国南宋の儒学者である朱子も、豆腐詩で淮南王が豆腐を作った、と歌っています。豆腐はその頃から豆腐の文字を与えられていました。納豆は2世紀頃に文献に登場します。納豆は「豉」の文字を充てられていました。豉の文字は、現代に於いても豆豉という調味料として中国で使われています。豉には淡豉と塩豉の2種類があり、淡豉は糸引き納豆で、塩豉は一休納豆や浜納豆や大徳寺納豆のような納豆です。調味料の豆豉は塩豉の仲間です。納豆が日本に伝わったのは平安時代と考えられています。煮た大豆を煮沸した藁苞に包んで発酵させる方法は日本人が発明しました。さて、豆腐ですが、「腐」の部首は肉ですが、肉を取り除くと府になります。府は庫の事で「くら」です。倉庫に狩で獲った肉を収めて置くと、死後硬直が解けて柔らかくなる・・・・さらに進むと腐敗する。その柔らかくなる過程や状態を腐と表しました。中国の古代医学では胃での初期消化を腐熟と呼んでいました。白くどろどろの状態の事を指していたようです。なので、豆腐の製造工程の、煮た大豆を擂り潰し、固める前の状態に腐の文字を充てていたのではないか?と考えられます。豆腐は、おそらく鎌倉時代には日本に伝わり、室町時代には日本のあちらこちらにまで広まり、江戸時代には庶民の重要な食べ物になりました。江戸時代初期の豆腐は総て木綿豆腐でした。絹ごし豆腐を初めて作った笹の雪は台東区根岸2丁目にありました。店の生垣には、店名に因む笹がたくさん植えられ、正岡子規の句碑もありました。なんと創業は1701年です。浅野内匠頭が吉良上野介に刃傷に及んだ年ですよ。建物建て替えの為に移転し、令和3年の秋に再開のはずが、未だ開店の知らせは届きません。赤穂浪士も食べ、正岡子規も愛した店だそうです。いずれにしても、豆腐は江戸時代の庶民も、そして大名も食べた食品なのです。1782年に出版された豆腐百珍には100種類もの豆腐料理が掲載されています。豆腐百珍 原本現代訳が新潮社から出版されていて購入する事ができます。
さて、今回は木綿豆腐に鰹節をまぶして揚げます。鰹節はカツオの身を煮てから乾燥させた日本の保存食品です。ギネスに世界一堅い食品として掲載された事もあります。節は様々な魚で作られたものがあります。宗田節はソウダガツオ、鯖節はサバやゴマサバ、鮪節は主にキハダマグロの幼魚、鯵節は主にムロアジ、鰯節はカタクチイワシ、マイワシなどから作られます。農林水産省大臣官房統計部の「水産加工統計調査」で、都道府県別の節製品(節類・削りぶし)の生産量 が公表されています。令和3年の様々な節製品の合計生産量は66,000tです。その6割がカツオから作られたもので、次いでサバが15%の1万tです。鰹節の生産都道府県のトップは鹿児島で73%、次いで静岡で26%です。残りは1%しかないのです。面白いのはカツオの漁獲量の県別ランキングと大分様子が違う事です。カツオの漁獲量は、1位静岡で宮城、東京、三重、高知、宮崎、神奈川、新潟、鳥取、長崎の順です。鰹節生産のNo.1の鹿児島は10位以内にも入っていないのです。
さて、鰹節の作り方です。大きな鰹は、まず頭を落とし、ハラモの部分を切ります。ハラモとは、鰹の首の下にある脂の多い部分からお腹の部分です。ここは脂が多いので、美味しい鰹節には邪魔になるのです。最初3枚に下ろし、その後5枚に下ろします。3枚に下ろした鰹の片身の真ん中には血合があるのですが、血合部分は腹側部分に入るように切り分けると5枚下ろしの完成です。背側の2枚を雄節、男節、または背節と呼びます。腹側の2枚は雌節、女節、または腹節と呼びます。小さな鰹は3枚に下ろし、身の部分を亀節と呼びます。次に節を煮ます。業界では煮熟(しゃじゅく)と呼んでいます。節を蒸籠に並べ、その蒸籠を何枚も重ねて釜の中にいれます。時間は大体、1時間~2時間くらいで95℃以上の状態を保ちます。煮上がると、なまり節になります。放冷したら骨を抜きます。肋骨にあたる腹骨と、三枚に下ろした魚の真ん中に有って、毛抜きで抜く骨(正式名称は上椎体骨)を抜きます。次は燻製にします。再び蒸籠に節を並べて燻製にするのですが、業界では焙乾と呼びます。薪を燃やして煙と熱を当てていきます。薪はクヌギやナラ、桜などです。焙乾にはいくつか方法があるのですが、何度も何度も場所を変えて乾燥と燻製を繰り返します。乾燥と燻製が終ると荒節になります。荒節になるまでで、大体1ヶ月かかります。そして元のカツオの重さの1/5にまで、減ってしまいます。荒節を削ると、皆さんが通常スーパーマーケットなどで購入される「花かつお」になります。荒節は、未だ柔らかく、節同志をぶつけると、ゴツゴツと音がします。荒節は削り節にすると、燻した風味が強く、魚の旨みのしっかりしたお出汁を引くことが出来ます。
次の工程はカビ付けです。カビを付ける前にお掃除をします。焙煎された荒節には滲み出た脂やタール状のヤニが付いていますのでそれを綺麗に取るのです。ぐるぐると回転している砥石に節を押し当てて削り取ります。汚れが綺麗に取れたら、カビを付けます。カビを付ける目的は2つあります。ひとつは澄んだお出汁を引くために脂肪を分解する為と、もう一つは水分を更に抜いて保存性を高める為です。表面を削って綺麗にした鰹節にカビの胞子を振り掛けます。鰹節に使用するカビは、ユーロティウム属のカビです。ユーロティウム属のカビは、こうじ菌属(アスペルギルス属)のカビに似ていて、乾燥状態が好きなカビです。胞子を振ったら業界で「むろ」と呼ぶ部屋にいれます。むろは温度約30℃で湿度約85%に設定してありカビが繁殖しやすい環境となっているのです。
2週間余り、むろに保管し充分にカビが増殖したら、天日干しを行い、一度カビを取り去ります。この一連の作業でカビ付け1回となります。1回で大体20日間かかります。このカビ付けを3回~5回繰り返すと本枯節(ほんがれぶし)という鰹節が完成します。5回カビを付ける本枯節は、生の鰹から約5か月もかかるのです。カビは、1回目は青白いカビが生えますが、カビ付けを繰り返すごとに色が茶色になっていきます。本枯節は、荒節よりも水分が抜けており、芯まで堅いです。節同士を叩き合わせると荒節は低い音がしますが、本枯節を節同士で叩くと、「カーンカーン」という、高くて澄んだ音がします。本枯節の削り節は荒節に比べ、澄んだ上品な味わいで高級料理店の一番出汁になります。一般社団法人全国削節工業協会によると、「かつお削りぶし」と「かつおかれぶし削りぶし」は、全く違うものだそうです。「かつお削りぶし」は荒節を薄く削ったもの、「かつおかれぶし削りぶし」は本枯節を薄く削ったもので、高級でほんの少量しか生産されていない貴重品なのです。
花かつおの揚げ豆腐を作ります。木綿豆腐は水切りをして一口大にします。小麦粉を水で溶き、豆腐をくぐらせて、花かつおをまんべんなくまぶし、軽く押さえるようにしながら豆腐を包んで揚げます。汁は、だし汁、しょうゆ、みりんを火にかけ、一度煮立たせて作ります。
この花かつおの揚げ豆腐にテイスティングメンバーが選んだイチオシワインは、ミオネット ヴァルドッビアーデネ DOCG プロセッコ スペリオーレ エクストラドライでした。プロセッコはイタリアのスパークリングワインで、ヴェネト州の東部と一部フリウリ・ヴェネツィア ジュリア州の特定エリアでつくられます。2009年のDOCに認定されグレーラ種主体(85%以上)と、最大15%までのビアンチェッタ、ヴェルディゾ、ペレラ、グレラ・ルンガといった土着品種やシャルドネ、ピノ・ネロ(ピノ・ノワール)をはじめとしたピノ系品種をブレンドすることが認められています。軽やかでフルーティな味わいが特長のスパークリングワインで、2003年に本数でシャンパンを抜き、2020年には5億本を突破、直近20年でなんと20倍にも成長しています。最上級のDOCGに選ばれているエリアが2つあります。コネリアーノ ヴァルドッビアーデネ プロセッコ、アゾーロ プロセッコです。ミオネットは1887年創業の老舗で、プロセッコの心臓部分であるヴァルドッビアーデネにワイナリーを構えています。ミオネット ヴァルドッビアーデネ DOCG プロセッコ スペリオーレ エクストラドライはグレーラ種100%で醸されます。青りんごや爽やかな柑橘、アカシアの花のような爽やかなアロマが感じられ、繊細な香りがグラスから立ち昇ります。きめ細かい泡を伴って口の中に広がる。優しい味わいのプロセッコです。
花かつおの揚げ豆腐と合わせると、花かつおの香ばしい香りとミオネットの爽やかな香りとが良くマッチしています。
「鰹節を衣にして揚げると、こんなにパリパリになるんですね」
「揚げ出し豆腐の味わいを、出汁の鰹節と衣の鰹節のダブルで囃し立てるので、めっちゃ鰹風味になりますね」
「プロセッコと合わせると、その鰹節の風味が、素直に引き出されますね」
「シャルマ法ですが、酵母の自己分解の風味があるから、アミノ酸の旨みで、鰹の旨味が強化されるのでしょうね」
「滑らかな豆腐の豆感が、弾ける泡で強調されています」
「ミオネットがブリュットじゃなくて、少し甘さを感じますよね。そこが、出汁のほのかな甘さと調和しています」
「甘さの同一性原理・・・・ワインと食のマリアージュの大原則ですね」
皆様も、揚げ出し豆腐をする時に、花かつおの衣を思い出してください。そしてミオネットとの素晴らしいマリアージュを是非、体感くださいませ。