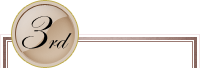今回の料理はタンシチューです。シチューが料理として確立したのは、16世紀後半のフランスである、というのが定説です。イタリアのメディチ家のカテリーナがアンリ2世に嫁いだのが16世紀の前半です。その時に帯同したイタリアの料理人たちによって、フランスの料理のレベルが飛躍的に向上したといわれていますから、それから、ほんの暫く経った時なのですね。シチューする=長く煮込む事で、肉の堅い部位も柔らかく食べ易くなり、また、味わいも格段に上がります。今回は鈴木薫先生にワインスクエア流の、ワインに良く合うタンシチューのレシピを考えて頂きました。牛タンは、塊で購入し、2㎝の厚さに切ります。塩、こしょう少々、小麦粉をまぶして、しっかりと焼き色を付けて、タンは一旦取り出します。その鍋で、玉ねぎ、にんにく、セロリ、にんじんをしっかり炒め、トマトペーストをいれ小麦粉を加えてさらに炒めます。牛タンを戻し、赤ワインをいれて、これからが本番の煮込みなのですが、赤ワインを2人前で400ml!!たっぷりと入れるのがポイントです。ふたをして弱火で2時間ほど煮ます。牛タンが柔らかくなったら再び取り出して野菜を潰しながら濾すのですが、イタリア風に濾さずに形の残ったままの野菜を添えるのでも大丈夫です。いずれにしても煮汁を弱火にかけて、とろりとするまで煮詰めて、肉に絡むようにするのがポイントです。
この、タンシチューに、テイスティングメンバーが選んだイチオシワインは、シャトー ラグランジュでした。シャトー ラグランジュはボルドー地方メドック地区サンジュリアン村にある格付け3級のシャトーです。17世紀頃のワイン地図には既に“ ラ・グランジュ”という名で記載されているほど古くからあるシャトーです。1983年の12月にサントリーが経営を引き継ぎました。総責任者に、ボルドー大学のワイン醸造の権威エミール ペイノー氏の門下生であるマルセル・デュカス氏、日本人のトップとして鈴田健二という布陣で、畑から醸造施設、城館や庭園に至るまで徹底的に改革しました。前のオーナー時代には半分を超えていたメルロ比率を下げ、特に良い区画を選んでカベルネ・ソーヴィニョンに植え替えました。補助品種には、シャトー レオヴィル ラス カーズのドゥロン氏のアドバイスもあってプティ・ヴェルドを植えました。現在の栽培比率はカベルネ・ソーヴィニヨン67% メルロ28% プティ・ヴェルド5%です。2019年の出来については、シャトー ラグランジュだよりに詳しく掲載されていますが、今までで最高と評価された2016年ヴィンテージをも上回る素晴らしい出来のようです。どんなワインになっているのか期待で胸が膨らみます。マリアージュ実験には今までで最高の出来と評価された2016年ヴィンテージを使いました。グラスに注ぐと黒々と濃い色です。ダークチェリーレッドで、縁に紫色の色合いを帯びています。ブラックチェリーやカシスを思わせる香りと、甘草やブラックペッパーなどをイメージさせるスパイシーな香りがあります。口に含むと力強く凝縮した果実味があります。タンニンの量は極めて多いのですが、きめ細かくシルキーなので気になりません。
タンシチューをいただきます。分厚いタンを切り、ソースを絡めます。濃厚で力強いタンの旨味が口一杯に広がります。そこにラグランジュを一口飲もうとグラスを鼻に近づけるだけで、タンの香りとラグランジュの香りとがマリアージュするのがわかります。
「香りだけでもマリアージュしていますね」
「単体でラグランジュを香ると、まだ若いので、果物の生き生きとした香りが主体に感じられるのですが、タンシチューの香りが近づくと、動物的なニュアンスやスパイシーなタッチが、ぐっと前面にひきだされます。それだけで、『もう絶対、美味しいやつやん!』って感じますよね」
「タンシチューって改めて、美味しいんだなぁって実感しました」
「分厚い、タンを噛めば噛むほど、タンの味わいが滲みだしてきて、ラグランジュの旨味とがっちりと合うのがわかります」
「煮込みって、時間と手間がかかりますが、ご馳走の極致なんですね」
皆様も、タンシチューを作ってみませんか?スーパーなどでは、なかなかブロックの牛タンは取り扱っていないかもしれませんが、ネットだと1kg4,000円でアメリカ産やオーストラリア産の牛タンが販売されています。是非一度タンシチューに挑戦してみてください。そして、シャトー ラグランジュとの抜群の相性をお楽しみくださいませ。