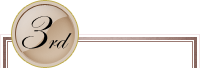今回の料理はラムチョップとラタトゥイユです。ラタトゥイユは、南仏プロヴァンス地方のニースの郷土料理です。ディズニー映画の「レミーのおいしいレストラン」の原題がRatatouilleなんですよ。語源は、オック語の「ratatolha」ラタトゥーリャだと言われています。「ratatolha」は「野菜の炒め煮」で、炒め続けてつくる料理の意味だそうです。現代のフランス語でもラタトゥイユの後半部分の「touille」は「かき回す」を意味します。イギリスの大手新聞であるガーディアン(The Guardian)の、飲食部門記者のFelicity Cloakeによると、ラタトゥイユが初めて書物に記載されるのは1877年だそうです。やはり、「かき回す」料理だったようですが、初期は、お肉の煮込み料理で、ズッキーニ、ピーマンやトマトなどの野菜中心の煮込みになったのは第一次世界大戦以降くらいの時期のようです。ヨーロッパにはラタトゥイユに似た料理がいくつかあります。イタリアのカポナータやスペインのピストが代表格でしょうかね。カポナータはシチリアの郷土料理が発祥で、野菜の中心はナスです。ラタトゥイユと決定的な違いは、味わいが甘酸っぱい事です。スペインのピストはラタトゥイユよりもトマト少なめで、パプリカパウダーでしっかりピーマン系の香りを効かせるのが特徴です。今日は子羊のローストが相棒です。フランスで子羊の名産地というとノルマンディのモンサンミッシェルやピレネー、ボルドーのポーイヤックなどが有名ですが、プロヴァンスも有力な産地です。日本にもプロヴァンスのIGP認定を受けているアニョー・ド・システロンなどが輸入されているようです。
鍋にオリーブオイル、赤唐辛子、にんにくを入れたもので、ラムに焼き色をつけていきます。焼き色が付いたら、一旦、ラムは取り出し、その鍋でラタトゥイユを作ります。野菜から出る水分で、じっくり煮込んで、全体がしんなりしたら白ワインを加え、更に汁気が少なくなるまで煮込みます。最後にラムを入れ、温まったら出来上がりです。
さて、このラムチョップとラタトゥイユにテイスティングメンバーが選んだイチオシワインはシャトー ラグランジュが醸すオー・メドック ド ラグランジュでした。オー・メドック地区のサン・ローランやキュサックに新たに購入した畑でつくったぶどうを使い、ラグランジュのスタッフが、ラグランジュと同じフィロソフィーで丹精込めてつくりました。シャトー ラグランジュの歴史は古く、17世紀初頭には、すでに王室砲兵隊輜重隊長のジャン・ド・ヴィヴィアンの所有だったことが古文書に記されています。「ラ グランジュ」というのは「自立した小さな集落」の意味で、ボルドーには、サンジュリアンだけでなく、ポムロールやペサック・レオニャンにも在る名前なのです。シャトー ラグランジュは19世紀には、ルイ・フィリップ朝で内務大臣などを歴任したデュシャテル伯爵が所有者となり、当時のボルドーでは指折りの規模の醸造設備が整えられました。品質向上のために、畑の土の中に素焼きの土管を埋め込み、水はけを良くする設備も伯爵が考案したものです。そして、1855年、パリ万博の時に制定されたボルドー メドックの公式な格付けで「グランクリュ第3級」として格付けされました。しかし、シャトーの名声にかげりが見られる時期がきます。1925年にオーナーになったスペイン系のセンドーヤ家が、1929年の世界大恐慌、続く戦争で経済的に没落してしまったのです。畑は切り売りされ、シャトーは荒廃し、当然ワインの品質も低下していきました。そんな中1983年、日本のサントリーが経営に参画しました。欧米以外の企業がシャトー経営者になったのは、この時が初めてでした。ボルドーの新聞に「眼鏡を掛けて、首からカメラを下げた日本人がシャトーを踏みにじっている」挿絵が掲載されたりもしました。そう言った反感とは関係なく、ラグランジュの「復活のステージ」は着々と進められました。ボルドー大学のエミール ペイノー博士を顧問に迎え、総責任者はペイノー博士の門下生であるマルセル デュカス、副会長にはサントリーの鈴田健二があたりました。荒れ果てた畑は、大規模に植えなおしました。センドーヤ家時代にはメルロの比率が高かったものを、カベルネ・ソーヴィニヨン中心に改植したのです。醸造設備も一新し、シャトーのシンボルといえる城館や庭園の修復まで徹底的な大改革に取り組みました。そうして、ようやくグランクリュ シャトーとしての名声を復活させることができたのです。「シャトー物」と呼ばれるファーストラベルの品質基準に見合うぶどうは、基本的に樹齢が20年以上の樹から収穫します。サントリーが経営参画した1983年以降に、新たに植えた苗木が、21世紀に入って、ラグランジュの主力になってきました。前副会長の鈴田健二の後継として2004年、椎名敬一が副会長に着任。「復活」に続く次の段階を「創造のステージ」と位置づけ、さらなる品質向上を目指しています。更に2008年ヴィンテージより始まった第2期の大型投資で、区画毎に仕込みが出来るように小型タンクに入れ替えました。総責任者に若きマティウ ボルドを起用、ラグランジュ生え抜きのベンジャマンとタッグを組んで品質向上に取り組んでいます。
グラスに注ぐと、濃いめのルビー色で、紫を少し含んでいます。香り華やかで、ブルーベリーやさくらんぼを思わせるピュアな果実香とスパイシーさがあります。シャトー ラグランジュの系譜らしいエレガントなワインに仕上がっています。ラムチョップとラタトゥイユと合わせると、子羊の旨みが、ぐっと前に出てくるのが判ります。
「メドックのワインと子羊は、やはり鉄板の組み合わせですね」
「まさに、本質的な相性と言うんですかね、奥深いところでがっちり握手しているようです」
「ラタトゥイユとも馴染んでいます」
「特に、パプリカの風味やトマトのニュアンスとカベルネ・ソーヴィニョンの香りとがマリアージュしています」
「子羊だけ、ドン!だとこの季節にはちょっと重いかなぁ、と思ったのですが、このアレンジは軽やかさがあって、丁度良い感じです」
夏野菜の美味しい季節です。日本ではズッキーニやトマトなどは、年間を通して、市場にありますが、路地物の味わい深さは格別です。是非ラムチョップとラタトゥイユに挑戦してみてください。そして、オー・メドック ド ラグランジュとの素晴らしいマリアージュをお楽しみください。