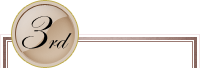今回の料理はラムチョップ ハーブグリルです。ラム=子羊はフランス料理では使用される肉の中で、最高位にランクされます。日本人にとっての、最上級の肉は、牛肉でしょうかね。イメージとしては黒毛和牛で、松坂牛や神戸牛のようなブランド牛の、それもA-5ランクのものでしょうか・・・・一方、ヒツジのほうは、日本人には、そんなに高級なイメージは、まだ余り無いようです。一時期羊肉を専門的に扱う店が増えたのですが、最近では一巡した感じもあります。ヒツジは鯨偶蹄目ウシ科ヤギ亜科ヒツジ属で、ヤギとならんで、肉や乳を目的にした牧畜動物としては最古である、と言われています。紀元前7000-6000年ごろの古代メソポタミアで家畜として飼われていたようで、野生のヒツジとは明らかに違う骨が大量に見つかっています。日本では、最初のヒツジの記録があるのは、日本書紀で、推古天皇に百済から2頭献上されました。今から1200年近く前の820年の出来事です。以降何度か、プレゼントで日本にやってきた形跡はあるのですが、増えたり、定着した、という記録はありません。19世紀に入り、長崎の浦上で飼育に挑戦したようですが、それも失敗しました。その後、幕府が、現在の文京区の小石川薬草園で飼育し、一時は300頭にまで繁殖に成功し、羅紗を織って将軍に献上もしましたが、何度かあった江戸の大火で継続する事が出来なかったようです。明治2年には、メリノ種も導入されました。メリノ種は15世紀末のスペインが、羊毛王国になる原動力になった、当時としては、考えられないくらい高品質の羊毛がとれるヒツジです。当然、門外不出で、スペインから生きているメリノ種を持ち出した者は、理由の如何を問わず死罪だったそうです。明治8年には現在の成田空港のすぐ傍の印旛郡に大規模な下総御料牧場を設置しましたが、高温多湿に苦しみました。北海道への導入は、下総御料牧場と、ほぼ同じ時期です。みなさんは札幌市南区の真駒内公園にある「エドウィン・ダン記念館」をご存知でしょうか?エドウィン・ダンは北海道の畜産の父と言われる方で、まだ、若干24歳の時に、ふるさとオハイオからヒツジと牛あわせて300頭を引き連れて日本にやってきました。記念館にはダンの銅像もあり、その銅像のダンは子羊を肩に担いでいるのです。このときのヒツジもメリノ種で主たる目的は羊毛を取る為でした。そして、紆余曲折はありましたが1957年には、日本で95万頭も飼育され、うち70万頭近くは、北海道で飼育されていました。良い羊毛が取れなくなったヒツジは当然、食用になるのですが、若いラムと違い成羊であるマトンの肉には独特の匂いがあります。それを美味しく食べる為に編み出したのが、漬けダレに工夫を凝らしたジンギスカンだったのです。いろいろ調べている中で古いデータを見つけました。農林水産省「畜産統計」(農林水産省統計速報)の1980年代のものです。そのデータを見ると1957年の飼育頭数95万頭に対して、飼育農家数はなんと64万戸、1戸あたりわずか1.5頭という小規模飼育だったのです。農家が自分で育てた羊から糸を紡ぎ、手袋やセーターなどを作る「ホームスパン」が実践されていたのでしょうね。その後、徐々に、羊毛のための白くて、もこもこした羊は減り、代わりに食べて美味しい品種が多く育てられるようになりました。ほっそりとした体つきで、顔と足が黒い、あのサフォーク種です。現在、北海道の各地で育てられており、特に海岸近くで育てられたものは、フランスの、有名なアニョー ド プレ サレと間違えるくらい美味しいものが出来ています。
今回は日本産ではなくオーストラリア産のラムを使ってラムチョップ ハーブグリルを作りました。ラムは切り分けられているものではなく、塊のほうが豪華に見えます。塩、こしょう、にんにくをすり込み、ハーブとオリーブオイルを一緒にポリ袋のなかにいれ、しばらく休ませませてから、オーブンで30分ほど焼けば出来上がりです。見た目の豪華さの割には、手間そのものは、さほどかかりません。
さて、ラムチョップ ハーブグリルに、テイスティングメンバーが選んだイチオシワインはシャトー ラグランジュでした。シャトー ラグランジュは1983年にサントリーが購入したボルドーのメドック地区サンジュリアン村のシャトーです。1855年のパリ万博の時に行われたメドック公式格付で3級にランクされました。買収当時の日本はエコノミックアニマルと蔑まれていた一面があり、フランス国民の「自国の象徴ともいえるボルドーの格付シャトーを日本人に買われてしまった」という反発感情はかなりのものがありました。当時のアキテーヌ地方の新聞の挿絵に、眼鏡をかけて、首にカメラをぶら下げたチビの男がシャトーを踏みにじっている絵が掲載されたほどです。ラグランジュの歴史は古く、最も古い文書上の記載は1631年の"モンテイユの高貴な館 ラグランジュ"というものです。先ほどのメドック公式格付に先立って行われたトーマス ジェファーソンの格付けでも第3級に格付けされています。サントリーの買収直前には、前のオーナーであるスペイン人のセンドーヤ家が、経済状況の悪化のあおりを受け、収量は減り品質・評価も低下し、食いつなぐ為に周辺の畑から切り売りしている状態でした。当時のラグランジュの窮状を心配したサンジュリアンの他のシャトーの後押しもあって、1983年12月にサントリーが取得する事が出来ました。ぶどう畑の半分が放棄され荒れ地となっていたのですが、ラッキーな事に、ポテンシャルの高い中心部の畑は切り売りされずに残っていたのです。総責任者にはボルドー大学のペイノー教授の門下生であるマルセル・デュカス、副会長には鈴田健二が就任し、畑から醸造施設、城館や庭園に至るまで徹底的な改革に取り組みました。まず最初に行ったのは、それまで多く栽培されていたメルロを抜き、土壌改良のために地下1mくらいのところに素焼きの土管を埋めていく作業でした。その作業中に発見されたのが何百年前のか判らない素焼きの土管です。その当時から土壌改良に取り組んでいた証です。良い区画にはカベルネ・ソーヴィニヨンを植え、補助品種にレオヴィル ラス カーズのドロン氏のアドバイスもあってプティ・ヴェルドを植えました。土壌は主に、なだらかな二つの丘陵に広がるギュンツ氷河期の砂礫質土壌です。石灰質粘土層の基盤の上に、氷河期に堆積した水はけの良い砂礫土壌が堆積しており、一部には粘土質や砂もあります。栽培面積はメドック格付シャトーでは最も広い118haです。現在では椎名敬一副会長と、マティウ・ボルドの新しい体制のもと、『復活』から『創造』の第二ステージへ歩みを進めています。現在のラグランジュは、畑においては「収穫はぎりぎりまで待つ」「収量は従来以上に抑制する」そして「自然な栽培(リュット・レゾネや有機栽培)に取り組む」という事を実践しています。また、区画も更に細分化し、きめ細かく、それぞれの個性を発揮できるようにしました。仕込みにおいては、2008年より小型タンクへ切り替えて小ロットでの醸造が可能になりました。2009年より光学式選果台による更なる選果の徹底を行っています。そうした地道な取り組みが功を奏し、徐々に評価も高まっているのです。
マリアージュ実験に使ったヴィンテージ2014はカベルネ・ソーヴィニョン76%、メルロ18%、プティ・ヴェルド6%で醸されています。グラスに注ぐと、濃いめのダークチェリーレッドです。まだ紫が多く含まれています。香りは黒いニュアンスのベリー、カシスやブラックチェリーのイメージです。口に含むとフルボディで大きな構造、リッチなタンニンで非常にキメが細かいのが判ります。
ラムチョップ ハーブグリルと合わせると、シャトー ラグランジュのもつフレッシュハーブのニュアンスと子羊の香りとが自然にマリアージュしています。
「うん、納得の味わいですね」
「定番の、鉄板の強さですかね・・・・・・・。なんなんでしょうね、羊が持っている個性的な香りと、ラグランジュのカベルネ的な香りとが、自然に溶け合っています」
「こういうのを、本質的な相性と言うんでしょうかね、まるで、ぴたっと鍵穴に刺さった鍵のような、がっちりと手を握りあった印象です」
「もともとの子羊だけでも、ハーブ、スパイスのトーンがあるところに、ハーブでマリネしてありますから、更に生き生きとした香りが強まっています。それとラグランジュとが良く合っているんですよ」
「子羊の脂は、肉よりもクセの要素が凝縮した感じです。このクセをいっぱい持った動物性脂肪と、ラグランジュの、まだ若いタンニンとが出会って甘さに転換して別の美味しさになっています。ちょっと感動ですね」
ボルドーの鉄板のご馳走とは何か!を心底納得できるシャトー ラグランジュとラムチョップハーブグリルの相性を是非お確かめくださいませ。