- No.sfa0059(2024/3/27)
-
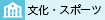
第55回(2023年度)サントリー音楽賞は近藤 譲 氏に決定
 |
|
©Jörgen Axelvall |
公益財団法人サントリー芸術財団(代表理事・堤 剛、鳥井信吾)は、わが国の洋楽の発展にもっとも顕著な業績をあげた個人または団体に贈る「サントリー音楽賞」の第55回(2023年度)受賞者を近藤 譲(こんどう じょう)氏に決定しました。贈賞式は2024年5月13日(月)に執り行います。
●選考経過
2024年1月8日(月・祝)国際文化会館において第一次選考を行い、候補者を選定した。引き続き2月29日(木)国際文化会館において最終選考会を開催。慎重な審議の結果、第55回(2023年度)サントリー音楽賞受賞者に近藤 譲氏が選定され、3月25日(月)の理事会において正式に決定された。
●賞金 700万円
●選考委員は下記の7氏
伊東信宏、片山杜秀、白石美雪、長木誠司、沼野雄司、舩木篤也、松平あかね(敬称略・50音順)
(ご参考)サントリー音楽賞および受賞記念コンサートについてはこちら
<贈賞理由>
近藤譲はちょうど半世紀前の「線の音楽」シリーズ以来、その創作、著作を通じて日本の聴衆、音楽家を深いレベルで啓発し続けてきた。近藤の作品は、声高に激情を叫ぶようなものとは異なり、いつも静かに、しかしくっきりとした輪郭を示すもので、その影響は年月を超えて、今一層光を放つようになっている。
2023年度の「コンポージアム」(5月23―28日、東京オペラシティ)は、近藤の人と作品に焦点をあてたもので、ドキュメンタリー映画の上映とトーク、世界初演2曲を含む管弦楽の演奏会(そこには70年代の作品から最新作までが並んだ)、そして武満徹作曲賞の審査、さらには同時期に開催された作曲のマスタークラスや関連公演も含めてこの作曲家の現在を一望できる機会となった。
一つの音を置き、それを繰り返し聴くことによって次の音を見出し、さらにそれらの音を繰り返し聴くことによって第三の音を置く、といった近藤が繰り返し述べてきた作曲法は、かつて様々な作曲技法がもてはやされた時代には素朴すぎるように見えたし、その作品自体はかえって謎めいて聞こえたのだが、パンデミックや戦争によって人間(と人間集団)の孤立が深まり、さらにAIによる芸術の侵食が現実のものとなった今、近藤の音楽と言葉は、我々に深い覚醒が必要なことを告げているように思われる。
CD『近藤譲室内楽作品選集「昼と夜」』も含めて、前述のコンポージアムの諸成果を考えると、今年はこの世界的に見ても稀有な、知的で誠実な活動を続けてきた作曲家を顕彰する絶好のチャンスである。ここにサントリー音楽賞を贈るものである。
(伊東信宏委員)
<略歴>
近藤 譲(こんどう じょう) 作曲
1947年10月28日東京生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。1977~78年ロックフェラー3世財団フェローとしてニューヨークに滞在。1979年カナダ・カウンシルの招きでブリティッシュ・コロンビア州ヴィクトリア大学において客員講師を務める。1986年ブリティッシュ・カウンシル・シニア・フェローとしてロンドンに滞在。1987年米国ハートフォードのハート音楽大学コンポーザー・イン・レジデンス。同年及び2000年英国ダーティントン国際サマースクールで講師を、2015年米国ロチェスター大学イーストマン音楽院において特別客員教授を務めた。これまでに、ハーヴァード大学、ニューイングランド音楽院、エディンバラ大学、ヨーク大学、ケルン大学、ハンブルク音楽大学、アムステルダム音楽院等、欧米の多くの大学で自作についての講演を行っている。国内においては、エリザベト音楽大学教授、お茶の水女子大学・大学院教授として、また、東京藝術大学でも長年教鞭をとり、現在、昭和音楽大学教授、お茶の水女子大学名誉教授。
1980年には現代音楽アンサンブル「ムジカ・プラクティカ」を結成し活動、1991年の解散まで音楽監督を務めた。
国内外の優れた演奏家や演奏団体、音楽機関から委嘱を受け、独奏曲から室内楽、管弦楽、声楽曲、オペラ、そして電子音楽作品まで、広範にわたる作品を発表。180曲近くにのぼる作品のほとんどが英国のヨーク大学出版(UYMP)から、そして一部がニューヨークのピータース社から出版されている。また、多くの作品の録音が、ALM、フォンテック、ドイツ・グラモフォン、HatHut(スイス)、Wergo(ドイツ)等のレーベルからリリースされている。
ロンドン・シンフォニエッタ(英国)、バーミンガム・コンテンポラリー・ミュージック・グループ(英国)、アイブズ・アンサンブル(オランダ)、ニュー・アンサンブル(オランダ)、アンサンブル・ルシェルシュ(ドイツ)、アンサンブル・ラール・プール・ラール(ドイツ)、ボッツィーニ弦楽四重奏団(カナダ)、アンサンブル・ノマド(日本)、オリヴァー・ナッセン、ポール・ズコフスキー、井上郷子など優れた演奏家たちが、近藤作品を好んで繰り返し演奏している他、「パリの秋(フランス)」「アルメイダ国際音楽祭(英国)」「フィレンツェの5月(イタリア)」「ハダースフィールド国際音楽祭(英国)」「タングルウッド音楽祭(米国)」を始めとして多くの国際音楽祭において特集が組まれている。
2023年2月には、ロンドンのRoyal College of Musicが近藤譲の75歳を祝うコンサートを開催した。
国内でも、サントリー音楽財団(現・サントリー芸術財団)主催によるオーケストラ作品個展(2004年)、近藤の70歳を祝う有志による室内楽作品個展「近藤譲七十歳の径路」(2017年)、東京オペラシティ文化財団主催「コンポージアム」のオーケストラ作品個展「近藤譲の音楽」(2023年)、同音楽祭の関連公演の室内楽作品個展、合唱作品個展などが開催されている。
毎年5日連続で放送されているNHK・FMラジオ番組「ベスト・オブ・クラシック~コンテンポラリーを聴く」では、長年、選曲とパーソナリティーを担当している。
作曲と美学に関する執筆活動も活発に行っており、『線の音楽』『音楽の種子』『耳の思考』『〈音楽〉という謎』『音を投げる-作曲思想の射程』『聴く人』などがあり、『ものがたり西洋音楽史』では毎日出版文化賞特別賞(2020年)を受賞。翻訳においても、J.ケージ著『音楽の零度』、D.ヒューズ著『ヨーロッパ音楽の歴史』(共訳)、M.E.ボンズ著『「聴くこと」の革命-ベートーヴェン時代の耳は「交響曲」をどう聴いたか』(共訳)等の著作がある。
これまでに、日本音楽コンクール作曲部門、ガウデアムス国際作曲コンクール(オランダ)、国際現代音楽協会国際音楽祭(香港)、芥川作曲賞(現・芥川也寸志サントリー作曲賞)、ハダースフィールド国際作曲コンクール(英国)、ソウル国際作曲コンクール(韓国)、日本現代音楽協会作曲新人賞、武満徹作曲賞(2023年)等の作曲コンクールの審査員、柴田南雄音楽評論賞審査委員、京都賞音楽部門選考委員なども務めている。現在、日本現代音楽協会理事長。
1991年尾高賞(オーケストラ作品「林にて」)、2005年中島健蔵音楽賞、2018年3月平成29年度(第68回)芸術選奨文部科学大臣賞(音楽部門)を受賞。2012年にはアメリカ芸術・文学アカデミー(American Academy of Arts and Letters)外国人名誉会員(終身)に選出された。
出版
UYMP(University of York Music Press) www.uymp.co.uk
Edition Peters www.edition-peters.com
音楽之友社 www.ongakunotomo.co.jp
公式サイト
https://jokondo.b-sheet.jp/
以上
〔ニュースリリースに関するお問い合わせ・広報用画像お申し込み〕
公益財団法人サントリー芸術財団 音楽事業部
ongakujigyo@suntory.co.jp
TEL:03-3582-1355(平日10:00~17:00)
FAX:03-3582-1350







