- (2023/9/13)
-
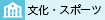
第45回 サントリー地域文化賞 選評・受賞者活動概要
選評
今年の候補には地域の特性を生かした魅力的な活動が多かったが、最終的に、受賞がなんらかの追い風になるようにとの願いも込めて、以下の5団体に決定した。
「若狭小浜ちりとて落語の会」は、小浜で育った少女が落語家を目指すという連続テレビ小説「ちりとてちん」の放送をきっかけに、「全国女性落語大会」の開催など地元への落語文化の定着をはかってきた。明治期の芝居小屋「旭座」の移築復原や、上方落語協会との連携協力協定締結など、さまざまな動きを呼び起こしてきたのも、本会の活動への共感あればこそ。ドラマの舞台を一過性の観光地にするのではなく、新しい文化が根づくよう地道な活動を続けてきた、その姿勢にエールを送りたい。
「伊勢型紙技術保存会」のある鈴鹿市では、江戸時代、小紋などの模様を染める型紙の主要産地として独自の技術を発展させてきた。後継者育成のための伝承講座に一般公募を取り入れて20年、今年初めて一人前とみなされる「会員」7名が生まれた。会員のほとんどが男性という中で、新会員6名が女性であることも大きな変化。着物需要の激減という逆風もあるが、4種の彫りの技術の深さ、型紙自体の美しさは心に残る。ぜひこれを機に業界全体で伊勢型紙の新しい可能性も拓いていってほしい。
「和歌祭保存会」は、1,000人40種以上の芸能行列で構成される、紀州徳川家お膝元の祭りを、現代に甦らせようという壮大な試みに挑んでいる。参加者を集めるだけでも大変だし、失われた芸能を復活させること自体にも大きな困難が伴うが、復活させようとすることで地域の魅力が再発見され、新たなつながりが生まれることも多いだろう。今後、広く持続的な人的、財政的な協力体制を探りながら、和歌山市全体の祭として、ますます活力あるものになっていくことを願いたい。
「広島文学資料保全の会」は、40年近くにわたって、広島市の文学、特に、被爆地として原爆文学の資料の収集・保全・出版などにつとめてきた。本会がなければ散逸、消滅、忘れ去られていたものも少なくなかったろう。恒久的な保存場所もない中で、いわば手弁当でこうした資料を守り続け、次の時代につなげようとしてきた姿勢には頭が下がる。文学には、記録とはまた別の力がある。人類の未来への貢献として、こうした活動が実を結び、文学館の設立につながるよう願ってやまない。
「キッズミュージカルTOSU」では、年に一度の本公演のほかに、地元依頼のミニ公演を年20回ほどこなし、所属する子供たちも一度は主役級の役につくという。160以上に及ぶ地元企業から広く浅い寄付をつのり、コロナ禍でも揺るがず継続できる体制を築いてきた。事務局の大変な努力あってのことと思うが、こうした運営体制作り自体が地域文化の礎であり、範でもある。今後も地元に支えられ求められる活動として、ぜひ子供たちの笑顔を育み続けていってほしい。
沖本 幸子(東京大学教授)評
| 福井県小浜市 若狭小浜ちりとて落語の会 |
◎受賞理由
若狭地域の各地で寄席や落語会、子ども向け落語体験教室を開催するほか、16年にわたって開催される全国女性落語大会を支え続けるなど、地域における落語文化の浸透に精力的に取り組む姿勢が高く評価された。
◎活動概要
福井県の南西部、若狭地域のほぼ中央に位置する小浜市は、古くから日本海側の要港として栄えてきた。北陸に位置しながらも、風俗、習慣、言語などは近畿地方とのつながりが深く、地域の住民にとっては昔から上方落語も身近な存在だった。「この地域に落語をもっと根付かせて、地域を盛り上げていきたい」という熱い思いを抱いた市民有志が「若狭小浜ちりとて落語の会」を立ち上げたのは2007年(当初の名前は「ちりとて落語の会」)。会の名前は、小浜市で育ったヒロインが落語家を目指す内容で大人気となったNHK朝の連続テレビ小説「ちりとてちん」にあやかった。
同会は現在、小浜市内にある芝居小屋「旭座」を拠点に活動を展開している。ここは、明治期に建てられた芝居小屋を小浜市が市指定文化財として移築復原したもので、今では地域の落語文化発信基地として広く市民から親しまれている。ここで催される寄席には、プロだけでなくアマチュアの落語家も高座に上がり、場内はいつも大きな笑いで包まれる。また「旭座」で行う寄席以外にも、若狭地域一円に出向いて小・中学校、公民館やお寺など様々な施設で地域住民が気軽に参加できる落語会を開催しており、これまでに開いた寄席や落語会は300回を超える。さらに、子ども向けの落語体験教室を催したり、地元高校生にボランティアを募ったりするなど、次世代の落語ファンを増やすための活動にも力を入れている。そんな精力的な取り組みは大阪にも伝わり、今では、大阪の上方落語協会に所属する落語家も「旭座」の高座に定期的に上がるようになった。
年間を通じて様々なイベントを開催している同会にとって、なかでも最も大きなイベントは「ちりとてちん杯全国女性落語大会」だ。会員らが大会実行委員会の中核として2008年から16年続くこの大会を支えている。この大会はプロ・アマ問わずに参加できる女性落語大会で、日本で最大の規模を誇るといわれる。毎年全国各地から磨き上げた自慢のネタを持った参加者が集まり、地域住民の中にも、開催を心待ちにしているファンがたくさんいるという。
代表を務める西村氏は「将来的に『小浜と言えば落語』といわれるようになるのが目標。その日が来るまで『旭座』を拠点に広く笑いを発信し続けたい」と話す。同会の笑顔の絶えない活動は、これからも広く親しまれ続けるだろう。
◎代表者および連絡先
|
〈代表〉 |
◎福井県内のこれまでの受賞者
坂井市 日本一短い手紙「一筆啓上賞」活動(1999年)
越前市 今立現代美術紙展実行委員会(1991年)
福井市 朝倉氏遺跡保存協会(1985年)
| 三重県鈴鹿市 伊勢型紙技術保存会 |
◎受賞理由
着物などの生地に模様を染めるために用いる「伊勢型紙」の技術の練磨と研究、次世代への伝承などに取り組む。公募した未経験者が受講する「伊勢型紙技術伝承講座」から新たに後継者が誕生していることも高く評価された。
◎活動概要
「伊勢型紙」とは着物などの生地に模様を染色するための工芸用具で、型地紙と呼ばれる特殊な紙に彫刻刀で精緻な模様を彫ったもの。この型紙を用いて生地に糊を置くと、染めたときに糊の部分が白く残り模様となる。江戸時代中期以降、現在の三重県鈴鹿市の白子・寺家地域で発展した伊勢型紙は、小紋やゆかた、手拭いなどを染めるために欠かせない用具として全国的に流通した。
布地に芸術的な模様をうつしだす伊勢型紙には、「突彫(つきぼり)」「錐彫(きりぼり)」「道具彫(どうぐぼり)」「縞彫(しまぼり)」の4つの彫刻技法と、染色の際に型紙を補強する「糸入れ」という技法があり、職人は一つの技法を生涯をかけて極める。
この技術を継承するため、1963年に鈴鹿市による「伝承者養成事業」がスタートし、職人による若手の指導が始まった。1991年、同事業を引き継いで「伊勢型紙技術保存会」が発足。1993年に国の重要無形文化財保持団体に認定された後も市が事務局を務めており、同会の「会員」と認定された者は伊勢型紙の「わざ」の保持者とされる。
会の発足当初は、修業中の業界関係者を対象に指導を行っていたが、着物離れが進み型紙の需要が減る中、受講者も減少したため、2003年からは公募した未経験者を対象に「伊勢型紙技術伝承講座」を開催するようになった。かつての職人は師匠が専門とする技法のみに接し、この講座でも受講生は自らの専門技法を選択するが、保存会の様々な活動を通して他の技法に自然と触れる機会があるため、伊勢型紙についてより包括的に知ることが出来る。講座は白子の型紙問屋だった古民家を活用した「伊勢型紙資料館」の一角で行われ、受講生は型紙を彫るための彫刻刀づくりから修業を始め、「研修生」、「研修者」、「伝承者」、「会員」と昇級してゆく。技術の習得に長い年月を要するため、新たな「会員」が生まれないことが長年の課題だったが、2023年に公募者から初めて7名(40~60代。男1名、女6名)の新会員が誕生し、会員はそれまでの12人(60~90代。男11名、女1名)から19名となった。
伊勢型紙は染色を支える裏方の道具であるが、鈴鹿市内の小学校では授業や課外学習で伊勢型紙を学ぶほか、彫刻体験をする機会も充実しており、郷土が誇る文化として市民に親しまれている。また近年の研究で、伊勢型紙の斬新なデザインが19世紀後半に海外の多くの画家や工芸家に影響を与えたことが明らかになり、伊勢型紙をインテリアや日用品などに活用する試みも進んでいる。こうした背景に加えて、伊勢型紙技術保存会に新たな会員が誕生したことで、伝統ある技術を継承しつつ伊勢型紙の世界をより広げる活動が展開されることが期待される。
◎代表者および連絡先
|
〈代表〉 |
◎三重県内のこれまでの受賞者
多気町 三重県立相可高等学校「調理クラブ」(2011年)
鳥羽市 島の旅社推進協議会(2010年)
松阪市 あいの会「松坂」(1989年)
志摩市 佐藤 忠勇氏(個人)(1981年)〈的矢湾での無菌カキ養殖〉
| 和歌山県和歌山市 和歌祭保存会 |
◎受賞理由
400年以上の伝統を誇る祭で披露される多様な芸能を復興させ、祭の歴史的・文化的価値を高めた。地元大学と協力した体制づくりなど、祭を活性化させ、永続させるための様々な取組みが高く評価された。
◎活動概要
和歌山県北部に位置する和歌浦は、万葉集にも詠われた風光明媚な地として知られる。紀州徳川家初代当主・徳川頼宣は、ここに父・家康を祀る東照宮を1621年に創建。翌1622年に和歌祭を創始した。祭では約1,000人もの民衆が神輿や山車を引き、40種目以上の芸能を披露しながら街中を練り歩く。それぞれの芸能は家臣団による「株」という組織が担い、明治以降も旧藩士らがその技芸を代々継承してきた。しかし徳川家というパトロンを失って以降資金面で苦慮することになり、太平洋戦争中、祭は完全に途絶えた。
1948年、和歌山市の商工会議所の尽力により商工祭の中で祭が再開されたが、パレード行進を中心とした内容で、道中での芸能披露の機会が減少。その後、費用などの問題もあって1984年を最後に祭は再度中断した。
こうした中、和歌浦の住民を中心に1985年に和歌祭保存会が結成された。当時10程度存続していた株の名簿を作成して株同士が連携できる体制を整え、1990年に祭を再開。1999年には保存会の若手有志が青年部(現在の実行委員会)を結成した。若手ら自身は祭の歴史や技芸について知らないことが多く、存続していた株の親方に教えを請いながらあらためて祭について学び直すと同時に、祭の活性化を目指して芸能の復興に取り組むことになった。
芸能の復興は、和歌山大学の協力を仰ぎつつ、地域住民が主体となって持続できる形を目指した。例えば、2010年「唐船(とうぶね)」という種目で歌われていた「御舟歌(おふなうた)」を復興した際は、今後の担い手を考慮して女性も一緒に歌える音程に変更したほか、担い手確保のために和歌浦地区でワークショップも開催した。
御舟歌復興の反響は大きく、他の株からも自分たちの技芸も復興させ歴史的価値を高めたいという相談が保存会に寄せられるようになり、2012年には「餅搗踊(もちつきおどり)」のお囃子が復興、2017年には和歌山大学の研究プロジェクトの一環として352年ぶりに「唐人(とうじん)」が復興した。唐人は当時日本に来た外国人を模した種目で、装束の考証から和歌山大学の留学生が関わった。その後も唐人の株は和歌山大学が継承し、学生が入れ変わっても毎年株を維持している。2021年にはさらに3種目が復興、この3種目の新たな株は地元企業や小学校の運動部が引き受け、祭の担い手の輪は着実に広がっている。
芸能の復興を通じて祭を活性化させた原動力は、祭を続けたいと願う地域の人たちの思いだ。祭の永続に向けて、先人たちの思いをつなぎ、地域内外の力を合わせる役割が、保存会にはますます期待されている。
◎代表者および連絡先
|
〈代表〉 |
◎和歌山県内のこれまでの受賞者
田辺市 南方熊楠顕彰会(2009年)
和歌山市 紀州 ふるさとの歌づくり(1990年)
和歌山市 ミュージカル劇団「ヤング・ゼネレーション」(1986年)
| 広島県広島市 広島文学資料保全の会 |
◎受賞理由
広島にゆかりの深い作家の文学資料を調査・収集し、「広島文学」としてその価値を高めてきた。散逸の危機にあった資料を地域の文化的財産として守り、その意義を国内外に伝える継続的な取組みが高く評価された。
◎活動概要
広島は戦前には鈴木三重吉、倉田百三などを輩出し、戦後は大田洋子、原民喜、栗原貞子、峠三吉といった作家たちが原子爆弾による惨禍と対峙しつつ、優れた文学を生み出してきた。「広島文学資料保全の会」は、こうした広島ゆかりの作家、特に被爆作家たちによる肉筆原稿、書簡類、所有していた書籍等の資料の調査・収集を行っている。
発足は1987年。広島市に文学館設立を求める市民運動として始まった。6千人の署名と文学資料2万点を集めたが願いは叶わず、資料は広島市立中央図書館に寄贈されることになった。市はこれを基に図書館内に「広島文学資料室」を設置。しかし図書館は博物館などの資料保管を目的とする施設とは機能が異なるため、専門の学芸員はおらず、恒温恒湿の収蔵庫もない。そのため本会は、図書館を一時的な「避難場所」と位置付けつつ、これ以上の散逸を防ぐべく、作家の遺族らが保有する資料を発掘・整理し、中央図書館等へ寄贈する橋渡し役を務めてきた。作家の遺族らと丁寧に関係を築いてきたことで、本会には厚い信頼が寄せられている。2009年には広島女学院大学の栗原貞子記念平和文庫開設に尽力。2022年には峠三吉の遺族が資料のより良い活用方法を検討し、全ての著作権管理を本会へ委譲した。
本会は、市民が「広島文学」と出会い、より深く知るための場づくりにも大きな役割を果たしている。広島文学に関する本の出版を行うほか、年に数回、文学資料展・シンポジウム・交流会・朗読会・演劇・文学散歩などのイベントを実施している。2002年から毎年8月15日に開催する「原爆・反戦詩を朗読する市民のつどい」では、文学作品と音楽を組み合わせたプログラムなど、様々な形で広島文学の魅力を紹介している。また平和記念公園にある峠三吉詩碑の前で行う朗読会や旧広島陸軍被服支廠(戦時中は軍服等の製造・貯蔵を担い、被爆直後は臨時救護所として使用された施設)で開催するトークイベントなど、広島の歴史を感じられる場所でのイベントも好評だ。
2015年からは広島市と共同でユネスコ「世界の記憶」への「広島の被爆作家による被災直後の資料」の登録に向けた申請活動を展開している。この活動を通して、広島に遺された文学資料は、人類が忘れてはならない歴史的文書であり記録であることを国内外に訴えるとともに、地域の文化的な財産であることをあらためて市民に伝えたいと考えている。
戦後70年以上を経た今だからこそ、その記憶を時代や地域を超えて人々の感性に訴える文学の力がますます見直されている。より多くの市民がその素晴らしさに触れるためのつなぎ役として、本会は広島の中核にいる。
◎代表者および連絡先
|
〈代表〉 |
◎広島県内のこれまでの受賞者
安芸高田市 ひろしま安芸高田 神楽の里づくり(2020年)
尾道市 因島水軍まつり実行委員会(2018年)
呉市 歴史と文化のガーデンアイランド 下蒲刈島(2015年)
廿日市市 説教源氏節人形芝居「眺楽座」(2004年)
広島市 トワ・エ・モア(1989年)
福山市 日本はきもの博物館(1982年)
| 佐賀県鳥栖市 キッズミュージカルTOSU |
◎受賞理由
約20年にわたり質の高い子どもミュージカルを運営。保護者・卒業生・地元企業をはじめとする地域住民が子どもたちの熱意を支え、地域に愛される存在として活動している点が高く評価された。
◎活動概要
佐賀県鳥栖市を拠点に活動するキッズミュージカルTOSUは、「ミュージカルという表現活動を通しての子どもの健全育成と地域からの質の高い文化の発信」を目的として、子どもたちによるミュージカルの公演を長年続けてきた。
同団体を立ち上げ、長年支えてきたのが鳥栖市出身の有馬治子氏だ。きっかけは2003年、「鳥栖市市制50周年記念事業」の一環として子どもミュージカルを企画し参加者を募ったところ、大勢の市民が参加した。迎えた2004年の公演は立ち見客が出るほどの大成功をおさめ、もともと一回限りの公演の予定だったが、観客の拍手と「またミュージカルをやりたい」という演者の声に後押しされ、継続を決めた。翌年「キッズミュージカルTOSU」を立ち上げて活動を開始し、以降は毎年1回の公演を欠かさず続けている。
現在は小学2年生から中学3年生までの31人の子どもたちが所属し、週2回の練習に励む。子どもたちは、演技や歌、ダンスなど各分野のプロによる厳しい指導を受けながら「大勢の人に夢と希望と感動を届けたい」という目標に向かって切磋琢磨しており、ほぼ全員が卒業までに一度は主役クラスの役を任されるという。主役を演じることで責任感が育まれ、その結果、自然と後輩の面倒を見るようになり、お互いに助け合う心が育っていくのだと有馬氏は話す。
また、ミュージカルの運営には保護者や卒業生の協力も欠かせない。子どもたちの舞台衣装は全て保護者の手づくりで、小道具の製作、本番のメイクや舞台進行、会場スタッフまで保護者が担当している。加えて、本公演当日には毎年30人ほどの卒業生も裏方として駆けつけるという。さらに、周年記念などの特別な公演には、子どもたちと共に卒業生も出演することもある。
そして、地域住民との繋がりの強さも、キッズミュージカルTOSUの特徴だ。2023年2月に開催された設立20周年記念公演では、地元企業を中心とした160社あまりの協賛企業と、50以上の賛助会員が寄付をよせ、公演を支えた。また、地域のお祭りや福祉施設、佐賀県や鳥栖市、商工会議所等のイベントからも頻繁に声がかかり、いまでは年20回ほど子どもたちが出演している。
こうして子どもたちと関係者、地域住民らが一体となってつくり上げる舞台は、時に「まるで宝塚のような舞台だ」と称賛されるほど。有馬氏は「うちの子どもたちは舞台に立つのが大好き。ミュージカルをやりたいと言う子がいる限り、活動を続けていきたい」と笑う。キッズミュージカルTOSUはこれからも、地域に笑顔を届ける存在として活動していくだろう。
◎代表者および連絡先
|
〈代表〉 |
◎佐賀県内のこれまでの受賞者
鹿島市 鹿島ガタリンピック(2017年)
有田町 玄海人クラブ(1999年)
佐賀市 地球市民の会(1988年)
多久市 多久古文書の村(1985年)
以上





















