- (2022/11/15)
-
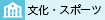
第44回 サントリー学芸賞 選評
鎌田 雄一郎(カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院准教授)
『雷神と心が読めるヘンなタネ ―― こどものためのゲーム理論』(河出書房新社)
サントリー学芸賞の政治・経済部門の受賞作品の中で、本書は挿絵が最も多い書として記録されることだろう。その意味で、歴代受賞作品の中でひときわ異彩を放っている。本書は、副題にもあるように、こどものためのゲーム理論の解説書という体裁をとりつつ、数学的なロジックに裏付けられたフィクション(作話)で描写したリアリティで全体が構成されている。本書は、挿絵が添えられた5つの物語が展開されている。経済学の中で1つの中心的な理論として数学的基礎を持ったゲーム理論という「学」と、それをフィクションで描写するという「芸」が見事に融合しており、サントリー学芸賞を授与するにふさわしい。
鎌田雄一郎氏は、カリフォルニア大学バークレー校准教授で、ゲーム理論とその応用を専門としている。農学部に在学中、経済学のゲーム理論に関する講義を履修して刺激を受けたことが契機となって大学院では経済学を志すようになったという。鎌田氏の研究業績は、若くして質量ともに素晴らしく、世界の経済学界でトップ5やそれに準ずるものと位置付けられる国際学術誌に多くの論文を掲載している。そのうちの1つに、小島武仁・東京大学大学院経済学研究科教授との共著論文で、2人の候補者が競う選挙で、有権者の政策に関する好みが左寄り、中庸、右寄りと分かれている中で、各候補者はどのような政策を掲げるかを分析したものがある。この種の古典的な理論では、両候補は票を奪い合うように中庸な政策に寄って行き、結局は似たような政策を掲げる、との結論が頑健に導かれる。ところが、鎌田氏らは、有権者の政策の好みがちょっとした差異でも看過できないと感じる状態であるとか、いくつかの条件が重なると、この理論に基づいても2人の候補者は、多く得票しようとして敢えて両極端の政策を掲げることになる、という結果を導いた。ゲーム理論を政治に応用した見事な分析だ。
鎌田氏は、既に邦文で『ゲーム理論入門の入門』(岩波新書)、『16歳からのはじめてのゲーム理論』(ダイヤモンド社)と2冊の書を世に出している。ただ、本受賞作品のように、挿絵付きの物語でゲーム理論の核心に迫るのは、『16歳からのはじめてのゲーム理論』に次いで2作目である。この1作目も、ゲーム理論に裏打ちされたストーリーに引きつけられたのだが、斬新さがゆえに評価に戸惑うところもあった。しかし、2作目となる本書では、鎌田氏が持つ理論家とストーリーテラーの双方の能力の高さが大いに証明され、確固たる地位を築いたと評せよう。
滝沢啓一という小学6年生の男子が本書の主人公である。題名にあるように、雷神が啓一少年の前に現れて、心が読めるヘンなタネを繰り出すという奇想天外な物語が展開される。1つ1つの物語の後には、雷神によるゲーム理論の解説が付いている。ゲーム理論の考え方を使って、「相手の立場に立つ」ことが自然にできるようになることを、本書の狙いとしている。ここにも、ゲーム理論の醍醐味を感じさせる。
優れた学術的な研究業績を積み重ねながら、読者を引きつける物語をも創造する。数学的な理論は現実に擬した「フィクション」ともいえ、学界で注目される新理論を構築する知的作業は、読者を魅了する物語の創作とも共通するものがあるのかもしれない。鎌田雄一郎氏のさらなる活躍を期待したい。
土居 丈朗(慶應義塾大学教授)評
今野 元(愛知県立大学外国語学部教授)
『ドイツ・ナショナリズム ―― 「普遍」対「固有」の二千年史』(中央公論新社)
今野元氏による『ドイツ・ナショナリズム』は、西洋的価値観という「普遍」と民族の伝統や文化に根ざした「固有」の間で苦悶してきたドイツ・ナショナリズムを、一貫した枠組みで分析したスケールの大きな歴史分析である。
ドイツはその国民形成の過程で優勢な西欧の「普遍」に晒され、軍事的にも文化的にも圧力を受け続けてきた歴史的背景がある。それに対抗するために自身の「固有」を積極的に発掘し、しばしばそれを過剰に拡張しようとする衝動を示してきた。しかし他方で、一旦「固有」の極端な拡張が挫折すると、今度は「普遍」よりも普遍的になることで自尊心を回復しようとする、逆説的なナショナリズムが高まるという力学が作用した。
もちろん「普遍」の圧力にどのように対応するのかという課題は、ドイツの過去に限られた問題ではない。これは自らの「普遍」を問いなおす必要のない特権的な帝国以外の国々、つまり日本も含む世界の多数派の国々で、大なり小なり知識人が直面してきた問題に他ならない。またこれが単なる過去の問題でないのも、冷戦後の時代が終わり、最終的に勝利したとまで考えられた欧米の「リベラル」な「普遍」の限界が表面化し、様々な「固有」が噴出している今日の時代状況を一瞥しただけでも明らかであろう。
このような大きな問題意識を正面から論じた本書だが、著者は記述の随所に人物像やエピソードを織りこみ、難解な論争や複雑な出来事の展開を活き活きとした躍動感に富む読み物にすることに成功している。そうした叙述の背後に、膨大な量のドイツ語文献資料を緻密に読み込んだ、著者の正統的な研究の蓄積が垣間見える。その上でマイネッケ、ウェーバー、ハーバーマスといった、往々にしてその解釈論にとどまりがちな知的権威を俎上に乗せて、臆することなく批判的に分析し、正面から評価を加える著者の颯爽たる知的姿勢に、胸をすくような爽快感を感じる。
他方で、「エステルライヒ」(オーストリア)、「シュヴァイツ」(スイス)、「ベートホーフェン」(ベートーベン)、「連合国」(国際連合)といった表記は、単なる趣味ではなく明確な根拠に基づくものではあるが、戸惑う読者もいるだろう。知的挑戦が非生産的な論争に迷い込まなければよいがという微かな気がかりは、年寄りの老婆心にすぎないと考えよう。
すでに『マックス・ヴェーバー』(東京大学出版会)や『教皇ベネディクトゥス一六世』(同)などの浩瀚(こうかん)な研究書で、学識には定評のある著者が、幅広い読者を対象にコンパクトな形で意義深い知的挑戦を世に問うたことを称え、今後のさらなる発展を一読者として期待したい。
田所 昌幸(国際大学特任教授)評
邵 丹(東京外国語大学世界言語社会教育センター専任講師)
『翻訳を産む文学、文学を産む翻訳 ―― 藤本和子、村上春樹、SF小説家と複数の訳者たち』(松柏社)
異なった言語や文化をつなぐ存在である翻訳は、それ自体魅力的な研究テーマでもあるが、翻訳というと、どうしても元のテクストの意味がいかに正しく伝わるかという点からばかり考えがちになり、訳した側の文化の方からものを考えるような議論にはなかなかなりにくかった。しかし、文学作品が国境をこえて世界的な広がりをもつようになり、「世界文学」的な発想が広がる今日、「トランスレーション・スタディーズ」などの名で呼ばれる新たな研究が進み、翻訳の周辺には新しい景色がひらかれてきている。翻訳された先の新たな文化的コンテクストのなかで、元の作品にはなかった展開が生まれ、時には新たな創作を誘発するなど、その文化のあり方全体を変えてゆく力になる、翻訳のそんな側面に焦点があてられるようになったのである。
本書は、このような新しい見方をふまえて、それを1970年代の日本に適用したケース・スタディとして、翻訳論の豊かな可能性を具体的に示した快著である。1970年代といえば、村上春樹、高橋源一郎などの世代の作家たちが日本文学界の状況を大きく変貌させる動きの「前夜」にあたるが、この時期にはリチャード・ブローティガン、カート・ヴォネガットといったアメリカ文学の新たな潮流を代表する作家たちの作品が次々と翻訳され、活況を呈していた。
本書は、1970年代のこれらの翻訳を、こうした日本文学の新たな動きの動因として捉えるものだが、その最大の特徴は、両者を因果関係で安易に結びつけるのではなく、これらの翻訳自体とそれを担った翻訳者たちに焦点を定め、その来歴や活動の文脈にまで分け入って考察することで、これらの作品を受容する日本文学界の側に新たな時代の感性が形作られており、それがこうした動きを可能にしていったという構図を浮き彫りにしようとしたところにある。
ブローティガン作品の翻訳の多くを手がけている藤本和子の活動を論じた章では、藤本が1960年代にアングラ演劇に関わり、またアメリカで黒人女性などの差別をめぐる対抗運動に接するなどした来歴が徹底的に洗われ、そのような同時代的風土に培われた藤本の感性が、従来にない翻訳上の考え方やスタイルに流れ込んでいったさまが描き出される。
また、ヴォネガットの作品については、当初SF界の翻訳者たちによって訳され、その世界で受容されていた事情が考察され、主流文学の世界にそれがSFの枠をこえて流れ込んでくることで、新たな感性がもちこまれ、文学界の再編成へとつながっていった経緯が余すところなく描き出される。
文学の話をはるかにこえて、背景にあるこの時代の文化の重層的な文脈が次々とあぶり出されてくるさまは、まさに圧巻というほかはないが、このような手法は今後、他の人文諸学にとっても大いに参考になるだろう。
この博覧強記の塊とでも言うべき研究をなしとげたのが、中国から留学してきた若い研究者であるということには驚くほかないが、そのこと自体がまさに、異なった言語や文化がつながり、新たな広がりが作られてゆくプロセスを体現したものになっていることをあらためて実感するとともに、それが見事に結実したこの成果の誕生を喜びたい。
渡辺 裕(東京大学名誉教授)評
奈倉 有里(翻訳家、早稲田大学等非常勤講師)
『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』(未知谷)を中心として
2002年、ロシア語を学ぶある日本人女性が単身ロシアへ渡った。語学学校を経て国立ゴーリキー文学大学に入学し、たくさんの人や本との出会いを重ねながら日本人として初めて卒業し、「文学従事者」なる資格を得た。帰国後、日本の大学院で執筆した博士論文に基づく本書『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』は、日露で教育を受けた稀有な経歴の持ち主が結実させたハイブリッドな研究書にほかならない。
ブロークは20世紀初頭に活躍したロシア象徴主義を代表する詩人。著者のブローク熱は本物で、本書は大枠として芸術家の生涯と作品という正統的な評伝形式をとり、一方で、ブロークの人生に関して徹底的に資料を調査し、家庭環境、恋愛や結婚、友人関係、革命に絡む悲劇的な最期などを冷静に跡づける。他方で、最初の詩集『麗しの貴婦人の詩』から晩年の物語詩『十二』にいたるまで、暗喩や曖昧さを孕むブロークの詩を丹念に解きほぐし、その詩学を浮かび上がらせる構成となっている。とはいえ、著者はブロークの詩の内実と意味を、世紀末の芸術家を演じたかのようなその人生に単純に還元するのではなく、またさまざまな文学的、思想的な影響関係の網の目を透かして安易に説明するのでもない。
本書の眼目は、バシュラールの『火の精神分析』を導きの糸とし、ブロークの詩に一貫して見られる「火」のイメージとその変容を析出する企てにあり、詩作の根源にある動因とその多様な表れを追跡するプロセスが読みどころとなる。最初は理想や情熱とつながっていた「火」(火花、焚火、火の輪、夕焼けなど)は、やがて死や災厄に近しい形象を取り込み(焼死、火災、戦火など)、無や消滅のテーマとも親和性を持つ(街灯、消える火、煙など)。「火」はまた雪や闇などと対比的な関係を取り結ぶようにもなり、ブローク独特の矛盾する言葉の並置や多義性をも統御していく。付け加えれば、簡潔な言葉が喚起する形象や色彩が鮮やかに際立つ、視覚性に優れた詩とも評者には映る。いずれにせよ、詩人の内的な叙情の世界が時代の空気や社会の亀裂と感応するその作品は、現代のわれわれにも響いてくるようだ。
ただし、ロシア語を知らない日本の読者にとって、著者が強調するブローク詩の韻律の素晴らしさを、翻訳を通じて味解するのは難しい。音を重視し、朗読を前提として作られているブローク詩の魅力、ロシア語独特の良さを伝えることは、すでに翻訳家として活躍する著者の今後の課題となろう。
ほぼ同時期に刊行された著者の自伝エッセイ『夕暮れに夜明けの歌を ― 文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス)を併読すれば、本書への興味はさらに増す。言葉と文学と学問への愛を披瀝し、ロシアの友人や教師たちとのかけがえのない交流を綴った快作である。「文学が好きだ」を言い切る爽快さ、分断された世界を言葉でつなごうとする志は貴重であり、いわゆる学術賞とひと味違うサントリー学芸賞は、多彩な才能を開花させる期待を込めて、「文学」に生きる著者に贈られる。
三浦 篤(東京大学教授)評
村島 彩加(明治大学兼任講師、青山学院大学非常勤講師)
『舞台の面影 ―― 演劇写真と役者・写真師』(森話社)
好きこそものの上手なれ。著者は少女時代、しばしばお母様に連れられて東京宝塚劇場で宝塚歌劇を観、行く度に宝塚グッズの物販店でブロマイドや舞台写真を買って貰っては、お菓子の空き缶に入れてコレクションしていたという。中でもお気に入りは、雪組の鮎ゆうきが『ベルサイユのばら』のロザリーに扮した舞台写真。長いこと自室の壁に飾って、憧れを日々に新たにしていた。本書のあとがきに、そう記されている。
この育ち方あっての本書であろう。人は憧れしものの面影を追うようにできている。長谷川伸の『瞼の母』ではないが、本物を抱けねば似姿を求め、そこから本物を想像して、思いに耽(ふけ)る。銀幕の面影に憧れれば、プログラムや映画雑誌を買い漁り、スチール写真を眺め、映画館での記憶を忘れぬようにと努める。舞台の面影を追うとなると、思いはなおいっそう切実であろう。映画みたく複製芸術ではない。その日の舞台は一期一会。好きな芝居ほど後に引きずる。ゆえに劇場には物販場ができる。その種の欲望を満たす業界も成立する。“面影産業”とでも呼べばいいか。
たとえば、江戸時代の歌舞伎なら錦絵である。だが、豊国や写楽の時代はいつまでも続かない。幕末維新期から写真が広まる。絵画から写真へ。視覚メディアの大変革期の到来。けれども、その探究は容易でない。絵画史と写真史を股にかけねばならない。技術史的観点も必須となる。並みの博捜では追いつかない。ましてや、芝居の錦絵から演劇写真へ、さらに写真本位の演劇雑誌へという流れとなると、それはむろん演劇史であると同時に、メディア史・出版史にもなって、土俵はますます錯綜してくる。よほどの好き者でないとやりきれない。
ところがそういう好き者が現れた。本書は、ほとんど未踏の密林を、前代未聞の深さと広さで掘り起こしている最中に編まれた、経過報告書であろう。しかし、その内容は既に十分に驚倒物。史実に照らして「嘘のない歌舞伎」を目指した九代目市川團十郎の活歴物の背景に、嘘なくありのままを写し伝える写真の登場の齎(もたら)した感性のパラダイム・シフトを読み取る。五代目尾上菊五郎の情感豊かな演技術を記録しようとするとき、写真の顔に影が付けられたことに注目し、同時代の横山大観の陰影を強調した画法にまでさらりと話を及ぼす。本邦における近代人の心の奥行きの誕生過程を巡るとてつもない示唆がある。他にも魅力的論点多数。演劇写真が面影を留めるための単なる道具というだけでなく、演劇の質を変革して行く大きな起動因となったらしいことに筆が及んでいる。画期的である。
そうした作業を可能ならしめているのは、ひとえに著者の汲めども尽きぬ想像力と思う。本書には、後の新劇の名女優、田村秋子が、少女時代に『演芸画報』のバックナンバーを眺めてはまだ観ぬ舞台を思い描いて時を忘れる挿話が紹介されているが、それはまさに著者の面影に重なろう。とにかく、見事に探し出された細かな資料から、その時代の写真師、役者、観客の心根を摑まえる著者の力量は並大抵ではない。アナール派も驚く感性の歴史学の成果ではないか。
本書は内容豊富でありすぎるがゆえに、残された課題もまたとても多い。たとえば七代目松本幸四郎の一種の変装を記録した顔写真の話は新劇史に架橋して大著になりうる気もする。今後に期待する。
片山 杜秀(慶應義塾大学教授)評
岩間 一弘(慶應義塾大学文学部教授)
『中国料理の世界史 ―― 美食のナショナリズムをこえて』(慶應義塾大学出版会)
初めて訪ねた異郷の地で、知り合いもおらず、土地勘も働かない。刻々と夕闇が迫るなか、温かい食事にありつこうと街を歩き回り、中国料理店を見つけて安堵する。そんな経験を有するのは評者だけではないだろう。中国料理店は世界の津々浦々にまで行き渡り、さまよえる空腹人を優しく迎えてくれる。
もちろん源流は中国である。古代から南北二つの料理系統があり、清代初期までに北方、江南、四川、広東・福建の四大料理が認知された。海を渡ってシンガポール、マレーシアなど東南アジアでも中国食文化が花開き、香港、台湾では英・日の植民地時代に独自の発展を遂げ、更に欧米にも中国料理は進出してゆく。
こうして各地域、各国で展開された中国料理の受容と変容の歴史を著者は記してゆく。空間的広がりを追い求めるあまり記述の深さが犠牲になったのではないかという懸念は杞憂だ。たとえば長く中国文化圏の中にあったベトナムにおける記述を例とすると、阮朝時代以後が特に厚く、広東人商人が持ち込んだ粥や湯麺などの料理が「フーティウ」と呼ばれるライスヌードル料理に進化し、フランス植民地時代、ベトナム戦争の時代に麺料理「フォー」を生み出す経緯が詳しく紹介されており、十分な密度を備えている。
中国料理のナショナリズムとトランス・ナショナリズムのサクセス・ストーリーを描きたかったのではないと著者は書く。たとえば日本で「和食」が時を遡って「発見」されたように、料理をナショナリズムに回収しようとする政治的風潮は強い。中華人民共和国でも20世紀後半から先の四大料理が主に外国人向けに整理されて国民料理として語られるようになった。しかし、中国料理の場合、事実を丁寧に示すことがナショナリズムへの安易な回収を困難にする。生物種が急増した古代の「カンブリア爆発」のように中国料理が多彩に展開するのは、むしろ中国が帝国・国家としては衰退していた時期だし、中国料理の伝播・普及には中国人だけでなく、それを受け入れるホストカントリーの多彩な人たちの貢献がある。
本書は各国、各地域の中国料理史を束ねたもので、世界史として全体を統一的に記述しようとする指向に欠けると感じる読者もいるかもしれない。しかし、「世界」とはそもそも統一的に語ろうとしても、その思惑をすりぬける多様性こそを本質とするものではないか。世界史がひとつの法則性の下に語られている場合は、むしろ特定の信仰やイデオロギーによって曇った眼差しによって実態を見誤っていると疑うべきではないか。
本書を読んでいて思い出したのは、評者がベトナムを取材していたとき見聞きした「王の掟は街の掟に敗れる」という意味の諺だった。生活者たちの手で、しなやかに、したたかに変容してきた中国料理の世界は、まさに「街の掟」にのみ従い、統一的な上からの意味づけになじまない。そうした中国料理の世界を、あたかも料理自体に物語らせるかのように実証的に描き出した本書は、世界史記述のひとつのモデルにもなるのではないか。
武田 徹(ジャーナリスト、評論家)評
藪 耕太郎(仙台大学体育学部准教授)
『柔術狂時代 ―― 20世紀初頭アメリカにおける柔術ブームとその周辺』(朝日新聞出版)
今の柔道は、国際的な競技のひとつになっている。明治前半期に講道館ではじまったそれとは、形をかえてきた。選手を体重別にわける。故意に寝技へもちこむことをいましめ、スタンディングの構えを重視する。たとえば、そういった変形を、柔道は世界へひろがっていく過程でこうむった。
柔道より古い形をとどめる柔術にも、国際化の波はおよんでいる。レスリングをはじめとする海外の格闘技とまじりあい、様がわりをとげてきた。
そうした変容を、最初に大きくうながしたのは、20世紀初頭のアメリカである。この本は彼地(かのち)で、当時おこった事態を、細大もらさずしらべあげている。アメリカで作動したグローバル化の内実を、えがききろうとした読み物である。
1904年にはじまった日露戦争では、多くのアメリカ人がロシアの勝利を予想した。しかし、その翌年には日本が勝ちをおさめている。そのミラクルが、日本の武術を神秘的にかがやかせた。柔術、つづいて柔道への興味がアメリカで高まったのは、そのせいである。新渡戸稲造の『武士道』があびた脚光も、この潮流とともにある。
新しく台頭した柔術は、レスラーやボクサーの敵愾心をかきたてた。渡米した日本の柔術家は、彼らとの対戦を余儀なくされている。いわゆる異種格闘技戦が、彼地ではもよおされた。柔術や柔道のハイブリッド化は、そこから始動する。レスリングなどの良いところを、とりいれようとする気運が高まった。
それだけではない。この時期には、自らの身体をかがやかせようとする文化が、欧米でおこっている。いわゆるボディコンシャスの源流は、このころまでさかのぼれる。東洋のヨガなどには、強い興味がいだかれた。柔術には、そちらの方面からも期待がよせられている。エレガントな身体をもとめる女性には、ぜひ柔術を、というように。
こうした情勢下に、現地ではさまざまな思惑がうごめきだす。ブームでひと山あてようとするような人びとも、あらわれた。今ふりかえればフェイクとしか言いようのない情報も、とびかうようになる。
この本は、そういううさんくさい動きにも、光をあてている。と言うか、その匂いたつようなさわぎのなかに、柔術や柔道を位置づけた。グローバル化の端緒が、混沌の坩堝とともにあったことを、うかびあがらせている。運動競技の歴史が書かれた本である。体育史の一冊だと思う。しかし、評者はそこに風俗史のおもしろさも、あじわった。
あつめられたデータの数々にも、感心する。よくもこれだけの、とりわけ図像資料を渉猟しきったものだなと、脱帽した。また、その掲載をうけいれた出版社の度量も、多としたい。
日本文化のグローバルな展開は、今後も人文社会諸学の課題となりつづけるだろう。これは、そうしたテーマへいどむ人たちにとって、導びきの糸となりうる書物である。
井上 章一(国際日本文化研究センター所長)評
筒井 清輝(スタンフォード大学社会学部教授)
『人権と国家 ―― 理念の力と国際政治の現実』(岩波書店)
人権とは長らく、一般的に、国際政治学の学問の世界では周辺的に位置づけられることが少なくなかった。いわゆる現実主義の国際政治理論の伝統においては、巨大な軍事力を有する大国のパワーや、それを単位とした勢力均衡によって国家と国家の関係を論じることが主であった。
スタンフォード大学で現在、政治社会学を教える筒井清輝氏による本書は、そのような現状に巨大な一石を投じ、「人権力」の効用を説く。すなわち、「人権力」を適切に行使すること、すなわち、「意見を支配する力」(E.H.カー)を活用することによって、日本を含めた各国は国際情勢の中で自らの好ましいかたちで国際秩序を形づくることができるのだ。「この『人権力』とも呼べる能力は、民主主義勢力と権威主義勢力がぶつかり合う現在の国際情勢の中で、ますます重要になってくる」という。それは単なる、理想主義の追求というような次元に収まるものではない。
著者は本書の前半において、普遍的人権が人類の歴史の中でどのように表出し、どのように国際社会で大きな位置を占めるようになったのかを概観する。本書の魅力は、冷戦後の国際政治の中で人権の規範と実践が翻弄されてきた現実を曇りのない目で直視して、その限界と可能性の鬩(せめ)ぎ合いを、緊張感をもって描写していることである。それを読むことで読者は、冷戦後の国際政治がいかに国際人権の問題と密接に結びついているかを認識するであろう。その上で、「実効性を肯定的に見るにしろ、否定的に見るにしろ、国際人権の現実的な理解をベースに、過剰な期待も悲観もすることなく、人権機構の影響力を向上する地道な努力が引き続き求められる」という。これは、戦争と平和を論じた、国際政治学者の高坂正堯の、『国際政治』の著書の中の、次の有名な締めくくりの言葉を想起させる。すなわち、「われわれは懐疑的にならざるをえないが、絶望してはならない。それは医師と外交官と、そして人間のつとめなのである」。
第4章の「国際人権と日本の歩み」において描かれる、国際社会の中での日本の人権外交の軌跡についての記述は、本書の中でもとりわけ高い価値を持つ。すなわち、日本の人権外交の特色が、「対話と協力を主眼とする独自の関与」であると論じ、「欧米の民主主義諸国とは一線を画す外交姿勢であった」と位置づける。だが、そのようななかでも、暗い影が忍び寄っている。それはポピュリズムとシニシズムである。この二つは、平和への脅威となると同時に、国際人権の発展にとっての脅威にもなる。単なる国際人権の発展の歴史を概観するのみならず、これからの国際社会の行方、そしてあるべき日本外交の姿を考える上でも、必読の一冊といえる。幅広い教養と、鋭敏な国際政治を洞察する力を有する著者の、今後の旺盛な研究と論壇での活躍を期待したい。
細谷 雄一(慶應義塾大学教授)評
中 真生(神戸大学大学院人文学研究科教授)
『生殖する人間の哲学 ―― 「母性」と血縁を問いなおす』(勁草書房)
子どもが生まれること、子どもを育てることは、だれにとっても、あるいはどのような時でも喜ばしい出来事であるとは限らない。子どもを生むことがじぶんのキャリア形成にとってマイナスであると思われる時期も、子どもを育てるさいに必要となるひとつひとつの手順がたまらなく煩わしくなる場合もあるだろう。妊娠することの不安、妊婦であることによって奪われる身体の自由、出産にともなう危険と痛み等々はいま措いておくとしても、出産後のたとえば授乳、また離乳食をつくり、ちいさなスプーンでそれを与えること、風呂に入れて、壊れそうなからだを清潔に保つこと、夜泣きする子どもをあやし、外に連れだすことなどが、その「終わらなさ」において果てしない苦行であるかのように思われることもあるだろう。そうしたすべてをひとりの女親にだけ押しつけることはとてつもない不正であるかもしれず、その「不正」に押しつぶされそうになっている女性を、「母性」なるものを振りかざして批難することは、端的に不正義ともなるはずである。
母性をめぐる「神話」が命脈を断たれることなく生きつづけ、その神話が女性に対して(ときに男性にとっても)抑圧的なものとなるのは、およそ「親」のあり方が固定され、とりわけ「母」と「父」とが強く区別されて、「生みの親」と「育ての親」とが決定的に分断されるからでもある。そうした抑圧、固定化、分断が生じるのは、遡ればさらに、「出産」に過剰な意味が付与され、揺るがすことのできない出来事と見なされてしまうことにも起因するのではないだろうか。ここに本書の問い、単純なものでありながら本質的な、もしくは本質的であるがゆえに単純とも見える問いかけがはじまる。言葉遣いをあらかじめすこし整えておき、「産む」とは出産することであるとし、子どもを「生む」ことは子どもを「持つ」ことであるとするならば、母親のみが産むとしても、父親もまた子どもを生むといってもよいし、出産することの周囲に中心化される「生殖」の問題を、むしろ子どもを育てること、育てることをつうじて子どもとの関係を形成してゆくことを中軸として再考し、そのことで生殖の中核的な意味を考えなおすこともできる。そのとき同時にまた、子どもにとっての母と父とのあいだの差異、生みの親たちと育ての親たちとのあいだの相違が相対化され、そこに存在するのは乗りこえがたい落差ではなく、むしろ緩やかな濃淡の違いであることともなるだろう。
哲学的な思考とは経験と論理とに由来し、また経験を論理化して、個別的なもののうちに普遍的な意味を探ってゆくものである。哲学的思考はそのことでまた、世界の見えかたを変化させ、ときに世界のあり方そのものを変容させる。本書で展開されているのは、そうした思考のすぐれた典型にほかならない。本書で問われている問題は折りかさなり、交錯し、複合的であることは言うまでもない。問題を解きほぐす本書の文体は、望みうるかぎりでもっともしなやかで、繊細なものであることも特筆にあたいする。本書はそのことでまた、「子どもを持ち、育むこと」をめぐって、あらたな希望を紡ぎだす一書ともなっているといってよい。
熊野 純彦(東京大学教授)評
以上







