- No.13378(2019/2/1)
-
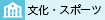
サントリー文化財団設立40周年 活動方針と記念事業について
~〈知〉をつなぐ、〈知〉をひらく、〈知〉をたのしむ~
公益財団法人サントリー文化財団(大阪市、理事長:鳥井信吾)は2019年2月1日で設立40周年を迎えました。
当財団は「社会と文化をめぐる国際的、学際的な探求の深化をめざして、広い分野に亘って有能な人材を発掘援助し、独創的で冒険的な研究を助成し、あわせて世界と日本との文化的な交流の飛躍的な発展に寄与する」との趣旨を掲げ、1979年2月1日、サントリー創業80周年を記念して設立されました。
以来、「学芸文化振興事業」として人文学、社会科学の領域における研究助成と調査研究、サントリー学芸賞の贈呈、海外出版助成を、「地域文化振興事業」としてサントリー地域文化賞の贈呈と地域文化活動の支援を行ってきました。さらに、近年では若手研究者への支援にも積極的に取り組み、これからの社会を担う人材のサポートに務めてきました。また、アカデミズムとジャーナリズムの交流の場を設け、研究者と社会の橋渡しにも取り組んできました。
このたび、40周年を迎えるにあたり、新たに『〈知〉をつなぐ、〈知〉をひらく、〈知〉をたのしむ』というコンセプトを掲げ、40周年記念事業を展開していくと共に、従来の事業についても見直しを行い、さらに発展させていきます。
|
【目次】 |
(1)40周年コンセプトと活動方針
〈知〉をつなぐ、〈知〉をひらく、〈知〉をたのしむ
学術の世界においては、専門分野間の分断や、短期的な成果を求める傾向がとみに強まっており、その結果、長期的視野での幅広い知的な営みを行うことが困難になってきています。また、それに伴い、学術と社会との距離が遠くなりつつあります。
一方で、現代社会は国内外でさまざまな問題が複雑に交錯しており、それらを解きほぐすと共に解決へと導くような知恵がこれまで以上に必要となっています。
当財団では、分野の壁を取り払い、多様な領域で〈知〉にかかわる人々をつなぎ、広く社会にひらくことをめざしていきます。そして、より多くの人が「目から鱗が落ちる」ような経験をたのしむことができる〈場〉を提供していきます。こうした想いを『〈知〉をつなぐ、〈知〉をひらく、〈知〉をたのしむ』というコンセプトに込めています。
主な40周年記念事業は、以下の通りです。
1)異なる分野の有識者が、普遍的なテーマをめぐり、自らの専門領域を超えて、予定調和なしで議論をくり広げる「学芸ライヴ」。
その場でしか味わえない知的交流をメディア関係者と共有します。
2)書店と協力し、各界を代表する有識者が学芸の面白さをやわらかい言葉で語る「プレミアム・ミニトーク」。その面白さを読者と共有します。
3)さまざまな課題に直面する「課題先進国」日本からどのような知見やアイデアを世界に発信できるのかという知的対話を行う「国際シンポジウム」。
これまでのプロジェクトの成果を踏まえた議論を展開します。
4)日本の豊かな地域文化をどのようにすれば未来に残せるのかを考える「地域文化フォーラム」。全国5つの地域で地域文化の実践者・支援者と共に考えます。
5)直近10年分のサントリー学芸賞の選評をまとめた『サントリー学芸賞選評集2009~2018』。10年前の30周年選評集に続き、新たに刊行します。
また、既存事業についても上記コンセプトに沿って見直しを行い、40周年にふさわしい特別な企画にも挑戦していきます。
例えば、研究助成事業では、従来の「研究」や「学問」の枠におさまらない知的冒険に満ちた研究活動を後押しするプログラムに変更します。また、財団発行の論壇誌『アステイオン』では、2019年末号で『100年前のいま、いまの100年後』という特集を組み、多くの分野を超えた幅広い執筆者の方に寄稿いただきます。
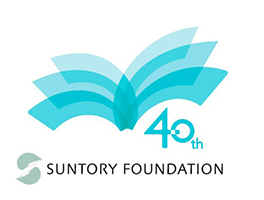 |
|
【ロゴ】 |
ひらかれた書物にも、翼にも見えるこのデザインは、これまでの40年の学芸・文化の積み重ねを象徴しています。さらにそれがひらいて飛び立ち、飛躍、発展していきたいという想いも表現しています。
 |
|
【キャラクター】 |
舞い上がる紙とペンを鳥に見立てたこのキャラクターには、言葉が時代を超えて〈知〉を伝え、自ら世界を飛び回ってほしいという願いを託しています。
1)学芸ライヴ
異なる分野の有識者の方々に、「人間にとって知とはどのような営みなのか?」という普遍的なテーマについて、予定調和なしにとことん議論いただく知的な、臨場感に溢れる舞台です。
メディア関係者や研究者を対象に、大阪、東京で2回ずつ、計4回開催します。大阪では大竹文雄氏(大阪大学教授)が、東京では玄田有史氏(東京大学教授)がそれぞれ自ら企画立案したテーマについてファシリテーターを務めます。東阪それぞれに特色があり、毎回思いもかけない新たな〈知〉の誕生が期待されます。
大阪 第1回
「役に立つって何? - モンゴル×超ひも理論×シロアリ - 」
ゲスト
小長谷有紀氏(国立民族学博物館教授)
橋本 幸士氏(大阪大学教授)
松浦 健二氏(京都大学教授)
大阪 第2回
「これからの時代をどう生きるか - 宗教×労働×その日暮らし - 」
ゲスト
稲場 圭信氏(大阪大学教授)
大内 伸哉氏(神戸大学教授)
小川さやか氏(立命館大学准教授)
東京 第1回
「『語る』ということ、『わかる』ということ - 言語・AI×数学 - 」
ゲスト
川添 愛氏(作家・言語学者)
森田 真生氏(独立研究者)
東京 第2回
「『表現する』ということ、『伝える』ということ - どもる×チンパンジー - 」
ゲスト
伊藤 亜紗氏(東京工業大学准教授)
齋藤 亜矢氏(京都造形芸術大学准教授)
2)プレミアム・ミニトーク
書店と協力し、サントリー学芸賞受賞者などの著者らが、学芸の面白さをやわらかい言葉で読者に語りかける「プレミアム・ミニトーク」を開催します。日頃は著作を通じてしか接点のない有識者と読者が直接会い、近い距離での知的対話を楽しめる特別な場です。
大阪の「梅田 蔦屋書店」と東京の「八重洲ブックセンター 八重洲本店」で各3回ずつ、計6回開催し、参加者は各書店で公募します。
詳細については決まり次第ウェブサイト(https://www.suntory.co.jp/sfnd/)にてお知らせします。
3)国際シンポジウム「高齢化社会はチャンスになりうるか」
当財団では2012年より、少子高齢化問題やエネルギー問題など、日本が直面している課題について、日本固有のものとしてとらえるだけではなく、国際的視野で考えるプロジェクト「グローバルな文脈での日本(Reexamining Japan in Global Context)」を行ってきました。
今回は、世界的に活躍しているジャーナリストや研究者が、これまでのプロジェクトの成果も踏まえながら、議論を展開します。
このシンポジウムは、メディア関係者、研究者を招待するほか、国際文化会館と協力し公募を行い、一般の方にもご参加いただきます。
テーマ 「高齢化社会はチャンスになりうるか」
日時 5月17日(金)17時
場所 東京 国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
基調講演 ビル・エモット氏(国際ジャーナリスト)
パネリスト
デイヴィッド A.ウェルチ氏(ウォータールー大学教授)
マルガリータ・エステベス・アベ氏(シラキュース大学准教授)
吉川 洋氏(立正大学教授)
ジョナサン・ラウシュ氏(米誌『アトランティック』編集者)
司会 田所 昌幸氏(慶應義塾大学教授)
4)地域文化フォーラム「地域文化の未来を考える」
当財団では2016年より、地域文化活動の存続と発展のための課題、現場での現状と取り組み、地域の優れた指導者の展望などを考える「地域文化の未来を考える研究会」を行ってきました。地域文化活動の実践者へのヒアリングを行い、現状や意見をまとめ、地域文化の継続、発展に寄与する提言を、地域文化活動の担い手にお届けします。
第1回の東京では、全国の地域文化活動の担い手およびその支援者である行政とメディア関係者に提言書を披露すると共に、参加者の皆さんからも直接話を伺います。
第2回~第4回は福島、富山、広島で、地元で地域文化活動を実際に行っている方やそれを支援する行政やメディア関係者、地域文化に興味のある一般の方を公募し、開催します。
最終回の大阪では、それまで4回のフォーラムの総括も含めた内容で開催します。
第1回 9月28日(土)東京 ANAインターコンチネンタルホテル東京
サントリー地域文化賞受賞者、行政関係者、メディア関係者、研究者を招待
登壇者
御厨 貴氏(東京大学名誉教授)
飯尾 潤氏(政策研究大学院大学教授)
第2回 10月20日(日)福島 福島県文化センター
第3回 11月16日(土)富山 北日本新聞ホール
第4回 2020年2月 広島 中国新聞ホール
地元の地域文化活動の実践者、行政関係者、メディア関係者ほか、地域文化活動に興味ある一般の方を公募
第5回 2020年3月8日(日)大阪 NHK大阪ホール
上記フォーラムの内容を踏まえた、総括的な内容
5)『サントリー学芸賞選評集2009~2018』
当財団設立30周年を記念して、2009年に30年間の「サントリー学芸賞」の選評を再録した選評集を刊行しました。このたび、その後の10年間の選評をまとめた冊子を新たに刊行します。受賞者および選考委員が、この間の社会と文化をどのように捉え、思索し、語ってきたかが記された本冊子が、今後の社会を考える一助となることを願い、まとめました。
本冊子では、「サントリー学芸賞四十周年によせて」と題し、歴代の受賞者の中から8名の方にご自身と学芸賞との関わりについてエッセイを寄稿いただきました。また、併せて当財団の40年間の年表も掲載しています。
本冊子は、非売品とし、学界、経済界、メディア関係者などに寄贈します。
なお、これを機に、電子書籍でも刊行します。この電子書籍は、本冊子に加えて2009年に発行した30周年選評集も公開し、広くどなたでも見ていただけるようにします。
「サントリー学芸賞四十周年によせて」 執筆者
塩野 七生氏(1981年度 思想・歴史部門受賞者)
青木 保氏(1985年度 社会・風俗部門受賞者)
猪木 武徳氏(1987年度 政治・経済部門受賞者)
東 浩紀氏(1999年度 思想・歴史部門受賞者)
武田 徹氏(2000年度 社会・風俗部門受賞者)
岡田 暁生氏(2001年度 芸術・文学部門受賞者)
田中 優子氏(2001年度 芸術・文学部門受賞者)
飯尾 潤氏(2007年度 政治・経済部門受賞者)
なお、記念事業の名称、および内容については現時点での案ですので変更になる可能性があります。ご了承ください。
〈ご参考〉
「公益財団法人サントリー文化財団」について
サントリー文化財団は、サントリーの創業80周年を記念して、1979年2月に大阪で設立されました。その目的は、国際化、情報化、高度大衆化社会の時代に応えて、それを支える学術研究の育成、文化活動の振興ならびに国際理解の促進に寄与することにあります。2010年5月に財団法人から公益財団法人に移行しました。
ホームページ https://www.suntory.co.jp/sfnd/
以上







