- (2018/11/16)
-
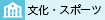
第40回 サントリー学芸賞 選評
阿南 友亮(東北大学大学院法学研究科教授)
『中国はなぜ軍拡を続けるのか』(新潮社)
1997年、中国の国防費の規模は、日本の2分の1だった。十年後の2007年、中国の国防費は日本の2倍以上となった。さらにその十年後の2017年、中国のそれは日本の5倍に膨れ上がっている。(ストックホルム国際平和研究所)
一体、中国は何のために、こうまで軍拡を続けるのか。そもそもなぜ、中国において軍拡が展開されるに至ったのか。
軍拡の背景に、1989年の天安門事件がある。そこで露になったことは、党は共産党独裁を守るために戒厳令を布告し、最後は、人民解放軍が学生と市民を虐殺したという真実だった。中国では、治安維持にかかる経費は「公共安全費」という支出項目のなかに組み込まれている。2011年以降、その支出が国防費を上回る状態が続いている。このことは、中国国内の反体制的力学がいかに強いかということを物語っている。
そして、天安門事件後生まれた江沢民政権の誕生が、軍拡の起点となった。
江沢民は、上海市党委員会書記として上海市内での学生デモを封じ込めた手腕を買われ鄧小平と保守派長老によって1989年6月、総書記に抜擢された。半年後、鄧小平は、中国の支配者の証である党中央軍事委員会主席の椅子を江沢民に譲った。そして、かつて第二野戦軍時代の鄧小平の部下で当時、委員会副主席だった劉華清上将を党中央政治局常務委員に引き上げた上で、江沢民の後見人にすえた。軍に人脈のない江沢民の中央軍事委員会での地位を補強するためである。江沢民は、軍の整備と将兵の待遇を改善するために国防費を大幅に増やすと宣言した。解放軍の能力と党に対する忠誠心を高めるための措置だった。劉華清らが裏で解放軍幹部の給与の大幅アップを江沢民に要求したことは言うまでもない。
1989年以降、中国の国防費の公表額は、ほぼ毎年10%以上増え続けている。今日に至る軍拡路線は、こうして始まった。中国の国防費は独裁政権の存続に必要なコストという側面も持っている。「そのコストが年々上昇し続けていることは、共産党の統治が軍に大きく依存せずには成り立たず、その依存度が拡大傾向にあることを示唆するもの」であると筆者は言う。
中国の対外政策を分析する上で、押えておくべきことは、内政の必要が外交・軍事の方向を決める、そして、統治が戦略を規定するという動態である。党中央軍事委員会を束ねるものが中国を支配する、党が軍を支配するのである。その脈絡を筆者は鮮やかに隈取っている。
惜しむべきは、習近平時代が本書の分析スコープに十分に入っていないことである。
軍拡路線が量だけでなく質の面でも急速に進んでいるのかどうか。
AIスーパーパワーとして異形のAI軍事力を生み出すのか。
AIとビッグデータは、社会監視と政治統制を強化し、強権体制を延命させるのかどうか。
そのモデルは、民主主義国との間で、新たな体制・システム競争をもたらすのか。
筆者に今後、期待する研究テーマは多い。
西側がこれまで維持してきた「関与」政策は、中国との政治体制の差異に起因する摩擦はやがて克服されるという希望的観測にもとづいている、そして、経済で結びついてさえいれば、日中関係は安定するという言説は、もはや説得力を失った――「おわりに」で、筆者が発する警告はずしりと重い。
船橋 洋一(アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長)評
君塚 直隆(関東学院大学国際文化学部教授)
『立憲君主制の現在 ―― 日本人は「象徴天皇」を維持できるか』(新潮社)を中心として
政治現象とは権力によって生じるものであり、政治分析の焦点は権力にある、という考え方は、今日の政治学の根幹をなしている。
権力、すなわち自分以外の個人や集団に何かを強いる力こそが、政策選択を含むさまざまな政治現象を生み出すのだから、政治学はそれを理解するための学問であるべきだ。こう考えるとき、政治学は社会科学の一領域として、経済学や社会学と並び立つことになる。
しかし、政治には秩序を生み出し、維持するという役割もある。この役割には、政治ではなく統治という言葉が与えられることが多い。秩序がどのように作られ、維持されているのかを考察する学、すなわち統治の学として政治学を捉えるならば、憲法学をはじめとする法学、そして歴史学との関係は強まる。
君塚氏がこれまでの諸業績において解明してきたのは、秩序を生み出し、維持する統治が、いかなる原理や制度、人々によって担われてきたのか、という問題である。イギリス二大政党制の確立期における首相奏薦メカニズムの分析から出発し、イギリス国王が果たす役割の変遷を追究してきた同氏は、権力という要素に収まりきらない統治の本質に、一貫して目を向けてきた。
その延長線上に『立憲君主制の現在』があることは論を俟たない。本書は、分析の対象をイギリス一国から大陸ヨーロッパやアジア諸国にまで広げ、今日の立憲君主が統治に対していかなる役割を果たすのかを明らかにする。柔らかく読みやすい文体から受ける印象とは正反対に、現代政治における「君臨」の意味を探求した骨太な著作である。
本書においては、国教会の首長ではなくなることによる多文化共生への配慮、退位を通じて高齢になったときの身の処し方の提示、絶対的長子相続制によるジェンダー平等の推進など、現代の君主と王室は新しい社会的行動規範を積極的に受け入れ、各国の統治にとって重要な役割を果たしていることが、多くの事例から明らかにされる。
立憲君主制を語る上でしばしば用いられる「君臨すれども統治せず」という常識的表現には、政治を権力のみから考え、統治の複雑性を過度に捨象するという視野狭窄があるのではないか。本書からは、そのような問いかけも導ける。それは、歴史学の手法で政治を分析してきた君塚氏ならではの、政治学への問いかけかもしれない。
大きなテーマであるだけに、なお残された課題もあろう。たとえば、現代の立憲君主制が持つどの要素が、いかなる契機によって統治に役割を果たしうるのか、帰納的であっても一般化された知見を得たいように感じる。日本の皇室の将来像についての議論に当たっては、貴族がいないことなど考慮すべき他の要因もあるのではないだろうか。しかし、イギリス王室を知り尽くした練達の書き手である君塚氏は、それらの課題を既に十分認識しているに違いない。今後のさらなる展開が期待される。
待鳥 聡史(京都大学教授)評
韓 載香(北海道大学大学院経済学研究院准教授)
『パチンコ産業史 ―― 周縁経済から巨大市場へ』(名古屋大学出版会)
パチンコは、日本中どこにでもある。一度でもパチンコをしたことがあるという人は相当な数になるだろう。多くの人がパチンコをすることで時間を使っているのは事実であり、本書によれば20兆円の産業になっているという。パチンコは、パチンコ玉をゲームで獲得し、それを景品に交換するという仕組みで法律上はギャンブルではない。しかし、特殊景品と交換できる。それを景品交換所で現金と交換できるので、事実上、ギャンブルである。パチンコの依存症になって社会的な問題を起こすということも時々話題になる。パチンコ産業の歴史を分析するというのであれば、多くの人は、法律のぎりぎりのところで成長してきたことから、地下産業に関する議論を期待するだろう。実際、多くの研究や書物では、脱税、暴力団との関係、民族マイノリティの関わりや外国への送金という側面に焦点が当てられてきた。加えて、規制当局である警察との関係もパチンコ産業の歴史には欠かせないものだろう。
そうした視点が重要なのは事実ではある。しかし、パチンコ産業の当事者からみれば、つぎつぎと変わっていく規制や技術にいかに対応していくかということの歴史であった。その側面に限って言えば、多くの産業が直面している問題と本質的に変わらないのだ。例えば、派遣労働業界は、派遣法規制が変わっていく中で、その規制に対応してビジネスモデルを変えてきた。出版業界は、インターネットや電子書籍の登場で、ビジネスモデルの大変革を迫られている。自動車の排気ガスの規制強化が、日本の自動車産業の技術革新を促して、成長のきっかけになったこともあった。少子高齢化という環境変化が子供向けの産業にビジネスモデルの変更を迫った。
本書のオリジナルなところは、多くの人がパチンコ産業は特殊な産業だと思っている中で、規制への制度的対応、技術革新と規制の関係、新しいビジネスモデルの開発というどの産業にも普遍的な枠組みで分析しているところである。しかし、細かい技術的変化、制度的変化とそれにどのようにパチンコ産業が対応していったかを調べるのは、容易な作業ではない。パチンコ業界の個別企業のデータを手に入れる必要があるからだ。著者は、そうした入手困難なデータを入手し、インタビューを行い、パチンコ業界といういわば特殊な産業の歴史を経済学的に分析する。
例えば、パチンコ業界が、射幸性の程度について時代によって変化する規制に対応していく過程、技術開発の促進と普及を図るための特許の扱いの制定、暴力団を排除するための換金制度の制定などが、データをもとに論証されている。新しいパチンコ台の特許を守るための相互監視システムの構築や景品交換所での換金に障がい者や未亡人という社会福祉と組み合わせて公的性格を持たせるという工夫は、一種のイノベーションだろう。また、1980年代に入ってのパチンコ店の大型化、郊外立地についてもGIS(地理情報システム)や個別企業の資料を用いてその戦略を検討している。著者の優れた文章力と経済学的な思考力が印象的である。
大竹 文雄(大阪大学教授)評
京谷 啓徳(九州大学大学院人文科学研究院准教授)
『凱旋門と活人画の風俗史 ―― 儚きスペクタクルの力』(講談社)
本書の題名を見て、ああそうかとピンと来る人はまずいないだろう。「凱旋門」は西洋美術に関係しそうだが、「活人画」とはそもそも何か、しかもこの二つをつなぐ回路がさっぱり見えてこない、というあたりが普通の反応ではないか。
読んでみると次第にわかってくる。古代ローマに端を発する凱旋門だが、実はルネサンス期には君主の入市式の壮麗な行列を迎える仮設建造物、つまり華やかだが仮初めのお飾りとなるハリボテ凱旋門であった。同じく入市式に組み込まれたのが仮設舞台で演じられた活人画(の原型)で、複数の人間が静止して「キリスト降誕」「パリスの審判」といった絵画のような場面を作り、君主称揚のページェントに花を添えた。
もはや言うまでもないであろう。凱旋門と活人画の共通点とはその場限りで消滅するスペクタクルであること、エフェメラル(束の間の、一時的な)という特質なのだ。著者はイタリア・ルネサンス美術を専門とする研究者だが、本来は残存するモノを研究対象とするはずが、消えてしまうモノを復元する試みに足を踏み入れた。それも、これまで聞いたこともないような組み合わせで。
本書の白眉は後段にある。近代以降、凱旋門と活人画は別々の道を歩む。仮設の凱旋門は国民国家の記憶となる戦勝記念として作られ続け、西洋文化を移入した近代日本においても、日清、日露戦争後にハリボテ凱旋門が数多く制作された。だが、著者の声音がひときわ生彩を放つのは、近代になって前景に躍り出た活人画の運命(さだめ)を語る件である。
18世紀に誕生した本来の活人画は上流市民階級の娯楽という役割を担った。それ以前との違いは、ゲーテの『親和力』における活人画の場面が示すように、模倣すべき原作があるかどうかで、生身の人間たちがポーズして有名な絵を束の間再現するのに打ち興じ、公的な場の余興としても採用されたという。その後、大衆化の道を歩む活人画は、19世紀後半には民族主義的なイヴェントで演じられ、ボロディン、シベリウス、ミュシャなど作曲家や画家たちも関わる一方で、一般家庭でも流行していた。ただし、無視できないのは、それが裸体見物の場、ひいてはショウ・ビジネスや性風俗産業にも組み込まれたことで、西洋から活人画を輸入した近代日本における大衆化の帰結を新宿帝都座の額縁ショウに見るという流れで、本書は幕を閉じる。
犠牲者あっての戦勝を祝う凱旋門と日本のヌードショーにまでつながる活人画。とすれば、あらゆる芸術、芸能の根源がそうであるように、「凱旋門と活人画」とはまさしく死とエロスの別称ということにもなろう。だからこそ、美術と見世物を架橋した本書のテーマは、他のジャンルとも縦横に交差していくに違いない。演劇、小説、写真のみならず、バレエ、オペラ、映画などともまた。
スペクタクルの持つ力や機能を浮かび上がらせるための資料・文献調査は行き届いているが、図版を刈り込んで大きく見せる配慮があってもよかったか。芝居好きの趣味が高じて西洋美術史と近代芸能史を力業でつなげた著者が、奇書(?)を連発することを密かに期待している。
三浦 篤(東京大学教授)評
真鍋 昌賢(北九州市立大学文学部教授)
『浪花節 流動する語り芸 ―― 演者と聴衆の近代』(せりか書房)
浪花節は本格的に論じられてこなかった。戦前にはレコードでもラジオでも圧倒的な人気を誇るジャンルとして、この時代の文化のカギをにぎる存在だったはずなのに、あたかも前近代的な文化の残滓であるかのような扱いを受けてきた。兵藤裕己の『〈声〉の国民国家・日本』が2000年に出版されてようやく、近代国家としての日本を支える忠孝のモラルを浸透させてゆくための装置として浪花節の果たした大きな役割が明らかにされ、新たな視界が開かれたが、これで問題が片付いたわけではない。およそ文化というものは、すべてがそのような単一のストーリーに還元されてしまうほど一枚岩的なものではない。その実践の「現場」におりたってみれば、このストーリーを随所で裏切るかのような様々な活動が、その合間を縫うように展開されている。文化を語ることのおもしろさは、実はそのような部分にこそあるのだ。
本書の最大の特色は、浪花節のこの部分をしっかりつかまえたことにある。特に本書の中心をなす、寿々木米若(すずきよねわか)を具体的な事例として取り上げ、昭和戦前期から戦中、戦後にかけて、この演者が様々な状況とどのように対峙したかを論じてゆく部分の記述は圧巻である。レコード、ラジオなどの新しいメディアが次々と登場し、上演のあり方を大きく変えていった時代、そして「愛国浪曲」なるレパートリーが登場し、一気に戦時下の戦時協力体制に入ってゆく時代、さらにすべての価値観が180度ひっくり返ったかのような戦後占領期の時代へと続いてゆく激動の時期である。浪曲界全体をゆさぶった大きな動きの話に終始してしまいがちなこの時期を描くにあたって本書は、演者としての米若に焦点を合わせ、このような状況の中でいかにして彼の口演空間やそこでの聴衆との関係が作り上げられ、また維持されていったかを克明に描き出してゆく。
そこから明らかになるのは、レコードと劇場での興行とでレパートリーを微妙にずらし、レコードの演目を取り込みつつも劇場空間のあり方を保ち続ける工夫であり、国家が期待していた「愛国浪曲」の受け取り方を微妙に回避するかのようにそれらを受けとめる聴き手の姿である。そして、すべてが180度転換したかにみえる戦後においてもなお、過去のレパートリーの遺産を十二分に生かし、そのヴァリエーションで時代に適応してゆくことで、こうした口演空間の連続性を維持してきた彼らのしぶとく、またしなやかな対応が見事に浮き彫りにされてゆく。
本書を読むと、この激動の時代、浪花節が大きな存在感をもってしぶとく生き延びてきたことをあらためて実感させられるのだが、その存在感の大きさは今では失われてしまったようにもみえる。本書の記述は1950年前後のところで終わってしまうが、その後の時代の浪花節にどんな変化があったのか、あるいはその変化は見かけだけのことで、口演の「現場」に密着してみれば依然として同じようなしぶとさをもって生き延びているということなのか、そんなことも著者にきいてみたい気がした。
渡辺 裕(東京大学教授)評
溝井 裕一(関西大学文学部教授)
『水族館の文化史 ―― ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界』(勉誠出版)
評者は、長い間ファーブルの『昆虫記』翻訳にたずさわってきたので、南フランス、アヴィニョンの法王宮にはよく行った。そこでいつも見入ったのは、養魚池の壁画であった。絵の中には、中世の服装をした人物が四人、四角いプールのような池のまわりでそれぞれ何かしている。一人は、さで網を持ち、一人は投網、また一人は、釣りのような仕草、そして最後の一人は弓で水面を射ようとしているところである。本書にこの絵についての解説を見つけて、楽しく読んだ。
「古代人と同様、中世人はただ水族を捕まえて利用していただけではない。養魚池も盛んにつくられた。中世ヨーロッパの養魚池は、ローマの伝統を受け継ぐものと考えられており、やはりステータスシンボルとして機能した。養魚池は、宴会や賓客の接待のさいに魚を供給するためにも、鑑賞して楽しむためにも重要であった。養魚池の建設が活発化したのは11世紀以降のことで、王や司教など聖俗の権力者ならびに修道院が保有した。云々」
人類は古代から水中世界に対して、好奇心と共に畏怖の念を抱いてきた。河にも、湖にも、むろん海にも、どんな怪物が棲んでいるかわかったものではない。大魚の群れ――これを捕えることはもちろん、大きな願望だが、飼育し、思う存分見ることが、やがて人間の願望となっていく。水中世界に対する知的好奇心の発展である。
しかし、魚を飼うことは難しい。まず水の管理という大問題がある。淡水でも大変だが、海水となるとさらに難しい。それに、容器に入れた水は漏る。一つ間違えば魚は大量死する。それでも科学技術の発達とともに、ガラスや鉄、今ではプラスチックの材料が工夫されて、ジンベエザメを展示するなどということまで可能になった。
本書は、古代世界の人々の魚との付き合い方、アヴィニョンの法王宮の壁画に描かれた養魚池の話などから説き起こし、西欧世界の人々の水族に対する好奇心が徐々に“海洋の神秘”のヴェールを剥いで行く過程を詳しく語って行く。記述は具体的、実証的で、水族の展示における、モナコ、ポルトガルの王侯の権力と財力の誇示、帝国主義の問題、メデイアの発達、19世紀西洋の博覧会を通じての博物学の大衆化、水族館の未来など、興味が尽きない。日本の水族館の歴史についても詳しく調査がなされていて、そこだけでも充分読み応えがある。学術的にも隙が無く、豊穣で、楽しい、水族館研究の決定版と言える。
ところで、またファーブルの話の蛇足なのだが、その最晩年、不遇だった彼のために、友人たちが業績を祝ってささやかな記念祭を計画した。ところが直前になって出席予定の生物学者らが次々に出席をキャンセルしてきたのである。その理由が、モナコに建設された豪勢な海洋研究所の祝典と重なったため、というのであった。学者たちも、田舎の古ぼけたホテルでの食事より、大金持ちの大公のところで、キャビアにシャンパンの方を選んだというわけである。
奥本 大三郎(埼玉大学名誉教授)評
島田 英明(日本学術振興会特別研究員)
『歴史と永遠 ―― 江戸後期の思想水脈』(岩波書店)
これはまさしく「ドーダ」にほかならない。選考にあたったある委員の評言である。たしかに、みずから「豪傑」となり、歴史に名をのこして「不朽」の栄誉を手に入れようと奮闘する。そうした一群の知識人たちが登場したことに、著者は十八世紀から幕末までの日本政治思想史の特色をみる。
しかし、彼らの「永遠性獲得願望」は――ここで「永遠」と著者が呼んでいるのは、あくまでも歴史に長く名をのこすという意味である――はじめから深刻な屈折を抱えていた。そのうち多くは武士の身分に属していたが、もはや戦場での活躍の機会がない、太平の世に生きる武人という存在がそもそも矛盾をはらむ。さらにまた、科挙のような人材登用の制度がない以上、学問の素養を統治の実践に活かすこともむずかしい。
従来の学問を一新する「豪傑」となって、みずからの名を後世の歴史書に刻みつける。そうした展望を大胆に示したのが、本書における荻生徂徠の登場の意味である。しかし徂徠の弟子たちは「不朽」をどんな方向に求めるかで分裂していった。服部南郭は統治への参与を諦め、詩文における名声を求めようとする。太宰春台はあくまでも統治の「道」に関する「豪傑」たらんと志向したが、その営みはまた、師説をものりこえ、「新見」の独創性・奇想性を誇ろうとする態度をも生んでいった。
こうして、新奇な学説を提示することで「豪傑」たらんとする者が輩出した時代として、著者はポスト徂徠の時期を位置づける。学派にとらわれない「自得」を強調した折衷学派も、古文辞派の詩文を批判する性霊説の儒者たちもまた、そうした傾向を共有していた。それが、国学・洋学などさまざまな学問が華ひらいた十八世紀後半の気分だったのである。これに対して、寛政の異学の禁ののち、「新奇」さを戒め、朱子学の「正学」を堅持する一種の反動が生まれる。だがそれは同時に、儒学史の「正統」の歴史の末端にみずからを位置づける歴史意識と、学問所のネットワークが全国に広がったことによる「文藝の共和国」の成立と結びついていた。
歴史への強烈な意識をもち、同時に「文藝の共和国」での名声の獲得を追求した頼山陽の登場によって、歴史は新たな段階に入る。山陽自身はあくまでも歴史書を書き、英雄たちの事業を書き記すことで、「文士」としての名声を「不朽」のものにしようと試みた。だが、その歴史書『日本外史』『日本政記』を愛読した世代は、吉田松陰を代表として、歴史に名をのこそうと望み、幕末の政治実践へとなだれこんでいった。そして時代が明治へと移ったあとも、この「永遠性獲得願望」が形をかえて持続することを、内村鑑三『後世への最大遺物』を例にあげて示唆しながら、著者は巻を閉じている。
本書は、明確に理論化されない気分や感情に焦点をあて、それを説得的に解明しながら、他面でミクロな分析に終わらず、思想の広いコンテクストを指し示した業績として、徳川思想史研究に新生面を切り開いた仕事と評価することができる。幕末の政治過程の進行とどのように関連していたのかをもっと教えてほしいといった感想も残るが、それは著者の今後の研究に待ちたい。魅力的な文体も含め、受賞にふさわしい傑作である。
苅部 直(東京大学教授)評
新居 洋子(日本学術振興会特別研究員)
『イエズス会士と普遍の帝国 ―― 在華宣教師による文明の翻訳』(名古屋大学出版会)
産業革命以前のヨーロッパと中国との間にどのような知的やりとりがあったか。イギリスで産業革命が始まったのは偶然に過ぎないという最近しばしば見られる見解は、やや誇張されており他の構造的要因を軽視していると評者は考えるが、それにしても、18世紀のヨーロッパと中国を比較したとき、前者が後者を経済的にもそして知的にも圧倒していたわけではないことは確かだろう。
「科学革命」を構成するさまざまな知的営為がなされていたとはいえ、18世紀ヨーロッパの「科学」観は、現代のわれわれのもつ認識とは相当異なるものであった。そのようなヨーロッパに対して、当時中国に滞在していたイエズス会士たちは、ヨーロッパ以外にも「普遍」が存在し、「科学」が存在することを膨大な著述の形で伝えた。本書は、彼らの著述とりわけアミオの著述を徹底的に検討することで、彼らがどのように「文明の翻訳」を行ったかを、多面的かつ徹底的に明らかにしようと試みた分析である。
本書を読むことで、読者は、当時の中国における音楽理論、支配者の言語としての満洲語、中国の統治機構(皇帝のあり方や朝貢体制)、歴史観を知ることができるだけでなく、当時のヨーロッパ人がイエズス会士のもたらしたこれらの中国事情に接して、どのように反応したかを知ることができる。
たとえば、当時ヨーロッパでは、アイルランドの大主教アッシャーによるウルガタ訳聖書を基礎とした聖書年代法が広く受け入れられていた。それによると天地創造は紀元前4004年、大洪水が紀元前2348年と推定されていた。ところが、宣教師マルティのもたらした中国史によれば、最初の帝王伏羲の治世は、大洪水以前の紀元前2952年となってしまうのであった。マルティニは、この「不都合」を回避するためウルガタ訳聖書ではなく七十人訳聖書に基づく年代法を採用したという。七十人訳聖書による年代推定からすれば天地創造は紀元前5200~5199年、大洪水が紀元前2957年となり、数年の違いで矛盾が回避されるというのであった。
しかし、この回避策は、ヨーロッパの知識人の間にイエズス会士たちの中国史に対する疑いをさらに生み出し、以後、ヨーロッパの知識人とアミオに至るイエズス会士たちの間で、延々とこの年代矛盾の問題や中国の年代推定の正しさ、その根拠となる中国における天体観測の正確さなどが議論されつづけた。本書は、この議論を丁寧にたどることによって、ヨーロッパにおける中国史に関する認識が格段に進んだことを示している。聖書による年代推定からヨーロッパが解放されることはなかったにしても、この時代の中国とヨーロッパの知的対話は、ヨーロッパにおける歴史に対する見方を格段に緻密なものにしたのではないかと評者は推測する。
このように全篇にわたって魅力的な分析のちりばめられた本書であるが、あえて難点をあげるとすれば、このヨーロッパと中国との知的対話の構造が今ひとつわかりにくいことである。本書で明らかにしたイエズス会士の苦闘をその一部として取り込むような、骨太な思想のグローバル・ヒストリーを期待したい。
田中 明彦(政策研究大学院大学学長)評
山本 芳久(東京大学大学院総合文化研究科准教授)
『トマス・アクィナス 理性と神秘』(岩波書店)
宗教は、信じるか信じないかの問題であって、論理や理性の問題ではない。信仰は、苦しい現実から逃れ、それを直視しないための幻想に過ぎない。私たちは日々、このような言説に接する。しかしながら、このような宗教や信仰の理解は、いささか偏っているのではないか。宗教は必ずしも論理や理性を排除するものではないし、信仰は逃避とは限らない。そのような豊かな思考の可能性を開いてくれるのが、山本芳久氏の『トマス・アクィナス 理性と神秘』である。
新書として書かれたこともあり、本書は平易な言葉で書かれ、挙げられる例も親しみを持ちやすい。にもかかわらず、そこで展開されている内容は高度であり、安易な入門書ではまったくない。
トマス・アクィナスというと、「遠い中世ヨーロッパの神学者」、「『神学大全』を書いた、権威ある保守的な神学者」というイメージを抱きやすい。しかしながら、本書を読めば、トマスが当時、最新の哲学であったアリストテレスの著作と、キリスト教神学をダイナミックな相互関係に置き直し、独自の総合を成し遂げた、「既存の権威への挑戦者」であったことがわかるだろう。
本書の魅力は、著者の次のような表現に典型的に示される。「「理性的」とは、自らの限界を充分に弁(わきま)えながらも、どこまでもあらゆる実在――それは人間理性を超えた神の神秘をも含む――に対して自らを知的に開いていこうとする根源的に開かれた態度を意味している」。
人間の知性にはたしかに限界がある。しかしながら、そのことは理性が無力であることを意味しない。むしろ、人間の理性は、人間の理性を超えた神秘と出会うことによって促され、あくまで理性的な探究を続けていく。神秘を理性によって理解し尽くすことはできないが、むしろ理解を超えているからこそ、神秘は汲み尽くせない意義と魅力を持っている。山本氏が描き出すのは、そのような理性と神秘の関係である。
トマスにおいて、人間は天の祖国を目指し現世を生きる旅人である。ただし、この世はかりそめというわけではない。この世という道を歩む人間は、様々な経験を通じて、人生という道を適切に歩み続ける力を学ばなければならない。それが徳であるが、あくまで自らの持って生まれた能力を十全に開花させるためのものであり、「喜び」に満ちている。山本氏の描くトマス像はつねに明るく、肯定的である。節制や賢慮が求められるが、けっして抑圧的ではない。
本書の最大のメッセージは、善は自己伝達し、自己拡散するというビジョンであろう。私たちは善を贈与されることで生き、そして人に善を贈与していく。読者は山本氏が描き出すトマスの思考を追うことで、人が学ぶこと、そして人が生きることの意味を再考するヒントを得るはずだ。
およそ西欧的思考というものがあるとすれば、その骨格はトマスにおいてはじめて完成された――本書を読めばそのような知の見通しが得られる。そして今日、あらためてトマスを読むことは、キリスト教や西欧的世界の枠を超えて、多くの人々に学び、生きるための知恵を与えてくれることを知る。学芸賞という名にふさわしい、学知と人間知に満ちた本である。
宇野 重規(東京大学教授)評
以上
