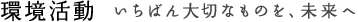水中生活から進化した陸上動物にとっても、水は欠かすことのできない命の源です。体の仕組みは陸上生活に適応するように変わってきましたが、その基本を成す細胞や細胞内における水を触媒とした生化学反応は、水中時代と変わりません。
陸上動物は体温を一定に保つために、発汗をして体内の水を使いながら調整をするなど、さまざまな工夫が体内機構に仕組まれています。
私たち人間を含む哺乳類や鳥類は定温動物(恒温動物)で、体温を一定に保たなければ生きていくことができません。人間は、体温が2度上がっただけでも「発熱した」状態になり、体調を崩してしまいます。このため、気温とともに温度が変化する変温動物である爬虫類や魚類と違い、体温を一定に保つシステムが必要になるのですが、その体温調整に汗が重要な働きをしています。
人間の体は気温が上がったり運動をしたりして体温が上がりそうになると、皮膚の血管を広げ、皮膚に熱を集め、その熱を皮膚から放出することで、体の深部の温度を一定に保とうとします。しかし、夏の暑いときに運動をしたりすると、このシステムだけでは温度調節が追いつかなくなってしまいます。そこで、さらに皮膚の血流量を多くして、汗を出し、体温を調整します。汗をかくと水分が蒸発するため、そのときの気化熱で体温が下がるのです。
では、イヌやネコなどの動物たちも汗をかくのでしょうか。ウマのように汗をかく動物もいますが、汗をかかない動物も実はたくさんいます。
例えばイヌやネコは、体温調節の方法として「暑いときには、なるべく動かないようにする」ということを基本にしています。野生動物の多くは真夏の炎天下には狩りをしませんし、人間に飼われているペットも、暑いときはどこか涼しい場所を見つけてじっとしています。それでも暑いときは、例えばイヌなどは、口を開けて舌を出し「ハーハー」とすることで体温を調整します。これはパンチング呼吸といって、温かい息を吐き、水分を舌から蒸発させることで体温を下げているのです。また、ゾウが大きな耳をパタパタとさせている姿を動物園や映像で見たことがあるかと思いますが、これは、耳の血管の血流をよくして、そこから熱を放出し体温を下げていると考えられています。

水の少ない砂漠のような環境でも生きていかなければならない動物は、さまざまな工夫をして水の少ない状況に対応しています。
例えばラクダは、1日に100キロメートル以上の距離を、水を飲まずに歩くことができると言われています。もし、厳しい労役をさせなければ、なんと10日以上も水なしに生きていけるそうです。また、反対に、水を飲むときは、一度に100リットル以上も飲めるといいます。
ラクダが飲んだ水は血液中に吸収されます。他の哺乳類よりも水を多くの血液中にためることができます。また、大きなコブの中味は脂肪が詰まっているのですが、食料がなくエネルギーが不足するとこの脂肪をエネルギーとして活用、脂肪がエネルギーに分解されるときにできる水(代謝水)も利用し、水不足に対応しているのです。この水袋の水は熱を蓄えておくこともできるため、ラクダは暑い昼にはここに熱をため込み、砂漠の寒い夜にはためてあった熱を活用して生活しています。
ラクダの体には、このほかにも工夫が凝らされています。一般的に、哺乳類は気道粘膜や肺を保護するため呼吸粘膜の表面積を増やして呼気を一度加温加湿し、その後温度を下げることで呼吸によって放出される空気中の水蒸気を結露させ回収しているのですが、ラクダは、そのシステムをさらに発展させて、水の節約に活用しているのです。ラクダの鼻の中は巻紙のようになっており、それを広げると吸い込んだ空気と接する表面積が1000平方センチメートルにもなるといいます。乾いた空気を吸い込むと、粘膜の水分が蒸発し蒸発熱によりそこが冷えます。冷えたところに肺からの湿った吐く息が通るため、冷えた粘膜で結露します。このようにして、呼吸で失われる水蒸気の何割かを回収し、水分を節約しているのです。
さらに、ラクダは鼻の穴を閉じることもできます。この体の仕組みは、砂漠の風塵が体内に侵入するのを防ぐためと、体内の水分を蒸発させないためという2つの理由から生み出されたと考えられています。呼吸をするときは、肺の水分が蒸発して吐く息と一緒に体外に出てしまいますが、一度、鼻の穴を閉じることで鼻の中で息を溜め、水分を体内に吸収してから、乾いた息を吐き出しているのです。


【参考文献】
- 中村運/著 『生命にとって水とは何か』 講談社