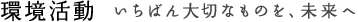日本の空に復活した シジュウカラガンとハクガン @宮城県・伊豆沼、蕪栗沼
日本の「冬風景」そのものだった
大きな水鳥のガン。
かつては日本全国の水辺で
普通に見られる鳥でした。
ところが明治から昭和にかけて
次第に数が減少。
とくにシジュウカラガンとハクガンは、
日本からほぼ絶滅に近い
状態になってしまいました。
この美しい鳥たちを
再び日本の空に復活させたい
今から約40年前、
こんな夢物語のような思いを
実行に移した人たちがいます。
日本雁を保護する会の人々です。
そして、今、
ついにそれは現実のものとなり、
日本の空を大群で
舞うようにまでなっています。
今回はそんなシジュウカラガンとハクガンの
復活に努力を続ける人々の
現場を視察しました。

日本のガン類最大の越冬地・
宮城県伊豆沼と蕪栗沼へ

2019年11月、私たちは、復活したシジュウカラガンとハクガンを見るために、宮城県北部にある伊豆沼と蕪栗沼を訪ねました。
ラムサール条約湿地に登録されている伊豆沼と蕪栗沼・周辺水田は、日本最大のガン類の越冬地。なんと日本のガン類の80~90%が集中しています。
ガン類が越冬するには、ねぐらとなる冬でも凍らない水深の浅い広い湖沼と、採食するための広大な水田のセットがなければなりません。現在の日本には、このような環境がほとんどないため、ガン類は伊豆沼と蕪栗沼の周辺に集中してしまうのです。


かつてガン類は、日本全国どこでもいる水鳥でした。それは万葉集では2番目に多く詠まれている鳥であることや、江戸時代の浮世絵にたくさん描かれていることでもわかります。
それほど普通にいたガン類は、明治時代に解禁された狩猟によって数を減らし、太平洋戦争後に、開発によって生息環境が消失したことで、一時はたった約3,300羽まで激減してしまったのです。
その後、1971年にマガン、ヒシクイ、コクガンの3種は天然記念物に指定され、なんとか絶滅を回避。現在、マガンは約20万羽まで増えています。
絶滅の危機に直面した
シジュウカラガンとハクガン
日本に渡来記録のある10種のガン類の中で、いちばん数を減らしたのが、シジュウカラガンとハクガンです。
シジュウカラガンは、江戸時代には仙台周辺でガンを捕ると、10羽のうち7~8羽がシジュウカラガンだったとされるほどたくさんいた鳥で、1935年頃までは、仙台市福田町と多賀城市の七北田(ななきた)低地に数百羽の群れが毎年越冬していたことがわかっています。
ところが1938年にはまったく渡ってこなくなり、その後もごく希に1羽または数羽が渡来するだけで、ほぼ絶滅状態になってしまいました。
絶滅の原因は、シジュウカラガンの繁殖地であった千島列島に毛皮をとる目的でキツネが放されてしまったことです。
1915年頃は世界的なキツネの毛皮ブームで、日本政府は千島列島の多くの島々でキツネの放し飼いを開始。とうぜん、肉食獣のキツネは、シジュウカラガンを襲って食べてしまいます。その結果、全ての個体が食べ尽くされてしまったのです。
ハクガンは明治初期には、東京湾に「残雪と見まごうほど」と表現されるくらいの大群が渡来していたとあり、それほど珍しい鳥ではなかったと記述されています。ところが明治時代に解禁された狩猟により、白く目立つハクガンは格好の標的となって、あっというまにいなくなってしまったのです。


シジュウカラガンを探しに
絶滅の危機に瀕したシジュウカラガンが復活したのは、日本雁を保護する会が中心となり、ロシアやアメリカと共同で行った羽数回復計画の成果です。
今回の視察では、その計画を実施した日本雁を保護する会会長の呉地正行さんと、その姉妹団体である雁の里親友の会の池内俊雄さんに案内をお願いしました。
日本雁を保護する会は、1970年に発足したガン類を地球規模で保全研究する団体で、「サントリー世界愛鳥基金」では、1991年度の第2回から活動資金を助成しています。
会長の呉地さんは、羽数回復計画の中心人物で、ガン類の保護に関わってすでに50年近く。また、池内さんは古くから国内外の調査に尽力され、越冬地での観察を毎日のように行っている方です。

ガンを見るには、車に乗って広大な水田をめぐって探します。シジュウカラガンがよく利用する水田はだいたい決まっているので、過去に実績がある場所を中心に見ていくのですが、この日は風が強く、なかなか発見できません。
それでも1時間ほど探し続け、ようやく風があたらない場所で30羽ほどの群れを見つけることができました。その後は、あちこちでシジュウカラガンの群れを見ることができ、本当に復活したのだなと実感することができました。


最初の放鳥は失敗
シジュウカラガンの羽数回復計画が、具体的に動きだしたのは1980年のこと。アメリカから提供を受けた親鳥から誕生した若鳥を越冬地の日本で放すことから始まりました。
ところが、放した鳥が春になっても北に飛んでいかずに失敗。越冬地での放鳥ではうまくいきませんでした。ガン類は初めて飛んだ場所を繁殖地と認識する習性があり、かつての繁殖地、千島列島での放鳥がどうしても必要だったのです。
しかし、当時のソ連、特にガンと深く関係があるカムチャツカや千島列島には政治的な壁があり、たとえ科学調査であっても日本人は行くことができませんでした。
シジュウカラガンの羽数回復計画と平行して、日本に渡来するマガンやヒシクイの繁殖地や渡りルートを解明する研究もはじまりました。
当時、日本のガン類は、漠然とソ連(現在のロシア)から来ることはわかっていましたが、具体的な繁殖地や中継地などはまったく不明だったのです。
1991年7月、それまでかたく閉ざしていた扉をソ連は開放。初めて日本雁を保護する会のメンバーがカムチャツカ州とその北のアナディリ低地(チュクチ自治管区)に行き、ヒシクイとマガンに数字の入った首輪標識を装着することができたのです。


この日ソ(日露)共同現地調査はその後も数年間続き、その費用の一部に、「サントリー世界愛鳥基金」の助成が役立てられました。その結果、標識された鳥たちは日本で発見され、マガンはアナディリから、ヒシクイはカムチャツカから来ることがわかりました。
じつは、この調査はシジュウカラガンやハクガンの羽数回復計画と無関係ではありません。
ソ連(現:ロシア)側で、日本に確実に渡るであろうマガンやヒシクイを見つけ、その場所でシジュウカラガンやハクガンを放せば、マガンやヒシクイがガイド役になって確実にシジュウカラガンやハクガンを日本へ連れてきてくれるからです。
ついに千島列島で放鳥を開始!
そして、5,000羽の群れに
政治的な壁により、立ち入ることさえ不可能だったシジュウカラガンのかつての繁殖地である千島列島でしたが、1991年ソ連の崩壊によって、日本人が入れるようになり、ついに1995年に日露米の共同チームは、カムチャツカの増殖施設で生まれた16羽の若鳥をヘリコプターで運搬。
繁殖地のひとつだったエカルマ島で最初の放鳥を実施することができたのです。その後、放鳥は2010年まで合計13回行われ、合計551羽の若鳥が放されました。
その結果、2007年には、初めて幼鳥を連れた家族群が日本に渡来し、野生下で繁殖していることが判明。
2010年には、100羽を超えるようになり、その後も順調に増加し、2017年にはついに5,102羽を記録。5,000羽を超えるシジュウカラガンの群れが日本に復活したのです。1980年の計画スタートから37年の年月が経過していました。



復活、そして次のステップへ
5,000羽を超え日本の空に復活したシジュウカラガン。羽数回復計画は一段落し、今、次のステップに入っています。
まず、これまでの経緯と成果を多くの人に知ってもらうための普及啓発活動です。農耕地を利用するシジュウカラガンが将来も安心して生きていくためには、人々の理解がなければなりません。それには今までの経緯と意義を理解してもらう事がどうしても必要です。

また、千島列島で繁殖し、日本で越冬するシジュウカラガンの個体群ができたことは、じつはとても重要な意味を持ちます。それまで世界のシジュウカラガンは、アメリカのアリューシャン列島で繁殖し、米国西海岸で越冬する個体群だけでした。
この個体群も、1962年に奇跡的に発見された少数の鳥をアメリカ政府がプロジェクトチームを作り、復活させた成果なのです。
そして今、日本に提供されたその子孫が、千島列島で繁殖を始めたことにより、絶滅の危機からまた一歩遠ざかったことになりました。その意義を伝えるためにも、啓発活動は不可欠です。
さらに千島列島で今後も調査を進める必要があります。現段階では、エカルマ島に繁殖地ができたことは推定でしかなく、きちんと確かめられていないからです。また、エカルマ島は火山島なので、噴火によっていつ繁殖地が消滅してもおかしくありません。
その危険を回避するためにも、他の島に新たな繁殖地をつくる必要があります。2019年には、「サントリー世界愛鳥基金」の助成を受けて、呉地会長がエカルマ島に行き、シジュウカラガンの繁殖が確かめられました。

アジアのハクガン復元計画
ハクガンの復元計画は、1992年に始まりました。激減してしまったアジアのハクガンを復活させる必要性を感じていたロシアのシュレチコフスキー博士は、かつての越冬地でもっとも安全な日本へ渡る群れをつくる計画を北米極地ガン会議で提案。
北米のハクガン研究者であるジョン・タケカワ博士と日本雁を保護する会に協力を求め、日露米の研究者が共同で計画を実行することになったのです。

実際に復元計画が行われたのは1993年6月。アジア最後のハクガン繁殖地であるロシア・ウランゲル島で100個の卵を採集し、ヘリコプターで日本に渡るマガンが繁殖しているアナディリ低地(チュクチ自治管区)に運びました。
そこで発見した6つのマガンの巣に41個の卵を托し、この後、全ての卵が孵化。マガンとハクガンの混成家族をつくります。

また、残りの59卵はふ卵器で孵化させ、しばらく飼育した後に、マガンの群れのそばで放鳥したのです。
マガンを親にすると雑種の心配がありそうですが、ガン類は自分が生まれた同じ巣の雛を見て種類を認識する習性があり、雛の数が多ければ多いほどその認識が強固なものになります。その習性を利用すれば雑種ができる心配を排除することが可能です。
マガンとハクガンの混成家族は、秋には親に連れられ、かつての渡り経路をたどって日本にやってくるはずです。また、ガン類ははじめて飛んだ場所を故郷として認識する習性があるため、翌春には日本を飛び立って、再びこの地に戻ってきて、やがて繁殖を開始するというのがこの計画の作戦です。
2019年、ついにハクガンの数は1,000羽を超えた!
1993年と1994年のシーズンには、放鳥したハクガンの幼鳥を確認する調査を日本と韓国で行いました。その結果、北海道や宮城県、秋田県などでマガンの群れに混ざっている4羽のハクガンを確認、韓国では15羽の群れが観察されました。
また、その翌年も韓国で調査を行いましたが、ハクガン成鳥8羽の群れを発見するに留まりました。この調査には「サントリー世界愛鳥基金」の助成が役立てられています。
その後、2007年までの14年間は日本へ数羽が渡来する程度で、なかなか成果が見られませんでした。
ところがそれ以後、徐々に数が増え出し、2012年の冬には100羽を突破。そして2019年には、ついに1,000羽を超える群れが北海道で観察され、復元計画は27年かかってようやく成果を上げることができたのです。


あきらめない気持ちが
夢を現実に
みごとに復活したシジュウカラガンとハクガン。1980年の計画開始から、約40年にも渡る長い長い年月が必要でした。その間、なかなか成果が見られない時期がありましたが、粘り強くあきらめない気持ちが夢を現実のものにしたのです。
また、国境のない渡り鳥を守っていくには、ロシアやアメリカとの国際協力がいかに大切であるかも今回の視察で知ることができました。
大きな群れを回復するという目標が達成された今、また新たな目標が設定されています。それは、1935年までシジュウカラガンが定期的に越冬していた仙台市福田町と多賀城市の七北田(ななきた)低地の水田に再びシジュウカラガンを呼び戻すことです。
すでに2018年1月には、目的地のすぐ近くを飛ぶ77羽のシジュウカラガンが目撃されているので、その可能性はとても高いと考えられています。
現在、日本のガン類は、その個体数の約90%近くが宮城県北部に集中し、すでに伊豆沼や蕪栗沼のねぐらだけでは足りなくなっています。これらのガンたちが一極集中するのは、伝染病の蔓延の危険もあり、好ましいことでありません。
私たちは今回の視察で、夕方、蕪栗沼へ次々と美しい隊列を組んで飛んでくるガンたちに出会いました。それは本当に心奪われる光景でした。
現在の一極集中の状況が解消され、かつての日本のように、全国各地の水辺でガンがごく普通になり、この美しい雁行(ガンの編隊飛行)が東京の空でも見られる日が来るのを願わずにはいられません。