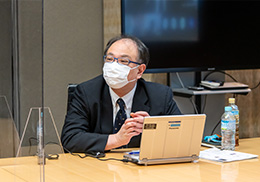サントリーグループは「Growing for Good」の志のもと、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けるべく2019年にサントリーグループ「サステナリビリティ・ビジョン」を策定しました。そこでテーマとした7つの重要領域から、特に「水」「CO2」「容器・包装」について、有識者の方々にご紹介させていただき、評価やご意見をいただきました。
-
● 開催日:2021年1月14日(木)
-
● 場所:有識者:リモートによるご参加
サントリー参加者:サントリーワールドヘッドクウォーターズ(お台場オフィス)
有識者
-

足立 直樹氏
(株)レスポンスアビリティ 代表取締役 -

平林 由希子氏
芝浦工業大学 土木工学科教授 -

古木 二郎氏
(株)三菱総合研究所 サステナビリティ本部 環境イノベーショングループ 主席研究員
サントリー
-

福本 ともみ
サントリーホールディングス(株)
執行役員 コーポレートサステナビリティ推進本部長 -

北村 暢康
サントリーホールディングス(株)
コーポレートサステナビリティ推進本部 サステナビリティ推進部長 -

内藤 寛
サントリーホールディングス(株)
コーポレートサステナビリティ推進本部 サステナビリティ推進部部長 -

井床 眞夫
サントリー食品インターナショナル(株)
専務執行役員 MONOZUKURI本部長 -

横井 恒彦
サントリーMONOZUKURIエキスパート(株)
執行役員 SCM本部 包材部長
司会
今津 秀紀
学会「企業と社会フォーラム」プログラム委員長
「水」に加え「環境」でもトップランナーだというイメージをもっと伝えるべき
- 司会
- 2019年に策定したサントリーグループ「サステナビリティ・ビジョン」のなかでも水、CO2削減と気候変動、および容器・包装からは特にプラスチックについて、本日は有識者の方々からさまざまなご意見をいただきたいと思います。まずは、「水」に関してお願いいたします。
- 足立
- 水については、サントリーは一貫して熱心な取り組みをされていますが、その取り組みが本業にストレートにつながっています。メッセージ性という意味でもとても素晴らしいと思います。特に国内の水源涵養(かんよう)に関して、工場で汲み上げる地下水の2倍以上の水を工場の水源涵養エリアの森で育んでおり、ウォーター・ポジティブと言っていい内容で、とても素晴らしいと思います。また、コロナ禍にあっても「森と水の学校」や「出張授業」など教育活動「水育」を継続されていることも大変評価できると思います。一方で、国内の水源涵養以外の取り組みについてはいかがでしょう。原材料をつくる畑で使う水について、どのような取り組みが行われているのかも気になります。
- 平林
- 水に対する取り組みのなかで、特に「水育」に関して私たち専門家も努力していますが、サントリーのような企業が率先して教育を進めてくださるということは、大変素晴らしいことで感謝しています。
また、印象やイメージだけではなく、現地で科学的な調査や評価に基づいて活動していることや、そこで科学的知識を得るだけでなく、しっかり伝えているところが高く評価できます。継続的な調査によって、例えば日本のみならず海外において環境や気候変動、人口増加といった変化の影響がすでに見えてきているかもしれません。その上でさらに、そういった変化にどう対応していくのかという見通しまで示したり、モニタリングを継続的に進めるといった長期の展望につながる活動を進めていただけるとより良いのではないかと思います。
「水ストレス」(1人当たり年間使用可能水量が1,700tを下回り日常生活に不便を感じる状態)に関して、数ある工場の中でどの工場が高いのか評価をして対象拠点を選んだうえで調査をされていますが、現在では対象拠点に選別されていない場所が2030年や2050年といった将来には、一定以上の水ストレスになっているかもしれません。観測を通じて、そういった将来のリスクが高くなることが見込まれるような場所を早めに予測し、指摘してもらえることを期待しています。
- 古木
- まず水の取り組みについて目に飛び込んできたトピックが、水の使用量削減についてです。加えて、水源涵養や地域に根差した取り組みというのは、とても素晴らしいと思います。そこについても定量的に表せる指標といったものがあれば、なおいいのではないでしょうか。現在では、ローカルSDGsや地域循環共生圏といったことがブームですからそういう流れに乗って、サントリーがそれぞれの地域でリーダーシップをとって活動するということもできるのではないかと思います。
- 北村
- 私たちは水領域のトップランナーとなるべくさまざまな取り組みを行っていますが、水のトップランナーといってもいろいろな定義があります。そこに絶対条件はないとは思うのですが、サントリーという企業としてどんなことに期待されますか? もしくは、どういうことがなければならないでしょうか?
- 平林
- 私ごとではありますが、2011年の東日本大震災を機に『サントリー 南アルプスの天然水』を毎月まとめ買いしています。水循環を研究する専門家としては、ブランドにこだわらず科学的に判断すべきですが、子供の母親としては、水はしっかりした安全なものをという思いがあります。数十円安い製品があっても、それは選ばない。これが企業イメージではないかと思っています。
ただ、水のトップランナーでありながら、環境に関してもトップランナーだという認知がまだ消費者には伝わっていないようにも感じます。実際には脱炭素や循環型社会への貢献など、多くの努力をされているわけですから、水に加えて環境でもトップランナーなのだというイメージを一層伝えていく必要があるのではないでしょうか。そうすることで、消費者にとっては「サントリーの製品を買っていれば、環境に対していいことをしている」というイメージが持てるように思います。
- 足立
- 私も、これほどの規模で水源涵養をしているのですから、「完全にウォーターニュートラルになっている」あるいは「ウォーターポジティブです」ということをもっと積極的にアピールすべきだと思います。こうしたことは、積極的に伝えようとしないと伝わりません。また、こうした先進的な取り組みについて、国内のみならず海外に向けてアピールしていただきたい。サントリーは海外事業も大きいですし、働いている方も海外の方が多いわけですから。
水に関しては教育にまで広げてやり尽くしているように感じますが、1つだけ足りないことがあると思っています。それは、今後間違いなく深刻化する水不足に対して、サントリーはどのようなソリューションを提供するのかということ。水に困っている人は世界中に何億人といて、残念ながら今後もっと増えていきます。必ずしもお客様ではない方々に対して何をするべきか。どの分野でも世界的な企業はそこまで求められています。SDGsの視点がまさにそうですが、お客様ではないステークホルダーに対して、どこまでできるか、それが企業の本当の価値になってくると思います。
行動変容していることをサントリーのブランディングに変える
- 司会
- 続いて「CO2」、気候変動への取り組みについてお伺いしたいと思います。サントリーグループでは、2030年目標として自社工場・事業所などからの直接排出25%削減、すべてのバリューチェーンからの排出20%削減を掲げています。また、2050年ビジョンとして、バリューチェーン全体で温室効果ガス排出の実質ゼロを目指しています。
- 足立
- 2050年にバリューチェーン全体でゼロを目指すというのは、とても難しいことです。ですが、本当にそれで十分なのだろうかとも思います。昨年、日本は国全体として2050年にカーボンニュートラルを目標とする宣言をしました。
サントリーの目標が易しいものだとは言いませんが、航空や鉄鋼、コンクリート、セメントなど実現が難しい業界が多くある中で、国全体での達成を考えてみたときにサントリーとして2050年カーボン・ニュートラルでいいのでしょうか。世界に目を向けてみると、すでにお酒や飲料、食品でカーボンニュートラルを謳うものがありますから、サントリーとしてもう少し早い実現を狙わなといけないのではないかと思います。
- 平林
- サントリーは、「CDPウォーターセキュリティ」(国際的な非政府組織CDPによる企業の水セキュリティに関する情報公開プログラム)のAリスト企業に5年連続で選定されています。このプログラムには気候変動リスクの評価もありますから、A評価ということは気候変動リスクについても適切に進めておられるのだと思います。ですが、今回ご紹介いただいた内容からは、気候変動と水循環へのリスクというものがあまり見えてきませんでした。温暖化が進むことで、例えば日本ではバリューチェーンが水害や風水害に遭うリスクが高くなっていたり、海外の工場では反対に渇水が増える地域も出てきたりしていると思います。
- 内藤
- 気候変動対策のなかで、緩和策(排出量削減または吸収量増加)は世界的な温室効果ガス排出量の算定・報告ガイドラインにおけるScope1(直接排出量)、Scope2(間接排出量)、あるいはサプライチェーン全体の排出量であるScope3(その他間接排出量)も減らすといった取り組みを実施しています。緩和策は私たちに課せられたミッションですので、目標を立てて、やり方を決定し、どのように実行していくかというサイクルをしっかりと回していきたいと思っています。
適応策(悪影響の軽減または好影響の増長)としては、「TCFD」(気候関連財務情報開示タスクフォース)におけるリスクと機会の評価などをツールとして確立していこうと取り組んでいるところです。まずは、今あることとうまく結び付けていければと考えています。たとえば社会に対して熱中症対策の飲料を商品として提供するといった基本的なものや、自社においては、水害に対しては海沿いにある工場では充電設備を嵩上げして設置するなど、予防的な対策も行っています。
- 平林
- 「IPCC」(気候変動に関する政府間パネル)でもよく取り上げられますが、どのように資金を回すのか──企業はまずは利益を追求しなければなりませんが、気候変動の取り組みは一部持ち出しになってしまいます。そこで、環境に配慮している、行動変容しているといったことを企業のブランディングに変える。このブランディングを進めることによって最終的には利益につなげるような取り組み方が、企業の成長のためには必須であるという動きも増えてきています。
- 福本
- 適応策として、これまでも自然災害へのリスクマネジメントとしてBCP(事業継続計画)の観点も含めて取り組んできていますが、これから一層歩みを進めていかなければいけないのが、中長期の原材料への影響、バリューチェーン全体での長期の安定調達です。これまでも、一部の原料について取り組んできましたが、現在、改めて各事業部門と、その事業にとって不可欠な原材料は何か、気候変化あるいは水不足等の影響を受けるリスクが高い原材料は何か、代替のきかないものは何か等について検討を進めています。これからドライブをかけていかなければならないと考えていますが、アドバイスがあればぜひお伺いします。
- 足立
- 日本のある食品メーカーで伺った話ですが、例えばある果物が今までの調達地から入手できなくなったそうです。気候変動により価格が上がったり、品質が悪くなったりということがもう実際に起きているんです。私はこれは未来の話ではなく、目の前の問題として、かなり大至急取り組まないといけないことだと心配しています。
- 井床
- 例えばコーヒーであれば2050年問題というものがあり、地球温暖化の影響で今までよりも標高が高いところでしか栽培できなくなるという問題があります。現在、ブラジルをはじめとした農園で契約栽培を行っていますが、調達のリスクと栽培に必要な水への対応という部分まで考えて取り組んでいきたいと考えています。この原材料の中長期調達に関するプロジェクトは、2021年1月からサントリーホールディングスのMONOZUKURI本部でより深めて検討していくべくスタートしています。
- 足立
- ぜひ進めていただきたいと思います。そこがみなさんのビジネスを継続するための一番のポイントですから。サントリーは水がないと事業が成り立たないという説明がありましたが、大切なのは水だけではない。麦やコーヒーなど、いろいろな原材料がないとビジネスができないので、本当に力を入れていただきたいと思います。
- 司会
- CO2の排出量削減について、具体的にどのような取り組みを行っていけばいいのか、足立さんからご意見を伺えればと思います。
- 足立
- すでにサントリーでは省エネは十分にやっていると思います。さらに別の方法として、たとえば再生可能エネルギーの導入はPPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約モデル)で長期契約をすることで安定して購入できますし、経済的にも合理的です。一方で、再生可能エネルギーは日本ではなかなか買えなかったり、価格も高いという問題があります。これは行政にもっと頑張ってもらわなければいけない部分ですが、その行政を企業がどう動かすか、志を同じくした企業同士が一緒になり働きかけていくのが良いと思います。
- 北村
- 私たちはビジョンとして成長を掲げており、事業を受け持つ立場からすると、成長とCO2の排出量削減にはジレンマがあります。これは弊社だけのことではないとは思いますが、その2つを実現していくことの難しさを感じます。
- 足立
- 事業が成長しても、CO2の排出量削減は可能です。というのは、再生可能エネルギーにシフトすればそこを考えなくていいわけです。エネルギーの消費量が万が一上がってしまったとしても、そもそもCO2を出さないエネルギーなので気にしなくていいというのが1点。もう一つのやり方としては、リジェネレイティブ・アグリカルチャー(環境再生型農業)というものがあります。アメリカの大農家や穀物メーカーが注目して、いま急速にシフトしています。これまでの集約型で肥料や農薬をたくさん使う農業ではなく、なるべく自然なやり方、日本で言う自然農法のようなものに戻しているのです。農業は世界全体で25%のGHG(温室効果ガス)を排出していると言われていますが、この方法ですと土壌がCO2をたくさん吸収してくれるので、バリューチェーン全体で発生量をかなり減らすことができます。たとえば、こうしたやり方はとても有用ではないかと思います。
ペットボトルの機能を損なわない素材での事業継続に期待
- 司会
- 「プラスチック」について、サントリーグループでは「プラスチック基本方針」に基づき、2030年までにグローバルで使用するすべてのペットボトルをリサイクル素材あるいは植物由来素材100%に切り替え、新たな化石由来原料の使用ゼロの実現を目指しています。プラスチックについてもご意見を伺えればと思います。
- 足立
- 2030年に向けた目標は高く評価したいと思います。国内企業の多くは国内の相場感であったり、国内のベンチマークで終わっていることが多いように思いますが、サントリーの目標は国際的な相場感に合致しています。
- 古木
- プラスチックにつきましては、国内の大手ボトラーの中でもトップの目標設定をされていると思います。また、サントリー1社単独ではなく業界を横断してアライアンスを組んだ取り組み(使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む新会社 「株式会社アールプラスジャパン」の設立)もとてもいいと思います。一方で、目標達成に向けたやり方、持続性といったことを考えると、CO2のカーボンニュートラル達成へのハードルが高くなってきている今、リサイクル素材あるいは植物由来素材のバランスについても考えていかなければいけないと思います。
- 横井
- 古木先生がおっしゃったように、今の段階ではいろいろなカードを持っておかないと先行きがどうかるかわからない部分があります。例えば、2011年からボトルtoボトルのメカニカル・リサイクル技術を進めてきましたが、原料になる使用済みペットボトルが十分に集まるのかという問題もあります。ですから、もっと間口を広げられるようにケミカルリサイクルであったり、あるいは天然素材のバイオプラスチック素材であったり、いろいろなことに挑戦しています。どれも道半ばの段階ではありますが、止まってしまえば切れるカードがなくなりますので、やり続けたいと思います。
- 古木
- 業界の方とお話すると、ペットボトルはほかには代え難い優れた機能性があり、消費者の選択によって現在の形になっていると言います。ですから、将来的にもペットボトルのみで商売をするのかどうかということに関しては、単純にほかの素材で代替するのではなく、ペットボトルが持っている機能もある程度損なわずに飲料を売る仕組みといった──かなり無理を申しているとは思いますが、そういう事業のやり方も考えていったほうがいいのではないかと思います。
- 横井
- 2019年には、烏龍茶や麦茶で2リットルのペットボトル製品に代わるものとして、濃縮させたものを190グラムの缶で製品化しています。先生にご指摘いただいたことへの対応策の1つではないかと思います。
- 井床
- この濃縮缶は、スチールですのでリサイクルしやすいのはもちろん、物流面にもやさしい製品です。現在、日本の物流業界ではドライバーの人手不足があり、売上を保ちながらも物流量は落としたいという状況があります。今後、食品事業としてはすべてをペットボトルでということではなく、お客様のご家庭にある程度のご負担をいただきながらも、同じおいしさのものをお届けするという手段も1つだと考えています。
- 足立
- プラスチックではありませんが、海外ではワインボトルやウイスキーボトルを紙にするといったことが試されています。それぞれは決定版ではなく、こういうやり方も試してみようという試行錯誤の段階だと思います。その試行錯誤のなかで、きっと新しいもの、本当にいいものが生まれるでしょうし、経験も積まれるのではないでしょうか。
- 古木
- この問題に関してはまだこれという打ち手が世界的にもはっきりしていない。バックキャスティングで野心的な目標を掲げてこれから考えていこうというところが多く、なかなか今の段階でこれが最適解だというのは正直難しいと思っています。ですから、これは私見ですが、最終的には担当している方の思いがとても重要で、なおかつその人の思い描いている未来を実現できる環境が整っているかどうかも考えて決めていくしかないと思います。
- 福本
- 「プラスチック基本方針」のなかでも、代替素材の探索は方策の1つとして掲げています。難しいのは、代替素材を検討する際にも、海洋汚染の問題だけでなく、気候変動問題等、他の環境や社会課題についてライフサイクル全体で考える必要があるということです。おっしゃっていただいたように、これという打ち手がまだまだ特定できない中で、あらゆる選択肢を排除せず、総合的な判断をしながら選択、決定していきたいと思います。
世界に向けたコミュニケーションで企業の価値を高める
- 司会
- 先生方からいろいろなアドバイスをいただきましたが、最後にサントリーに対して応援の意味を込めて、ここを頑張ってほしい、伸ばしていってほしいといったメッセージをいただけますでしょうか。
- 平林
- CO2削減と事業成長のジレンマについてお話がありました。それをジレンマと捉えずに、CO2削減が事業発展にポジティブであるという考え方で、バランス良く事業を進めていただくことが、企業のリスクを下げることにもつながると思います。今後のより良い社会、より良い日本ないし世界の発展に貢献するんだという自信を持って、ぜひ取り組みを進めていただければと思います。
- 古木
- 2つあります。1つはプラスチックについて、ペットボトルもそうですがポリスチレンといった素材も世界では目の敵にされています。しかし、日本はそういった素材の回収・リサイクルシステムを構築して、高い回収率・リサイクル率を実現しています。そういう努力を発信するという役割も、サントリーならできるのではないかと思っています。もう1つは、今後アライアンスや長期ビジョンといった、サントリーが思い描く未来を世界に向けて伝えていくことがすごく重要になってくると思います。
- 足立
- 伸ばしてほしいということであれば、もちろん水です。すでに十分にいろいろなことをなさっていますが、さらに水の最後の砦として、水で困るような人たちにどういうソリューションを提供するのかということも必要だと思います。
最後にもう1つ、せっかくなのでここにも力を入れるといいんじゃないかというヒントも加えさせていただくと、2021年には生物多様性条約のCOP15が開かれ、2030年までの目標がつくられます。しかも、かなり野心的な目標にしようということをビジネスリーダーが言っています。パリ協定で気候変動に対する流れが一気に変わったように、これで一気にドライブがかかり得るので、ぜひ注目していただきたいと思います。
- 福本
- 先生方からいろいろなご指摘をいただきましたので、私から総括として2つだけお話しさせてください。
まずは、サステナビリティを経営や事業の戦略として、プラス・マイナス両面のインパクトを見据えていかなければならないと改めて肝に銘じました。気候変動対策もジレンマという受け止めではなく、リスクを低減するとともに、これをオポチュニティに転換していく、いかに事業とベクトルを合わせてそのドライバーにしていくかという観点を社内で共有していきたいと思います。
2つ目は、先生方のサントリーへの期待をひしひしと感じました。特に水については、私たちのビジネスの源泉として、これまでも理念に基づいて推進をしてきましたが、自分たちのお客様だけではなく、より広く社会全体をステークホルダーと捉えて対応していきなさいということだと受け止めました。そして、日本のありよう、日本ならではの強みを広く世界に発信していきなさいと。サステナビリティの世界はどうしても欧米からの発信が多く、日本やアジアの実態にそぐわない、欧米主導のルールに追随する形になってしまうという問題意識を持っています。サントリーこそ、日本やアジアからの発信を行い、ギャップを埋めていくことができるはずだというご期待だと思います。今後の取り組みについては、世界の中でどのような役割を果たしていくべきか、もう1つ視座を上げて、考えていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。