- (2023/11/14)
-
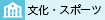
第45回 サントリー学芸賞 選評
宇南山 卓(京都大学経済研究所教授)
『現代日本の消費分析 ―― ライフサイクル理論の現在地』(慶應義塾大学出版会)
リーマンショック後の緊急経済対策として定額給付金が支払われ、新型コロナウイルス感染症の行動制限による景気対策として2020年4月から特別定額給付金が支給された。消費者にお金を渡すのだから、受け取った人は、その分消費を増やし、モノが売れるので景気がよくなるはずだと多くの人は考えるだろう。しかし、標準的な経済学では、そのような効果は小さいと考えられている。人は、今の所得だけをもとに、今の消費額を決めているのではない。貯蓄をしている人は、将来の生活が苦しくならないように貯蓄をしているか、将来により豊かな生活をしたいから貯蓄をしている。1ヶ月分の給料を一度にもらう人は、給料をもらった日に全額使い切ることをしないだけでなく、その後の所得のことも考えて、お金の使い方を考える。つまり、人々は今の所得だけではなくて、将来の所得がどうなるかを予測して今の消費額を決めていると想定されているのだ。このような消費決定に関する考え方は、ライフサイクル理論と呼ばれている。逆に、定額給付金が景気対策になるという考え方は、人はその時の所得だけをもとに消費する額を決めているというものだ。
一回限りでもらう10万円は、一時所得としてはある程度大きいが、保有している資産と将来の所得総額の合計と比べると小さい。これからの生涯で利用可能な資産に基づいて、現在の消費を決めるという考え方からすれば、今日だけ所得が10万円上昇する効果は小さいのだ。
人々がライフサイクル理論に従っているのか、それとも将来のことを考えないで暮らしているのか、経済学者は長い間研究を続けてきた。ライフサイクル仮説が成り立っているのか、どの程度の人に当てはまるのかを明らかにするのは極めて重要である。財政政策の効果が大きく異なるからだ。著者の宇南山氏は、この分野で世界的な業績をあげてきた研究者である。
人々が、将来のことを考えて消費を決定しているのなら、予想された所得の変化では消費を変動させないはずである。所得変化が事前に予想できる例に、定年退職前後の所得変化や公的年金の年間支給回数の変更がある。この場合、ライフサイクル理論に従っていれば、消費額はその前後で変わらないはずだ。ライフサイクル理論が成り立つかどうかを検証するためには、年金や児童手当などの政策変更を巧みに利用し、同じ人の所得と消費を追跡したデータを用いる必要がある。こうしたデータを用いて著者は、日本でライフサイクル理論が本当に成り立っているのかを、厳密に検証してきた。その結果、日本経済ではライフサイクル理論がかなり成り立っていることが説得的に示されている。本書は、ライフサイクル理論の基礎から最先端の検証方法まで、著者自身の日本経済に関する貢献を含めて体系的に紹介していることが特徴である。大部だが非常に丁寧な説明なのでわかりやすい。論理を飛ばさないでわかりやすく説明している著者の文章は、著者が研究者としてだけではなく、教師としても優れていることを示している。
大竹 文雄(大阪大学特任教授)評
東島 雅昌(東京大学社会科学研究所准教授)
『民主主義を装う権威主義 ―― 世界化する選挙独裁とその論理』(千倉書房)
権威主義体制に世界的な注目が集まっている。かつては、民主主義体制に比べて安定性を欠き、脆弱で、民主化によって滅びゆく存在だと考えられていた権威主義体制は、多くの論者の予測よりも遙かに強靱であった。それどころか、中国の台頭やロシアによるウクライナ侵略などは、権威主義体制が世界の行方に大きな意味を持つことを示している。
今日の世界が、民主主義対権威主義という体制間競争あるいは対立の時代だという見方も珍しくない。しかし、民主主義体制が多様で一枚岩ではないように、権威主義体制にも豊富なヴァリエーションがあり、体制内の差異は無視できない。
権威主義体制の多様性を生み出す大きな一因が選挙である。選挙は民主主義の証だと思われがちだが、実際には権威主義体制の下でも選挙実施は例外的ではない。ロシアが現在も大統領選挙を継続しているのは、その典型例である。
それはなぜなのか。権威主義体制の支配者は何を求めて選挙を行うのか。選挙のあり方にはどのような特徴が見いだされるのか。そして、他の統治手法との関係はいかなるものか。本書において著者の東島氏が解明しようと試みるのは、権威主義体制下で行われる選挙に存在する、民主主義体制とは異なった複雑な因果連関やダイナミクスである。
東島氏はこれらの問いに答えるべく、大規模データセットを構築して行われる緻密な計量分析と、中央アジア二カ国におけるフィールドワークに基づく事例分析を併用する。それによって、因果推論革命とも呼ばれる近年の社会科学における方法論的厳密化に棹さしつつも、歴史的要因や属人的要因を含む事例の固有性にも目配りが行き届いた、説得力ある知見を得ることに成功している。
従来、日本語での政治体制論は、特定の国や地域についての詳細な事例分析に基づくものが圧倒的に多く、計量分析による多国間比較を駆使した成果はほとんど見られなかった。本書は、権威主義体制についての知見を深めるだけではなく、政治体制論の研究水準を一気に高める画期的な成果であり、比較政治学への学術的貢献は極めて大きい。
加えて、読みやすさも本書の大きな魅力である。東島氏がアメリカの大学院で行った研究を出発点にしており、高い評価を得ている英語版が既に存在するが、本書は英語著作の邦訳とは全く異なる。日本の読者が持っているであろう背景的知識や、抱くであろう疑問などを十分に踏まえ、とりわけ冒頭の数章を使って丁寧な説明が与えられることで、先端的な成果が一般読者に開かれている。著者と編集者の努力に心からの敬意を表したい。
専門知への不信や陰謀論の横行は、主要民主主義国でも今日無視できないリスクになっている。学術上の先端的な知見が市民社会に広く共有される意義は、ますます高まっているはずである。東島氏には、今後も本書のような試みを継続していただきたいと願う。
待鳥 聡史(京都大学教授)評
菱岡 憲司(山口県立大学国際文化学部准教授)
『大才子 小津久足 ―― 伊勢商人の蔵書・国学・紀行文』(中央公論新社)
この本は、一般的には無名と言ってもよい江戸時代後期の富裕商家で文人である小津久足(おづひさたり)の生涯を追い、当人の営為から同時代の多様な言説空間を一望できるように構成された研究成果である。江戸文芸に限らず、近世思想と社会史に関する新しい知見に満ちている。久足は、生涯に紀行文を40数点著述しているが、広くは普及しづらい写本として伝わり、その大半が未翻刻で著者自身による読解を経て初めて読者の目の前に現れる。その作業だけでも高く評価すべき事柄だが、一次文献に即し一生の経過と著作を丁寧に描いたモノグラフであると同時に、そもそも人文学という学問領域とは何か、その研究対象とはどのようなもので、手法としてどうアプローチすべきか、という根本的な問いかけを私たちに投げかけるきわめて重要な学術的発信であると言わざるを得ない。
江戸時代の文芸を知ろうとする者は、現在の日本で「文芸」と目される著述とその作り手、あるいは作り手の言論環境にだけ注目していては不充分である。むしろ文と理を峻別する19世紀ヨーロッパの分類思考から一度離れ、同時代の日本列島において認識され通用した「文芸」(のようなもの)のプラクティスを視界に収めてはじめて日本の言語文化の幅と深度を推し量ることができる。物語(小説類)と詩歌を基軸としたジャンルの外部にも目を向ける本書にはそのような遠心力が発揮されている。
久足は紀行の他には本居宣長の孫弟子として国学を修め、古代考証と作詠に熱中するが、やがて一門との距離をおき、離反をして、いわゆる古道論を否定するまでに思考を転換させている。実際に生きている現在への傾斜を深める過程において、歌も散文も、「ありのままを表現する」立場を確立していく。その射程につながる結節点の一つひとつを掘り下げるかたわら、著者は同時代の他の地域と出来事を視野に入れ、久足の様ざまな営みの相対化を図っている。干鰯(ほしか)問屋という家業を司る立場から導かれる経済活動が、縫い目無く地理学、古典学、詩歌、本草学、物産学、海外情報などにまで広がる関心と行動の半径を押し広げていたように見受けられる。著者はその構図を精緻に描くことによって、近代へと向かう日本の学芸史・文芸史そのものの輪廓を新たに提示することに成功している。
久足は曲亭馬琴の年下の友人で良き理解者、馬琴作品のファースト・リーダーの一人として従来の近世文学研究ではある程度の注目を集めている。膨大な蔵書家でもあり、近年の研究では、久足のことを当代のもっとも優れた知識人の一人として定位する動きもある。本書で著者は、膨大な文献を渉猟し選別する能力と、自らが実証に基づいて得た知見の総合化を通して、時代の文芸の新たな地図を描こうとしている。平易で読みやすい文章と、鮮やかな論の運びが相まって多くの可能性を示していることにおいても高い評価に値する。
ロバート キャンベル(早稲田大学特命教授)評
鷲谷 花(映画研究者、大阪国際児童文学振興財団特別専門員)
『姫とホモソーシャル ―― 半信半疑のフェミニズム映画批評』(青土社)
批評としての迫力みなぎる映画論が展開されている。全10章、古今のさまざまな作品が俎上に載せられていく。ひょっとして、冒頭の『マッドマックス』やインド映画の話に関心が薄い向きは、とにかく『羅生門』を論じた第3章「真砂サバイバル」をご一読あれ。いつかだれかが書かなければならなかった、そして今だからこそ書かれ得た論考がそこにある。
フェミニズム的映画論の試み、と大まかには言える。だが副題にある「半信半疑」が効いている。一方には、フェミニズムがもたらした革新的な思考への信頼があり、男性中心主義的な発想が生むひずみを剔出することへの「謀叛気」みなぎるパッションがある。『羅生門』とはそもそも「強姦」被害の物語であるという点を、これまでほぼだれも論じてこなかった。それは男たちによる批評が生んだジェンダー的な「非対称性」の表れではないか。その理非を糾すためになすべき作業を、著者はきびきびと小気味よく進める。
他方には、映画への、そして映画を作り上げた者たちへの深い愛着がある。批評の刃をふるうことで作品そのものをばっさりと切り捨てるとしたら、あまりにむなしく独善的な正義の行使になりはしないか。とはいえ心配はいらない。「女性嫌悪的な世界と人間たちを描く映画それ自体が、完全に女性嫌悪的であるとは限らない。」たとえ「ホモソーシャル」、つまり女を排除して男だけで権力を独占する秩序体系のもとで製作された過去の作品であろうとも、そんな価値規範のくびきを脱し、女と男のよりまっとうな関係のあり方を示唆する要素をたっぷりと含んでいることがありうる。その点に向けて、著者の言葉は紡がれている。
「既存の性の規範を揺るがし、女性観客を力づけるポジティヴな可能性」のありかは、ホラー映画や宮崎駿のアニメにも見出される。緻密な議論の運びと、クールな(だが燃え上がる想念を秘めた)筆致ゆえに、論述に勢いがあり、読んでいて爽快ですらある。何と言っても文章の力だ。例えば、内田吐夢監督が未だ時代劇の所作がおぼつかない高倉健を起用して撮った『宮本武蔵 巌流島の決斗』について。武蔵(中村錦之助)に一撃のもとに倒された小次郎(高倉)は「苦痛でも悔しさでもなく、いったい何が起きたのか理解できていないような、あどけないともいえる表情を浮かべ、目をあいたまま崩れ落ちる」。内田吐夢の戦後作には「下の世代の若者を犠牲にして生きのびた『戦中派』の悔恨」が込められているという読解は、具体的な場面の鮮烈な“引用”によって支えられているからこそ読む者の胸を打つ。
第1章で『マッドマックス 怒りのデス・ロード』に関し、「快楽と公正の感覚を両立させる」仕組みが凝らされた作品であると記されていた。一冊を読み終えて、それがまさに本書の魅力だと感じる。これから鷲谷氏がどのような地平を切り拓いていくのか、楽しみでならない。
野崎 歓(放送大学教授)評
阿部 卓也(愛知淑徳大学創造表現学部准教授)
『杉浦康平と写植の時代 ―― 光学技術と日本語のデザイン』(慶應義塾大学出版会)
歴史や思想、思いを表すために私たちは文字を使う。しかしその文字のデザインそれ自体のうちにも、すでにして歴史や思想、思いがある。本書の主題のひとつは写植だが、まさに文字のひとつひとつの佇まいを丁寧にたしかめ、味わい、焼き付けたくなるような名著であった。
たとえば、杉浦康平のあの独特の文字詰めの技法。その拠り所になっていたのは、彼が親しんでいた筆書きであったと言う。文字とは本来、書き手の肉体性や身体運動の痕跡であるはずだ。印刷技術の時代に、どうすれば活字に書を与え直すことができるのか。つまり杉浦のあのツメツメのタイポグラフィは、ただ詰めることが目的なのではなく、意味の流れや書く人の息づかいが作り出すリズムを可視化するためだったのである。さらに、1960-70年代の日本における外来語の増加という時代背景も加わった。意味の厚みも歴史もないカタカナにいかにして書字的美しさを与えるか。文字のデザインは、日本語と日本文化の問題とダイレクトにつながっている。
邦文写植機を発明した石井茂吉と森澤信夫の運命にもハラハラしてしまう。二人の出会いは遡ること1920年代、場所は何と星製薬である。なぜ製薬会社から写植が生まれたのか? 星新一の父・星一(はじめ)が創業した星製薬は、新薬の開発ではなく、既存薬品の日本版を自社製造することを得意としていた。その際、力を入れたのがマスメディアを用いた宣伝である。星製薬は社内に印刷工場を持ち、欧米の写植機をもとに邦文写植機を開発。しかし、開発に携わった二人の社員、石井と森澤は、人間としてあまりにタイプが違う。石井は東京帝国大学工科大学を出たエリートである。一方の森澤は小学校卒。麺類の製造機械を作っていた家業の工場で、我流で技術を習得した。結局、邦文写植機を共同開発したあと、二人は東京と大阪で別の道を歩むことになる。
本書の魅力は、膨大な資料やインタビューにもとづく史実にズームインして高密度で記述する一方、それを突き破るようにして「文字とは何なのか」のようなスケールの大きな本質的問いへとズームアウトしていく、その目も眩むような、それでいて深い納得を伴う往復のリズムにある。自らが語る対象へと接近していく深い愛と、そこから決然と距離をとろうとする批評的まなざし。著者は言う。「人間の心の中では、瞬間的・情動的な反応と、理性的・論理的な判断といった、段階の異なる活動のあいだに、截然とした線を引くことはできない。それはむしろ、溶け合って連続したマグマのようなものとしてある。そして、ある個人が内面における坩堝(るつぼ)で迷い、結果を宙吊りにしているあいだにも、集団的な力学や技術革新の決定性によって、時代は不可逆に進んでいく」。本書の登場人物が、「溶け合って連続したマグマ」を生きているのと同様、著者もまた、その同じ振れ幅の中で書いている。本当の誠実さとは熱く、そして同時に冷めたものなのだろう。
伊藤 亜紗(東京工業大学教授)評
小俣ラポー 日登美(京都大学白眉センター/人文科学研究所特定准教授)
『殉教の日本 ―― 近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック』(名古屋大学出版会)
日本の研究者による、こうした国際水準の「読める学術書」を、私は30年以上も待ちわびていた。西欧中心史観とナショナル・ヒストリーと公文書主義の限界が指摘され、グローバル・ヒストリーとポストコロニアル研究と記憶研究の必要が叫ばれてきたわけだが、その条件すべてを満たす学術書は少ない。他方で歴史研究の精緻化は対象の細分化をまねき、幅広い読者の知的欲求に応えることは容易ではない。本書はそうした学芸の苦境に風穴を開ける一つの快挙である。
「暴虐と聖性の国」という日本イメージが17世紀西欧でいかに形成され、その記憶はいかに変容したか。それこそ著者が現地での徹底した史料調査を踏まえて解明した問いである。本書は狭義には「日本二十六聖人」をめぐるキリスト教布教のレトリック研究、あるいは「殉教」概念のプロパガンダ史だが、文明史としての射程は驚くほど広く長い。近世ヨーロッパで成立した「殉教の日本」イメージは、現代日本人の世界観にも大きな影響を及ぼしているからである。
日本二十六聖人とは、豊臣秀吉の命令により1597年(慶長元年)に長崎で磔刑に処された宣教師とカトリック信者の総称である。この殉教者が列福されて聖人(列聖は1862年)の扱いを受けたのは、処刑から30年後、三十年戦争(1618-48年)中の1627年のことであった。その5年前、1622年にローマ教皇グレゴリウス15世は対抗宗教改革を推進すべく布教聖省Sacra Congregatio de Propaganda Fideを設立している。周知のごとく、政治用語として今日も使われる「プロパガンダ」は、この教会用語に由来する。つまり、日本二十六聖人はカトリック教会が「宣教の勝利」を誇示したプロパガンダの象徴である。だからこそ真偽を問わず膨大な聖遺物、報告書、図像、受難劇が創出され、大切に保管されてきた。
宗教戦争の真っただ中で成立した「殉教」概念もプロパガンダと不可分である。当然ながら、日本の殉教者の言説にも「フェイク・ニュース」は含まれていた。こうしたプロパガンダ分析において、殉教者のファクト(事実)よりも信者へのエフェクト(効果)に著者が十分に目配りしていることも、私が本書を高く評価する理由である。殉教者の聖性の物的証拠と見なされた聖遺物についても真贋の識別よりも、それが記憶の依代として蒐集され継承された文化的意義の考察が重要なのである。
そうした記憶研究の白眉とも言えるのが、非文字資料である殉教図像と殉教演劇を扱った第4章、第5章と言えるだろう。「殉教の日本」図像は事実を描写したものというよりも、イエス・キリストの十字架の受難、当時の異端審問における処刑など西欧の既成イメージを流用した図像である。だからこそ多くの信者に理解され感動をもたらした。演劇もこのイメージを舞台上で再現し、「見ることがすなわち信じること」である宗教的開眼を可能にした。この殉教劇が上演された地域の片寄り、その演目や残虐シーンの増減など実証的データから、「日本の殉教」が日本よりも西欧の出来事に強く結びついていたことが解き明かされている。その意味で、情報社会における日本イメージ構築の考古学として本書を読むこともできるだろう。
佐藤 卓己(京都大学教授)評
池田 真歩(北海学園大学法学部准教授)
『首都の議会 ―― 近代移行期東京の政治秩序と都市改造』(東京大学出版会)
東京に住んでいてほかの地方を訪れた機会に、そこでの「政治」の存在感の大きさを実感することがある。もう20年前の話ではあるが、某県庁所在地でコンビニに入り、雑誌のコーナーをのぞいたとき、県政の専門雑誌が二種類も刊行されているのに驚いた。地元の商工業者にとって、業界の利益の実現のために県議会の議員に働きかけ、その党派の動向に目を配ることは当たり前だから、県政の専門誌も売れる。地域社会から上がってくる要求が、議会を通じて政府の政策へと統合されるという、近代社会において社会と国家(政府)をつなぐ回路のひな型のようなものである。
ところが東京では、地域と都議会とのつながりを、それほど強く実感することはない。もちろん地域の商工組合などに属している人にとっては状況が異なるだろうが、都政について専門的に報道するメディアもないため、一般の市民にとっては意識しにくい。つながりがはっきりと見えないにもかかわらず、大規模な人口を抱えた都市社会と、都政のメカニズムとが何らかの形で連動し、秩序を保っているのである。そこには、単に大都市だからそうなっているというだけには尽きない、歴史上の背景があるのではないか。
『首都の議会』は、近代史において東京に独特の政治のしくみが生まれてゆく過程を、みごとに描きだした。明治10年代に東京府会は、言論人たちが「実業家なき議会」を構成し、商工業者は商法会議所に集うという、〈政〉と〈商〉の分離状態から始まった。それは、府会が西洋からの最新の知識を導入し、江戸時代の町会所から引き継いだ共有金を元手として、都市インフラの整備を計画するのに適した体制だった。
しかし明治20年代以降、東京市会の時代になると、言論人に代わり政党政治家が議員となって「民力休養」の方針を掲げ、市会は都市改造事業に消極的になる。これに対して、産業革命の進行を背景としながら、鉄道や道路の大規模な整備を求め、市会の因循姑息ぶりを批判する声が地域の公民団体から上がってゆく。そこで政党は、利益要求に応える積極主義に転じることで、区会・公民団体との結合を果たそうとするが、すでに政党の腐敗ぶりに対する疑念や反感を抱いている議会外の住民は、汚職や市政の強引な運営に対して反対運動を展開する。そうした慢性的な緊張状態が続くのである。
一般的に言われる政党政治のしくみは、政党が地方の利益を吸い上げ、政党間の競争や交渉を通じてさまざまな利益の間の調整が行われるというものである。ところが東京ではこれとは全く異なり、区会・公民団体の活動が、むしろ反政党の立場で市議会を突き上げるという都市政治の構造が育っていった。この明治末期までの動向が、冒頭にふれたような現在の都政のあり方にどのように連続しているのか、それともその間に何らかの断絶があったのか。本書の充実した歴史叙述を楽しみながら、さらなる探究への期待が大いにそそられる。
苅部 直(東京大学教授)評
新城 道彦(フェリス女学院大学国際交流学部教授)
『朝鮮半島の歴史 ―― 政争と外患の六百年』(新潮社)
地味な書名である。何の変哲もない。
名は体を表す。内容もズバリ掛け値なしの「政争と外患の六百年」にわたる「朝鮮半島の歴史」、まさかカン違いして手に取る読者もいるまい。
「~~の歴史」といえば、どこでも、いくつでもありそうな本のタイトル、あえて地味だといったゆえんである。しかし地味は、必ずしも凡百を意味しない。
なかんづく「朝鮮半島の歴史」は然り。その「六百年」を描き切った日本語の通史は、思想プロパーを除けば、短く数えても四半世紀、存在しなかった。地味ながら貴重である。
朝鮮戦争の休戦から70周年。その間、半島の南北に別々の国家が分立しつづけた。史上「分断」は「異例」ながら「独立」も「異例」。「異例」も重なれば二重否定になるのであろうか。70年を経て、法的には戦時であっても、もはや「異例」ではなく常態といってよい。休戦協定締結日の7月27日、南北は各々の記念行事でも対極的な姿態を示した。
最も近い隣国のそうしたありようは、いったい何に由来するのか。われわれ日本人は、そこに至った事情をどこまで知っているだろうか。
知らないとすれば、知るすべがなかったからである。無味乾燥な教科書以外、普通に広く読める「朝鮮半島の歴史」・通史は久しく出なかった。既存のそれは、もはや古びてしまって、また偏りもまぬかれない。
そもそも南北それぞれ「独立」国家となる前、半島はまるごと日本の植民地だった。さらにその前は、王朝国家であると同時に、中華王朝の属国であったから、どの立場で歴史をみるかで、バイアスは避けられない。
多かれ少なかれ、そうした視座・偏向のままに史実を位置づけてきた。通史であれ研究であれ、「朝鮮半島の歴史」が日本に乏しい理由の一半は、そこに存する。かけ離れた各々をムリにつなげても、一貫するはずはない。忌避して当然ではあった。
そこで「六百年」の「朝鮮半島の歴史」を跡づけるには、数ある視座から超然とした俯瞰と根強い偏向に対峙する乾いた論述とが、同時に求められる。現行の関係学界でそれをかなえるのは、かなり難しい。
そこに挑んだのが、本書である。からみあう「政争と外患」のプロセスをわかりやすく説くだけでも、秀逸といってよい。しかもその構図が、王朝時代には朝廷の党争、20世紀前半には「独立」の運動、後半には南北の「分断」に展開現象した史的メカニズムを展望せしめる。
また近代日朝関係史を専門とする著者は、資料を縦横に駆使しながら、あえて得意な題材に深入りしない。「併合」「日帝」ばかりに耳目を奪われがちな読者に、冷徹な視座を提供するねらいだろう。装いに応じて、中身も浮華を廃し地味に徹したのは、意識的な抑制にちがいない。いよいよ非凡である。
もちろん著者も漏らしたように「「あれがない、これがない」的な批判を受ける」のは、通史の宿命。その尻馬に乗るなら、「政争と外患」・政治外交のみならず、思想文化・社会経済にもしかるべき目配りがなくては、なお通史というに足らない。
欠如の事情は察しつつ、ことさら蛇足の望蜀を記した。これを機に、「朝鮮半島の歴史」を掛け値なしの全体史として描く達成を著者に期待したいからである。
岡本 隆司(京都府立大学教授)評
以上
